★「かぐや姫」の歴史は➡こちら
第8位:『アビーロードの街』
第8位は「アビーロードの街」です。この単語だけで、都会のキラキラ感が出ていますね。
まずは、公式音源をお楽しみください。
🎵 公式クレジット
「アビーロードの街」 – かぐや姫(Kaguyahime)
作詞:伊勢正三 作曲:南こうせつ 編曲:石川鷹彦
© PANAM / Crown Tokuma Music. 収録アルバム:かぐや姫フォーエバー(2010年8月4日リリース)
📝 2行解説
伊勢正三が青春の日々をロンドンの“アビーロード”に重ねた、旅情あふれるナンバー。
かぐや姫らしい優しさと哀愁が溶け合い、時代を超えて胸に残るフォークの名曲です。
『アビーロードの街』の物語(Short stories)
青山の残響
1972年の秋、東京・青山通り。石川亮太は、薄手のトレンチコートを羽織り、広告代理店の仕事を終えて夜の街に溶け込んでいた。24歳。大学を出てこの街に就職し、2年が経つ。冷たい風がビルの谷間を抜け、遠くでタクシーのクラクションが短く響く。ネオンの光が濡れた舗道に映り、彼の影を細く伸ばしていた。
都会の喧騒は、昼も夜も途切れない。オフィスで企画書をまとめ、クライアントの目を気にする日々は単調で、未来への手がかりさえ掴めない。音楽は好きだった。学生時代、レコードを聴きながら夜を過ごし、フォークソングに心を重ねた。でも、自分でギターを弾くことはなく、ただ聴く側にいた。今は仕事が終われば、青山の狭いマンションに流れ着き、静かにラジオのダイヤルを回して、煙草の煙を夜に溶かす。それが亮太の暮らしだった。
「この街に、何か響くものがあるのか!?」
亮太は呟き、足を止めた。青山通りのビルの合間に、ネオンの明滅が踊り、サラリーマンの笑い声やハイヒールの音が交錯する。ここは、都会のざわめきと孤独が共存する場所だ。
バーの一夜
疲れを紛らわすため、亮太は表参道の裏路地に佇むバー「クロスロード」に滑り込んだ。ガラスドアを開けると、煙草の香りとジャズの残響が漂い、薄暗い店内に数人の客が佇んでいる。カウンターに腰掛け、コーヒーを注文した。酒ではなく、黒い雫を選ぶのは、夜のざわめきを少しだけ澄ましたいからだ。
「若いのに、コーヒーとは渋いね」
隣から声が響いた。40半ばほどの男、グレーのスーツに身を包み、伸びた髭が顔に陰を落としている。疲れた瞳に、遠い光が宿っていた。
「酒より、頭が冴える気がして」
亮太が返すと、男は唇の端を上げた。
「俺は高木さ。昔、この街の裏でギターを爪弾いてた。青山の夜が俺のキャンバスだったよ」
亮太は目を細めた。音楽は好きだが、自分で鳴らすことはなかった彼にとって、その言葉は遠い夢のようだった。
「俺、音楽は好きです。でも、弾いたことはなくて」
「そうか。でも、聴くだけでも音は生きてるよ。街の雑踏に埋もれてもさ」
高木はコーヒーを啜り、遠くを見つめるように目を細めた。ラジオから、かぐや姫の「アビーロードの街」が流れ始め、伊勢正三の声が響いた。亮太は黙って耳を傾けた。
遠い日の音色
高木は語り続けた。かつて渋谷のライブハウスで演奏し、仲間と共に夜を彩っていたが、やがて皆が別の道を選び、音は途絶えた。今は小さな印刷所で働き、細い暮らしを紡いでいる。
「でもさ、あの頃の音はまだ耳に残ってる。ビルの谷間に響き合うギターの調べ。あれが俺の青春だったよ」
高木の言葉に、亮太は自分の遠い日々を重ねた。学生時代、レコードでフォークを聴きながら、都会の夜に夢を見ていた。でも、自分で音を鳴らす勇気はなく、ただ聞き手として過ごした。今は広告の仕事に追われ、心のどこかが乾いている。
「俺、音楽を聴くだけで満足してたんです。でも、なんか物足りなくて」
亮太の呟きに、高木は一瞬目を丸くした。
「聴くだけでも、音はお前の中にあるよ。それを鳴らすかどうかは、お前次第さ」
高木はポケットから小さなハーモニカを取り出し、そっと吹いた。錆びた音が静かに流れ、都会のざわめきに溶け込む。亮太は目を閉じ、その旋律に身を委ねた。*「遠い日の夢さ」*と歌声が続き、ノスタルジーが胸に広がった。
街の灯影
コーヒーを飲み干し、亮太と高木は店を出た。秋の夜風が冷たく、青山通りの灯りが遠くで揺らめいている。二人は無言で裏路地を抜け、雑踏に紛れた。ネオンの光がビルの隙間に跳ね、まるで街が夜の旋律を奏でているようだ。
「この街は冷たくて、でもどこか温かい音がするよな」
高木がぽつりと漏らした。亮太は頷き、足を止めた。目の前には、かつて友人とレコードを買いに行った小さな店があった。今はシャッターが下り、看板も色褪せている。
「ここで、昔よくレコード漁ってたんです。自分で弾けなくても、音に浸ってた」
「いいじゃないか。聴いた音は、お前が街に放つ響きさ」
高木の言葉に、亮太の胸が軽やかに震えた。雑踏に埋もれた夢は、確かにこの街に息づいていた。
「いつか、自分で音を鳴らしてみたいな」
亮太が呟くと、高木は笑い、肩に軽く手を置いた。
「そうしなよ。街はいつだって、お前の調べを待ってる」
夜の調べ
翌日、亮太は代理店の仕事を終え、マンションに戻った。机の引き出しから、古いカセットプレーヤーを取り出し、埃を払う。昔買ったかぐや姫のテープをセットし、再生ボタンを押した。音が部屋に響き、都会のざわめきと混ざり合う。声は出さず、ただ旋律に耳を傾けながら、亮太は初めて穏やかな笑みを浮かべた。
窓の外では、青山の夜が広がっている。ビルの谷間にネオンが瞬き、タクシーの音が低く響く。雑踏の喧騒は止まないが、その中で自分の音が確かに息づいている気がした。亮太はプレーヤーを止め、窓を開けた。秋の風が流れ込み、遠くで誰かの足音が夜に溶ける。いつかこの街に、自分の響きを放ってみようと思った。成功や喝采は求めず、ただ音を紡ぐだけでいい。そんなささやかな意志が、心に灯った。
「アビーロードの街」──かぐや姫が描く都会の情景
かぐや姫の楽曲「アビーロードの街」は、1973年にリリースされたアルバム『かぐや姫さあど』に収録されています。作詞は伊勢正三、作曲は南こうせつが手掛けました。この曲は、都会の風景とそこで生きる人々の心情を繊細に描き出しています。以下では、この楽曲の背景、歌詞の内容、音楽的特徴、そして当時の社会状況との関連性について詳しく探っていきます。
楽曲の背景
1970年代初頭、日本は高度経済成長期を迎え、都市部の発展が著しく進行していました。地方から多くの若者が仕事や学業のために上京し、都会での新しい生活を始めていました。伊勢正三自身も大分県出身で、都会での生活に戸惑いながらも新しい環境に適応していく中で、この曲のインスピレーションを得た可能性があります。
「アビーロードの街」というタイトルは、ビートルズのアルバム『Abbey Road』を連想させますが、実際のところ、この曲が直接ビートルズに影響を受けたという明確な証拠はありません。しかし、当時の日本の音楽シーンにおいて、ビートルズは多くのミュージシャンに影響を与えており、その影響が間接的に表れている可能性は考えられます。
また、この曲が収録されたアルバム『かぐや姫さあど』は、かぐや姫の成熟期にあたり、フォークソングの枠を超えた表現の広がりを見せています。「神田川」や「赤ちょうちん」などと並び、彼らが都会の情景を描くことに挑戦した楽曲の一つといえるでしょう。
この曲が生まれた時期、都会での生活は華やかさと孤独が入り混じったものでした。高度経済成長がもたらした繁栄の影で、多くの若者が生活の厳しさや人との距離感を感じながら日々を過ごしていたのです。フォークソングは、そんな彼らの心の支えにもなっていました。さらに、この楽曲には、都会で生きる若者たちの「心の葛藤」と「過去の記憶」が繊細に織り交ぜられており、リスナーの感情を揺さぶる力を持っています。
歌詞の分析
歌詞は、都会の雨の日の情景と、そこで感じる孤独や懐かしさを描写しています。冒頭の「あの日の君は傘さして 青山通り歩いてた」というフレーズから始まり、具体的な場所や状況が描かれています。青山通りは東京の主要な通りの一つであり、都会の象徴的な場所として選ばれたと考えられます。
続く「ビートルズの歌が きこえてきそうと 二人で渡った交差点」というフレーズでは、過去の恋人との思い出が語られています。ビートルズの曲が聞こえてきそうだと感じることで、当時の若者文化や音楽シーンが垣間見えます。
また、「公衆電話 だから 大きな声で言えないけれど 好きなんだ」という部分では、直接的な感情表現を避けつつも、相手への想いを伝えようとする主人公の心情が表現されています。
海外フォークシーンとの関連性

1970年代、日本のフォークシーンはアメリカの影響を大きく受けていました。ボブ・ディランやサイモン&ガーファンクルなどの楽曲が人気を博し、歌詞のメッセージ性が重視される時代でした。「アビーロードの街」にも、その影響が見られ、都会の中での孤独や郷愁を歌う点で、海外フォークの精神と共鳴する部分があります。
音楽的特徴
楽曲はアコースティックギターを主体としたシンプルな編成で、かぐや姫らしいフォークソングのスタイルを踏襲しています。伊勢正三柔らかいボーカルと、南こうせつのコーラスが美しく調和し、楽曲全体に温かみを与えています。
また、楽曲のアレンジには意図的な抑制が見られます。派手なアレンジを施さず、静かに語るようなトーンが貫かれているのは、都会の孤独や静寂を表現するためかもしれません。シンプルなアレンジだからこそ、歌詞とメロディがより際立ち、聴く人の心に深く染み込むのです。
影響と評価
この楽曲はリリース当初、かぐや姫の他の代表曲「神田川」や「なごり雪」に比べると大きなヒットにはなりませんでした。しかし、フォークファンの間では高く評価され、現在でもアルバム収録曲として根強い人気を持っています。
特に、都会に住む人々にとっては、この歌の歌詞が自分の経験と重なり、深く共感できるものとなっています。また、現代においても都市の孤独や過去への郷愁は変わらぬテーマであり、新しい世代のリスナーにも響く楽曲となっています。
まとめ
「アビーロードの街」は、かぐや姫の楽曲の中でも、都会の情景と人々の心情を繊細に描いた作品として評価されています。伊勢正三の詩的な歌詞と、南こうせつのメロディーが融合し、1970年代の日本の社会状況や若者の心情を映し出しています。
この楽曲を通じて、都会の中で感じる孤独や、過去の思い出への郷愁といった普遍的なテーマが描かれており、時代を超えて多くの人々の心に響き続けています。
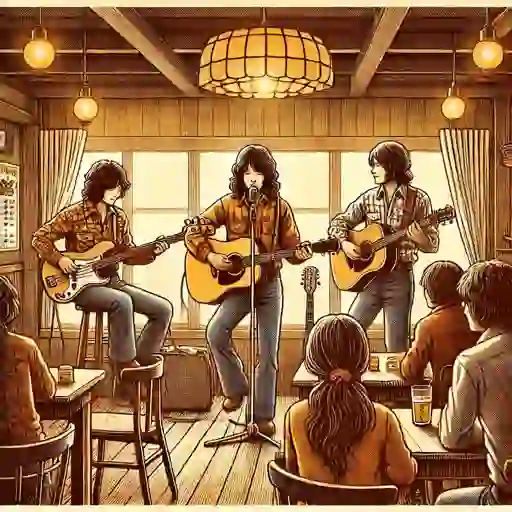


コメント