8月13日:イアン・ホーグランドの誕生日!
今日8月13日は、スウェーデンのロックバンドEuropeの名ドラマー、イアン・ホーグランド(Ian Haugland)の誕生日です。
1964年にノルウェーのストールスレット(Storslett)で生まれた彼は、生後8ヶ月でストックホルム郊外のメルスタに移住し、1984年の夏にEuropeに加入、前任のトニー・レノに代わってバンドの中核を担うことになりました。5歳から音楽に親しみ、Led Zeppelinを愛聴していた彼の力強いドラムプレイは、Europeの代表曲「The Final Countdown」に欠かせない要素となっています。
今日の紹介曲:
まずはYoutube動画(公式動画)からどうぞ!!
🎥 公式動画クレジット
曲名:The Final Countdown
アーティスト:Europe(ヨーロッパ)
公開元:Europe Official YouTube Channel
動画公開日:2009年10月26日
提供:℗ 1986 Sony Music Entertainment
レーベル:Epic Records / Sony Music
収録アルバム:『The Final Countdown』(1986年発売)
📖 2行解説
80年代シンセロックの象徴ともいえる世界的ヒット曲。
イアン・ホーグランドのドラミングが、壮大なイントロと共に高揚感を引き立てます。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 1986 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
僕がこの曲を初めて聴いたのは、リリース当時です。
会社の移動で、北九市の小倉にいたことです。仕事も生活も落ち着いてきており、まだまだ人生を謳歌していた頃です。前年に長女も誕生しており、不足感のない日々を送っていました。仕事をし、毎日のように麻雀をする日々、休日には家族でどかに遊びに行く。そんな絵にかいたような時期でした。当然後年に、付けが回ってくるのですが!!!その時にはなかなか気づかないものです。
ヨーロッパというバンドは、北欧のバンドですが、そんなことはお構いなしで、スケールの大きい歌だなと思っていました。正直、彼らの楽曲はこの曲以外はほぼ知りません。
何といっても、イントロのシンセのファンファーレが特徴的です。イントロ当てクイズならだれでもわかるようなが曲です(=^・^=)
宇宙への旅立ちを告げる壮大なファンファーレ
1986年5月26日にEpic Recordsからリリースされた『The Final Countdown』は、Europeの3枚目のスタジオアルバムであり、商業的に大成功を収め、アメリカのビルボード200チャートで8位まで上昇しました。この楽曲が生まれた1980年代中期は、レーガン政権下でのアメリカン・ドリームが絶頂期を迎え、宇宙開発競争の熱狂も冷めやらぬ時代でした。

同年1月に発生したスペースシャトル・チャレンジャー号の悲劇的な爆発事故は世界に衝撃を与えましたが、それでもなお人類の宇宙への憧憬は消えることがありませんでした。「The Final Countdown」の歌詞に込められた「Venus(金星)へ向かう」というテーマは、まさにこの時代精神を反映した壮大な物語です。
シンセサイザーが描く未来への序章
楽曲の最も印象的な要素といえば、冒頭から響き渡るあのシンセサイザーのファンファーレです。Yamaha DX7を駆使したこのイントロは、宇宙船の発進を思わせる金属的で機械的な響きを持ちながら、同時に古典的なファンファーレの荘厳さを併せ持っています。この音色は1980年代のデジタル・シンセサイザー革命の象徴的な成果であり、従来のアナログシンセでは表現できない新しい音響世界を提示しました。

当時のハードロック・シーンでは、ディープ・パープルやレインボーといったブリティッシュ・ハードロックの流れを汲むバンドが主流でしたが、Europeはスカンジナビア半島という地理的特性を活かし、よりメロディアスで叙情的なアプローチを取りました。これは北欧特有の音楽的伝統と、当時のポップ・メタルムーブメントが融合した結果と言えるでしょう。
イアン・ホーグランドのドラムワーク
イアン・ホーグランドのドラムプレイは、「The Final Countdown」において極めて重要な役割を果たしています。楽曲全体を通して聴かれる彼のドラムパターンは、4/4拍子の基本リズムを保ちながら、宇宙旅行というテーマにふさわしい浮遊感を演出しています。
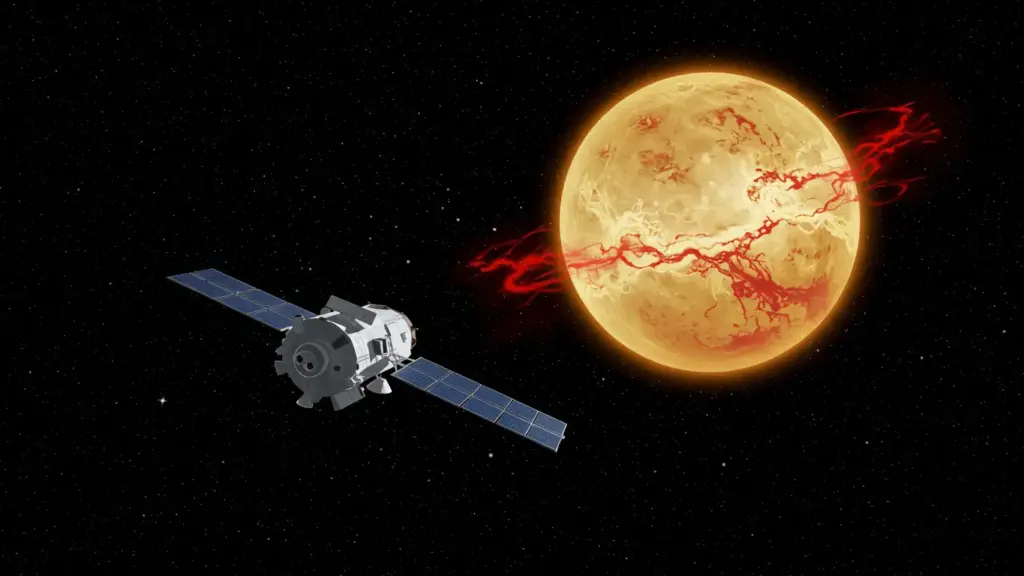
特に注目すべきは、サビ部分でのスネアドラムのアクセント配置です。通常のロックビートでは2拍目と4拍目にアクセントを置くのが一般的ですが、ホーグランドはここに微妙なシンコペーションを加え、楽曲に推進力と同時に宇宙空間での無重力感を表現しています。バスドラムの連打も機械的な精密さを保ちながら、有機的なグルーヴ感を失わない絶妙なバランスを保っています。
時代を超えたメロディーライン
ジョーイ・テンペストが作詞作曲した「The Final Countdown」のメロディーラインは、クラシック音楽の影響を強く受けています。主旋律は短調(マイナースケール)を基調としながら、サビ部分で長調(メジャースケール)へと転調することで、悲哀と希望を同時に表現する複雑な感情を描き出しています。
歌詞の構造も非常に計算されており、「We’re leaving together」から始まる導入部では、集団での旅立ちという共同体意識が歌われます。続く「But still it’s farewell」では別れの悲しみが表現され、「And maybe we’ll come back / To Earth, who can tell?」という部分では不確実な未来への不安が込められています。

このような感情の起伏を音楽的に支えているのが、ホーグランドの繊細なドラムワークです。彼は楽曲の情感の変化に合わせて、フィルインのタイミングや音量バランスを微調整し、歌詞の内容を音楽的に補強しています。
1980年代ポップメタルの金字塔
「The Final Countdown」は、1980年代のポップメタル(またはグラムメタル)ムーブメントの代表作として位置づけられます。この時期のハードロックは、1970年代のプログレッシブロックやヘビーメタルから発展し、よりメロディアスで親しみやすい楽曲構成を特徴としていました。

アメリカではBon JoviやDef Leppard、ヨーロッパではScorpionsやWhitesnakeといったバンドが活躍していましたが、Europeは北欧独特の叙情性とポップセンスを融合させた独自のスタイルを確立しました。「The Final Countdown」は25カ国でナンバー1を獲得し、このムーブメントの頂点を飾る作品となりました。
映画的スペクタクルとしての楽曲体験
「The Final Countdown」を聴く体験は、単なる音楽鑑賞を超えて、映画的な物語体験となっています。楽曲全体が一つの壮大なドラマとして構成されており、リスナーは宇宙船の乗組員として、地球を離れる瞬間から金星到達までの旅程を追体験することができます。
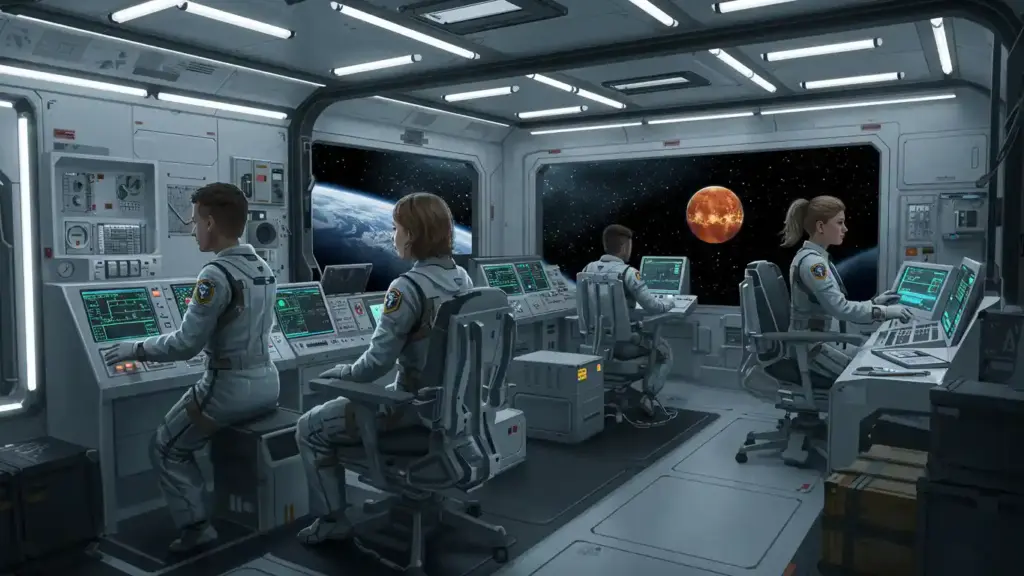
イントロのシンセサイザーファンファーレは発射台でのカウントダウン、ヴァース部分は宇宙船内での静かな瞑想、そして「It’s the final countdown」の大合唱は宇宙空間での歓喜の爆発として機能しています。ホーグランドのドラムは、この映画的構成において効果音的な役割も果たし、宇宙船のエンジン音や船内の機械音を暗示する音響効果を生み出しています。
現代への影響と普遍的魅力
リリースから約40年が経過した現在でも、「The Final Countdown」は世界中のスポーツイベントや祝典で使用され続けています。この楽曲の持つ祝祭性と高揚感は、時代や文化の違いを超えて人々に訴えかける普遍的な力を持っています。
イアン・ホーグランドの創り出したドラムパターンは、現代のロックドラマーたちにも大きな影響を与え続けています。彼の演奏スタイルは、テクニカルな正確性と音楽的表現力の理想的なバランスを示す見本として、多くのドラム教則本でも取り上げられています。
YouTubeの公式ビデオでは、1980年代特有のビジュアルスタイルと共に、バンドメンバーの若々しいパフォーマンスを見ることができます。特にホーグランドのドラムプレイは、この映像を通して彼の音楽的センスの高さを視覚的に確認することが可能です。



コメント