■【エリック・クラプトン】について、詳しくはこちらをご覧ください。・・・・
➡エリック・クラプトン物語 ― 栄光と試練のギターレジェンド!
🎸【エリック・クラプトン編】第6位『White Room』です。
第6位は、クリーム時代の代表曲。『White Room』です。60年ほど前の楽曲ですが、今でも新鮮なで強烈なインパクトを与えてくれます。またクラプトンのスタート時の雰囲気が理解できる一曲です。
超約
孤独な部屋と暗い街の中で、
別れと再会を繰り返す愛の記憶を見つめている。
駅での別れ、心に残る影、癒えぬ痛み。
彼女の瞳の中には、まだ過去の夜が生きている。
そして彼は、その影と共に静かに眠る。
🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
最初の動画のサムネは、僕が持っていたアルバムと同じです。もう手元にはないですが、懐かしいジャケットとです。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
Provided to YouTube by Rarity Music
Cream – “White Room”
(Original release © 1968 Polydor Records / from the album Disraeli Gears)
2行解説
クラプトン、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカーによるスーパー・トリオ〈クリーム〉の代表曲。
印象的なリフと陰影あるメロディが、サイケデリック期のロックを象徴する名演です。
🎬 公式動画クレジット(ライブ音源)
Provided to YouTube by Live Aid
Eric Clapton – “White Room (Live Aid 1985)”
(From Live Aid, performed July 13, 1985 at John F. Kennedy Stadium, Philadelphia, USA)
📖 2行解説
1985年のチャリティーイベント〈ライブエイド〉で披露された『White Room』の名演。
フィル・コリンズがドラムを務め、クラプトンが熱くギターを弾き鳴らした歴史的ライブ映像です。
◆ドラムはフィルコリンズが叩いています。これまたすごいことです。
リリースと基本情報
1968年、クリームが発表した2枚組アルバム『Wheels of Fire』のオープニングを飾るのが『White Room』です。
ジャック・ブルースが作曲し、詩人ピート・ブラウンが詞を担当。エリック・クラプトンはギターで全体の色彩を統べています。
この曲は、全米6位・全英28位を記録し、クリームのキャリア後期を象徴する作品として知られています。
同アルバムの中でも特に“構築美”が際立っており、白と黒、光と影、静と動の対比が音と詞の双方で表現されています。クラプトンが弾くワウペダルのギターリフは、サイケデリックの象徴として語り継がれていますが、この曲の本質は「別れを受け入れる静かな視線」にあります。

詩と映像が交錯する世界
“白い部屋”という心象風景
曲はこう始まります。
“In the white room with black curtains near the station”
(駅のそば、黒いカーテンのかかった白い部屋で)
たったこの一行で、舞台が見えるようです。
「白」は無垢であり、同時に空虚。そこに「黒いカーテン」がかかることで、閉ざされた感情の部屋が生まれます。この部屋には太陽の光が届かず、外界とのつながりを失ったような孤独感が漂っています。

ブラウンの詩は具体と抽象のあいだを自在に行き来し、聴く者に**“想像する余地”**を残します。駅という移動の象徴と、白い部屋という静止の象徴が対比されることで、「離別」のテーマが暗示されるのです。
旅立ちの情景と、感情の“反射”
“I’ll wait in this place where the sun never shines”
(陽の当たらない場所で、僕はここに留まる)
この一節には、単なる物理的な「日陰」ではなく、感情の冷却という意味が込められています。
相手を責めることも、追いかけることもせず、ただ“光のない場所”で心を鎮める――それは失恋や喪失のあと、人が無意識にとる防御反応に近いものです。
クラプトンのギターは、この感情の「抑制」を見事に支えています。
音数を減らし、あえて“語らない”フレーズを選ぶことで、詞の余白を広げているのです。彼の音は泣かず、しかし確実に痛みの温度を残します。
音よりも静寂が語る
ミュートされた激情

当時のクリームは、ブルースの枠を越えた即興演奏で知られていましたが、『White Room』ではその爆発力を抑え、内向的な緊張を持続させています。
ドラムのジンジャー・ベイカーは、あえて空白を多く取り、タムの連打で列車のリズムを模すように演出。
ジャック・ブルースのベースは流れるようでいて、常に“重力”を感じさせます。
クラプトンのギターは、まるで車窓を流れる街灯のように、点滅しながら消えていきます。
ひとつの音が鳴るたびに、空間が深く沈み、聴き手は無言の物語を見せられているような感覚に陥ります。
“影が自分から逃げる場所”
“Where the shadows run from themselves”
(影が自分自身から逃げ出す場所で)
この表現は、ピート・ブラウンの詩的センスを象徴する一節です。
影が自分から逃げる――つまり、自我の崩壊です。
人が誰かとの関係を失い、自己を見つめ直すとき、「自分」という輪郭すら曖昧になる。その瞬間の心理を、たった一行で表しているのです。
クラプトンのギターはこの行に重なるように、ワウペダルで波打つような音を描きます。
それは“逃げる影”を音で可視化するようであり、サイケデリックな演出でありながら、実は非常に人間的な痛みを内包しています。

“詩人”と“職人”の共犯関係
作詞家ピート・ブラウンは、かつて「この曲は実際に自分が住んでいた白い部屋がもと」と語っています。
黒いカーテン、駅の騒音、夕暮れの光線。すべてが現実の情景でした。
しかしその現実を、彼は抽象のレベルまで引き上げて**“心の部屋”として再構築します。
そこにクラプトンが音を重ねたとき、現実と幻想のあいだに一枚の薄膜のような世界**が立ち上がったのです。
音が語る「去り際の美学」
リズムと構成の妙
『White Room』の魅力のひとつは、リズムの変化にあります。
曲の最初は少し変わった5拍子で始まり、どこか不安定で、ゆっくり歩き出すような感覚があります。
やがて普通の4拍子に切り替わることで、少しずつ流れが落ち着いていきます。
このわずかな違いが、心の揺れや迷いを感じさせます。
まるで列車が動き出す前の静けさと、別れの直前に息をのむような瞬間が、音の中で重なっているかのようです。

ギターはワウペダルで音を歪ませながらも、フレーズの長さを極力抑えています。
クラプトンはこの時期、技巧ではなく節度ある情感を追求していました。
サイケデリックの中で「派手に弾かない」という選択こそが、彼らしい逆説的な主張だったのです。
ボーカルの演出と心理的距離
ジャック・ブルースの歌声は、熱量と冷静さのあいだにあります。
まるで語り手が“感情を再現する”のではなく、“記憶を再生している”ように聴こえるのです。
“You said no strings could secure you at the station.”
(君は駅で、どんな糸にも縛られたくないと言った)
この一節には、束縛を拒む相手と、それを見送る側の静かな理解がにじみます。
ブルースの声には悲壮感よりも、覚悟のような透明さが宿っています。
それは“関係を手放すことで残るもの”を描く、成熟した愛のかたちです。
1968年という時代の空気
ロンドンの夜明けと終焉
『White Room』が生まれた1968年は、世界が大きく揺れていた年でした。
ベトナム戦争、学生運動、公民権運動――音楽が社会の影響を強く受けていた時代です。
しかしこの曲には、政治的メッセージはほとんど見当たりません。
代わりに映し出されているのは、個人の孤立と再出発。
時代の騒音を外に置き、内面の物語を静かに描いた点に、クリームの成熟が見えます。

ロンドンのサイケデリック文化がピークを迎える中、クラプトンはすでに“次の段階”を見据えていました。
ブルースのルーツに戻りつつ、感情を抑えた表現を模索していた彼にとって、『White Room』は過渡期を象徴する楽曲でした。
ライブ版の再解釈
クリームの再結成公演(2005年ロイヤル・アルバート・ホール)でも、この曲は演奏されました。
テンポはやや遅く、クラプトンのギターも低域を強調した穏やかな音色に変化しています。
30年以上の時間を経て、この曲は“別れ”から“回想”へと意味を変えました。
かつては激情の中で弾かれたリフが、今は人生の輪郭を確かめる線描に聞こえます。
年月を経て初めて理解できる痛み――それを音で伝えるのが、熟練のクラプトンらしさです。
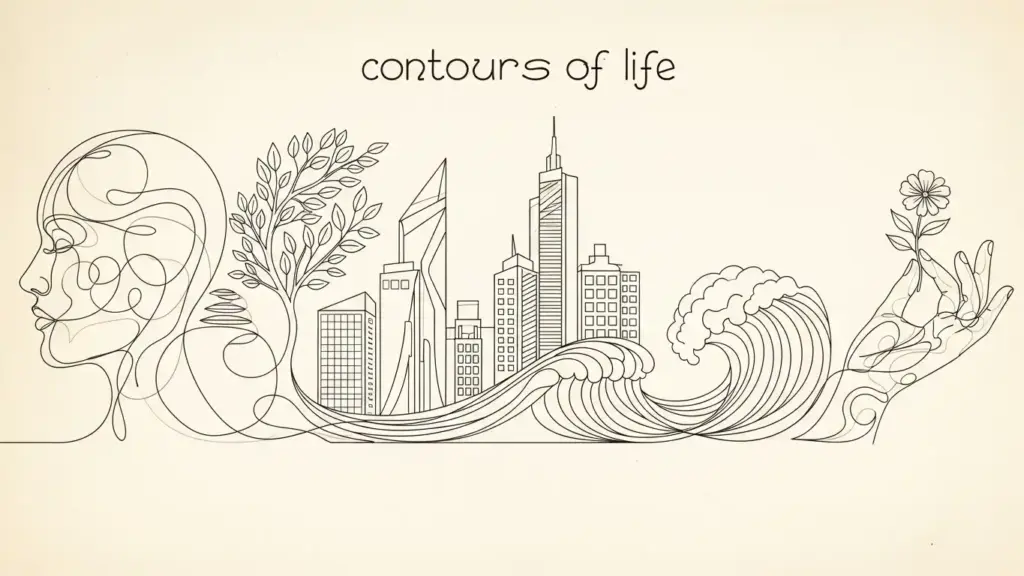
“White Room”が残したもの
無言の表現力
この曲を語るとき、どうしても注目されるのは詩と音の緊密な関係ですが、実際の魅力は“声にならない部分”にあります。
旋律の間に差し込まれる休符、ギターの切れ際、そしてリスナーが想像で補う空間。
それらが組み合わさって、ひとつの“静かなドラマ”を形づくっています。
クラプトンはこの時点で、既に「弾かない勇気」を身につけていました。
『White Room』のギターは、音の洪水ではなく、感情の残像を描く筆跡のように響きます。
それがこの曲を、半世紀を経ても色あせない名曲にしています。
終わりに:沈黙の中の確信
“I’ll stay in this place where the shadows run from themselves.”
(影が自分から逃げていくこの場所に、僕は留まる)

このラストラインは、諦めではなく再生の一歩を意味しています。
関係が終わっても、人は記憶の中で何度も立ち上がる。
“白い部屋”とは、過去を整理するための心の空間であり、同時に新しい自分が生まれる場所でもあります。
クラプトンのギターが最後にわずかに上昇する音を描く瞬間、聴き手はそのことに気づくのです――
この曲は「終わり」ではなく、「始まり」だったのだと。



コメント