■歴史【前編】北の大地から生まれたハーモニー(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
ふきのとう 僕の勝手なBest30 第22位は「五色のテープ」です。
ふきのとう 僕の勝手なBest30 第22位は「五色のテープ」。
ふきのとうを知らない人には、もしかしたらこれまで紹介した曲の違いも、良さも伝わってないかもしれません。ここまで9曲紹介してきましたが、気づいたことがあります。
僕の中では、数多くある、ふきのとうの楽曲の中のBest30(すなわち選ばれし者たち!)だとしても、他のミュージシャンの曲に比べるとどれも目立たない曲ばかり選曲してきたようです。
どの曲の解説にも必ず出てくる言い回しですが、その存在感のなさ、日常の延長線上にある情景・・・これが「ふきのとう」なんです。やさしくて、穏やかで、ただただやさしくて・・・・
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『春雷』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
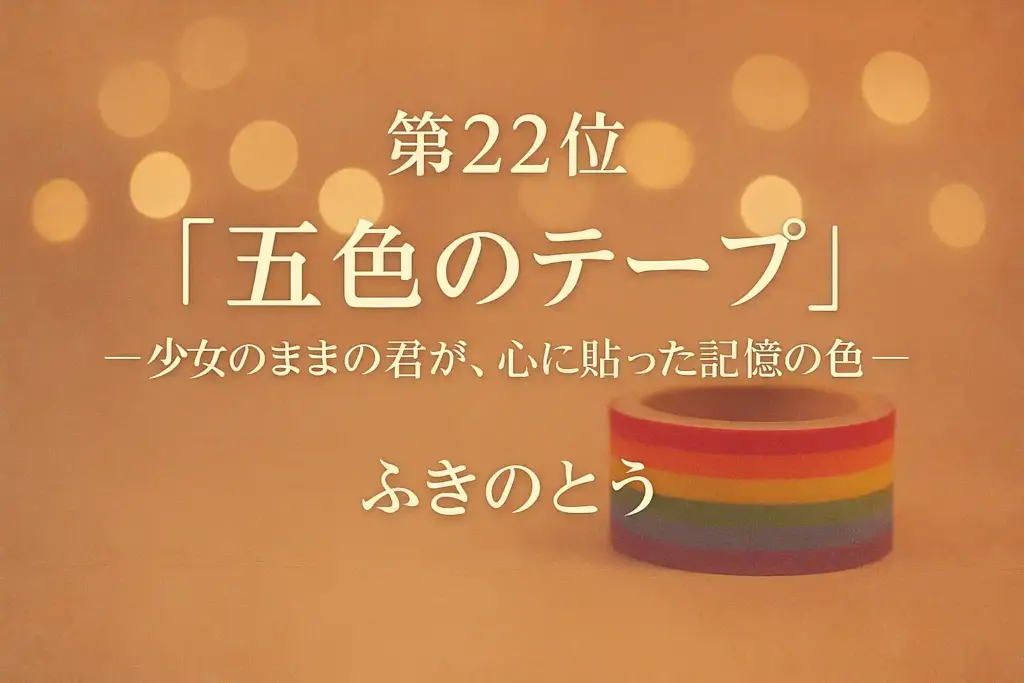
🎥【公式ライブ映像】
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
公開日;2015/02/07
歌手:ふきのとう
タイトル:五色のテープ
作詩・作曲:山木康世/編曲:ふきのとう
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。 ※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
色と想いが舞う――『五色のテープ』という楽曲
1979年7月21日にシングルとしてリリースされた『五色のテープ』は、ふきのとうの叙情世界を象徴する一曲です。港を離れる船、それを見送る人々、風に舞う色とりどりのテープ。そうした視覚的な描写を通して、“別れ”という出来事にやさしく寄り添う世界観が描かれています。

当時のオリジナルアルバムには収録されなかったにもかかわらず、この曲は単体で強い印象を残し続け、多くのリスナーの記憶に深く根づいてきました。誰の人生にも重ねられる「風景のような歌」として、現在でも静かな支持を集め続けています。
ふきのとうの楽曲には、しばしば「感情を風景化する」表現が見られますが、『五色のテープ』はまさにその真骨頂ともいえる作品です。情景が浮かぶのではなく、“感情そのものが情景を生む”という逆転の発想。これにより、曲の印象は聴くたびに変わり、時とともに熟成されるような魅力を持っています。
『五色のテープ』はどのアルバムにも収録されなかった?
実は“シングルのみ”という異色の存在
実はこの曲、1979年にリリースされた他の作品(『人生・春・横断』など)にも含まれておらず、当初は単独シングルとしてのみ展開されていました。
この“アルバム未収録”という扱いは、結果的に『五色のテープ』の独立した印象を強めることになりました。歌詞・旋律・構成すべてに物語性が凝縮されており、「アルバムの流れ」ではなく「1曲の映画」として記憶されている方も多いのではないでしょうか。

それでも愛され続けている理由
アルバム未収録ながら、ファンの間では「代表作のひとつ」として認識されています。
その後、1980年代以降に発売されたベスト盤やアンソロジーCDにはようやく収録されるようになりましたが、「初出当時にはアルバム未収録だった」という事実は、いまもファンの間で語り継がれています。このような例は、ふきのとうのディスコグラフィの中でも決して多くはなく、ある意味でこの曲の希少性や独立性を示すエピソードとなっています。
音楽的アプローチ――ふきのとうらしい“間”の使い方
“間”と“余白”の美学
『五色のテープ』のアレンジには、ふきのとうらしい“間”と“余白”の美学が息づいています。イントロから終始穏やかなテンポで進行し、派手な転調やドラマチックな展開は一切ありません。しかし、それこそがふきのとうの強みなのです。
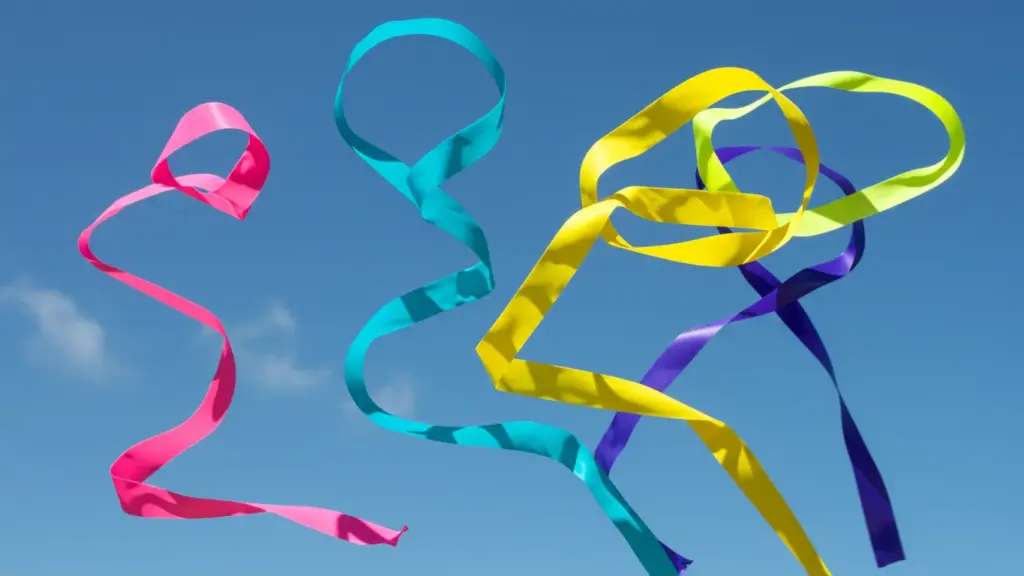
また、サビに向かって感情が高まっていく構成ではなく、あえて感情のピークを抑えて淡々と進行させることで、逆に“じんわりと胸に残る”印象を与えています。これは、いわゆる「名バラード」とは異なるアプローチですが、ふきのとうが長く愛される理由のひとつでもあります。
音楽的技巧で驚かせるというより、自然体のままで聴く人の記憶を呼び起こすという姿勢。これはデビュー当初から変わらぬ彼らの持ち味であり、『五色のテープ』では強く感じられる要素といえるでしょう。
聴き手の心に残る“余韻”こそが、この曲の核心
静けさの中に宿る深い感動
歌詞は決して複雑ではなく、むしろ淡々と日常の風景を描写しています。
しかしその裏側に潜む感情の層が深いため、聴き終えたあとに心が静かに波打つような感覚を生むのです。

技巧ではなく“余白”による共鳴
このような心象の余韻は、技巧的な構成や派手な演出ではなかなか得られないものです。
むしろ、語りすぎないことで生まれる“余白”が、聴き手の心に広がるのです。
『五色のテープ』もまさにその一例であり、結末や感情の整理をあえて歌詞内で語りきらないことで、聴き手の記憶や人生経験が、自然とその音楽に重なっていきます。
“誰にでもある過去”が蘇る瞬間
個人の記憶を優しく引き出す音楽
たとえば、学生時代に離れ離れになった友人。駅のホームで見送った家族。
あるいは、もう二度と会えなくなった大切な人……。

『五色のテープ』は、こうした“誰にでもある過去”をそっと呼び覚ましてくれます。
それは、歌詞の中で明確に語られていないからこそ可能となる作用です。
「五色のテープ」とは何を意味するのか?
別れの場面を彩る象徴的なアイテム
タイトルにある「五色のテープ」は、聴き手に強烈な視覚イメージを与える、非常に象徴的なフレーズです。1970年代から1980年代にかけて、港での出航風景では、岸壁と船の間に紙テープを投げ合う光景が各地で見られました。

その中でも、五色のテープは“別れの華やかさ”と“寂しさ”を同時に演出する道具として、特別な意味合いを持っていたのです。
絆を可視化する紙テープの力
この紙テープは、旅立つ人と見送る人をつなぐ“絆”の象徴でもありました。
遠ざかっていく船と岸辺を結ぶ一本の線——それが切れたとき、物理的にも心理的にも「別れ」が訪れるのです。
五色に込められた精神的な象徴性
ふきのとうが意図した可能性
ふきのとう自身がどこまで文化的背景を意識していたかは定かではありません。
しかし、『五色のテープ』というタイトルが単なる装飾ではなく、人と人との間にあった記憶やつながりを可視化する役割を担っていることは間違いありません。
テープが切れる瞬間に込められた感情のピーク
“別れ”の演出としてのラストシーン
楽曲の後半では、「テープがちぎれる」という描写が感情のクライマックスとして表現されます。
これはまさに、儀式的な別れの象徴であり、リスナー自身の“別れの記憶”を呼び起こすトリガーとして機能しているのです。

結びの言葉をあえて曖昧に留めたことで、聴き手は自らの経験と重ね合わせながら、静かな余情に浸ることができます。それがこの曲に、単なる叙情歌ではない“深み”をもたらしているのです。
どこか懐かしく、しかし決して古びない
「懐かしさ」の本質は、感情の記憶にある
『五色のテープ』を聴いて、「懐かしい」と感じる人は少なくありません。
しかしその感情は、単に1970年代の楽曲であるという“年代的懐古”ではなく、心の奥底に眠っていた感情が、曲によって静かに呼び起こされた結果だといえるでしょう。
ふきのとうが描く風景は、あくまでも日常の延長にあるもの。だからこそ、個人の経験や記憶と結びつきやすく、聴く人それぞれに異なる“懐かしさ”を届けてくれます。
世代を超えて届く普遍性
この曲には、特定の時代や場所を想起させる固有名詞が一切登場しません。
たとえば「東京」や「昭和」などの記号的ワードは用いられず、あくまで“誰にとっても我がこと”と感じられるような普遍的描写で貫かれています。

そのため、当時をリアルタイムで知らない若い世代であっても、曲を聴けば自然と情景が頭に浮かぶ。「個人的な記憶」が「集団的な情感」に昇華されていく構造が、この作品の底力なのです。
時代に流されないサウンドと語り口
現代のポップソングと比べれば、確かに派手さやフックは少ないかもしれません。
しかし、聴き込むほどに味わいが増すような魅力が、ふきのとうの持ち味。『五色のテープ』もまた、そうした“遅れて届く感動”を静かに届けてくれる一曲です。
ふきのとうが紡いだ、“別れ”の肯定
穏やかで前向きな別れを描くという選択
ふきのとうはこれまで、数多くの“別れ”を主題にした楽曲を発表してきました。
その中でも『五色のテープ』は、別れを悲壮感ではなく、静かな肯定として描いた一曲として際立っています。
1970年代の「別れ歌」とは異なる、静かな哲学
1970年代の音楽シーンには、「センチメンタルな別れ」を大仰に歌い上げる作品も多く存在しました。そうした中で、ふきのとうのスタンスは明らかに異質でした。
『五色のテープ』には、「悲しいけれど、それでもこの別れを肯定したい」という優しい眼差しが通底しています。まるで、「人生には別れもあるけれど、それがあるからこそ前に進めるんだよ」と語りかけてくれるようです。

いま、改めて聴き直す価値がある理由
“別れ”の実感が薄れた時代にこそ求められる歌
現代社会では、SNSやメッセージアプリの普及により、別れの形も大きく変化しました。
かつてのように、真正面から感情を交わし、別れを見送る機会は減り、“自然消滅”に近い曖昧な別れが増えているといわれています。
そんな時代において、『五色のテープ』のように、多くを語らずとも深い想いがにじむ“別れの歌”は、むしろ新鮮な響きを持ちます。
この曲には、かつて当たり前だった“関係性の温度”が、しっかりと刻まれているのです。
今だからこそ、改めて聴いてみたい
これまでこの曲に触れてこなかった方も、あるいは昔に聴いたきりだった方も、今あらためて耳を傾けてみることで、新たな感情の扉が開かれるかもしれません。
日常の喧騒の中で忘れていた誰かの顔、交わした言葉、別れ際の沈黙——
それらが『五色のテープ』の旋律とともに、静かに心の中によみがえる。
そしてその時、あなたの心にも、きっと“あの五色のテープ”が、風に揺れてたなびいていることでしょう。




コメント