■【レッド・チェッペリン】について、詳しくはこちら・・・・➡ 🎈(Zeppelin)
🎧 音声で聴く
この記事は、約3分の音声ナレーションでもお聴きいただけます。
文章の流れに沿って、第3位『Kashmir』が持つ、重くうねるリズムと悠久の広がりをたどります。
読む前に、または読み終えたあとに、音でもぜひお楽しみください。
JP 日本語ナレーション
US 英語ナレーション
🎸【レッド・チェッペリン編】第3位は・・・・
いよいよチェッペリンのBest25もあと3曲まで来ました。
そして、僕が勝手に第3位に選んだのは、『Kashmir(カシミール)』です。
彼らのキャリアにおいて、『最も壮大』という形容がこれほどまでに似合う楽曲は、他にありません。
僕がアパートで、ステレオから流れるこの曲を初めて聴いたとき、感じたのは「畏怖」に近い感情でした。それは、僕たちが知っているロックという音楽の「境界線」が、砂塵の向こう側に消えていくような感覚です。

良い時も悪い時も、この1年3か月のブログ更新を支えてきたのは、あの大学時代の「音楽があればどこへでも行ける」という純粋な確信でした。第5位『Good Times Bad Times』が若さゆえの宣戦布告であり、第4位『Achilles Last Stand』が限界状況での疾走だったとすれば、この第3位『Kashmir』は、もはや時間や空間の概念さえも超越し、僕たちを永遠という名の迷宮へと誘い込みます。
【超約:砂塵の彼方の永遠】
砂漠を貫く一本の道。立ち上る熱気と、終わりなき反復。
上昇し続ける旋律が、聴き手の意識を日常から切り離し、
物理的な「音」を、精神的な「祈り」へと昇華させる叙事詩。
それは、ロックが到達した、最も気高く、最も神秘的な地平です。
🎥 まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
楽曲名:Kashmir(カシミール)
アーティスト:Led Zeppelin
収録アルバム:Physical Graffiti(1975年)
作詞・作曲:Jimmy Page / Robert Plant / John Bonham
音源:リマスター版(公式オーディオ)
2行解説
8分半に及ぶ、ロック史に燦然と輝く金字塔。中近東風のスケールを用いた重厚なリフと、オーケストレーションが織りなす圧倒的なスケール感は、ZEPというバンドの底知れなさを物語っています。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
「Kashmir(カシミール)」
演奏:Led Zeppelin
収録公演:Celebration Day(2007年 アーメット・アーティガン追悼公演/ロンドン O2アリーナ)
© Led Zeppelin / Swan Song Records
公式YouTubeチャンネル公開映像
2行解説
2007年の一夜限りの再結成公演で披露された「Kashmir」の公式ライブ映像。
重厚なリフとオーケストレーションが融合した名演で、円熟したバンドの迫力が記録されている。
💡 ちょっとしたチップス
この2007年のステージにおいて、ひときわ胸を熱くさせるのは、背後で地鳴りのようなビートを刻むドラマーの存在です。彼は、1980年に急逝したジョン・ボーナムの愛息子、ジェイソン・ボーナム。
『Kashmir』は、父ジョン・ボーナムがそのキャリアにおいて「最も重厚で、最も独創的なリズム」を刻んだ、いわば彼の代名詞とも言える楽曲です。その巨大な椅子に息子が座り、父譲りの重戦車のようなグルーヴを叩き出す姿には、単なる技術の再現を超えた「血の継承」という名の凄まじい熱量が宿っています。
砂塵を巻き上げるようなあの上昇リフを支えるのは、やはりボーナムの血を引く者でなければならなかった――。そう確信させるほどの圧倒的な説得力が、この長尺の熱演を支えています。
それと、ロバートプラントも、この時60才直前ですが声質に衰えを感じません。流石です。
究極の反復がもたらす「トランス状態」の正体
この『Kashmir』を聴き始めた瞬間、僕たちの耳を支配するのは、執拗なまでに繰り返されるあの上昇するリフです。

3/4拍子と4/4拍子の幸福な衝突
この曲の「異質さ」を音楽的に解剖するなら、まず特筆すべきはポリリズム(複合リズム)の妙でしょう。
ジミー・ペイジが奏でるギターリフは、3拍子を基調としながら、階段を一段ずつ上るように上昇を繰り返します。それに対し、ジョン・ボーナムのドラムは、一歩も譲ることなくどっしりとした4拍子のビートを刻み続ける。この「3」と「4」が複雑に絡み合い、ズレながらも一点で合流する構造が、聴き手の脳内に奇妙な「浮遊感」と「催眠効果」をもたらすのです。
部屋で、タバコの煙を眺めながらこの曲に身を浸していた僕は、その心地よい「ズレ」の中に、まどろんでいました。単にリズムに乗るという体験を超え、宇宙の脈動と同期するような、一種のトランス状態に近いものでした。(もちろん、盛ってます!)

上昇し続ける階段という「視覚的」な音
この曲のリフには、終わりがありません。上り切ったかと思えば、また次の段が足元に現れる。この「永遠の上昇感」こそが、カシミールという曲を「静止した巨大建造物」のように感じさせる理由です。
多くのロック曲が、サビに向かってエネルギーを発散させるのに対し、この曲は内側へとエネルギーを凝縮し続けます。爆発するのではなく、ただそこに、重厚な質量を持って存在し続ける。この圧倒的な「プレゼンス」こそが、ZEP(レッド・チェッペリン)がトップ3という聖域に持ち込んだ、最大の武器なのです。

砂漠の風が運ぶ「精神の逃避行」
『Kashmir』というタイトルを冠しながら、この曲の着想が得られたのはインドのカシミール地方ではなく、モロッコの砂漠を縦断する果てしないドライブの最中であったという事実は、この曲の本質を雄弁に物語っています。

ロバート・プラント:旅人の独白
ここで響くロバート・プラントの声は、これまでのどの楽曲とも異なる、神秘的でどこか超越的な響きを湛えています。
「Oh, let the sun beat down upon my face(太陽に顔を焼かれようとも)」という一節。それは、物理的な旅の記録であると同時に、内面的な「真理への渇望」でもありました。
ヴォーカルが描く「色彩のない情熱」
プラントの歌唱は、決して感情を爆発させることはありません。むしろ、あの強固なリフの反復に身を委ね、風に乗って流れる砂のように、静かな、しかし確かな重みを持って響きます。この「抑制された情熱」こそが、カシミールという楽曲に、他のロック・ナンバーにはない「宗教的なまでの崇高麗さ」を与えているのです。

音響の巨大建築物:ストリングスとブラスの機能美
この曲を「壮大な叙事詩」に仕立て上げているのは、緻密に計算されたオーケストレーションです。
ロックと管弦楽の「幸福な共犯関係」
多くのロック・バンドがストリングスを導入する際、それはしばしば楽曲をドラマチックに盛り上げるための「装飾」に留まります。しかし『Kashmir』において、ストリングスとブラスは楽曲の「骨組み」そのものです。
あの下降するブラスのフレーズと、上昇するギターリフが交差する瞬間、音の空間には巨大な伽藍(がらん)が姿を現します。ジミー・ペイジはこの曲で、音を時間軸で流すのではなく、空間の中に「配置」することに成功しました。

ジョン・ボーナム:地響きを立てる「巨人の歩み」
そして、その巨大な建築物を支える基礎石となっているのが、ジョン・ボーナムのドラミングです。
この曲での彼のドラムは、驚くほどシンプルで、それゆえに圧倒的です。一切の装飾を排し、ただひたすらに重い一撃を打ち下ろす。その響きは、もはやドラムという楽器の枠を超え、巨大な生命体が大地を踏みしめる「鼓動」のように聴こえてきます。
なぜ、この曲が「第3位」なのか
25位から始まったこの思索の旅において、第3位という位置は、ZEPというバンドが到達した「完成された美」の象徴です。
完璧なるバランスの頂点
これまでの順位で見てきたように、彼らはブルース、フォーク、ハードロックといった多様な要素を吸収し、進化を続けてきました。カシミールという広大な大地の上で、それらの要素がこれまでにない形で混ざり合い、ロックという既存の枠組みを静かに塗り替えていく。それは、彼らがさらなる高みへと向かうための、極めて強固な足がかりでもあります。
この曲を聴くとき、僕たちは彼らがイギリス人のロック・バンドであることを忘れます。そこにあるのは、国籍も時代も超越した、純粋な「音の意思」そのものです。

終わりに:残された「二つの真実」へ
第3位、『Kashmir』。 この巨大な音の迷宮を通り抜けた今、僕たちの前にはもう、二つの答えしか残されていません。
饒舌な解説は、かえってその輪郭をぼやけさせるだけかもしれません。ここから先は、彼らがロックという表現に刻みつけた「核心」そのものが姿を現します。
次なる順位、第2位。 美しさと狂気が、これ以上ない精度で同居する不朽の名曲。 そこには、僕たちがロックに求めてやまない「救い」と「絶望」のすべてが詰まっています。
(第3位『Kashmir』 完)
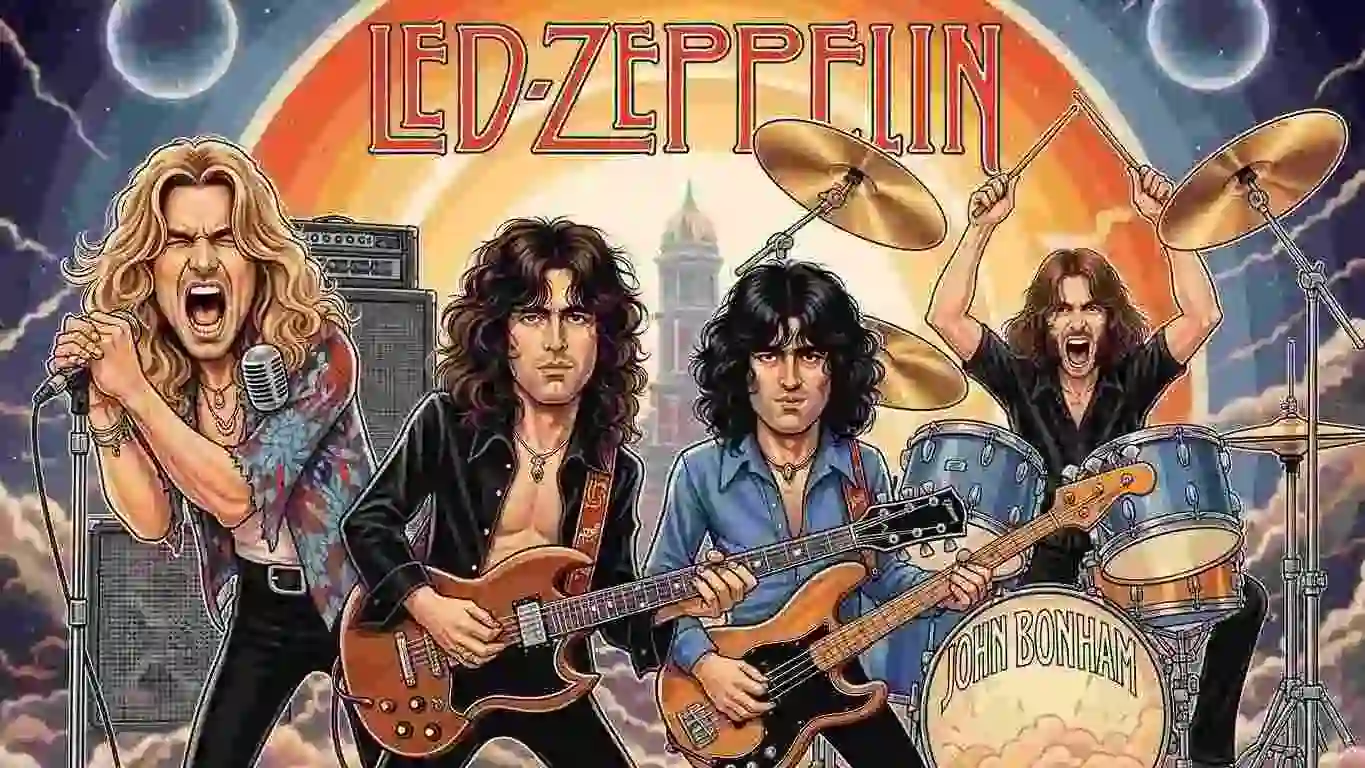



コメント