■【レッド・チェッペリン】について、詳しくはこちら・・・・➡ 🎈(Zeppelin)
🎧 音声で聴く
この記事は、約3分の音声ナレーションでもお聴きいただけます。
文章の流れに沿って、第2位『D’yer Mak’er』が持つ、孤独と自由が溶け合う独特の空気感をたどります。
読む前に、または読み終えたあとに、音でもぜひお楽しみください。
🇯🇵 日本語ナレーション
🇺🇸 英語ナレーション
🎸【レッド・チェッペリン編】第2位は・・・・
1973年の傑作『Houses of the Holy』に収録された『D’yer Mak’er』です。(僕はずっと「ディジャメイクハー」と読んできました。一般的な日本語表記は「ダイアー・メイカー(ジャメイカ)」が多いようです。)
第3位、あの『Kashmir(カシミール)』という巨大な伽藍を通り抜けた後。 僕が第2位に選曲したのは、それまでの重厚な空気とは対極にある、軽やかなリズムを纏った一曲です。
Led Zeppelinというバンドが持つ、ある種の「遊び心」が結晶化したようなこの曲。しかし僕にとって、これは単なる変化球ではありません。どれほど多くの名曲を通り過ぎても、この「愛すべき異端」のリズムだけは、常に僕の心の最も深い場所で鳴り続けてきました。

切ないメロディと、どこか場違いなほど明るいレゲエのリズム。 その奇妙な同居の中に、言葉にできないほどの孤独と、救いのような自由を感じるのです。
なぜ、この曲が頂点のすぐ隣、第2位なのか。 その理由を、理屈ではなく、ただ僕の「好き」という熱量だけで紐解いてみたいと思います。
【超約:置いていかれた者の挽歌】
行かないでくれ」というあまりにも青臭い懇願。 陽気なリズムを借りて、かろうじて保たれている理性の境界線。 去りゆく背中を前にして、言葉にならない叫びをレゲエの拍子に託す。 それは、強靭なバンドが見せた、最も繊細で、最も身勝手な愛の形です。
🎥 まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
楽曲名:D’yer Mak’er(ディジャ・メイカ)
アーティスト:Led Zeppelin
収録アルバム:Houses of the Holy(1973年)
作詞・作曲:Jimmy Page / Robert Plant / John Paul Jones / John Bonham
音源:リマスター版(公式オーディオ)
2行解説
ゼップが当時のレゲエ・ムーブメントを彼ら独自の解釈で取り込んだ異色作。ジョン・ボーナムの重厚なドラムと、ロバート・プラントのどこか甘く切ないボーカルが、不思議な化学反応を起こしています。
■ 聖なる館に差し込んだ、異国の光と影

1973年。レッド・チェッペリンは、前作までの「四つの記号」という神話性を一度脱ぎ捨て、より開放的で、かつ実験的なモードへと突入していました。その象徴こそが、アルバム『Houses of the Holy』です。
このアルバムの美しさは、完璧に統制された様式美ではなく、むしろ「はみ出した部分」にこそ宿っています。その最果てに位置するのが、この『D’yer Mak’er』です。
イントロが鳴り響いた瞬間、僕たちの耳を捉えるのは、ジョン・ボーナムの叩き出す、あの大胆で、どこか不器用なほどに力強いリズムです。通常、レゲエというジャンルは、音を削ぎ落とす「引き算の美学」によって成立します。ベースがうねるようなラインを描き、ドラムは軽やかに裏を打つ。それがジャマイカの乾いた空気感を生む定石です。
しかし、チェッペリンの、そしてボンゾのドラムは、その定石を真っ向から拒絶します。
あの大口径のドラムセットから放たれるのは、空間を埋め尽くすほどの残響と、岩盤を穿つような重厚な一打。彼は「レゲエを演奏」しようとしたのではなく、あくまで「レッド・チェッペリン」という巨大なモンスターの体躯のまま、異国のステップを踏もうとした。その結果生まれた、この「重すぎるレゲエ」こそが、この曲を唯一無二の存在にしています。

このぎこちなさ、この「ままならなさ」。それこそが、僕がこの曲に感じる人間味の正体なのです。
■ 孤独と自由が溶け合う、あの部屋の空気感
この曲を聴くとき、僕の視界には、ある「狭い部屋」の風景が鮮明に浮かび上がります。
そこは、世田谷区東松原の片隅。質素と呼ぶべき場所でしたが、当時の僕にとっては、音楽への渇望だけがすべてだった聖域でもありました。
これまで何度もこのブログで綴ってきたように、僕の歩みは常に、中学・高校時代から続く「飢え」とともにありました。1年3か月という月日、毎日言葉を紡ぎ続けてきた原動力も、その根底にある「渇望」に他なりません。
あの部屋の窓から差し込む西日の中で、僕は何度もこの曲のリズムに身を委ねました。
ロバート・プラントのヴォーカルは、50年代のドゥーワップを思わせる甘さと、消え入りそうな切なさを孕んでいます。
「Oh, oh, oh, oh, oh, oh…」
そのフレーズは、まるで去っていこうとする恋人への、無様で必死な懇願です。

歌詞の内容は悲痛そのものです。「行かないでくれ」「僕の愛を返してくれ」。その叫びが、あの独特の跳ねるようなリズムの上で踊っている。
この「感情の乖離」こそが、当時の僕にとってのリアリティでした。
人は、本当に深い孤独の中にいるとき、必ずしも重苦しい短調の曲を求めるわけではありません。むしろ、窓の外を流れる日常の無情な明るさと、自分の内側に沈殿する「どうしようもなさ」とのギャップにこそ、本当の自分が投影されることがあるのです。
一人の女性を想い、孤独と自由が入り混じった空気の中で、僕はこの「愛すべき異端」のリズムに救われていました。重厚な『Kashmir』では埋められなかった、個人の小さな隙間に、この曲はするりと入り込んできたのです。
■ 「ディジャ・メイカ」という名の、あまりに英国的な諧謔
この曲を語る上で避けて通れないのが、その奇妙なタイトルです。『D’yer Mak’er』。初見でこれを正しく発音できる者は少なく、ましてやその意味を一瞬で理解するのは困難です。
これは、当時の英国で親しまれていた古いジョーク、「My wife’s gone to the West Indies.(妻が西インド諸島に行ったんだ)」「Jamaica?(ジャマイカへ?/彼女を追い詰めたのか?)」という言葉遊び——「Did you make her?」のコックニー訛り——に由来しています。

この人を食ったようなタイトルこそが、レッド・チェッペリンというバンドの本質を象徴していると僕は思うのです。
彼らは、真実を語る際に、あえてそれを「冗談」というオブラートに包むことがあります。歌詞の中では、張り裂けんばかりの胸の内を吐露しながら、タイトルには軽いジョークを冠する。その照れ隠しのような、あるいは冷笑的なまでの客観性が、かえって曲の持つ「届かない想い」の切なさを際立たせます。
アパートの一室で、僕はこの言葉遊びの裏にある「ままならなさ」を噛み締めていました。一人の女性を想い、孤独と自由の狭間で揺れていたあの頃、ストレートな愛の歌よりも、こうした「ひねくれた優しさ」を持つ音楽の方が、ずっと僕の肌に馴染んだのです。
■ 完璧な調和を拒む、ジョン・ポール・ジョーンズの沈黙
音楽的な側面からこの曲を紐解くと、興味深い事実に行き当たります。バンドの音楽的頭脳であり、あらゆる楽器を操るジョン・ポール・ジョーンズ(JPJ)が、この曲を極めて嫌っていたというエピソードです。彼は、この曲のレゲエとしての完成度の低さ、そしてボンゾの「重すぎる」ドラムが、洗練されたアンサンブルを破壊していると感じていました。
しかし、その「不協和音」こそが、僕にとっての第2位の理由です。
もし、JPJが納得するような、完璧にレゲエの文法に則った洗練された楽曲に仕上がっていたら、この曲はこれほどまでに僕の心を揺さぶることはなかったでしょう。ジョン・ボーナムの、まるで地面を叩き割るような巨大な一打。ジミー・ペイジの、どこか投げやりで、それでいて繊細な裏打ちのギター。そして、ロバート・プラントの、祈るようなヴォーカル。

それらがバラバラのベクトルを向きながら、奇跡的に「チェッペリンという一つの生命体」として鳴っている。この危ういバランスは、計算して作れるものではありません。彼らが意図的に「崩そう」としたのではなく、全力で取り組んだ結果として「はみ出してしまった」という事実。その、制御不能なエネルギーの流出に、僕は人間の生きる姿そのものを見てしまうのです。
中高時代、まだ何者でもなかった僕が求めていたのは、教科書通りの美しさではありませんでした。自分の中にある、言葉にできない「澱(おり)」や、社会や日常からはみ出してしまう「違和感」。それらを肯定してくれるのは、いつだってこうした『D’yer Mak’er』のような「愛すべき異端」たちだったのです。
■ 聖域を通り抜けた先にある、僕だけの「真実」
第3位に据えた『Kashmir』。あの曲は、確かにロックの到達点であり、誰しもが跪くべき巨大な聖域です。しかし、どれほど素晴らしい建築物であっても、そこに住み続けることはできません。人はいつか、その重厚な伽藍を通り抜け、自分自身の体温が通う「個人の場所」へと帰らなければならない。
僕にとってのその場所が、この第2位という位置にあります。
この1年3か月、僕はブログを更新してきました。それはある種の修行のようでもあり、自分自身を削り出す作業でもありました。その歩みの中で、幾度となく「音楽を語ること」の意味を自問自答してきました。客観的な名盤ガイドを作るのか、それとも僕自身の魂の震えを記録するのか。
答えは、このランキングに現れています。
もし僕が客観的な評価だけを重視するなら、この場所に『D’yer Mak’er』を置くことはなかったでしょう。しかし、これは僕の物語です。僕が僕であるために、あの部屋で、あの孤独の中で、僕を救ってくれたこのリズムを、何よりも高く掲げる必要があったのです。
■ 渇望の果てに鳴り響くもの
「行かないでくれ」という切実な願いが、能天気なほど明るいリズムに乗せて繰り返されるフェードアウト。その終わりゆく音の中に、僕は今も、あの頃の自分を見つけます。

それらは今も僕の中で形を変え、こうして言葉を紡ぐ力となっています。このブログはここで終わるわけではありません。むしろ、この「異端」を正当な順位として受け入れたことで、僕の音楽の旅はさらに深い場所へと潜っていく予感があります。
完成された美しさよりも、歪んだ愛おしさを。
壮大な叙事詩よりも、震えるような一瞬の独白を。
『D’yer Mak’er』が僕に教えてくれたのは、正解のない世界で、自分の「好き」という感情だけを信じる強さでした。その確信を胸に、僕は第2位というこの高台から、いよいよ頂点の景色へと目を向けることになります。それを語るための準備は、ようやく整いました。
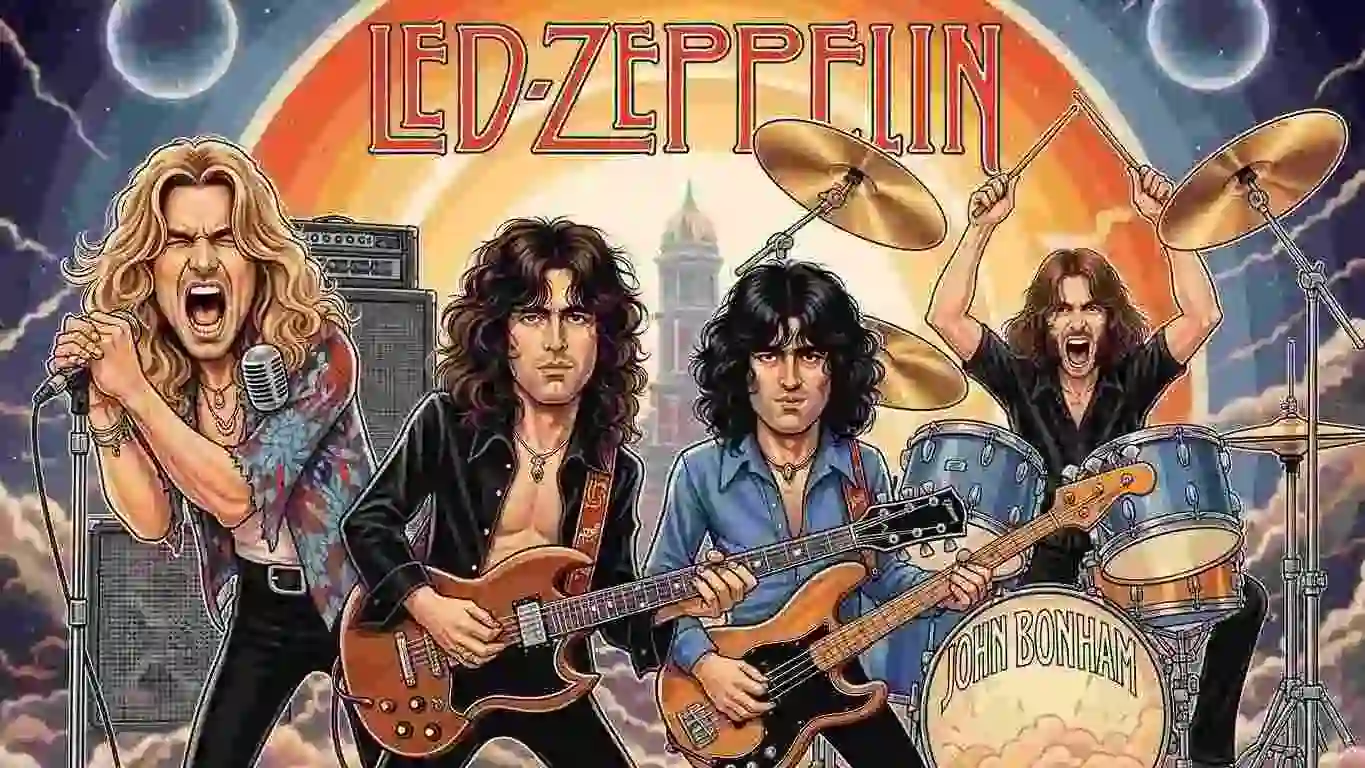



コメント