■【レッド・チェッペリン】について、詳しくはこちら・・・・➡ 🎈(Zeppelin)
※この記事は過去一番長い記事になっています。ナレーションは要約的役割にすぎませんので、ぜひゆっくりとでも、最後まで一読してください。感動の物語になっているはずです。
🎧 音声で聴く
この記事は、約3分の音声ナレーションでもお聴きいただけます。
文章の流れに沿って、この楽曲が持つ緊張感と途切れない推進力をたどります。
読む前に、または読み終えたあとに、音でもぜひお楽しみください。
🇯🇵 日本語ナレーション
🇺🇸 英語ナレーション
🎸【レッド・チェッペリン編】第1位は・・・・
第1位は「天国への階段」です。誰も驚かないはずです。この曲以外には考えられないからですね。
1971年発表の『Led Zeppelin IV』に収録された、8分2秒の叙事詩、『Stairway to Heaven(天国への階段)』。この曲について語ることは、もはやロックを語るという行為を超え、一つの神話の解釈に挑むようなものです。ついに、この場所へ辿り着いた。いや、「辿り着いてしまった」と言うべきかもしれません。
あまりにも有名で、あまりにも聴き古されたはずのこの旋律が、なぜ半世紀以上を経てもなお、僕たちの魂をこれほどまでに震わせるのか。それは、この曲が単なる「名曲」ではなく、人間の精神が到達し得る最高度の「構築美」そのものだからです。称賛の言葉をどれだけ積み上げても、この曲の放つ光を前にすれば、それはすべて霞んで消えてしまう。そんな無力感さえ抱かせる圧倒的な存在。それが、この曲なのです。

【超約:永遠へと続く黄金の梯子】
天へと続く階(きざはし)を求めるひとりの女性。
光り輝くものに心を奪われながら、
その向こうにあるほんとうの大切さには、まだ目を向けられずにいる。
風の気配、木々のざわめき、遠くから響く音の導き。
迷いと目覚めは、いつも心の内で静かに入れ替わる。
道はひとつではなく、ふとした気づきが進む先を変えていく。
やがてすべては響き合い、人はひとつの調べへと還っていく──そんなかすかな希望を残して。
静寂という種から芽吹き、一歩ずつ、しかし確実に光を目指して伸びていく音の蔦。
アコースティックの繊細さと、ハードロックの力強さが、完璧な黄金比で混ざり合い、
聴き手の魂を日常の重力から解き放つ、ロック史上最も美しい昇天の儀式。
それは、四人の天才が奇跡的に交差した瞬間にのみ許された、最高の芸術です。
🎥 まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
今回は公式映像を2本(音源/ライブ)、さらに特別枠としてトリビュート映像も1本用意しました。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
楽曲名: Stairway to Heaven(天国への階段)
アーティスト: Led Zeppelin
収録アルバム: Led Zeppelin IV(1971年)
作詞・作曲: Jimmy Page / Robert Plant
音源: リマスター版(公式オーディオ)
2行解説
ロック史上、最も多くラジオで流されたと言われる不朽の傑作。フォーク、ブルース、ハードロックを一本の線に繋ぎ合わせた、ポピュラー音楽の最高到達点の一つです。
🎬 公式動画クレジット(ライブ映像)
楽曲名:Stairway to Heaven(Live at Earls Court 1975)
アーティスト:Led Zeppelin
収録公演:Earls Court Arena(1975年5月25日/アールズ・コート公演)
映像作品:Led Zeppelin DVD(2003年)
2行解説
王者の余裕、という言葉が似合う時期の記録。巨大な会場を“ひとつの呼吸”で支配していく、ライブならではの時間の伸縮が味わえます。
1975年のアールズ・コート公演は、レッド・ツェッペリンが「現役の王者」として巨大会場を支配していた時期の記録です。ペイジのダブルネックが生む厚い響きは、会場全体をひとつの“伽藍”に変えていくようで、音が空間そのものを組み替えていく感覚があります。
さらに中盤でボンゾのドラムが入った瞬間、空気の密度が一気に変わる。静から動へ、そして熱へ――この曲が持つ“階段”の構造が、ライブでいっそう立体的に浮かび上がります。
公式トリビュート映像(2012年 ケネディ・センター名誉賞:Heart)
🎬 公式動画クレジット(授賞式トリビュート/公式映像)
楽曲名:Stairway to Heaven(Led Zeppelin Tribute)
演奏:Heart(Ann & Nancy Wilson)+ Jason Bonham(Drums)ほか
イベント:Kennedy Center Honors(2012年/Led Zeppelin 受賞回)
映像:Kennedy Center Honors 公式公開映像
🎖️ ケネディ・センター名誉賞という舞台

ケネディ・センター名誉賞は、アメリカの文化・芸術に長年多大な影響を与えた人物・団体に贈られる、国家的な顕彰です。2012年、その受賞者のひとつとしてレッド・ツェッペリン(ジミー・ペイジ、ロバート・プラント、ジョン・ポール・ジョーンズ)が選ばれました。授賞式には当時のオバマ大統領夫妻も出席し、まさに“国家が音楽の歴史を称える場”となりました。
そのような舞台で披露されたのが、Heartによる「Stairway to Heaven」のトリビュート演奏です。
なぜこのパフォーマンスが特別なのか
この演奏が歴史的な意味を持つのは、単なる名曲のカバーだからではありません。
受賞者であるレッド・ツェッペリンの三人が客席で見守る前で、自分たちの代表曲が“讃歌”として鳴り直される――その条件そのものが、すでに奇跡に近い状況でした。
式典の空気は音楽イベントではなく、人生の功績を称える国家的儀式。その中で「Stairway to Heaven」は、ヒット曲としてではなく、文化遺産として扱われている。ここにまず、通常のライブとは決定的に異なる重みがあります。

演奏の中心を担ったのはHeartのアン&ナンシー・ウィルソン姉妹。アンのボーカルは、憧れの再現ではなく、まるで祈りのように旋律を立ち上げていきます。
そして決定打となるのが、ドラムに座るジェイソン・ボーナムの存在です。彼は、1980年に急逝したレッド・ツェッペリンのドラマー、ジョン・ボーナムの息子。
父の不在を“空白”のままにせず、しかし“代替”でもない。あの一打一打は、楽曲の骨格を血縁の重さで支え直す行為そのものでした。
さらに演奏にはオーケストラ的な厚みと、Joyce Garrett Youth Choir(合唱団)が加わります。中盤以降、音楽はライブ演奏から儀式へと変貌し、「Stairway to Heaven」は若さの神秘でもロックの虚勢でもなく、長い時間を生き延びた者たちへの回顧と祝福として鳴り始めるのです。

ロバート・プラントの涙が意味するもの
この映像が語り継がれる最大の理由のひとつが、ロバート・プラントの表情です。
彼は静かに涙を浮かべ、感極まった様子を見せます。
プラントはかつて「他人による“Stairway to Heaven”のカバーを好まない」と語ったこともある人物です。それだけに、この夜の反応は特別でした。そこには“評価”ではなく、人生の回顧として曲を受け止める姿がありました。
隣ではジミー・ペイジが噛みしめるような笑みを浮かべ、ジョン・ポール・ジョーンズは穏やかな眼差しでステージを見つめている。彼らは「作曲者」としてではなく、自分たちの人生を外側から見つめる観客の顔をしていました。

この瞬間、「Stairway to Heaven」は彼らの“作品”ではなく、“歩んできた時間そのもの”へと変わっていたのです。
心に残る余韻 ― なぜ人は涙するのか
この演奏はテレビ放映され、その後 YouTube を通して世界中に広まりました。
多くの人が涙したと言われていますが、僕もこの映像を何十回となく見返しています。そしてそのたびに胸が熱くなり、気づけば自然に涙がこぼれてしまうのです。
Heart も大好きなバンドで、この歌唱の迫力は圧倒的です。
けれど、涙が込み上げる理由はそこだけではありません。やはり心を打つのは、客席に座るレッド・ツェッペリンのジミーページ、ロバートプラント、ジョンポールジョーンズの表情です。あの顔が映し出されるたびに、彼らと同じ時代に生きられたことへの深い幸福を、心の底から感じるのです。
■ 神話が「人間の歌」に戻る瞬間
曲が有名になりすぎ、神話になりすぎ、本人たちでさえ軽々しく触れられない存在になったあとで、他者の敬意と愛情によって、もう一度だけ「人間の歌」として取り戻される瞬間――この映像が捉えているのは、まさにその奇跡です。

そこに凝縮されているのは、
・永遠のクラシック曲と向き合うアーティストの想い
・友情と敬意の表現
・世代を超えた音楽の継承
そして何より、音楽が人の人生と重なったときにだけ生まれる感情の震えです。
だからこそ、この映像は単なるトリビュートではありません。
“他人の曲”が“自分たちの人生”へと変わる瞬間の記録として、伝説になったのです。
🎭 神話の頂点と、その後の時間
この2012年ケネディ・センターでの演奏は、若き日のレッド・ツェッペリンが鳴らしていた「神話の始まり」とは、まったく異なる場所に立っています。
1975年アールズ・コートの映像(2本目の動画です)を思い出してみてください。
あの時の彼らは、頂点に君臨する現役の王者でした。音楽は未来へ向かって放たれ、エネルギーは外へ、上へと噴き上がる。「Stairway to Heaven」は、まだ“進行中の神話”であり、観客を昇天させるための巨大な装置でした。
しかしケネディ・センターの夜、この曲は逆方向に流れます。
音楽は未来ではなく過去へ、外ではなく内へ向かう。
それは“到達するための階段”ではなく、すでに歩いてきた階段を振り返る音楽へと変わっていたのです。

■ 時間が与えた意味の変化
ここにあるのは演奏の優劣ではなく、時間の質の違いです。
若き日の原曲が持っていたのは、未知へ向かう神秘、精神世界への憧れ、そして上昇のエネルギーでした。
一方、2012年の演奏に宿るのは、人生を通り抜けた者だけが持つ静かな重み。
原曲が「象徴」なら、この夜の演奏は「記憶」。
原曲が「夢」なら、この演奏は「回顧」。
原曲が「神話の誕生」なら、ここで鳴っているのは「神話を生き延びた者の実感」です。
だからこそ、このトリビュートは“カバー”ではなくなった。
Heart が歌い、ジェイソン・ボーナムが叩き、合唱が加わったとき、「Stairway to Heaven」は作者の手を離れ、世代を超えた“共有された人生”へと変質します。

そして客席でそれを見つめる三人の姿が、その変化を決定づける。
彼らはもはや曲の「創造者」ではなく、自分たちの歩んできた時間を外側から見つめる「証人」でした。
■ 昇る音楽と、降りてきた音楽
アールズ・コートが“神話の頂点”だとするなら、ケネディ・センターは“神話の意味が回収された場所”。
前者が「昇る音楽」なら、後者は「降りてきた音楽」。
同じ曲が時間を通過することでここまで別の意味を帯びる――
その変化そのものが、「Stairway to Heaven」という楽曲が“作品”を超え、“人生の時間軸”に属している証なのです。
ここからは、この曲が「神話」になりえた理由を、誕生の背景/構造/歌詞/音の仕掛けから順に辿ってみます。まずは、その始まり――ヘッドリィ・グランジから。
ヘッドリィ・グランジの奇跡:暖炉の前で生まれた「光の素描」
この曲の誕生には、魔法のような瞬間が介在しています。1970年の終わり、バンドはイングランド・ハンプシャーにある古い屋敷「ヘッドリィ・グランジ」に籠もっていました。暖炉の火が爆ぜる音だけが響く静寂の中、ジミー・ペイジが爪弾いたアコースティック・ギターのフレーズに、ロバート・プラントがその場で歌詞を書き留めていったと言います。
当時、プラントはこの曲のインスピレーションについて「何かに取り憑かれたように言葉が溢れてきた」と語っています。特筆すべきは、その「多層的な楽器の選択」です。冒頭で鳴り響くリコーダーのアンサンブル。ジョン・ポール・ジョーンズが、あえてキーボードではなく木管楽器(リコーダー)を選択したことが、この曲に中世的なフォークロアの香りと、唯一無二の気品を与えました。

音楽的構造:下降するベースラインと、上昇し続ける「イ短調」の旋律
この曲を「階段」たらしめているのは、ジミー・ペイジが仕掛けた音の構成にあります。
イントロから響くあの切ない旋律。よく聴くと、ベースとなる低い音が静かに沈んでいく一方で、重なり合うギターやリコーダーの音色は逆に空へと昇っていくような、不思議な感覚に包まれます。この「土台が沈み込むことで、魂が相対的に浮き上がっていく」という構造は、視覚的な錯覚にも似た、音楽による心理的な「上昇体験」を生み出しているのです。
8分2秒の三位一体:ペイジが定義した「3つのセクション」
ジミー・ペイジ自身、この曲は綿密に計算された「3つの独立したセクション」によって構成されていると語っています。
- 静寂(静): アコースティックギターとリコーダーによる、霧深い森を思わせるフォーク・セクション。
- 展開(動): エレクトリック・ギターが層を成し、ジョン・ポール・ジョーンズの奏でるフェンダー・ローズが色彩を添えて、リズムが躍動し始めるセクション。
- 爆発(熱): ジョン・ボーナムのドラムが均衡を破り、ハードロックとしてのカタルシスが全開になるセクション。
この、序盤の静寂から後半の爆発へと、長い時間をかけて徐々に熱量を蓄積していく「スロー・バーン」の構成こそが、後のロック音楽における構成美のスタンダードとなりました。

歌詞の深淵:ロバート・プラントが描いた「黄金」の虚妄
プラントが綴った言葉は、単なる歌詞を超えた一つの哲学詩です。提供された歌詞の断片を紐解くと、そこには痛烈な社会批判と神秘主義が同居しています。
「黄金」という名の呪縛
“There’s a lady who’s sure all that glitters is gold / And she’s buying a stairway to heaven”(光り輝くものすべてが黄金だと信じ込んでいる貴婦人がいる。彼女は天国への階段を買おうとしている)
あまりにも痛烈なこの一節。物質的な成功が魂の救済を約束すると信じる姿は、半世紀を経た現代社会への預言のようにさえ響きます。金で買えるのは、あくまで物質としての階段。その先にある「天国」という精神の解放は、決して対価で購えるものではない。そんな残酷なまでの真実を、プラントは23歳の若さで看破していたのです。

道の選択と「沈黙」が語るもの
“Yes, there are two paths you can go by, but in the long run / There’s still time to change the road you’re on”(そう、二つの道があるけれど、長い目で見れば、今いる道を変える時間はまだ残されている)
この一節は、多くの迷える魂を救ってきました。しかし、プラントは単に「やり直せばいい」という無責任な希望を語っているわけではありません。続く歌詞では、“And it makes me wonder(それが僕を思索に誘う)”と繰り返されます。安易な正解を出すのではなく、沈黙の中で自らに問い続けること。その思索のプロセスそのものが、天国への階段を一歩上る行為なのだと解釈しています。

機材の秘密:テレキャスターが切り拓いた「音の壁」
音楽的な驚きとして語り継がれるべきは、あの歴史的なギターソロです。ライブではレスポールやダブルネックのイメージが強いペイジですが、スタジオ録音でのあのソロは、ヤードバーズ時代にジェフ・ベックから譲り受けた1959年製フェンダー・テレキャスターで弾かれています。アンプは小型のSupro。
なぜレスポールではなかったのか。それは、テレキャスター特有の「鋭く、かつ繊細な倍音」が必要だったからです。中盤までのアコースティックな響きから、終盤のハードな爆発へと繋ぐミッシングリンクとして、あのテレキャスターのトーンは不可欠でした。あのソロが始まった瞬間、楽曲は「歌」であることをやめ、純粋な「意志の咆哮」へと昇華するのです。

ソロのフレーズは完全にアドリブで、3テイクほど録った中からベストなものが選ばれました。計算し尽くされた構成の中に、剥き出しの即興性が入り込む――この絶妙なバランスこそが、チェッペリンが「生きた音楽」であり続ける理由です。
ジョン・ボーナムの沈黙:4分18秒の「溜め」
この曲が世界最高のロック・ナンバーである理由の一つに、ジョン・ボーナムの「参加のタイミング」があります。
多くのバンドであれば、もっと早い段階でドラムを入れて、曲を盛り上げようとするでしょう。しかし、ボンゾはこの曲で4分18秒もの間、ただの一打も叩かずに沈黙を守り続けます。

この「溜め」がもたらす緊張感。聴き手は無意識のうちにリズムを渇望し、鼓動を早めていきます。そして、ついに彼が重厚なスネアを打ち下ろした瞬間、楽曲の質量は一気に数倍へと膨れ上がる。これは、単なるドラミングの技術ではなく、楽曲全体を俯瞰して「いつ、どこで爆発させるべきか」を知り尽くした、音楽家としての卓越したセンスの勝利です。
都市伝説と真実:逆再生論争(バックマスキング)の周辺
この曲を語る上で避けて通れないのが、1980年代に加熱した「バックマスキング(逆再生)」を巡る論争です。「逆再生するとサタンへのメッセージが聞こえる」という荒唐無稽な噂は、キリスト教福音派の説教者たちによって広められ、社会現象にまでなりました。

ペイジのオカルトへの傾倒(アレイスター・クロウリーの旧居を購入したことなど)が、この噂に拍車をかけました。しかし、これに対してペイジは一貫して否定しています。
「曲を作るだけで精一杯だった。逆さまに聴いて意味が通じるように作るなんて、当時の技術でも僕らの才能でも不可能だよ(笑)」
結局、それはパレイドリア(意味のないものに意味を見出してしまう心理現象)の一種に過ぎませんでしたが、そのような「呪われた噂」さえも飲み込んで肥大化していくこと自体が、この曲の持つ魔力のような影響力を物語っています。
終わりに
「天国への階段」を語るということは、単に一曲を紹介することではなく、自分自身が長いあいだ受け取り続けてきた音楽の重みと、あらためて向き合う時間でもありました。
この楽曲は、聴くたびに違う表情を見せます。若い頃に感じた高揚、少し時を重ねてから気づく陰影、そして今だからこそ胸に落ちてくる静かな実感。音楽が人生と重なりながら意味を変えていくことを、これほどはっきり教えてくれる曲は、そう多くありません。
“To be a rock and not to roll”
(岩の如くあり、転がることなかれ)
最後に響くこの言葉は、変わり続ける世界の中で、それでも自分の内側に一本の芯を持ち続けることの大切さを示しているように思えます。時代が移ろっても、音楽の中にある「変わらないもの」は確かに存在する。その象徴のひとつが、この曲なのかもしれません。
先日、僕のブログを読んでくれている知人と話していたのですが、今回25曲を紹介するにあたり、レッド・チェッペリンを再度隅から隅まで聴き返す機会を得て、以前よりさらにこのバンドが好きになりました。
このベスト25を始めた頃より、今のほうがさらにこのバンドへの思い入れは強くなった気がします。
25曲を紹介し終えたばかりですが、今度はゆっくりと全アルバムを通して聴き返してみようと思い始めています。
ここまで読んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。
この先も音楽の旅は続いていきますが、そのどこかでまた、心を震わせる一曲と出会えることを願っています。
(第1位『Stairway to Heaven』/レッド・チェッペリン編)
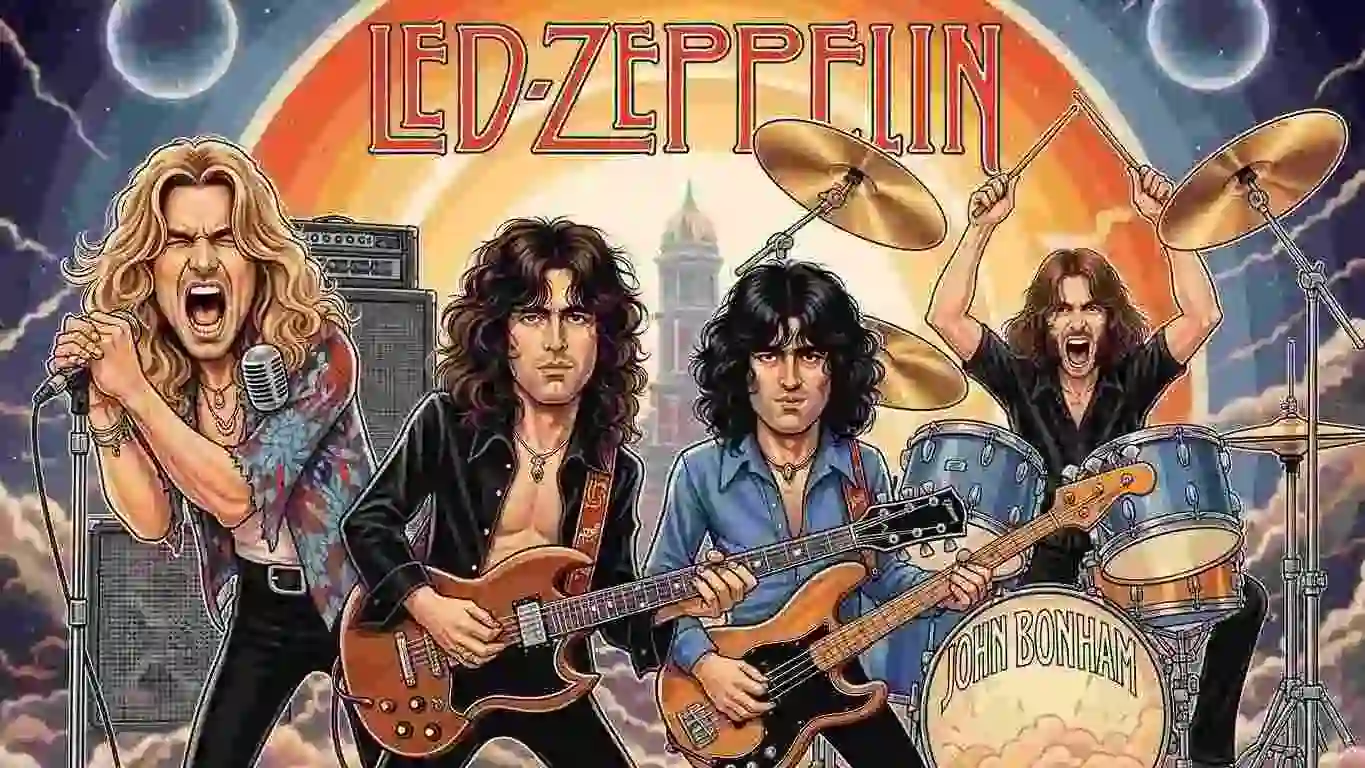


コメント