今日はロジャー・マッギンの誕生日
1942年7月13日にアメリカ・シカゴで生まれたロジャー・マッギンは、フォークロックの旗手「The Byrds(ザ・バーズ)」の中心人物として、60年代の音楽シーンに確かな足跡を残しました。彼の代名詞ともいえる12弦リッケンバッカーの煌びやかな響きは、ビートルズ以降のギター音楽に新しい風を吹き込み、フォークとロックの境界線を心地よくぼかしてみせました。

The Byrdsの代表曲『Turn! Turn! Turn!』は、そんなマッギンの魅力と哲学が凝縮された一曲です。1965年にリリースされ、ビルボード全米チャート1位を獲得したこの楽曲は、ピート・シーガーが旧約聖書「伝道の書(Ecclesiastes)」の一節をもとに書いたフォークソングが原型になっています。つまり、この歌のほとんどの歌詞は、何千年も前から伝わる「すべての物事には時がある」という思想を土台にしています。
今日の紹介曲:『Turn! Turn! Turn! 』!
まずはYoutube動画(公式動画)からどうぞ!!
🎧 公式動画クレジット
The Byrds - Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season) (Audio)
公開元:TheByrdsVEVO(Sony Music / Columbia Records 管轄)
公開日:2013年12月20日/音源初出:1965年
📝 2行解説
ピート・シーガー作のフォークソングを、バーズが美しいハーモニーでロックに昇華。
アメリカの60年代を象徴する名曲として、今なお多くのリスナーに愛され続けています。
🎧 公式動画クレジット
The Byrds "Turn! Turn! Turn!" on The Ed Sullivan Show
公開元:The Ed Sullivan Show(認証済チャンネル/著作権管理下)
放送日:1965年12月12日(番組オリジナル映像)
公開日:2021年8月16日
📝 2行解説
伝説のTV番組「エド・サリヴァン・ショー」に出演したバーズ。アメリカの黄金期を彩った貴重なライブ映像です。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 1965 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
僕がこの曲を初めて聴いたのは、恐らく大学時代です。
楽曲自体のリリースは、僕が小学校低学年の頃ですので、早く聴いていても中学生ですが、当時の記憶に「バーズ」はまったく登場しません。
何でもありで、音楽を聴きまくっていたのは大学の4年間ですから、その中の一曲だと思います。
以前紹介した、ボブ・ディランの作品でバーズがカバーした「ミスター・タンブリングマン」の解説でも、同様に大学時代でしょう・・・てなことを書いていますので、両曲とも大学時代だと思います。この曲を聴いて、ラズベリーズも雰囲気がなんか似ているなぁと感じるのは、はい、僕だけです(;´∀`)
『Turn! Turn! Turn!』という楽曲の出自と魅力
聖書に基づいた不朽のメッセージ
『Turn! Turn! Turn!』は、もともとピート・シーガーが1959年に作曲した楽曲が原型となっています。歌詞の大半は旧約聖書「伝道の書」第3章に基づいており、「すべてのことには時がある」という一貫したテーマが繰り返されます。The Byrdsはこの普遍的なメッセージに、当時の最新サウンドであるフォークロックの形式を加え、新たな命を吹き込みました。
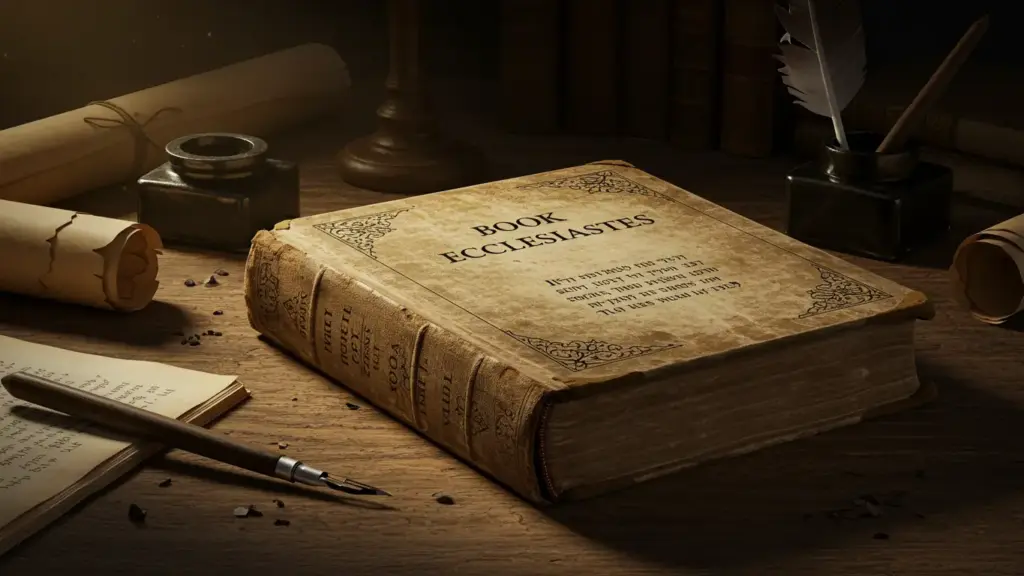
このアレンジがなされることで、宗教的な詩句が政治的・社会的な意味合いを帯び、世代を超えて共有される“祈りの歌”へと昇華されたのです。
なぜ1965年にこの曲が共感を呼んだのか?
1965年のアメリカは、ベトナム戦争の泥沼化に突き進みつつある緊張の時代でした。ジョンソン政権下でアメリカは北ベトナムへの爆撃を開始し、国内では反戦デモが活発化。公民権運動も激化し、社会が分断されるなかで、多くの若者たちは自分たちの「生きる意味」や「抗う術」を探していました。
そのようななかで、「すべてのことには季節があり、出来事には時がある」と歌うこの曲は、直接的に戦争を非難するわけではないものの、“自分たちに今必要な言葉”として心に届いたのです。鋭さを抑えたメッセージと、The Byrdsの瑞々しい演奏が美しく溶け合い、深い共鳴を生み出したことが、ヒットの大きな要因となりました。
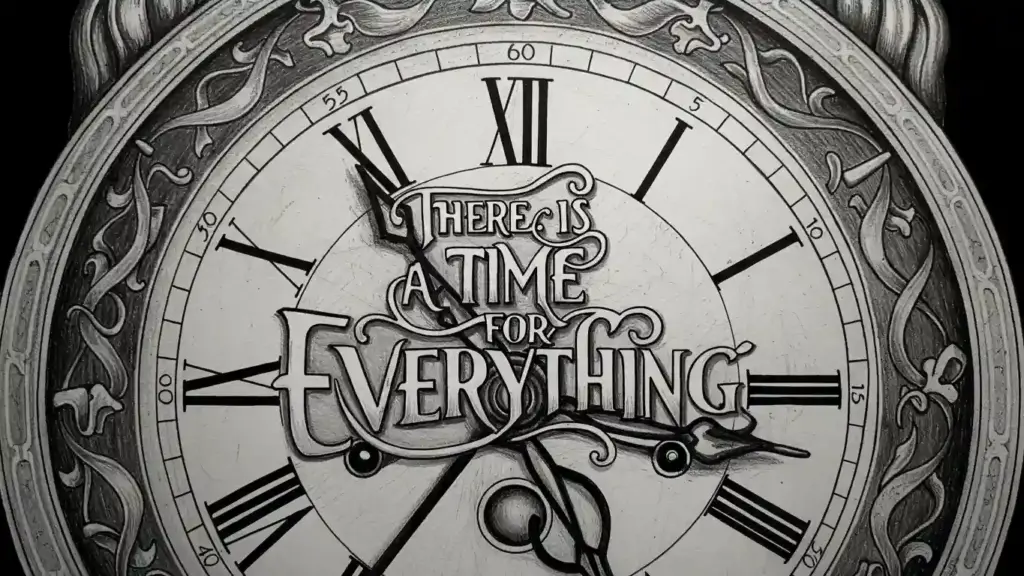
ピート・シーガーとロジャー・マッギン、それぞれの役割
ピート・シーガーはアメリカのフォークリバイバルを牽引した存在であり、彼が残したこの楽曲には、すでに強い社会的意義が込められていました。ただし、それを“時代の音楽”へと変貌させたのは、間違いなくThe Byrdsの手腕によるものです。
ロジャー・マッギンは、原曲の素朴さを損なうことなく、12弦ギターの煌びやかな響きと美しいコーラスワークによって、普遍性と同時代性を両立させました。彼のボーカルは淡々としていながらも誠実で、だからこそ「人生に与えられた時を受け入れる」というメッセージが、より深く染み入るのかもしれません。
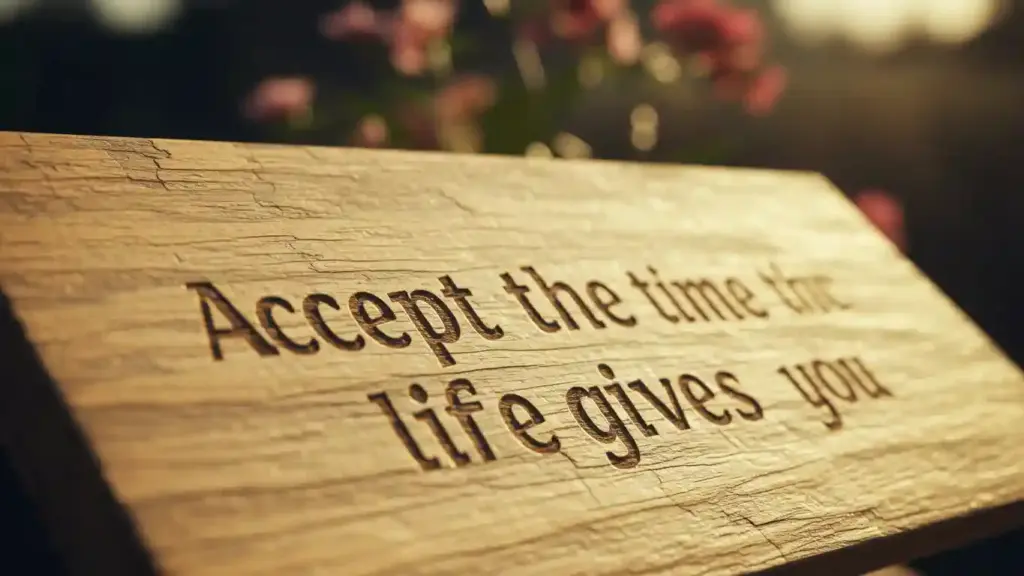
メロディの美学と12弦ギターの魔法
音の中核を成す——リッケンバッカーの響き
『Turn! Turn! Turn!』を語るうえで欠かせないのが、ロジャー・マッギンが操る12弦リッケンバッカー・ギターの独特な響きです。ジョージ・ハリスン(ビートルズ)の影響を受けたマッギンは、このギターを自らのサウンドの中心に据えました。結果としてThe Byrdsの楽曲には、クリスタルのような清澄さと、伸びやかな余韻を伴った音色が息づくようになります。
とりわけこの曲の冒頭、ギターによるアルペジオは、聴いた瞬間に空気が変わるような感覚をもたらします。フォークの素朴さとロックの躍動感、それぞれの要素が静かに溶け合いながら、新しいジャンルの風景を描き出しているのです。
アレンジと構造の妙
『Turn! Turn! Turn!』のコード進行は一見すると極めてシンプルで、繰り返しも多く、難解な転調などは用いられていません。しかし、その反復が逆に歌詞の「時の巡り」という主題と呼応し、楽曲全体に説得力を与えています。
リズム面でも特徴的なのは、必要以上に装飾を施すことなく、淡々としたテンポを維持している点です。ベースとドラムスは支えに徹し、中心となるギターとヴォーカルが生きるように設計されています。
録音技術と音像の工夫
1965年当時のレコーディング環境としては先進的だったコロンビア・スタジオで収録されたこの曲は、ステレオ音像の設計にも工夫が凝らされています。12弦ギターの広がりを意識したパンニング、空間を意識した残響処理、そしてコーラスの定位に至るまで、シンプルな構成のなかに精密な構築美が光ります。
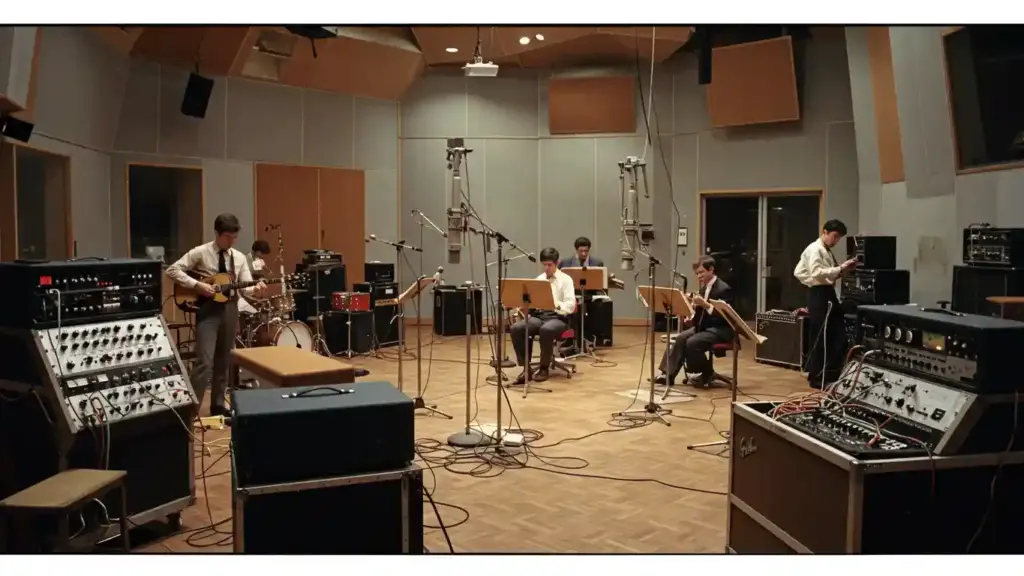
こうした技術的な完成度の高さも、『Turn! Turn! Turn!』を単なるカバー曲から、時代を超えて愛される名曲へと押し上げた要因のひとつだと言えるでしょう。
アメリカと日本、それぞれの1965年
アメリカ社会の現実と音楽の役割
1965年のアメリカでは、社会的分断が一層深まり、音楽は単なる娯楽ではなく、言葉を持った“社会の声”としての意味合いを強めていきます。ベトナム戦争への抗議、公民権運動、女性の権利獲得運動など、多くの若者たちが音楽に自分の立場や想いを重ねるようになりました。
そのなかで、『Turn! Turn! Turn!』は特異な位置にありました。政治的に尖った表現を用いることなく、しかし確かに“今を見つめるまなざし”を宿していたのです。リスナーは、直接的な怒りではなく、包容力のある“静かな励まし”としてこの曲を受け取っていたのではないでしょうか。
日本での洋楽受容とバーズの立ち位置
一方の日本では、グループ・サウンズの黎明期。加山雄三やザ・ベンチャーズ、平尾昌晃といった存在が人気を集めるなかで、The Beatlesを筆頭とするブリティッシュ・ロックが圧倒的な注目を浴びていました。しかし、The Byrdsの音楽は、そうした大波の陰にあっても静かに受け入れられていきました。

とくに、英語の意味が完全に理解できなくとも、“穏やかさ”や“哲学的な空気”が伝わってくる『Turn! Turn! Turn!』は、日本の若い音楽ファンにも深い印象を残したといわれています。当時の音楽雑誌やラジオの特集でも、バーズの“知的で内省的なスタイル”が一部で高く評価されていた記録が残っています。
国内で同時期に話題を集めた音楽たち
1965年の日本では、坂本九の『明日があるさ』、ザ・ピーナッツの『恋のバカンス』、弘田三枝子の『ヴァケーション』などがヒットチャートを賑わせていました。これらはいずれも、明るく前向きな雰囲気や、甘く軽快なメロディが特徴的です。(なんとも懐かしい名前が並びましたね!!)
ロジャー・マッギンという人物と、その後の展開
フォークの知性とロックの感性を併せ持つアーティスト
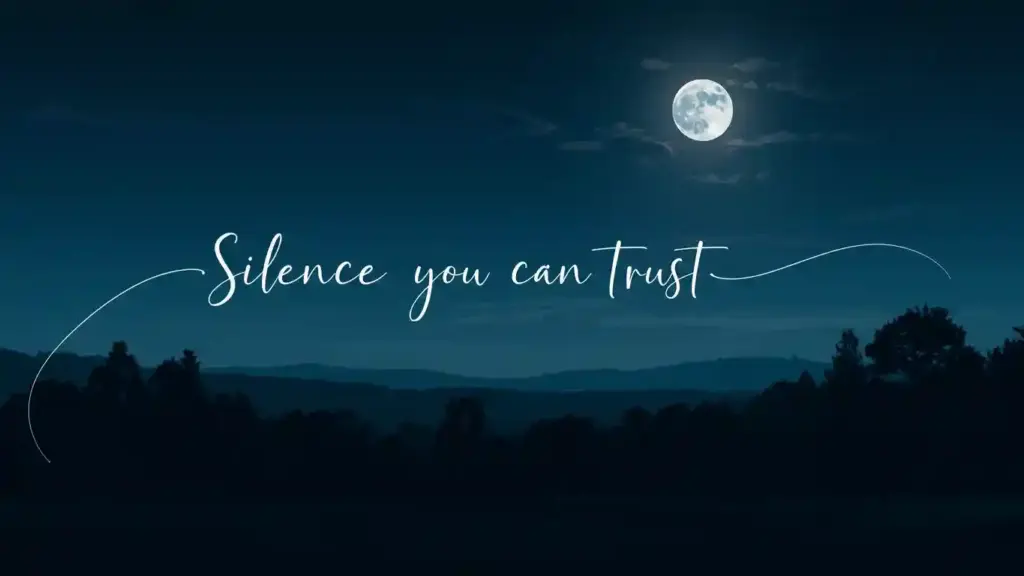
ロジャー・マッギンは、The Byrdsでは中心的存在としてサウンドの方向性を示し、編曲や演奏にも深く関わりながら、バンドの顔としての役割も担いました。12弦ギターの活用だけでなく、ハーモニーの構築や選曲の妙にも彼のセンスが色濃く表れています。知性に裏打ちされた音楽性と、派手さを避けた実直な姿勢が、結果としてバーズの“信頼できる静けさ”を支えていたといえるでしょう。
『Turn! Turn! Turn!』以降の足跡と影響
バーズはこの曲以降、『Eight Miles High』や『Mr. Spaceman』など、よりサイケデリックな方向へと歩みを進めました。そして1968年には、カントリーロックの原型ともいえる名盤『Sweetheart of the Rodeo』をリリースし、アメリカ音楽の流れに新たな流派を作ることになります。

この変化においても、マッギンは柔軟に方向転換をはかり、アーティストとしての視野の広さを証明しました。その後も彼はソロ活動を続け、デジタル時代に入ってからは「Folk Den Project」などのオンライン活動を通じて、フォークの伝承にも尽力しています。
彼の影響は、トム・ペティやR.E.M.、ジェフ・トゥイーディ(Wilco)などのアーティストにも及び、今も多くの後進ミュージシャンからリスペクトされ続けています。
まとめ:ひとつの季節が、またひとつ巡る
『Turn! Turn! Turn!』とは、数千年前の預言者の言葉が、20世紀のフォークミュージシャンによって旋律を与えられ、そしてロックバンドによって現代的な生命を吹き込まれた――それはまるで時代そのものが共同作業をしたような、不思議な連なりです。
そしてその中心にいたロジャー・マッギンという人物は、流行に惑わされず、音楽の本質を探求し続けるまなざしを持っていました。彼がこの曲に込めた響きは、今も私たちの耳元でささやいているようです。
「今は、待つべき時なのかもしれない」「今こそ、手放すべき瞬間なのかもしれない」――そんなふうに、自分の“今”を見つめ直すきっかけとして、今日この曲を聴き返してみてはいかがでしょうか。


コメント