高橋真梨子さんについて詳しくはこちらから➡『ウィキペディア(Wikipedia)』
高橋真梨子:第2位『五番街のマリーへ』をご紹介!
高橋真梨子の楽曲から選んだ「僕の勝手なBest10」。その第2位に選んだのは、1973年リリースのペドロ&カプリシャス時代の代表曲『五番街のマリーへ』です。
この楽曲を単なる「ヒット曲」として扱ってしまうのは、あまりにも惜しいと思います。それは、約4分間に凝縮された一篇の文学作品であり、聴く者の心の奥にそれぞれの映像を投影する短編映画のような存在です。

本記事では、既出の基本情報を極力抑え、なぜこの曲が50年の時を超えてなお人々の胸を打つのか、その根源に迫っていきます。阿久悠が仕掛けた言葉の妙、都倉俊一が設計した音の世界、そして1973年という日本社会の空気。それらを丁寧に読み解きながら、歌謡曲の高みへと至った奇跡の一曲を、改めて見つめていきたいと思います。
まずは公式動画から紹介しましょう。
🎥【公式ライブ映像】
🎬 公式動画クレジット
五番街のマリーへ – 高橋真梨子
アルバム『the best ~new edition~』収録(2004年11月17日リリース)
配信元:Victor Entertainment公式
💡 2行解説
別れた恋人への複雑な想いを、静かに語りかけるように歌い上げた名バラード。研ぎ澄まされた高橋真梨子の歌声が、心の奥にそっと触れる一曲です。
🎬 公式動画クレジット
五番街のマリーへ(ライブ映像) – 高橋真梨子
アルバム『CARNEGIE HALL N.Y. COMPLETE LIVE』(1993年開催ライブ)より
提供:高橋真梨子公式チャンネル
💡 2行解説
哀愁と品格を携えたステージが、世界的ホールでの熱唱によって新たな命を得る。“別れ”の情景を、極上の歌声とともに深く心に刻むライブ・パフォーマンスです。
歌詞の空白が紡ぐ、無限の物語
― 阿久悠が仕掛けた「不在の美学」
『五番街のマリーへ』の魅力の本質は、その未完の物語性にあります。物語は語られていながらも結末を持たず、むしろ語られない部分の「余白」こそが、リスナーの想像力を刺激し、それぞれの「マリー」と「僕」の物語を自由に描かせるのです。
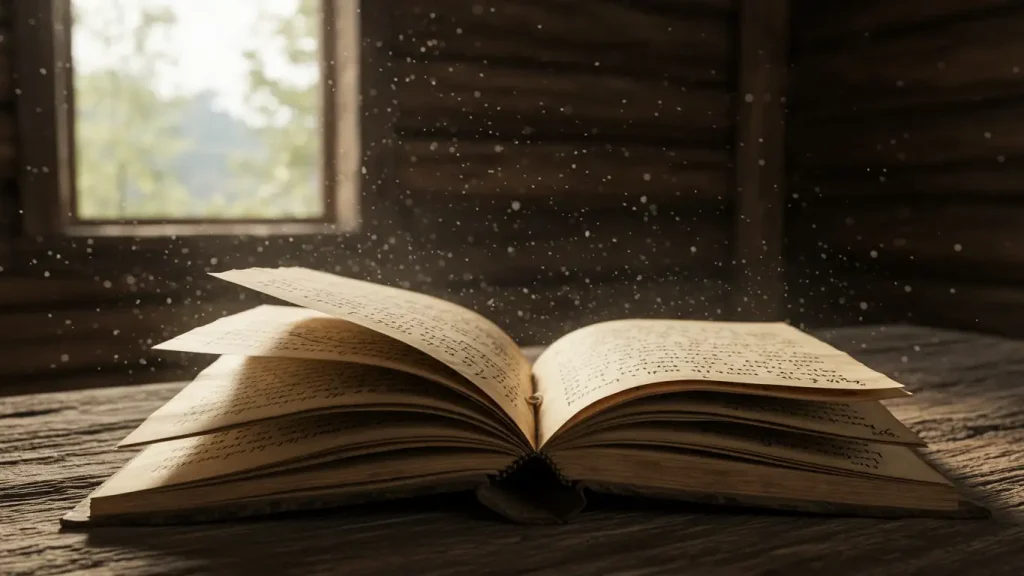
作詞家・阿久悠がここに仕掛けたのは、「語らないことで語らせる」という、文学にも通じる構造的仕掛け。まさに「不在の美学」と言うべき技法です。
「マリー」は誰か?「五番街」はどこか?
― 固有名詞が持つ魔力と普遍性
まず注目したいのが、タイトルに登場する「五番街のマリー」という言葉。
「マリー」とは誰なのか――歌詞の中では一切、その人物像は明かされていません。聴き手が知るのは、彼女が「やせたこと」、そして「五番街にいるらしい」ということだけです。あまりに少ない情報量ですが、それゆえにリスナーの想像力が無限に膨らんでいくのです。

「マリー」という名前は、聖母マリアを連想させる慈愛や純潔を持つ一方で、マリリン・モンローのような儚さと妖艶さをもイメージさせます。聴く者それぞれの人生経験によって、マリーは恋人にも、友人にも、姉妹にもなりうる。阿久悠はあえてこの人物を特定せず、「あなた自身の物語」として成立させることに成功しているのです。
次に、「五番街」という舞台設定にも注目です。
ニューヨークの5th Avenueが連想されますが、歌詞中で直接言及されているわけではありません。これは「五番街」という言葉が、単なる地名ではなく、富や自由、そして憧れといった象徴的な意味を持っているからです。日本の銀座や新宿では担えない、異国の、そして手の届かない距離感が、この曲の持つ切なさを一層強調しているのです。
語り手「僕」の正体
語り手「僕」の正体
この楽曲における「僕」は、マリーの元恋人だったと考えるのが最も自然です。「マリーという娘と 遠い昔にくらし」「悲しい思いをさせた」という歌詞から、ふたりがかつて親密な関係にあり、共に過ごした時間を共有していたことが読み取れます。

なかでも印象的なのは、「もしも嫁に行って 今がとてもしあわせなら 寄らずにほしい」という一節です。ここには、相手の現在の幸せを願い、あえて距離を取ろうとする姿勢が明確に表れています。語り手はマリーを探し出して関係を取り戻そうとしているわけではなく、ただ彼女の今を案じ、知りたいと願っているにすぎません。
「もう一度会いたい」と訴えるのではなく、「昔の話をしたい」と静かに語る姿勢には、未練ではなく、過去をやさしく抱きしめるような成熟した眼差しが漂っています。過去に縛られるのではなく、過去と対話することで現在を生きる――その姿勢が、この歌に深い陰影と静けさを与えているのです。
このような語り口は、1973年当時、急激な経済成長を経験し、自らの歩みをふと立ち止まって見つめ直し始めていた多くの日本人の心情と、強く共鳴したに違いありません。
さらに注目すべきは、この物語がまるで「手紙」のような構成で綴られている点です。歌詞中に直接「手紙」という言葉は登場しませんが、「見て来てほしい」「知らせてほしい」「たずねてほしい」といった言葉遣いや語りの調子は、まさに誰かに思いを託すような“手紙的構造”を感じさせます。

当時は電話の普及が進みつつありましたが、それでも遠く離れた人とのやりとりは、依然として手紙が中心でした。なかでも、返事があるかもわからない、想いを一方的に伝える手紙は、不確かさやタイムラグを含みながら、強い感情を内に秘めています。
『五番街のマリーへ』がこのような“手紙のような語り”を選んだことによって、届くかどうかもわからない想い、そしてそれを抱えて生きる語り手の姿がよりリアルに、より切なく描かれることとなったのです。
静寂と情熱の交差点
― 都倉俊一のメロディと高橋真梨子の声が織りなす音響のドラマ
この詩的な世界観を、より豊かに肉付けしているのが、作曲・編曲を担当した都倉俊一の音楽的設計と、高橋真梨子の圧倒的なボーカル表現です。
シンプルさの裏に隠された、計算され尽くした旋律
冒頭のピアノのアルペジオは、夜の都会の静寂や孤独を思わせ、曲の舞台となる情景を一瞬で描き出します。

AメロからBメロにかけては抑制された旋律が続きますが、サビで一気に開放されるメロディが感情の起伏を丁寧に表現しています。とりわけ「マリーのことをきいてくれ」以降の旋律は、語り手の抑えきれない思いが静かに、しかし確実に溢れ出していくように感じられます。
また、間奏に入るフルートのソロは、語られなかった想いを代弁するかのように、聴く者の胸に余韻を残します。まるで言葉にならない「僕」の心情が、音楽だけで描かれているようです。
高橋真梨子の「声という名の演技」
この曲の魂とも言えるのが、高橋真梨子のボーカルです。
Aメロでは息遣いを多く含んだウィスパーボイスで語り始め、Bメロで少しずつ温もりを帯びていきます。そしてサビに至っては、まるで想いが空へと放たれるような高音が、透明感をもって聴く者の心を震わせます。
ラストの「マリーへ」と呼びかけるロングトーンには、微かなビブラートが宿り、届かぬ想いの切なさを見事に表現しています。
ペドロ&カプリシャスの音楽的背景とラテンの香り
忘れてはならないのが、ペドロ&カプリシャスというバンドが持つ音楽的土壌です。
彼らのサウンドにはラテン音楽の要素が根付いており、本楽曲でもコンガやボンゴといったパーカッションがさりげなく使われています。(さすがに50年間気がつきませんでいた。)これが、しっとりとした情緒の中にも独特のグルーヴを生み出し、楽曲全体を都会的で洗練された質感に昇華させているのです。

1973年という「黄昏時」
― なぜこの歌は時代に求められたのか
名曲が名曲として成立するには、時代との相互作用が欠かせません。『五番街のマリーへ』が生まれた1973年という年は、日本が「成長の終わり」と「自分自身を振り返る時代」に差し掛かった節目でした。
高度成長の光と影
― 「豊かさ」の先に見えたもの
1973年、日本は高度経済成長の最終局面にありました。同年10月には第一次オイルショックが発生。生活物資の買い占め、ガソリン価格の高騰、そして「経済成長神話」の崩壊という大きな社会の揺らぎが人々を襲います。

それまで「モノを持つこと」や「上昇すること」が目標だった日本社会は、この年を境に「本当の幸せとは何か」「何を失ってきたのか」という内省へと向かい始めたのです。
『五番街のマリーへ』が提示したのは、そんな転換点における一つの「心の灯り」でした。豊かさの裏で忘れてきた人、離れてしまった思い出、もう戻れない風景。そうした喪失に対して、「会いたい」とは言わずに、「せめて伝えてほしい」と託すような切実さが、人々の胸に静かに沁みわたったのです。
「アメリカ」への憧憬と距離感
戦後の日本は長らく「アメリカ」に対する強烈な憧れを抱いてきました。文化、音楽、経済、ライフスタイル――あらゆる面での模範だったアメリカに対し、1970年代に入るとその光と影が見え始めます。

ベトナム戦争の泥沼、ウォーターゲート事件、ドルショック。そうした影の中で、「憧れの地・五番街」もまた、もはや輝かしい象徴ではなくなっていたのかもしれません。
『五番街のマリーへ』における「五番街」は、もはや到達すべき場所ではなく、「遠くなってしまった場所」として描かれています。それは、アメリカに対する日本人の心象変化をも象徴しており、どこか哀しみと諦念を含んだ距離感が、曲全体を貫いているのです。
音楽シーンの潮目
― 歌謡曲・フォーク・ニューミュージックの狭間で
1973年当時の日本の音楽シーンは、フォークソングの台頭と、従来型の歌謡曲の交錯期でした。
吉田拓郎、井上陽水といったアーティストが台頭し、自らの内面を赤裸々に歌うフォークソングが若者たちに支持されていた一方で、テレビで流れる「大衆向け」の歌謡曲は形式化しつつありました。
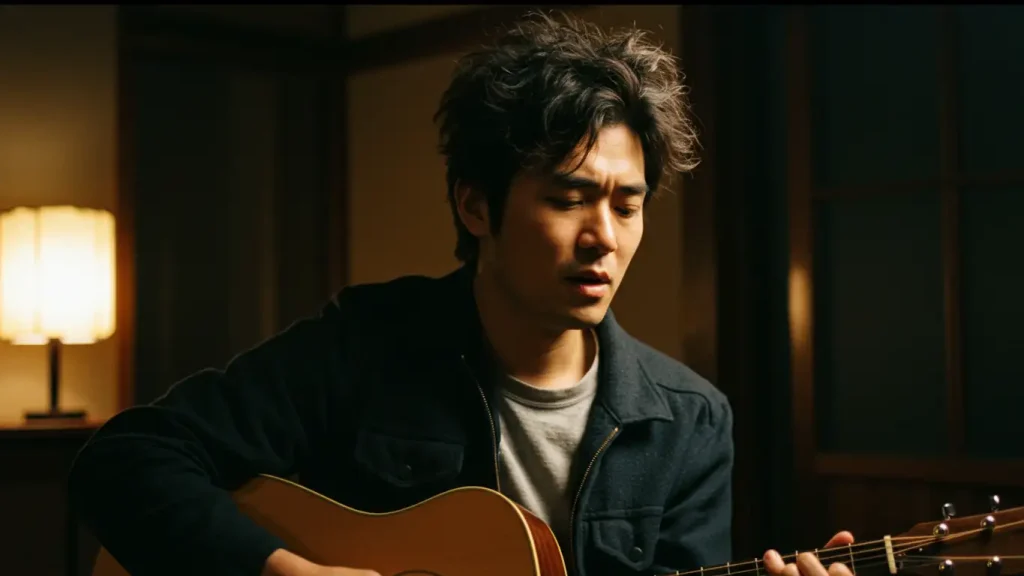
『五番街のマリーへ』はその両者の美点を絶妙に融合させた存在でした。
- フォークが持つ私小説的な語り口
- 歌謡曲が備える普遍的なメロディの強さ
- そして、ペドロ&カプリシャスによる洋楽的アレンジの洗練
これらが融合した本作は、のちのニューミュージック、さらに言えばシティポップへと繋がる美意識の原型とも言えるのです。
結論:あなたの心に響く、永遠の調べ
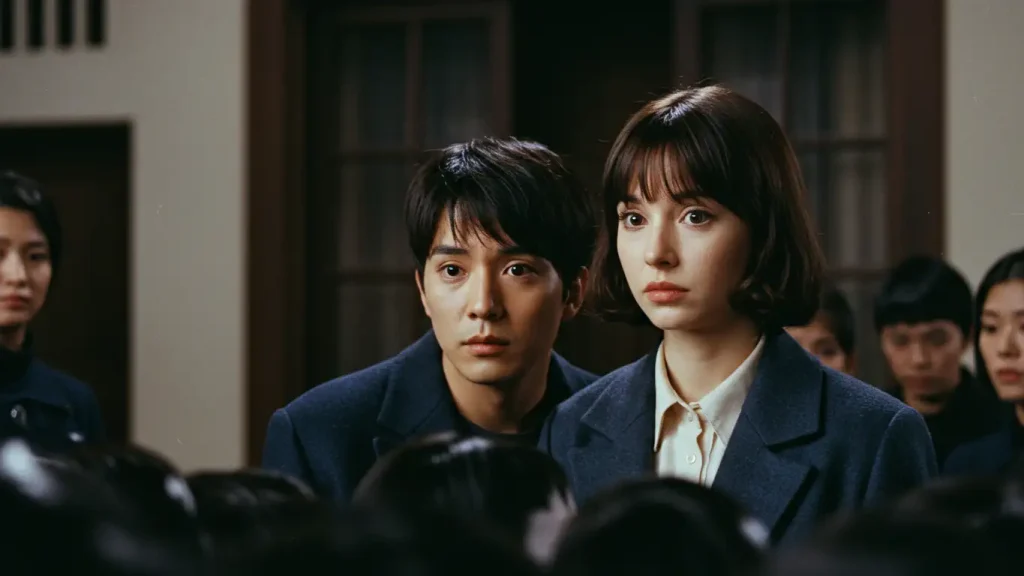
『五番街のマリーへ』は、誰かの物語であると同時に、「あなた自身の物語」として成立します。
- 阿久悠が仕掛けた「余白」
- 都倉俊一が紡いだ「情景」
- 高橋真梨子が注ぎ込んだ「魂」
この三位一体が、聴く人一人ひとりの記憶や感情に「物語」を芽生えさせ、何十年経っても色褪せることのない楽曲として息づいています。



コメント