ジ・エッジの誕生日に想う
U2サウンドの中心にいたギタリスト
1961年8月8日──この日にイングランドのエセックス州バーキングで生まれたのが、U2のギタリストとして知られるジ・エッジことデヴィッド・ヒューウェル・エヴァンスです。
後にアイルランド・ダブリンで育ち、U2の音楽的中心人物となった彼のギターは、その名のとおり刃物のように鋭く、冷ややかな質感を伴っています。ディレイやハーモニクスを駆使した音作りは、従来のロックギターとは一線を画し、空間的かつ抑制の効いたトーンが特徴です。U2のサウンドスケープにおいて、彼は唯一無二の存在として常に核となる役割を担ってきました。
彼の誕生日を記念する今日は、U2の代表曲『Sunday Bloody Sunday』に改めて焦点を当てたいと思います。この楽曲は、政治的・歴史的な背景と、音楽的挑戦が結実した傑作として、40年以上経った今も世界中で演奏され続けています。
今日の紹介曲:『Sunday Bloody Sunday』-(U2)
まずはYoutube動画(公式動画)からどうぞ!!
📺 公式動画クレジット(YouTubeより)
曲名:Sunday Bloody Sunday
アーティスト:U2
チャンネル:U2(公式)
リリース:1983年(Island Records)
作詞作曲:Bono(ボーカル・作詞)、The Edge(ギター・作曲)
📖 2行解説
U2の代表曲「Sunday Bloody Sunday」は、北アイルランド紛争に対する怒りと悲しみを表現した社会派ロック。The Edgeの鋭いギターと軍隊的なドラムが、曲に緊張感を与えています。
🎥 公式動画クレジット
🎥 Live Aid公式チャンネル
📅 公開日:2018年9月21日
✅ 2行解説
U2が1985年7月13日の「Live Aid」で披露した歴史的パフォーマンス。
ボノのメッセージとジ・エッジの鋭利なギターが、世界中に衝撃を与えました。
🎥 公式動画
Bono & The Edge – Sunday Bloody Sunday – January 30, 2022
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=_xHNDiZQv6w
📖 2行解説
1972年「血の日曜日事件」から50年、ボノとジ・エッジが静かに奏でたアコースティック版。
映像と演奏が剥き出しの現実を伝える、U2史上もっとも沈痛なバージョンの一つ。
📝クレジット表記
公式動画:『Sunday Bloody Sunday(Live at Red Rocks 1983)』
U2公式YouTubeチャンネルより公開/2021年リマスター版
✍️2行解説
1983年、アメリカ・コロラド州レッド・ロックスでの伝説的なライヴ映像。
白旗を掲げて熱唱するボノの姿は、U2のメッセージ性を象徴する歴史的瞬間として語り継がれています。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 1983 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
この曲を始めてきたのは、恐らくリリースから1~2年程度は過ぎていたと思います。
結婚をし、上の子が生まれた前後だとおもいます。
これまでも、U2の楽曲は2曲紹介しており、好きなバンドの一つです。イメージとしては、メッセージ性の強い曲を歌うバンドという認識と、以下の強烈なエピソードの当事者としてです。忘れもしません。(appleファンなので!!)
AppleとU2──音楽配信の“黒歴史”?
2014年、突如すべてのiPhoneにU2が現れた
2014年9月、AppleのスペシャルイベントでU2が登場し、新アルバム『Songs of Innocence』を世界中のiTunesユーザーに無料配信することを発表。
しかもその配信方法は「自動追加」。iPhoneやiTunesを使っている人すべてのライブラリに、勝手にU2のアルバムが入ったのです。(僕もこの中の独りなので、よく覚えています。個人的には、迷惑どころか、ありがたいことだと感じていました(;´∀`))

ユーザーの怒りと混乱
この施策は予想外の反応を引き起こします。
「なぜ見知らぬバンドの音楽が勝手に入っているのか」「削除できない」といった苦情がSNSに殺到。
Appleは後日、アルバム削除専用のページとツールを公開するはめになりました。
本人たちも“やりすぎた”と反省
ボノの謝罪と釈明
U2のボーカル・ボノは後に、「自分たちは善意でやったが、選択の自由を奪ったことは申し訳なかった」と謝罪コメントを発表。Appleとのコラボで革新的なプロジェクトに挑んだつもりが、結果的には**“暴走した好意”**として記憶されることになってしまいました。

前代未聞の配信キャンペーンだった
5億人に配信されたアルバム
この一件は、世界で5億台以上のiOS端末に対して同時に音楽が届けられたという、史上最大の音楽配信キャンペーンでもありました。
Appleにとっては「iTunesの力」を世界に示す試み、U2にとっては「音楽を広く届ける」理想の具現化。
その裏にあった戦略は、今のサブスク時代にも通じる先駆的なものでもありました。

一言でまとめるなら…/もちろんU2に悪気はなかったのです!
U2は、「世界で唯一、“勝手にあなたのスマホに現れたバンド”」として、デジタル音楽配信の歴史に名を刻んだ。
鋭く世界を切り裂いたU2の名曲『Sunday Bloody Sunday』を深く読む―背景にある事件
北アイルランドで何が起きたのか
1972年「血の日曜日」事件の概要
1972年1月30日、北アイルランドのデリー(ロンドンデリー)で、カトリック系住民による平和的なデモに対してイギリス陸軍が実弾を発砲。13人が即死、後にもう1人が死亡しました。
この「血の日曜日事件(Bloody Sunday)」は、長引く北アイルランド紛争(The Troubles)をさらに激化させ、国家による暴力の象徴として深く記憶されることになります。

アイルランド社会に残された爪痕
この事件は、単なる過去の悲劇ではありません。真相解明を求める声や怒りは、次の世代へと受け継がれ、アイルランド社会の分断と不信を象徴する記憶となっていきました。
U2が選んだ立場と表現
ダブリンに育ったバンドの視点
U2のメンバーはアイルランド共和国・ダブリン出身で、事件の現場である北アイルランドとは物理的な距離があります。しかし、日常に根付く宗教的・政治的緊張の空気の中で育ち、暴力の現実から目を背けることはできませんでした。

音楽で示した“当事者”としての姿勢
事件から約10年後、1983年にU2は『Sunday Bloody Sunday』をリリースしました。
特定の立場に与することなく、「暴力そのもの」を告発するという形で、音楽を通じて人間としての声を上げたのです。
歴史の再現ではなく、未来への問い
U2がこの曲に込めたのは「過去の記録」ではなく、「このままでいいのか?」という普遍的な問題提起です。
失われた命への追悼と同時に、暴力が正当化される社会への静かな怒りを描き出しています。
フレーズに込めた意思と構造
“This is not a rebel song.”
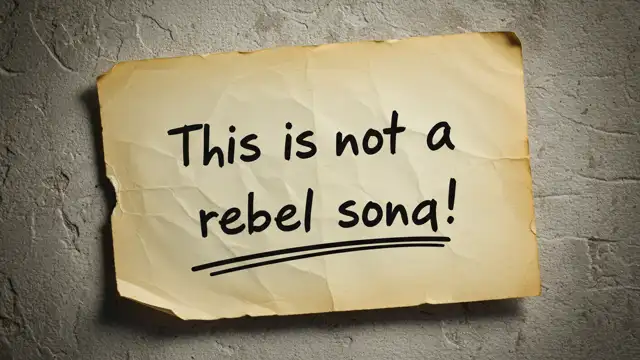
U2のライブでは、ボノがこのフレーズを必ず口にします。
「This is not a rebel song.(これは反逆の歌ではない)」
この一言は、政治的な誤解を避けると同時に、U2のスタンス──誰かの「正義」ではなく、「暴力の否定」という立場──を明確にする象徴となっています。
“How long…”という問いの重み
“How long, how long must we sing this song?”
(いつまで僕たちはこの歌を歌い続けなければならないのか?)
繰り返されるこの問いは、争いの終わらない現実、声を上げても届かない無力さへの、切実な叫びそのものです。この一節がコーラスではなく“問いかけ”であることが、この曲の普遍性を支えています
音で伝えるという選択
歌詞だけでは届かないメッセージ
『Sunday Bloody Sunday』は、歌詞に込められた意味だけでなく、演奏そのものがメッセージを語っている楽曲です。
バンドの4人それぞれのパートが、「怒り」「緊張」「無力感」といった感情を音として可視化し、聴き手に強い印象を残します。
ラリー・マレン・ジュニアのスネアが描く緊張
抗議の足音のようなドラム
曲の冒頭を飾るスネアの連打は、あたかも抗議デモの足音を模しているかのようです。
ラリー・マレン・ジュニアはマーチングドラムのようなリズムを用いて、規則性の中に緊張を持ち込みます。

鳴らさないことが意味になる
このスネアは、決して派手ではありません。
むしろ「必要な音しか鳴らさない」ことによって、情報を制限し、聴き手に緊張感を強制するような構造になっています。この“抑制された怒り”こそが、曲の導入部の核心です。
ジ・エッジのギターが築く音の壁
冷徹で静かな主張
ラリーのスネアに続くギターは、ジ・エッジ特有のクリーントーンとディレイを多用した響きです。
彼のギターは、**爆発ではなく「静かなる確信」**として存在し、音の持続と残響が空間に重なりを作っていきます。

無慈悲な現実を刻む旋律
感情を露わにするのではなく、感情の内側をなぞるように刻まれるリフは、まるで現実の非情さを黙って突きつけているようです。
ひとつの音が複数の意味を帯びるような設計により、リスナーの内面に不穏な“空白”を作り出します。
アダム・クレイトンのベースが支える重心
動かないことで生まれる緊張
アダムのベースは、この楽曲の構造を下支えする要となっています。
過度な装飾を排除し、太く、一定のリズムを保ったフレーズによって、全体に「動かなさ」をもたらします。

心地よさのない“支え”
ベースの響きは、調和や美しさではなく、動かないことで逆に落ち着かない空気を作る仕掛けです。
聴く者の足元を固めるのではなく、むしろ浮遊感と圧迫感を同時に与えています。
ボノのボーカルに宿る“語る力”
叫ばずに伝える言葉の重み
ボノの歌唱は感情過多ではなく、一文ずつを「語る」ように構成されています。
「Sunday Bloody Sunday」というフレーズを繰り返すその声は、単なるサビではなく、リスナーに意味を強制する“文字列”の提示となっています。
慰めではなく、目を開かせる歌詞
たとえば「Wipe the tears from your eyes(涙を拭って)」というライン。
一見すると優しげなこの言葉も、実は**“目をそらすな”という鋭い警告**を内包しています。
こうした表現が、優しさと厳しさの境界で緊張を持続させるのです。
構造そのものが放つ圧力
反復がもたらす心理的な揺さぶり
この楽曲の構成は、ヴァースとコーラスの繰り返しを用いつつ、問いかけを何度も投げることで、リスナーに静かな圧力を与えています。
“How long must we sing this song?”
このフレーズが複数回出てくることで、「まだ終わっていない」「変わらない」という現実を音楽的に体感させます。

時代を超える一節
後半に登場する次のラインは、とりわけ強い印象を残します。
“When fact is fiction and TV reality”
(現実が作り話になり、テレビが真実のように見える)
これは、現代の“情報の歪み”を先取りしたような警句でもあり、この曲のメッセージが時代を超えて通用する理由のひとつです。
この言葉は、観客に対して明確な立場を伝えるメッセージであり、暴力に対する否定、政治的立場への中立、そして普遍的な訴えを象徴しています。
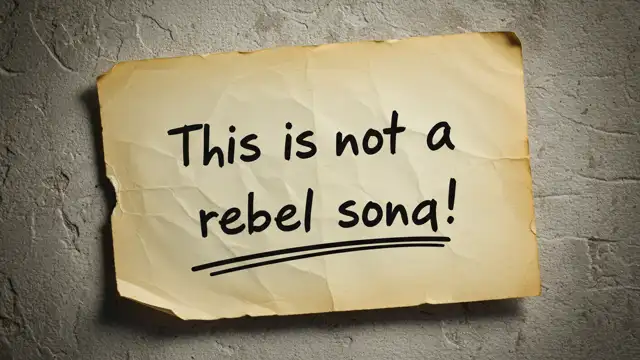
1983年レッド・ロックス公演の衝撃
映像作品『Under a Blood Red Sky』
1983年6月5日、コロラド州レッド・ロックスで行われたU2のライブは、映像作品『Under a Blood Red Sky』に収録されました。(公式動画の一番最後に紹介したのものです)
雨に濡れた野外ステージ、赤い松明、そして白旗を掲げて歌うボノの姿は、視覚的なインパクトとともに、暴力の否定と平和への意志を象徴する瞬間となりました。
白旗の意味とは
ボノが掲げた白旗は、「降伏」ではなく「これ以上殺し合わないという決意」の象徴です。
それは、どの陣営にも属さず、暴力の連鎖を終わらせるために掲げられた意志表示でした。
時の流れとともに変わる表現
アコースティック版に込められた内省

2022年、事件から50年の節目に、ボノとジ・エッジによるアコースティック・バージョンが発表されました。
このバージョンでは、スネアやエレクトリックギターの力強さは姿を消し、静かなアルペジオと語りかけるような声だけが響きます。(3番目に紹介している動画です)
怒りから沈黙へ──変化する感情の質
過去の演奏では怒りや抗議が前面に出ていましたが、このアコースティック版では、喪失感や諦念に近い感情がにじみ出ています。
特に、
“We eat and drink while tomorrow they die”
(僕らは食べ、飲む。明日、彼らが死ぬとも知らずに)
というラインには、現代社会の無関心や距離感への静かな告発が込められています。

今なお問い続ける楽曲として
歴史を超える普遍的な問い
『Sunday Bloody Sunday』が今日まで歌い継がれているのは、特定の事件や立場に限定されない問いを投げかけているからです。
それはたとえば次のような場面でも通じます:
◆ウクライナ侵攻やガザ情勢などの国際紛争 ◆民族や宗教の対立 ◆SNSやニュースにおける情報の偏り ◆日常に潜む差別や無関心

どの問題に対しても、この一節が響き続けます:
“How long must we sing this song?”(この歌をいつまで歌わなければならないのか?」)
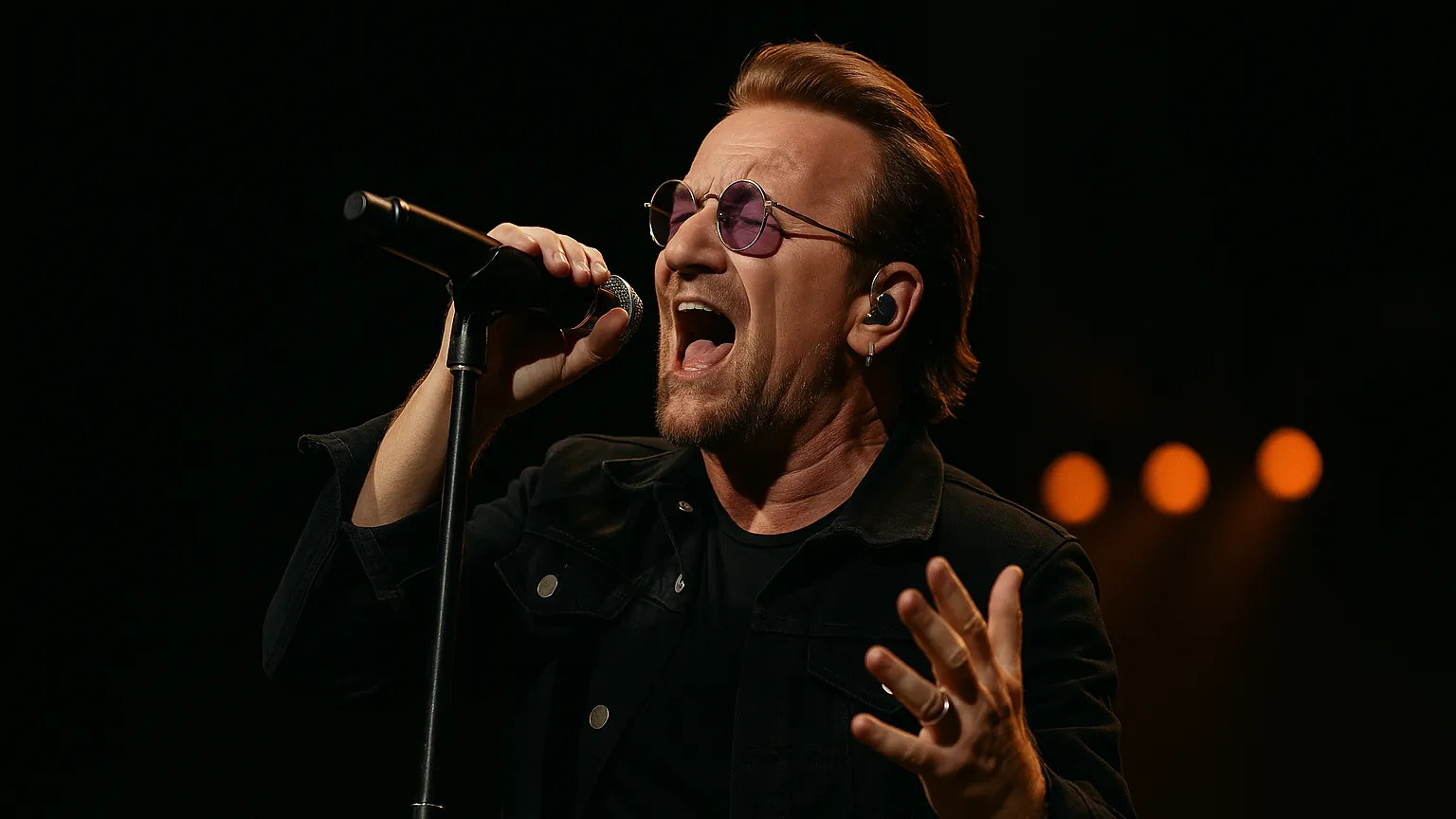

コメント