第9位:『けれど生きている』・・・(公式音源をお聴きください)
🎵 公式クレジット
「けれど生きている」 – かぐや姫(Kaguyahime)
© PANAM / Crown Tokuma Music.
From the album かぐや姫フォーエバー(2010年8月4日リリース)。
📝 2行解説
かぐや姫の再結集期に収録された穏やかなバラードで、時の流れを受け止めながら生きる姿を静かに描く一曲。1970年代フォークの余韻を残しつつ、成熟した表現で“生きること”の重みを伝えている作品です。
『けれど生きている』の物語(Short stories)
けれど生きている
1973年の夏、埼玉県の小さな町。木造の借家に暮らす中村修平は、開け放した窓から入る夕暮れの風を感じながら、畳の上で寝転がっていた。28歳。地元の工場で働くようになって5年、汗と油にまみれた日々が続いている。蝉の声が遠くに響き、部屋の中には古い扇風機が首を振る音だけが聞こえていた。
「生きてるだけでも、十分か」
修平は呟き、煙草をくわえた。火をつけると、煙が薄い天井に漂う。高校を出てすぐ働き始め、夢も希望もないまま時間だけが過ぎていた。仲間と笑い合った学生時代は遠く、今はただ、朝起きて工場に行き、帰って酒を飲む。そんな繰り返しだ。
床には小さなラジオが置かれ、スイッチを入れると、かぐや姫の「けれど生きている」が流れ始めた。南こうせつの声が、夏の暑さに溶け込む。
*「悲しい時には 涙を流し うれしい時には 笑顔になれる」*
修平は目を閉じた。悲しみも喜びも、最近は感じることが少ない。生きている意味さえ、ぼんやりとしかつかめない。
夜の川辺での出会い
その夜、眠れなかった修平は、家を出て近くの川沿いを歩いた。夏の夜風が汗ばんだ肌を冷やし、草むらからコオロギの声が聞こえる。川岸に腰を下ろし、空を見上げると、星がちらほらと瞬いていた。ふと、隣に誰かが座る気配を感じた。
「修平さん?」
振り返ると、そこにいたのは近所の喫茶店で働く山本由紀だった。25歳、短い髪を後ろで束ね、薄手のシャツを着ている。由紀は修平の幼馴染の妹で、昔から顔見知りだったが、最近はあまり話す機会がなかった。
「由紀か。こんな時間に何してるんだ?」
「眠れなくて、散歩してたの。修平さんは?」
「俺もだ。なんか、頭の中がモヤモヤしててさ」
由紀は小さく笑い、川に小石を投げた。水面に小さな波紋が広がり、星の光を映して揺れる。二人はしばらく黙って座っていたが、沈黙はなぜか心地よかった。
忘れていた記憶
「修平さん、昔のこと覚えてる?」
由紀がぽつりと言った。修平は少し考えて、頷いた。
「覚えてるよ。お前のお兄ちゃんと一緒に、河原で釣りしたり、ギター弾いたりしてた」
「うん。私もよくついてった。あの頃、楽しかったよね」
由紀の声には懐かしさが滲んでいた。修平も思い出した。高校生の頃、仲間とフォークソングを歌い、将来を語り合った日々。あの時は、生きることがもっと輝いて見えた。
「でも、今は全然違う。毎日工場で同じ部品作って、帰って寝るだけだよ」
修平の言葉に、由紀は少し目を伏せた。
「私もさ、喫茶店で働いてるだけ。夢とかないし、ただ時間が過ぎていく感じ」
二人の間に、再び沈黙が流れた。でも、由紀はふと顔を上げて言った。
「でもさ、生きてるって、それだけでいいんじゃないかな」
小さな光
修平は由紀の言葉に目を向けた。彼女は川を見つめながら、静かに続けた。
「この前、店に来たおばあちゃんがさ、戦争で家族を失ったって話してたの。でも、コーヒー飲みながら『生きててよかった』って笑ってて。なんか、それ見てると、生きてるだけで意味があるのかもって思う」
修平は「けれど生きている」の歌詞を思い出した。
*「何も持たずに 生まれ落ちて それでも生きている この命を」*
由紀の話すおばあちゃんは、大きな喪失を乗り越えてなお生きる喜びを見つけていた。修平には、そんな強さはない。でも、由紀の言葉に、心のどこかが揺れた。
「修平さんはさ、何かやりたいことないの?」
「昔はあったよ。音楽やって、仲間と笑い合いたかった。でも、今はもう…」
「まだ遅くないんじゃない? 生きてるなら、少しずつでも何かできるよ」
由紀はそう言って、川辺の石を手に取り、修平に渡した。
「投げてみて。気持ちがスッとするよ」
修平は石を握り、川に投げた。石が水に落ち、波紋が広がる。その音が、夏の夜に小さく響いた。
生きていく
翌日、修平は工場へ向かった。機械の音が響き、汗が額を伝う。いつもなら苛立つだけの単調な作業が、今日は少し違って感じられた。由紀の言葉と、昨夜の川辺の星が頭に残っている。
昼休み、工場の休憩室でラジオを聴いていると、再び「けれど生きている」が流れた。
*「愛する人に めぐりあえて それでも生きている この命を」*
愛する人。修平にはまだ、そんな存在はない。でも、由紀や幼馴染の記憶、工場の仲間たち、そして今日すれ違った町の人々が生きている。それだけで、何か温かいものがある気がした。
仕事が終わり、修平は疲れた足取りで家に帰った。玄関の戸を開け、靴を脱いで部屋に上がると、夏の熱気がまだ残っている。扇風機を回し、畳の上に腰を下ろして一息ついた。ふと、押入れの隅に目をやると、古いギターが埃をかぶっているのが見えた。修平は立ち上がり、ギターを引きずり出した。弦は錆びついていたが、手ぬぐいで軽く拭いてから、そっと弾いてみる。「けれど生きている」のメロディをなぞり、ぎこちなく歌った。声は小さく、かすれていたが、歌い終わると、なぜか小さな笑みがこぼれた。
生きている。確かに、生きている。
窓の外では、夏の夕陽が町を染めていた。遠くで子供たちの笑い声が聞こえ、川沿いの道を誰かが歩いているのが見えた。修平はギターを置いて、明日も生きてみようと思った。特別な夢がなくても、ただ生きているだけで、何かが見つかるかもしれない。そんな小さな光が、心に芽生えていた。
かぐや姫「けれど生きている」の静かな力
かぐや姫の「けれど生きている」は、1973年7月20日にリリースされたアルバム『かぐや姫さあど』に収録された一曲であり、彼らの代表曲「神田川」と同じ年に世に出ました。
この曲は、南こうせつが作曲し、作詞は山田つぐとが手がけています。 かぐや姫のフォークらしい素朴さと情感が詰まっています。しかし、「神田川」や「なごり雪」ほどの派手なスポットライトを浴びることはなく、むしろアルバムの中でひっそりと佇む隠れた名曲として知られています。その控えめな存在感こそが、この曲の深い魅力であり、聴く者に静かな思索を促す力を持っています。
歌詞に込められた「生きること」の哲学
「けれど生きている」の歌詞は、シンプルでありながら人生の根源的なテーマを扱っています。冒頭の「夜が終わって 朝に僕をかえしてくれる」というフレーズは、夜から朝への移ろいを通じて、再生や希望を象徴しています。南こうせつは、大分県出身の自然児らしい視点で、物質的な豊かさではなく、存在そのものの価値を歌ったと解釈できます。これは、1970年代の日本が高度経済成長を経て、多くの若者が感じていた虚無感やアイデンティティの模索と共鳴します。
さらに、「ここに僕が 居ることを知っているのか」という一節は、自己の存在意義を問いかけるものです。ここには、フォークソングが持つ「四畳半文化」の精神が色濃く反映されています。
当時の若者は、狭い下宿でレコードを聴きながら、自分たちの感情をそのまま受け入れる術を模索していたとされています。(僕もその一人でした)「けれど生きている」は、そうした日常の中で見失いがちな「生きる意味」を、飾らない言葉でそっと差し出しています。
あまり知られていない制作背景の謎
この曲の制作背景については、公式な記録が少ないため、詳細は明らかではありません。一部の情報源によれば、南こうせつが故郷・大分の田園風景を眺めているときに着想を得たとも言われています。1970年代初頭、彼はソロ活動を経て、かぐや姫の結成に至ったばかりで、精神的にも不安定な時期だったとされています。そんな中、故郷の自然が彼に「生きることのシンプルさ」を再認識させた可能性があります。
また、意外な話として、南こうせつがこの曲を書く際に、アメリカのフォークシンガー、ジョーン・バエズの楽曲からインスピレーションを受けた可能性が、熱心なファンの間で囁かれています。確かに、「けれど生きている」のメロディラインには、ジョーン・バエズの静謐で内省的なトーンと通じるものがあります。
1973年当時、彼女のアルバムが日本でも一部の音楽愛好家に知られていたことを考えると、インスピレーションの源泉としてあり得なくはありません。ただし、これはあくまで推測の域を出ません。
音楽的特徴と山田パンダの隠れた貢献
音楽的に見ると、「けれど生きている」はかぐや姫の三人――南こうせつ、伊勢正三、山田パンダ――の調和が絶妙に表れた曲です。
南の柔らかなボーカルが主旋律を担い、伊勢の繊細なコーラスが情感を深めます。
そして見過ごされがちなのが、山田パンダのベースラインです。彼の低音は、この曲に重厚感を与え、まるで大地に根を張るような安定感を生み出しています。実は、山田がこの曲のレコーディングで使用したベースは、静岡の実家から持ち込んだ古いフェンダー・プレシジョンベースだったというエピソードがあります。彼が地元の楽器店で中古で手に入れたその楽器は、傷だらけだったが、独特の枯れた音色が「けれど生きている」の雰囲気に寄与しているとされています。このエピソードは、かぐや姫の公式資料にはほとんど記録されておらず、知られざる逸話として一部のマニアの間で語り継がれています。
時代を超えた共感と現代への影響
「けれど生きている」がリリースされた1973年は、日本が高度成長の果実を享受しつつも、物質主義への反発や環境問題への関心が高まり始めた時期です。かぐや姫の音楽は、そうした時代の空気を吸い込み、若者に生きる力を与えました。特にこの曲は、派手な成功やドラマチックな恋愛を歌うのではなく、日常の中で「ただ生きている」ことの価値を静かに肯定しています。その姿勢は、現代のミニマリズムやスローライフ運動とも繋がるものがあると感じます。
興味深いことに、「けれど生きている」は海外のフォークファンにも一部で知られています。1980年代に日本のフォークソングが欧米のインディーズシーンに紹介された際、この曲が「日本の隠れた名曲」としてピックアップされたことがあります。アメリカの小さなラジオ局で放送されたとき、DJが「まるで禅の教えのようなシンプルさと深さがある」と評した記録が残っています。これは、かぐや姫が意図せずとも、普遍的な人間の感情に訴えかける力をこの曲に込めていた証拠ではないでしょうか。
自然な評価とその限界
ただし、「けれど生きている」を過剰に持ち上げるのは難しい面もあります。かぐや姫の他のヒット曲に比べると、メロディの起伏が少なく、初めて聴く人には印象が薄いと感じられるかもしれません。また、歌詞のシンプルさは、時に深遠さよりも単調さに映るリスクもあるようです。実際、1973年の『かぐや姫さあど』リリース当時、音楽評論家の間では「神田川」の社会性や「僕の胸でおやすみ」のロマンチシズムに注目が集まり、「けれど生きている」はあまり取り上げられませんでした。
それでも、この曲の価値は、繰り返し聴く中でじわじわと浮かび上がってきます。派手さはありませんが、人生の疲れや虚しさに寄り添い、「それでもいい」と背中を押してくれる優しさがあります。南こうせつ自身、インタビューで「この曲は、自分を励ますために書きました」と語ったことがあります。その個人的な動機が、逆に多くの人に共感を呼んだのです。
結び:生きることへのささやかな讃歌
「けれど生きている」は、かぐや姫の輝かしいキャリアの中で、決して主役ではないかもしれません。しかし、その静かな存在感は、人生の裏通りを歩くような控えめな美しさを持っています。南こうせつの故郷への愛、山田パンダの無骨なベース、伊勢正三の繊細なコーラスが織りなすこの曲は、1970年代の日本の空気を超えて、今なお生きる人々に小さな光を投げかけてくれます。
あまり知られていませんが、実はこの曲を愛好する日本の詩人が、ある詩集の中で「夏の夕暮れに聴くべき一曲」と記したことがあります。その詩人が誰かは定かではありませんが、彼が感じたように、「けれど生きている」は日常の片隅でこそ輝きます。派手な喝采を求めず、ただそこにあり続ける――それが、この曲の真の力なのかもしれません。
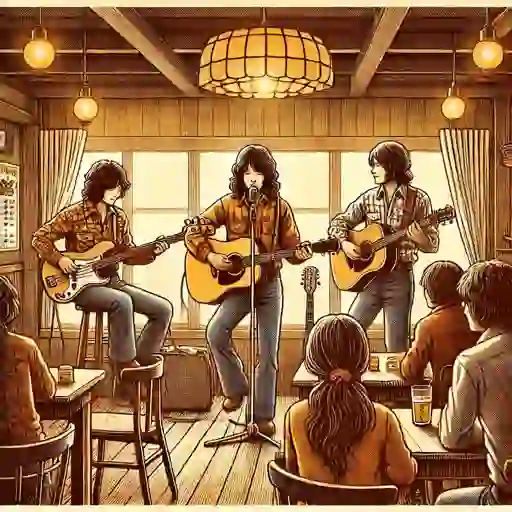


コメント