★「小椋佳」について詳しくは➡こちらのWikipediaでどうぞ!
心の残響を奏でる──小椋佳「めまい」の詩情と時代
「僕の勝手なBest10:【小椋佳】編-第8位は『めまい』です。
1975年11月21日、小椋佳の5枚目のシングルとしてリリースされた「めまい」。この楽曲は、彼の初期代表作としてだけでなく、1970年代半ばという社会と感情が揺れ動く時代の空気をとらえた、普遍的な名曲です。静かな旋律と深い内省の言葉は、現代においても色褪せることなく人々の胸に響きます。本記事では「めまい」を多角的に考察し、その魅力を丁寧に紐解いていきます。
Youtube動画でご覧ください

動画提供:春宮正勝 Song Channel(YouTube)
音源使用許諾元:株式会社ゴッド・フィールド・エンタープライズ(https://ogla-kei.club)
楽曲:「めまい」 作詞・作曲:小椋佳 © God Field Enterprise
動画の投稿者が、小椋佳サイドの管理会社(ゴッド・フィールド・エンタープライズ)から直接許可を得たとの表記もあり、許可内容は「音源使用に関する明示的な承諾」であり、非公式アップロードではなく「準公式(セミ・オフィシャル)」の位置づけと推測されます。従って、埋め込み動画とはせずにリンク形式でご紹介します。
1975年──不安と模索の時代
高度経済成長の終焉と心の彷徨
1975年の日本は、オイルショック後の景気後退に直面し、戦後の右肩上がりの経済神話が陰りを見せた年でした。消費者物価の急騰や失業率の上昇が生活に影を落とし、社会全体が先行きへの不安を抱える中、学生運動の熱も徐々に冷め、若者たちは社会変革から自己探求へと視点を移していきます。そんな時代背景の中、「めまい」は派手さとは無縁の、静かな感情の揺らぎを描きました。
フォークからニューミュージックへの橋渡し
同年、荒井由実が『COBALT HOUR』を発表し、シティポップの萌芽が見え始めた頃。吉田拓郎、井上陽水といったフォークの旗手たちは円熟期を迎えつつあり、新しい音楽の形が模索されていました。そんな中、小椋佳はフォークと歌謡曲、クラシック的抒情性を融合させ、独自の静謐な世界観を提示しました。

抑制された詩と旋律が紡ぐ、記憶の断片
風景が語る心のひだ
冒頭の「さよならを書こうとした口紅が 折れてはじけた」という一節は、別れの瞬間に訪れる感情の揺らぎを、あくまで抑制された描写で映し出しています。直接的な悲しみや動揺を表現するのではなく、身近な物の壊れ方に想いを託すことで、逆に心の動きを鮮やかに伝えているのが、小椋佳ならではの静かな詩情です。

サビに登場する「時は私に めまいだけを残してゆく」というフレーズは、過去の記憶が残像のように心に留まり、現実との境界が揺らいでいく様子を詩的に表現しています。「めまい」という言葉が象徴するのは、失われた愛や去っていった人への想いが、時間を超えてなお感覚の中に立ち上がる不確かさと余韻です。情熱や悲嘆ではなく、静かで曖昧な感情の残滓が、あくまで抑制された筆致で描かれています。
具体から抽象へ──記憶の構造
「めまい」は起承転結を持つ物語ではありません。記憶の断片が積み重なり、聴く者自身の記憶や想像によって補完されていく構造です。あえて空白を残すこの手法は、心理学でいう「投影」の効果を持ち、聴き手一人ひとりに異なる物語を立ち上がらせます。

ミニマリズムと情緒の音響構成
静けさの中の雄弁さ
アレンジは極めて控えめで、ピアノ、ストリングス、ベースが中心。イントロのピアノにはワーリッツァー風の温もりある音色が使われ、旋律の輪郭を際立たせつつ、歌詞が浮かび上がる空間を作り出しています。特定のフレーズに重なるストリングスの入り方は、感情を押し付けず、包み込むような印象を残します。
耳元で囁くような歌声
小椋佳の歌声は「歌う」よりも「語る」に近いスタイル。抑揚はあっても誇張されず、語尾まで丁寧に届ける姿勢が全体に親密なトーンを与えています。声質の透明感とほんのわずかなかすれが、余韻を強く残すのも彼ならではです。

小椋佳という存在の軌跡
東大卒銀行員から歌の世界へ
小椋佳は東京大学法学部卒業後、日本勧業銀行に入行。エリート官僚の道を歩みながら、裏で音楽制作を進める“二重生活”を送っていました。1971年にデビューし、その後『シクラメンのかほり』『さらば青春』などを次々と発表。合理主義と情感主義を併せ持つ彼のキャリアは、そのまま作品世界の二面性にも投影されています。
自作自演と提供曲の両輪
「めまい」は自作自演の中核作品ですが、小椋は布施明や美空ひばりなどへも楽曲を提供。表現者としても、作家としても高く評価されました。この二つの領域を自由に行き来できる作詞作曲家は、現在でも数少ない存在です。
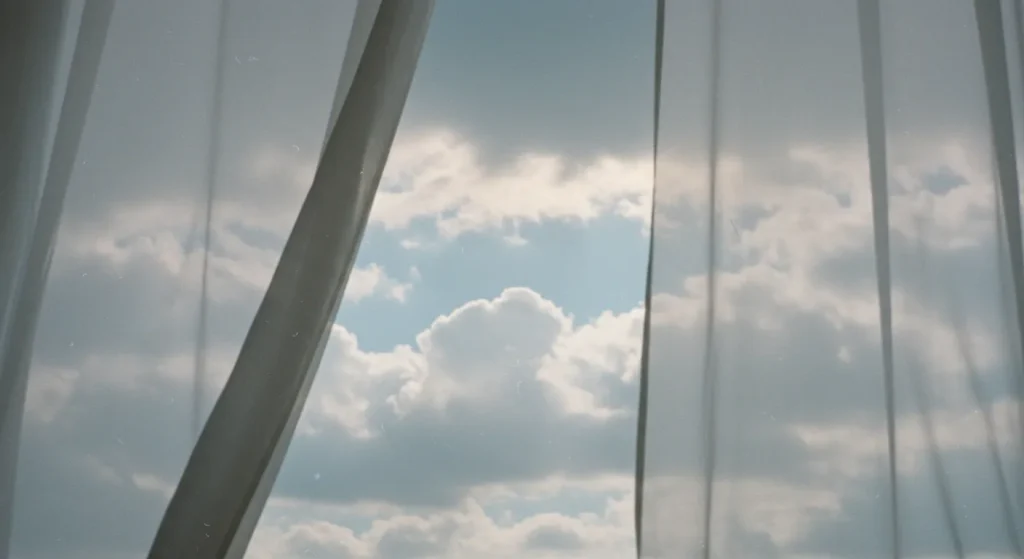
知られざるエピソードと評価の広がり
- ジャズピアニスト山下洋輔が1978年に「めまい」を即興演奏のテーマに採用。フォークの文脈を超えた音楽的普遍性が注目されました。
- 通信カラオケの統計によると、「めまい」は30代後半から50代の利用者に特に人気が高く、記憶と重ねる“再聴”の対象として選ばれています。
- 2015年のNHK『SONGS』で、本人の語りとともに当時のデモ音源やレコーディング風景が放映され、新たな世代に再評価のきっかけを与えました。
現代に響く「めまい」の余韻
「めまい」は、情報の洪水に溺れがちな現代において、“静かで個人的な時間”を取り戻すための処方箋のような存在です。情緒を直接的に訴えるのではなく、余白や抑制によって心の奥深くに触れるこの歌は、どんな時代にも通用する普遍性を持ちます。派手な展開も劇的な転調もないのに、聴き終えた後にふと深呼吸したくなる──そんな体験を提供してくれる作品です。



コメント