【8月1日】つのだ☆ひろの誕生日に聴く名曲 ―『メリー・ジェーン』をめぐって
ロックの系譜に刻まれた静かな衝撃
1949年8月1日、福島県に生まれたつのだ☆ひろは、音楽的多面性を持つ希有な存在です。10代でジャズドラマーとしてプロデビューを果たした後、ボーカリスト、作詞作曲家、さらには音楽教育者としても独自の活動を展開してきました。
彼の名を広く知らしめたのが、1972年発表の『メリー・ジェーン』です。シングルB面から始まったこの楽曲は、時間とともに深く浸透し、今なお多くの人々に聴き継がれています。
まずはYoutube動画の(公式動画)からどうぞ!!
🎬 公式動画クレジット
Provided to YouTube by Universal Music Group
Mary Jane · Hiro Tsunoda
© 1971 UNIVERSAL MUSIC LLC
📖 2行解説:
1971年にリリースされたアーバンなソウル・バラード。
つのだ☆ひろの哀愁あるボーカルが、日本のシティ・ポップ前夜を彩る名曲です。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 1971 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
僕がこの曲を初めて聴いたのは、リリース当時かどうかは覚えていませんが、中学時代には間違いないです。
「つのだひろ」という名前を先に耳にしていたので、外人が歌っているのではいと知りながら聞いた記憶があります。ただ、”英語上手いなあ”とは思いましたね。
この手のバラードに弱い僕なので、これまでの生涯で何度聴いたかわかりません。
前編英語の歌を、日本人らしくない歌唱で歌える人は少なく、つのだひろやゴダイゴのタケカワユキヒデくらいしか浮かびません。
『メリー・ジェーン』の誕生と構造
原型はサイケデリック・ロックの1曲だった
1971年、つのだ☆ひろとギタリスト成毛滋が結成したユニット「ストロベリー・パス」がリリースしたアルバム『When The Raven Has Come To The Earth』に、「Mary Jane On My Mind」という楽曲が収録されました。これが、のちの『メリー・ジェーン』の原型です。

サイケデリックな要素を含むこの楽曲は、当時は一般層には届きにくい作品でした。
再録・再構成されてB面に登場
翌1972年、つのだ☆ひろ名義で再録された『メリー・ジェーン』は、シングル『雨が空から降れば』のB面として世に出ます。A面は永六輔・いずみたくのコンビによる穏やかな歌謡曲であり、両面で全く異なる印象を与える構成でした。
表舞台に立つことのなかったB面曲でありながら、やがて多くのリスナーに届くこととなるのは、音楽そのものが持つ強度によるものでした。

1972年――大きなうねりの中で
社会が揺れた出来事の数々
『メリー・ジェーン』が発表された1972年、日本は内外の出来事に揺れていました。
- 2月:札幌で冬季オリンピックが開催。笠谷幸生らの金メダル獲得で日本中が熱狂。
- 同月:連合赤軍によるあさま山荘事件が発生。テレビ中継された突入劇は社会を震撼させました。
- 7月:田中角栄内閣が発足。「日本列島改造論」が打ち出され、インフラ整備が加速。
- 10月:日中国交正常化が実現。外交政策が大きく転換されました。
- 同年:上野動物園に中国からのパンダ「カンカン」「ランラン」が来日し、パンダブームが巻き起こりました。

こうした激動の中、音楽もまた新たな表現領域を模索していました。
音楽シーンの主役とロックの立ち位置
1972年の音楽シーンでは、歌謡曲が全盛期を迎えていました。宮史郎とぴんからトリオの『女のみち』は異例の大ヒットを記録し、フォークソングでは、よしだたくろう(当時)の『結婚しようよ』や『旅の宿』が若者の心をとらえていました。
また、天地真理、小柳ルミ子、南沙織といった「新三人娘」がテレビを席巻し、アイドル文化が本格的に形成されていきます。(みな僕よりお姉さんです!)
一方、ロックミュージックはまだ主流とは言えず、ラジオ番組や一部の深夜放送で取り上げられる程度。『メリー・ジェーン』も当初はスポットライトの外にありましたが、少しずつ浸透していきます。
楽曲構造と演奏が語るもの
ボーカルが持つ質感と表現力
つのだ☆ひろのボーカルは、声量で圧倒するものではありません。息遣いや声のかすれ方、言葉の途切れ方といった微細な要素に、情感が滲み出しています。
彼は10代の頃からジャズドラマーとして活動し、R&Bやソウルにも深く親しんできました。その経験が、言葉の運び方やリズムの取り方に反映されています。

また、ファルセットや絞り出すような低音の使い方に、感情表現を過剰に煽らずとも伝える技術の高さがうかがえます。
『メリー・ジェーン』に秘められた言葉と物語
英語詞が描くまっすぐな心情
『メリー・ジェーン』は全編英語で書かれています。作詞はクリストファー・リン。メロディに沿って綴られる言葉は、抽象ではなく、直接的な感情を表現しています。
Mary Jane on my mind
(メリー・ジェーン、君のことが頭から離れない)
I cry my eyes out over you
(君のことで泣きはらしている)
Long long and lonely night
(長くて孤独な夜)
Ever since you’re gone
(君がいなくなってからずっと)
これらのフレーズは、去ってしまった恋人に対する想いを正面から描いています。悲嘆に暮れる主人公は、夜ごとに彼女を夢に見て、彼女の髪を撫でる仕草を繰り返しながら、心のどこかで永遠に待ち続けることを受け入れています。

難解な比喩や技巧に頼ることなく、まっすぐな言葉だけで構成されているため、楽曲全体に一貫した誠実さと切実さが宿っています。
「Mary Jane」が持つもう一つの意味
スラングとしての「Mary Jane」
この曲のタイトルである「Mary Jane」には、実はもう一つの意味があります。それは、マリファナ(大麻)を指すスラングです。この語が比喩的に用いられる文化的背景はアメリカにあり、1960年代以降のロックやヒッピー文化ではよく知られた表現となっていました。
このため、『メリー・ジェーン』というタイトルに接した一部のリスナーやメディアは、失恋ソングではなく「依存」と「陶酔」の象徴として解釈したのです。
このような二重性が話題を呼び、曲そのものにミステリアスな魅力を付加したことは否定できません。
アンダーグラウンド・シーンとの親和性
1970年代初頭の日本では、まだ大麻に関する社会的認識は曖昧でしたが、欧米の音楽を嗜む層の間ではスラングの意味がある程度知られていました。その結果、この曲はサブカルチャーの文脈でも受容され、単なるバラードではなく“隠れた意味を持つ曲”として認識されるようになりました。
ただし、それが意図されたものだったのかは別の問題です。
本人が明かした創作の真相
モデルとなった「メリー・ジェーン」の存在
この「二重の意味」について、つのだ☆ひろ本人は明確に否定しています。複数のインタビューや記事によれば、この曲は彼が当時好意を寄せていた留学生「マーガレット」のために書かれたものだったと語られています。

マーガレットという名前は、歌詞やメロディの語感として使いづらかったため、彼女の友人の名である「メリー・ジェーン」を借りた――それが命名の真相だったのです。
この裏話は、謎めいた印象とは裏腹に、個人的で素朴な動機から生まれた曲だったことを示しています。
ひそやかな広がりと支持の蓄積
ラジオからディスコ、そしてカラオケへ
『メリー・ジェーン』は発売当初から爆発的なヒットを記録したわけではありません。テレビでの露出もほとんどなく、当時のヒットチャート上位に名を連ねたわけでもありませんでした。
しかし、深夜ラジオ番組でのオンエアが増えるにつれ、じわじわとその存在が知られていきます。さらに、ディスコブームが到来すると、チークタイムの定番曲として選ばれるようになり、若者たちの間で「知る人ぞ知る名曲」として広まっていきました。

時代が進むと、カラオケの普及によって再び脚光を浴びるようになります。ドラマティックなメロディと英語詞の情感が、歌いごたえのある一曲として定着。世代を超えて歌い継がれる要素となったのです。
ロングセラーへの道のり
B面曲として始まったにもかかわらず、最終的に『メリー・ジェーン』は累計200万枚以上のセールスを記録したとされています。これは、特定のヒット時期に依存せず、長い年月をかけて人々の支持を獲得してきた証です。
ミリオンセラーを超えてロングセラーへ。静かに、しかし確実に浸透していったこの曲の軌跡は、つのだ☆ひろの音楽的力量と、作品が持つ説得力の強さを物語っています。
作曲家・提供者としての才能
歌唱だけでないメロディメーカーとしての手腕
つのだ☆ひろは、他アーティストへの楽曲提供でも多くの実績を持ちます。たとえば、清水健太郎に提供した『失恋レストラン』は、つのだ作品の中でも大きなヒットを記録しました。(これも僕の青春を飾る名曲です。)この曲でも、哀愁あるメロディと印象的なフレーズが共通しており、彼の音楽的美意識がうかがえます。

また、研ナオコや南沙織といった女性アーティストにも楽曲を提供しており、幅広い声質・ジャンルに対応できるメロディセンスとアレンジ力が評価されています。
今なお響く曲として
「失恋」ではなく「記憶」の曲へ
当初は失恋ソングとして捉えられていたこの曲ですが、年月を経るごとに、「かつての記憶」「手放したもの」「戻らない時間」といった、より抽象的で内面的なテーマとして聴かれることが増えてきました。
その変化は、楽曲自体が古びず、聴き手の成長や変化に柔軟に対応できる構造を持っていたことの証でもあります。
今後も受け継がれるべき理由
つのだ☆ひろの音楽には、技術や知識だけでは到達できない人間的な厚みがあります。『メリー・ジェーン』は、その最たる結晶であり、世代や文化が変わってもなお、誰かの胸に届く可能性を持つ楽曲です。
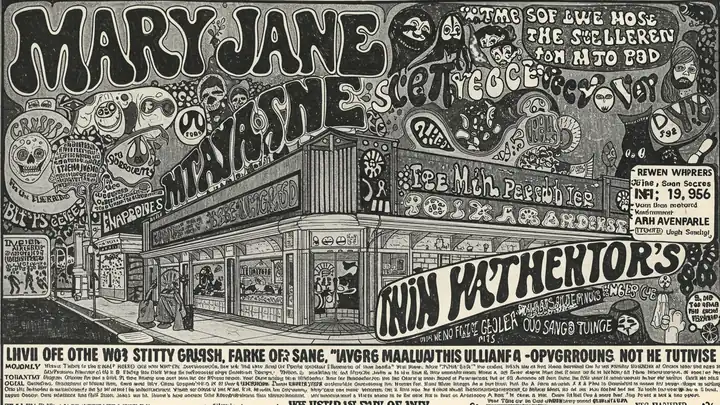


コメント