■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで~(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
〜絶望のキャンバスに描く、希望という名の欺瞞〜序盤だからこそ紹介したい、評価の難しい一曲 『青空』
こんにちは。「ふきのとう」ファンの皆さんも、初めて名前を聞いたという方も、ようこそお越しくださいました。
今回は、「僕の勝手なBest30」シリーズ第26位の紹介です。全体の構成でいえばまだ序盤の域ですが、すでに選曲にはかなり悩まされております。というのも、このあたりの順位には、単純な“好き嫌い”では語れない、評価の難しい楽曲が数多く並んでいるからです。
その代表格とも言えるのが、今回取り上げる『青空』です。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『青空』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
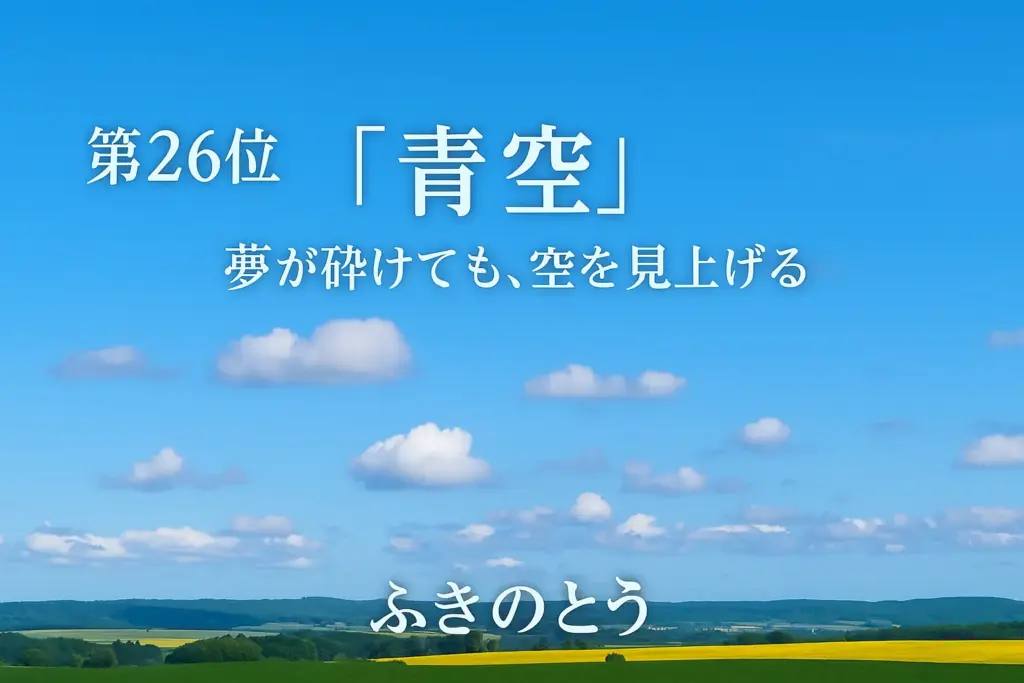
🎥 🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:『青空』(公開日:2015/07/01)
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。
※公式アカウントによる配信ではありません。
※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
一見、希望に満ちたタイトル。しかし…
『青空』は、1979年に発表されたアルバム『人生・春・横断』に収録された楽曲で、作詞・作曲は山木康世。ふきのとうの中でも特に文学性の強い作品の一つとされています。
このアルバム自体、ふきのとうのキャリアの中盤にあたり、フォークからポップスへと緩やかに移行していく過程を象徴するような楽曲群で構成されています。その中にあって『青空』は異彩を放っており、牧歌的でも、叙情的でもなく、あまりに内省的で重たい作品です。

タイトルだけを見ると、まるで前向きで晴れやかな印象を与えます。「青空」とは、どこまでも続く自由、澄んだ希望、閉塞からの解放――そんなイメージを喚起する言葉です。特にフォークデュオであるふきのとうにとって、自然や空の描写はお馴染みのモチーフであり、多くのリスナーはこの曲にも同様の爽快感を期待することでしょう。
しかし、『青空』の実像は、その期待を静かに、しかし確実に裏切ってきます。
“青空”は希望ではなく、逃避と幻影の象徴
この曲で描かれる「青空」は、決して現実を照らす光ではありません。それはむしろ、“傷を抱えた心が目を逸らす先”としての空であり、届かぬ理想としての空です。
歌詞の中には、現実から目を背けて空を見上げる人々が登場します。その姿は哀れでもなければ美しくもなく、ただ、どうしようもなく人間的です。

このような空の描き方は、当時のフォークソングでは稀でした。多くの楽曲が癒しや希望を強調する中で、『青空』はあえて「手の届かない理想にすがる哀しみ」や「現実逃避としての空」を描いています。ある意味でこれは、時代を先取りしていたとも言えるかもしれません。
三重構造で描かれる寓話的構成
この曲の最大の魅力は、詩的な構造の中に人間心理の多層性を織り込んでいる点にあります。
- 公園のベンチに座る男
- 薄暗い部屋に籠もる子供
- 死んだ夢を抱えたまま気づかぬ語り手
ひとつひとつの登場人物に直接的な名前や設定はありません。それでもなお、誰もがその中に“自分の過去”や“現在の心の断面”を投影してしまう――それこそが、ふきのとうの詩世界が持つ魔力でしょう。
公園の男と「鏡の裏」
ベンチに座る男は、社会と折り合えずに弾かれた存在のようであり、自ら孤独を選んだ人間のようでもあります。「彼の得意なポーズだってことは 鏡の裏に見えている」という言葉が、彼の強がりと心の奥を同時に暴いています。

語り手は彼を突き放すのではなく、同じ痛みを抱えているからこそ、そのポーズの裏にある心情を見抜くことができる。まさに「鏡の裏」から覗いているのは、自分自身なのかもしれません。
飴玉をしゃぶる子供
続いて登場する「薄暗い部屋にいる子供」は、孤独を“飴玉”と呼び、それをしゃぶっているという衝撃的な比喩で描かれます。自己防衛としての閉じこもり、自分の涙にしか関心を持たない姿は、大人の中に残る未成熟な感情の象徴です。
現代の「大人の子供化」や、「共感疲れ」など、今でこそよく聞かれる心理的傾向を、当時の段階で鋭く描き出していたのだとしたら、この歌詞の先見性は見逃せません。
語り手が見つめる「死んじまった夢」
物語はやがて、語り手自身の内面へと深く潜っていきます。かつて追いかけた夢が腕から滑り落ちていく――これは誰しもが経験するような、人生の節目における挫折の描写に見えます。

しかし、この楽曲はそこから一歩踏み込んでこう問いかけます。「本当に悲しいのは、その夢が壊れたことじゃない」と。
夢がすでに死んでしまっているのに、その事実にすら気づかず、自分はまだ何かを追いかけているつもりになっている。その姿は、現代の私たちにとっても決して他人事ではないのではないでしょうか。
「過去の夢にしがみつくこと」と、「それがまだ生きていると信じ込むこと」は、似て非なるもの。後者の状態にある時、人はもっとも危うく、そしてもっとも脆い存在になります。
サビに込められた爆発的メッセージ
廃墟を描く行為と“write way up”の謎
サビでは「空に絵を描こう」と語られますが、その絵にはクレヨン、絵の具、そして血が使われます。描かれるのは“廃墟”。

このイメージは、「痛みや現実から目を背けず、それを空に描き出すことで自分を再構成しようとする意志」と解釈できます。繰り返される “write way up” という表現は意味的には曖昧ですが、その分だけ「叫び」としての力を持ちます。
「正気でいられる方法が、もはや叫ぶことしかなかった」――このような状況で、あえて空に描くという姿勢。それは他人に理解されることを望まず、自らの傷と共に立ち向かう覚悟の表れです。
ボーカルとアレンジが果たす役割
細坪基佳の声が与える“浄化”
細坪の透明感ある声は、この暗い楽曲に不思議な浮力を与えます。直接的に癒すわけではなく、傷を丁寧になぞるような歌い方が、逆に聴き手に安心感を与えます。
特に中音域から高音域にかけての柔らかなニュアンスは、山木康世の作る鋭利な歌詞と対照を成し、音楽としてのバランスを絶妙に保っています。
乾いたアコースティックサウンド
アコースティックギターを中心としたアレンジは、過剰な感情表現を避けており、都市の冷たさや個人の乾いた心情を反映しています。この潔さが、逆に信頼感を生んでいます。

まるでドキュメンタリーのように情景を切り取る音の配置。余計な飾りを廃したそのミニマルさが、かえって言葉の強さを際立たせているのです。
なぜ今『青空』が響くのか
この曲が生まれた1979年、日本は物質的に豊かになり始めていたものの、精神的にはまだ満たされていない社会でした。40年以上が経過した今でも、「死んだ夢を抱えながら空を見上げる人間」の姿は、現代人の姿そのものと重なります。
SNS時代の自己演出、アルゴリズム化された夢、孤独と虚構の共存。『青空』はそれらを鏡のように映し出してきます。

今こそ必要なのは、誰かに褒められる夢ではなく、自分の内から湧き上がる「意味」。それを見つけるために、まずは自分の中にある「廃墟」を認めることから始めようと、この曲は教えてくれているように思えます。
青空とは何か:希望の象徴か、幻の理想か
「決して届かない理想」であり、「逃避の対象」としての空でもなお、語り手は空に絵を描こうとします。傷だらけの現実を抱えたまま、それでも表現しようとする姿勢が、この曲に逆説的な希望を与えているのです。
空は逃避の先にあるだけではない。自分の中の混沌や崩壊を、あえてその空に刻み込もうとする“逆流の営み”。それこそが『青空』という曲が持つ、静かで強い再生の力です。

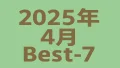

コメント