「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで~北の大地から生まれたハーモニー(1970〜1976)
■【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
僕の勝手なBest30:【ふきのとう】編 − 第24位『春雷』
2025年6月。梅雨の合間に揺れる不安定な空模様。そんな空を見上げると、ふきのとうの名曲『春雷』が、ふと脳裏に響き始めるようです。ってなわけで、第24位は「春雷」です。
この曲は、1979年4月25日にリリースされたシングル作品であり、同年7月21日に発売されたアルバム『人生・春・横断』にも収録されています。
“勝手なベスト30”では第24位に選出していますが、ランキング以上の印象と余韻を残す一曲であることは間違いありません。当然、ふきのとうファンならずとも、この曲のランクはもっと上位にあげるでしょうね!
しかし、すでにお気づきかもしれませんが、ここまで紹介してきた6曲は、穏やかなやさしい楽曲ばかりです。僕は「ふきのとう」を、基本その路線の曲中心に聴いてきました。なので「春雷」のようなパワーのある楽曲の方が、僕のセレクトとしては珍しい方だと思います。

春の移ろいや出会いと別れを、自然の力――すなわち「雷」をモチーフに描き上げたこの作品。そこには、ふきのとうらしい繊細な情感と、激しさを内包する詩情が共存しています。
本稿では、音楽構造・歌詞の世界・文化的背景・時代との関係・そして現代のリスナーの受け止め方という多角的視点から、『春雷』の魅力を丁寧にひも解いていきます。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『春雷』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
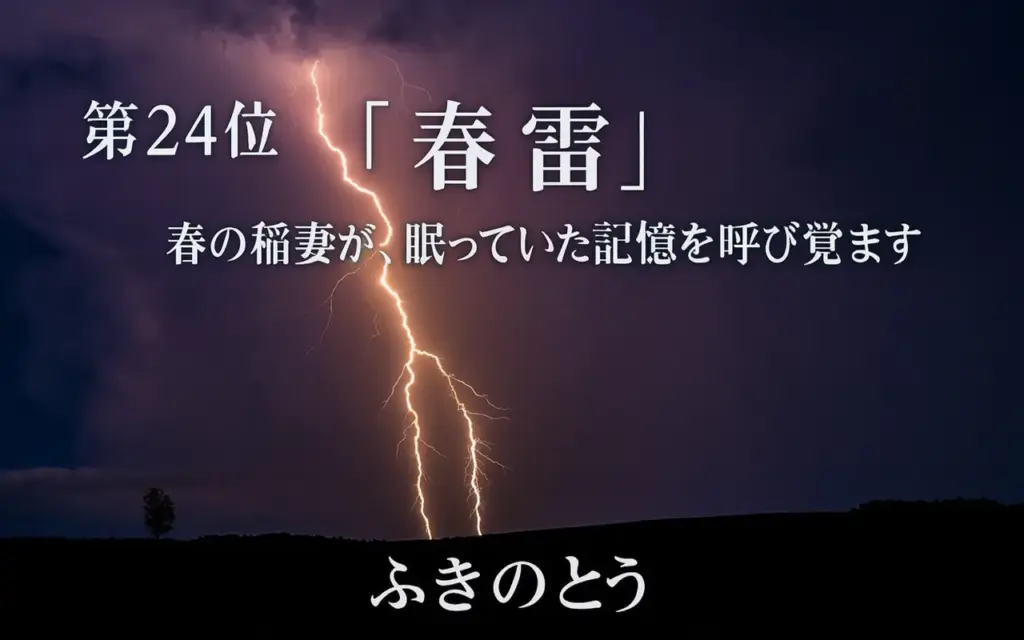
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより ♬ブロック解除記念☼*゚·*: ふきのとう/⑬春雷 (1979年2月25日発売) 作詞・作曲:山木康世/編曲:瀬尾一三 (公開日:2021/4/26) ※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。 ※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
音楽的構造:雷鳴のような抑揚と抒情性
ギターのストロークが切り拓く情景
『春雷』の冒頭に登場するギターのカッティングは、乾いた音色でありながら、まるで春の空を裂く一閃の雷鳴のような強いインパクトを放っています。

コード進行はマイナー調で始まり、サビでは明るいメジャー調へと移行していく構造。これにより、「曇天から晴れ間へ」という感覚の変化が自然と浮かび上がり、音の中に気象の移ろいを感じ取れるような感覚が生まれます。
この抑揚は、『春雷』という楽曲タイトルの比喩そのものといえるでしょう。
ボーカルとアンサンブルの呼応
細坪基佳の歌声は、この曲でも抜群の表現力を発揮しています。
Aメロではやや抑制された語りかけのようなトーンで、情景を丁寧に描写。一方、サビでは広がりのある音域を駆使して、抑えきれない感情のうねりを解き放っています。

その背後では、アコースティックギターやピアノが静かに旋律を支え、リズムセクションも最小限に抑えられた構成が採られています。静と動の対比が、この曲のドラマ性を一層引き立てています。
歌詞に宿る記憶と風景のリアリズム
桜と雷鳴、儚さと記憶の交錯
「春の雷に白い花が散り」「桜花吹雪 風に消えてゆく」――。こうした歌詞は、春の一場面を超えて、日本人の記憶に刻まれた“別れ”や“再会”の情景を呼び起こします。
桜と雷という対照的な自然現象を一つの画面に収めることで、美と無常、儚さと覚醒という二重性が強調されます。
また、「過ぎた日を懐かしみ」「肩組んで涙ぐんで」といったフレーズからは、かつての友情や恋愛への想いが感じられ、聴く者の個人的な記憶と結びついていきます。

終盤に込められた“命”の肯定
「この世の運命を 春の雷に 散るな今すぐに/桜花吹雪 命つづくまで」と繰り返される終盤の歌詞は、『春雷』の核心ともいえる部分です。
ここには、散りゆくものへの哀惜とともに、それでもなお命は続いていくのだという“再生”のメッセージが込められています。
雷鳴が過ぎ去ったあとに残る静けさのように、痛みの先にある希望をそっと提示してくれているのです。

日本文化における「春雷」というモチーフ
雷は恵みか、変化の予兆か
日本の伝統文化において“雷”は、しばしば神の使いとして描かれ、また稲妻は豊作の予兆としても扱われてきました。一方で、激しく鳴り響く音には破壊や不安の象徴としての側面もあり、雷は“二面性”を持つ自然現象とされています。
ふきのとうは、こうした日本古来の雷の捉え方を巧みに織り込みながら、「過去への思慕と未来への意志」を歌詞のなかに共存させています。
桜と雷を同時に描いた意義
日本では、桜の花が“散ること”によって美しさを完成させると考えられてきました。
その桜を、「雷によって吹き飛ばされる存在」として描いた『春雷』は、単なる花の描写にとどまらず、「抗えない力」と「諦めない心」のせめぎ合いを表していると読むこともできるでしょう。
リスナーの視点:心に重なる“雷鳴”
自分自身を投影できる楽曲
『春雷』には、具体的な登場人物も、明確なストーリーラインも登場しません。
だからこそ、聴き手は自身の体験――たとえば、春の別れや進学、忘れられない恋の記憶など――を投影しやすくなっており、「自分だけの物語」としてこの曲を受け止めることが可能となっています。
この普遍性と余白の多さこそが、『春雷』が今もなお幅広い層に愛され続けている理由です。
世代を超えて響く自然の象徴
春雷や桜といった自然のモチーフは、時代や年齢を超えて、多くの人の記憶や感情に残る存在です。
だからこそ、この曲の持つメッセージ――「変化」「別れ」「希望」――は、10代の若者にも、還暦を迎えた世代にも、同じように届くのです。

音楽的影響と現代への波及
自然と感情を融合した後進たち
『春雷』のスタイルは、直接的な影響を明言していないまでも、現代のアーティストたちの作品にその精神が色濃く表れています。たとえば、森山直太朗の『さくら』や、スピッツの自然描写、さらには藤井風の情緒的世界観の中にも、1970年代フォークの文脈が感じられます。
特に自然と心象風景を丁寧に結びつけるスタイルは、ふきのとうの系譜を継いでいるといっても過言ではありません。
再解釈される『春雷』
細坪基佳のソロライブでは、『春雷』がテンポを落とし、より内省的な表現で再演される場面が増えています。また、若手アーティストによるカバーや、ピアノによるインストゥルメンタル・アレンジなども登場し、曲の持つ“柔軟性”が浮かび上がってきました。
こうした再構築の動きは、『春雷』という楽曲が単なるノスタルジーではなく、現在進行形の「生きた音楽」として受け入れられている証拠といえます。
映像と融合する『春雷』の未来
音楽と物語が出会う瞬間
たとえば、桜の舞う並木道を、青年がひとり歩くシーン。空には薄い陽が射し、遠くで雷が鳴っている。そのときに流れる『春雷』――このイメージだけで、物語が生まれてきそうです。

テレビドラマ、映画、CM、ドキュメンタリーなど、さまざまなジャンルにおいて、この曲が使われる可能性は決して小さくありません。
結びにかえて:心を打つ一閃の雷
雷は、決して避けられない“転機”を象徴します。人生の節目に差し掛かったとき、どうしようもない感情が湧き上がったとき、誰かのことをふと思い出したとき――『春雷』は、そんな瞬間をやさしく後押ししてくれる音楽です。
春だけでなく、どの季節にもふと聴きたくなるこの曲を、あなたの心の“再起動スイッチ”として、ぜひこれからもそばに置いてほしいと思います。




コメント