今日は、デイヴ・ファレル(David Michael Farrell)の誕生日です。
今日(2025.2.8日)は1977年生まれのデイヴ・ファレル(David Michael Farrell)の誕生日です。
リンキン・パークのベーシストで、フェニックス(Phoenix)という名前で知られています。
今日の紹介曲:『Burning In The Skies』-(リンキン・パーク)です。-(公式動画)
クレジット
楽曲名: Burning In The Skies
アーティスト: Linkin Park
アルバム: A Thousand Suns
リリース: 2010年(アルバム収録)、シングルは2011年2月21日リリース
2行解説
エレクトロニカとロックを融合させた『A Thousand Suns』収録曲のひとつで、戦争と人類の過ちを静かに問いかける作品。メロディアスなサウンドとチェスター・ベニントンのボーカルが、深い余韻を残すバラードとして評価されています。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 2010 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
この曲を初めて聴いたのは、50才代には間違いないですが、ハッキリとは覚えていません。
恐らくYoutubeあたりで見かけて聴いたのだと思います。
リンキン・パークのことはほぼ知りません。他の曲も聴いてはみましたが、僕の耳には合いませんでした。( ;∀;) なので、今現在はこの曲しかお勧めできませんし、コアなファンには申し訳なく思います。
そんなにも好きか?と訊かれれば
大好きな曲です。理由は『静かなる疾走感』この感覚につきます。
ただ紹介する以上は、しっかり調べたものをしかりと紹介いたします。
『Burning In The Skies』深層分析:リンキン・パークが描いた崩壊と再生の美学
リンキン・パークの楽曲『Burning In The Skies』は、2010年にリリースされたアルバム『A Thousand Suns』の収録曲のひとつであり、バンドの音楽的進化を象徴する重要な作品です。これまでのヘヴィロックから一線を画し、電子音楽やアンビエントな要素を大胆に取り入れたこのアルバムは、賛否を巻き起こしながらも、彼らの革新的な姿勢を証明しました。
本記事では、『Burning In The Skies』に込められたテーマや、制作過程にまつわる興味深いエピソード、さらにはその音楽的アプローチについて深く掘り下げていきます。
アルバム『A Thousand Suns』と時代背景
2000年代後半、世界は政治的・経済的混乱に包まれていました。9.11同時多発テロ、環境問題の深刻化、戦争の影響など、人類の未来に対する不安が高まる中で、『A Thousand Suns』はまるで時代の不穏な空気を音楽に落とし込んだかのようなアルバムとなりました。
アルバム全体のコンセプトは、「核戦争後の世界」。マイク・シノダとチェスター・ベニントンを中心とするリンキン・パークは、単なる破壊のイメージだけでなく、その中に潜む希望や再生の可能性をも探求しました。『Burning In The Skies』はその象徴的な楽曲の一つであり、喪失感と未来への展望が交錯する作品として、多くのファンに深い印象を残しました。
歌詞の解釈:崩壊の美と再生への祈り
『Burning In The Skies』というタイトルが示すように、この楽曲は「空に燃え広がる炎」という壮大なイメージを描きます。これは、戦争や災害による破壊のメタファーであると同時に、個人の内面的な葛藤や喪失をも象徴していると言えるでしょう。
歌詞の一節には、次のようなフレーズがあります。
I’m swimming in the smoke
Of bridges I have burned
So don’t apologize
I’m losing what I don’t deserve…

「自ら焼き払った橋の煙の中を泳ぐ」という表現は、過去の選択や行動がもたらした結果に直面する主人公の心情を表しているように感じられます。人は時として、自らの過ちや逃れられない運命の炎の中に取り残されるものです。しかし、その後に続く「謝らなくていい」という言葉は、過去の喪失や傷を受け入れ、それでも前に進むべきだというメッセージを含んでいます。
また、「失う資格すらなかったものを失う」というフレーズは、人生において突然訪れる不条理な喪失や、後悔にさいなまれる感情を呼び起こします。これは個人的な体験だけでなく、社会全体の不安や絶望感をも象徴しているように思えます。
音楽的アプローチ:静と動の対比
『Burning In The Skies』は、従来のリンキン・パークの楽曲とは異なり、攻撃的なギターリフやラップ要素を排除し、エレクトロニカの要素をふんだんに取り入れた楽曲となっています。そのため、一見するとシンプルな構成に見えますが、実際には巧妙に設計されたサウンドデザインが施されています。
特に注目すべきは、イントロの静謐なシンセサイザーと、楽曲全体を包み込むようなアンビエントな音作りです。ミニマルなビートと広がりのあるシンセサウンドが、楽曲の持つ儚さや幻想的な雰囲気を強調しています。
また、楽曲は静かに始まり、サビへ向かうにつれて徐々に音の厚みが増していきます。(この状況を僕は「静かなる疾走感」と表現させてもらいました。)この「静と動」の対比が、楽曲の持つ感情的な起伏を際立たせているのです。
制作の裏話:隠された音と実験的アプローチ
『Burning In The Skies』の制作には、いくつかのユニークな手法が取り入れられました。例えば、一部の音にはスタジオ外で録音された環境音が使用されていると言われています。都市の喧騒や風の音、さらにはラジオのノイズのような微細なサウンドが、楽曲の背後でかすかに聞こえることがあります。
また、アルバム全体を通じて「歴史的な音源」が組み込まれているのも特徴の一つです。『A Thousand Suns』には、実際の政治演説や戦時中の音声がサンプリングされており、音楽を通じて社会的なメッセージを発信するという試みがなされています。『Burning In The Skies』でも、これらのサウンドが巧妙に溶け込んでいる可能性があり、リスナーが意識せずとも「歴史の断片」を感じ取ることができるようになっています。
まとめ:時代を超えて響く楽曲
『Burning In The Skies』は、単なるロックバンドの楽曲ではなく、社会や人間の心理を深く掘り下げた作品です。核戦争や環境破壊といった大きなテーマの中に、個人的な喪失や再生の物語が織り込まれており、聴く者に強い共感を呼び起こします。
音楽的にも、リンキン・パークの新たな挑戦が色濃く反映されており、エレクトロニカやアンビエントの要素を取り入れたサウンドは、後の音楽シーンにも影響を与えました。今なお、多くのリスナーにとって特別な意味を持つこの楽曲は、時代を超えて語り継がれるべき一曲であると言えるでしょう。


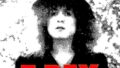
コメント