今日は、ブライアン・フェリーの誕生日
1945年9月26日、英国ノーサンバーランド生まれ。美術大学でリチャード・ハミルトンに学んだ審美眼をそのまま音へ移植し、1971年にロキシー・ミュージックを結成。初期は前衛色の濃い衝動、後期は磨き抜かれた品位へ。歌、言葉、装い、アートワークを統合して“ブランドとしてのロック”を打ち立てた存在です。
超約
パーティが終わった夜、更けゆく会場で“君”と突然の出会い。
言葉よりも動きで気持ちが通じ、サンバやボサ・ノヴァのステップが二人を導く。
景色は少しずつ変わり、行き先はまだ分からないまま高揚が増していき、そしてただ「Avalon」と名を呼ぶことで、理想の場所への確信が強まっていく・・・そんな感じの歌です。
まずはYoutubeの公式動画をご覧ください。
✅ 公式動画クレジット 🎵 Roxy Music – Avalon (公式MV / 1982年) 📺 YouTube公式チャンネル(Roxy Music Official / VEVO) ✨ 2行解説 アルバム『Avalon』の表題曲で、Roxy Musicの代表的なラスト期の名曲。 幻想的なサウンドと洗練された映像美が、バンドの成熟した世界観を象徴している。
僕がこの曲を初めて聴いたのは
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 1982 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
ロキシーミュージックの楽曲は、2025年1月31日に『More Than This』を紹介しています。
この曲も、今回紹介するアルバム表題曲の『Avalon(アヴァロン)』に挿入されている曲です。
『More Than This』は、ポップ的要素が強く少し派手な感じがしますが、今日紹介する「Avalon」はダンサンブルでおしゃれ、都会的雰囲気満載な楽曲です。
前回も書きましたが、独身寮に1年後から入寮してきた、同じ大学の後輩から教えてもらったらアルバムでした。
あれから、40年強が過ぎましたが、色あせることなく、今でもその都会的な雰囲気は通用します。
夜にお酒を楽しみながらゆっくり聞ける一曲です。
『Avalon』の核心を見通します
1982年5月に発表されたロキシー・ミュージック最終作『Avalon』は、同名曲が美学の中心を成し、同年6月にシングルとしても世に出ました。録音はバハマのコンパス・ポイント・スタジオ、仕上げのミックスはニューヨークのパワー・ステーションでボブ・クリアマウンテンが担当しています。フィル・マンザネラ(g)とアンディ・マッケイ(sax)に精鋭のセッション陣が寄り添い、余計な装飾を捨てることで密度を上げる方針が徹底されています。
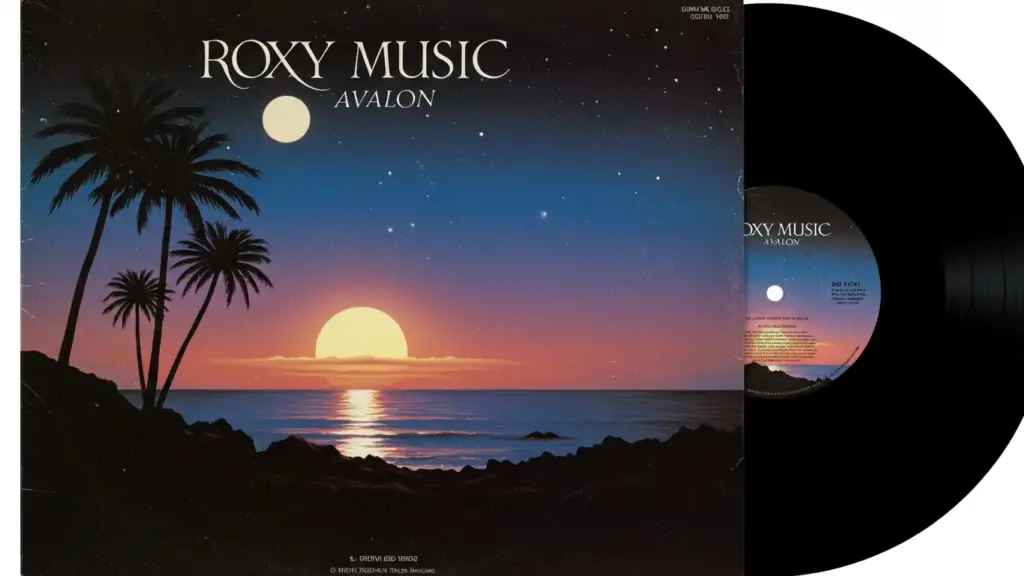
1982年の地図に置き直します
当時はMTVが浸透し、ニュー・ウェイヴやシンセ・ポップが台頭していました。多くのバンドが刺激やスピードを前面に押し出すなか、『Avalon』は異なる解を示します。音色の手触りと空間の奥行きを丁寧に連結し、聴き手の注意を自然に中心へ導く設計です。結果として、ザ・ブルー・ナイルやスウィング・アウト・シスターなどの“洗練派”に長期的な示唆を与える作品となりました。
その年の空気との呼応
英国社会が再編期にあった1982年、派手な躍動とは別の仕方で夜の時間を描く音楽が求められていました。本曲は、速度ではなく質感で耳をつかむ方法を選び、現実の騒がしさを直接的に押し返すのではなく、音の配置を整えることで聴取の焦点を澄ませています。

写真・現像のメタファーで
サウンドの露出を合わせます
この曲は、露出オーバーにもアンダーにも振らない適正露出の作法です。ドラムはシャッタースピードを速めない代わりに、ブレない基準点を与えます。ベースは一音の滞在を長く取り、黒つぶれしない深度を作ります。ギターはクリーンの小さなハイライトで点光源を置き、シンセはパッドでソフトフィルターをかけるように粒子を整えます。サックスはフレームの片隅で光のフレアを作り、画面の温度を上げます。被写体であるフェリーの声が、ノイズに埋もれずピントの芯として立ちます。

ミックスの現像工程を追います
中低域は濃度管理を丁寧に行い、高域の倍音は粒度を揃えてフィルム粒子のように散らします。コンプレッションは押し付けず、階調を残したままダイナミクスを整えます。リバーブは長尺に頼らず、左右と前後の被写界深度で空間を描きます。深夜の小音量でも像が崩れないのは、コントラストの配分が正確だからです。
タイトルと歌詞の焦点を映します
“アヴァロン”はアーサー王伝説に登場する理想郷の名として知られています。フェリーは神話の物語を語り直すのではなく、「パーティは終わった」という区切りから、どこからともなく現れる“君”へ視線を移し、言葉よりも身振りで通じ合う時間を描きます。歌詞に顔を出すサンバやボサ・ノヴァという語は、ジャンルの説明ではありません。ステップそのものを合図と捉え、会話より先に体が動く瞬間を指し示しています。

サビの反復が果たす役割
コーラスではタイトルの名を短く呼ぶだけで、ハーモニーの重なりとコードの転位が色合いを更新していきます。同じ旋律を回っているはずなのに、濃度だけが少しずつ上がる——その感覚が、理想郷の名に説得力を与えます。
ヴォーカルの佇まいとコーラスの寄与
フェリーの唱法は低域寄りで、母音の伸ばしを丁寧に扱います。語尾を鋭く切らず、次の拍へ橋を渡す発声が、曲全体の流れを穏やかに整えます。ここにハイチ出身のヤニック・エティエンヌの自由度の高いコールが重なると、音場の重心がふっと持ち上がります。彼女の声は主旋律を押しのけるのではなく、同じ場所を周回しながら色彩を変えるように寄り添い、和声の密度を一段深くしていきます。スタジオの廊下でその声に出会い、急遽起用したという逸話はよく知られていますが、実際の仕上がりは本曲の個性を決定づける効果を確かに持っています。
ミュージック・ビデオに映る設計
英国の古い邸宅を舞台にした公式映像は、登場人物の視線や足取りを丁寧に追い、音の設計と同じく“配置の妙”で世界観を示します。仮面や鷹を扱う人物は奇をてらう小道具ではなく、現実と象徴の境界を淡く示す装置として置かれています。ブライアン・フェリーはタキシード姿で過度な身振りを避け、カメラの前で音楽の重心そのもののように立ち、歌の一語一語が場の空気を整えていく様子を可視化します。ヤニック・エティエンヌの声が重なる場面では、編集の切り替えがサウンドの層の増減に合わせて微かにテンポを変え、映像と音が同じ脈拍で進むのを確認できるはずです。

1982年の現実との呼応
当時の英国は経済と社会の再編期にあり、ポップ・カルチャーの表面にはスピードと光沢が求められました。その一方で、『Avalon』は速度よりも質感、派手な起伏よりも音の手触りを優先します。MTV時代の映像主導の流れに抗うのではなく、映像の“見せ方”すら音の美学に従わせることで、耳で感じたバランスを目でも確かめられるように設計されていました。この姿勢は、のちの英国ソフィスティ・ポップや、チルアウト/ダウンテンポの制作思想に静かに影響を与えていきます。
アルバム内での役割
『Avalon』というアルバムは「More Than This」で入口を開き、「Take a Chance with Me」で軽やかな推進を与え、終盤にかけて音のトーンを一段ずつ濃くしていきます。その流れの上で、「Avalon」は結びの章として機能します。地名を短く呼ぶサビの反復は、これまで積み上がった質感の記憶を一気に定着させる仕組みで、聴き終えたときにアルバム全体の色調が一枚のフィルムのように残るはずです。
歌詞の読みどころを物語のように
歌は「パーティは終わった」という一言で静かに幕を上げます。ここで場所は現実の会場ですが、視線の交差と数歩のステップだけで、空間は別の風景に見え始めます。歌詞に出てくるサンバやボサ・ノヴァは、流行の参照ではなく、身体のリズムが言葉より早く合意を生む瞬間の記号です。サビでは詳しい説明を避け、地名を短く呼ぶだけに留めます。代わりにコーラスの重なり方やコードのわずかな転位が、同じ旋律を通過しながら色合いを更新し、聴き手の脳内で情景が勝手に濃くなっていく道筋を用意しています。

ヴォーカルの佇まいと合唱の設計
フェリーの声は低めの帯域を基調に、母音の伸びで艶を作ります。語尾は鋭く切らず、次の拍へ橋を渡すようにつなげます。そこへヤニック・エティエンヌの自由度の高い声が重なると、音場の重心がふっと上がり、同じフレーズが別の角度から照らされたように聴こえます。主旋律を押しのけるのではなく、輪郭を柔らかく太らせる働きで、結果としてサビの短い言葉に説得力が宿ります。
音源とリイシューの聴き比べ
『Avalon』は発売以来、いくつものリマスターや高音質盤が出ています。どの版でも共通しているのは、中低域の厚みと高域のきらめきの両立を目指す方向性です。スピーカー再生では部屋鳴りを利用して奥行きが出やすく、ヘッドホンではパッドの持続や残響の尾の質感が精密に捉えやすくなります。夜間の小さな音量でも輪郭が崩れにくいのは、本作のミックス特性の恩恵です。
結びとして
『Avalon』は、言葉を増やさずに音の配置で世界を立ち上げるための教科書のような一曲だと思います。地名を短く呼ぶだけのサビに説得力が宿るのは、リズム、低音、上物、合唱、そしてフェリーの声が、それぞれの“必要最小限”を過不足なく果たしているからです。ブライアン・フェリーの誕生日に改めて耳を澄ませると、理想郷の名が発せられるたびに色合いが深まっていく仕組みが、いまも鮮やかに機能していると感じられるはずです。



コメント