■【ボストン】について詳しくはこちらから!➡Wikipedia
僕の勝手なBest10:【Boston】編-第4位は・・・「A Man I’ll Never Be」の深層に迫る ―
【Boston】編-第4位は、『A Man I’ll Never Be(遥かなる想い)』です。言葉にすると魅力が伝わらないかもしれませんが、珠玉のバラードです。
明日紹介予定の第3位の曲と今の今まで悩んでいました。いずれも素晴らしい曲なんですけど。!(^^)!
🎥まずは、公式動画映像をご紹介します!
📌 クレジット(公式表記)
Provided to YouTube by Epic
© 1978 Sony Music Entertainment
🎵 2行解説
1978年にリリースされた、Bostonの名バラード。男としての弱さと真実の愛を描いた深い告白ソングです。
次の動画は、アルバム『Don’t Look Back』に収録されているスタジオ録音音源に、映像を組み合わせたプロモーションビデオの形式となっています。映像には、バンドの演奏シーンや関連するビジュアルが含まれており、楽曲の雰囲気やメッセージを視覚的に補完しています。
📌 クレジット(公式表記) Official Video for "A Man I'll Never Be" by Boston (提供元:Boston公式チャンネル、リンク先:Sony系列の配信リンク) 🎵 2行解説 1978年のアルバム『Don't Look Back』に収録された代表曲。切ないピアノとギターの旋律が、揺れる男心を静かに描き出します。
時代のうねりの中で誕生した“心の叫び”
1970年代後半、アメリカ音楽は転換期を迎えていました。ディスコの熱狂、パンクの登場、プログレッシブロックの深化という三極化の中で、Bostonはそのいずれにも属さず、独自の音楽美学を貫き通しました。バンドの中心人物トム・シュルツは、ギタリストでありながらエンジニアでもあり、徹底したサウンドメイキングで知られます。
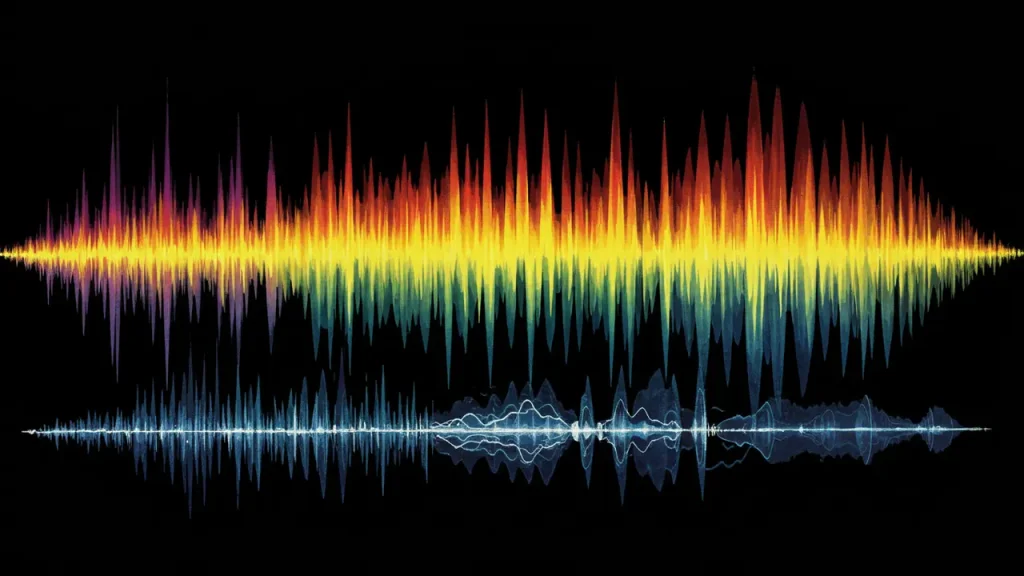
1976年のデビューアルバム『Boston』は、史上最も成功したデビュー作のひとつとして語り継がれており、その成功の余波を受けてリリースされたセカンドアルバム『Don’t Look Back』(1978年)には、今日まで語り継がれる珠玉のバラード「A Man I’ll Never Be」が収録されています。
言葉にできない“未完成な男”の告白
音の構造と感情の導線
「A Man I’ll Never Be」は、Bostonの中でも極めて内省的な作品です。バンドの代表作「More Than a Feeling」や「Don’t Look Back」のような高揚感とは異なり、静かに、しかし確かな熱を帯びて始まるこのバラードは、7分近い演奏時間を通して、自己否定と葛藤という感情の深部を丁寧に描いていきます。
静寂に近いギターのアルペジオから始まり、キーボードとドラムが徐々に感情を上乗せしていく構成は、楽曲が内面の波をそのまま反映しているかのようです。サビで放たれる「I’m just a man I’ll never be」というフレーズは、決して声を張り上げることなく、それでも心を打つ説得力を持っています。

歌詞のテーマとメッセージ
本楽曲のテーマは“理想と現実の断絶”。愛する人の期待に応えられない自分を責める語り手は、「あなたの望むような男にはなれない」という自己認識を受け入れながらも、その思いに苦しんでいます。
これは、単なる恋愛の悲哀ではありません。自己実現に失敗した者の孤独、他者への愛と自分への不信が交錯する、深い人間性の記録とも言えるのです。

Bostonというバンドの“内なるエネルギー”
Bostonは、レコード会社からの期待とトム・シュルツの完璧主義の間で常に揺れていたバンドでした。事実、『Don’t Look Back』の制作時にはレーベルからのプレッシャーに追われたシュルツが、「急ぎすぎた」と後に述懐するほど、創作の自由が奪われていたと言われています。

しかし、「A Man I’ll Never Be」に限って言えば、そうした制約の中にあっても、音楽の本質を見失わないバンドの力強さが感じられます。シュルツは、当時まだ珍しかった自宅スタジオを使い、独自の録音機材で徹底的にサウンドを追求しました。その努力が、この楽曲に繊細な感情表現と極めて高い音質をもたらしています。
時代の中で際立つ“孤高のバラード”
流行とは無縁の美学
1978年といえば、ビージーズやドナ・サマーがディスコチャートを席巻し、ヴァン・ヘイレンがハードロックを再定義していた時代。そんな中で「A Man I’ll Never Be」のような静謐で重厚なバラードがシングルカットされ、ビルボードで31位(Hot 100)を記録したのは異例とも言える現象でした。
この曲は、アルバム全体の構成上も特異な存在でした。疾走感のある他の楽曲に対して、時間の流れを止めるかのようなゆったりとしたテンポと、内面に迫るメッセージが際立っていたのです。

技術の粋を尽くしたプロダクション
「A Man I’ll Never Be」でも、ボーカル・トラックの重ね方やリバーブの配置に至るまで、スタジオワークが徹底されています。
特に注目すべきは、ブロッド・デルプのヴォーカルです。ただ感傷的に歌うのではなく、常に抑制の効いたトーンを保ちつつ、絶妙な情感を乗せています。リスナーはそこに、無理に訴えかけるのではなく、自然と染み入るような“真実の声”を感じ取るのです。
海を越えて共鳴した“メロディの重み”
日本ではBostonの楽曲が大々的にヒットすることはなかったものの、音楽に敏感な層の間では高い評価を受けていました。特に「A Man I’ll Never Be」のような叙情性に富んだ楽曲は、日本のメロディ志向と相性がよく、80年代以降の日本のロックバンドにも密かな影響を与えたと考えられます。
この楽曲に通底する“未完成さの受容”というテーマは、成熟を志向しながらも常に不完全であるという人間像を映し出しており、文学や映画といった他の表現領域とも共鳴しています。

隠された技術と哲学 ― トム・シュルツの信念
Bostonの活動スタイルはツアー中心ではなく、作品の完成度を優先するスタジオ型。これは商業的な成功よりも音楽の純度を守るという哲学に基づいた判断でした。「A Man I’ll Never Be」は、その信念の象徴とも言える楽曲です。

結びにかえて
心の奥底に届く“本当のメッセージ”
「A Man I’ll Never Be」は、恋愛のバラードという枠を超え、誰しもが抱える“なれなかった自分”への痛みと向き合う楽曲です。Bostonのメロディラインとシュルツの探求心、そしてデルプの誠実な歌声が融合し、この楽曲は静かに、しかし確実に私たちの心に残ります。
時代に媚びることなく、自分たちの理想と音楽の本質を追求したBostonの姿勢が結実したこの一曲は、今なお多くの人々の人生の節目で、静かに流れ続けているのです。




コメント