今日6月29日は、コリン・ヘイの誕生日!
本日6月29日は、オーストラリアが世界に誇るバンド「メン・アット・ワーク」のフロントマン、コリン・ヘイの誕生日です。1953年にスコットランドで生まれ、14歳の時に家族とともにオーストラリアへ移住した彼は、独特の鼻にかかった歌声とユーモアのある詞世界で、1980年代の音楽界に鮮烈な存在感を放ちました。

彼を語るうえで欠かせないのが、やはり代表曲『Down Under』。メン・アット・ワーク最大のヒットであり、オーストラリアという国をポップカルチャーの象徴として定着させた名曲です。
今日の紹介曲:『Down Under』(Men At Work)の世界!
まずはYoutube動画の(公式動画)からどうぞ!!
🎧 公式動画クレジット
🎬 Men At Work – Down Under (Official HD Video)
📺 公開日:2013年2月8日|視聴回数:4.6億回超
ショート解説
Men At Workの代表曲で、オーストラリアらしい風刺とアイデンティティを詰め込んだ1980年代の名曲。陽気なメロディと印象的なフルートが世界中で愛されました。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| 僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫ | |||||||||
| 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 曲のリリース | 1983 | ||||||||
| 聴いた時期 | ● | ||||||||
僕がこの曲を初めて聴いたのは社会人3年目の頃ですかね?
良く繰り返すセリフですが、この曲は大学生の時に聴いたものとばかり思いこんでいました。この曲について、友達と会話した記憶と共にです。
なんとまあ、ひとの記憶とはいい加減でしょうね?(僕だけ??)
で、解説でも書いていますが、当時は『ベストヒットUSA』が僕の洋楽情報仕入れの定番で、『Down Under』のMVも頻繁に流れていました。 それで知ったのだと思います。
リズムとテンポがマッチし、とても陽気な楽しい曲でしたし、コリン・ヘイの歌唱も良かったですね!! 大好きな楽曲の一つです。
時代が追い風を吹かせた80年代の“オージー・アンセム”
アルバム『Business as Usual』からの世界的ブレイク
『Down Under』が世界の音楽シーンを席巻したのは1983年。原曲は1981年にオーストラリアでリリースされたアルバム『Business as Usual』(邦題:ワーク・ソングス)に収録されており、同年に国内チャートで1位を獲得しました。
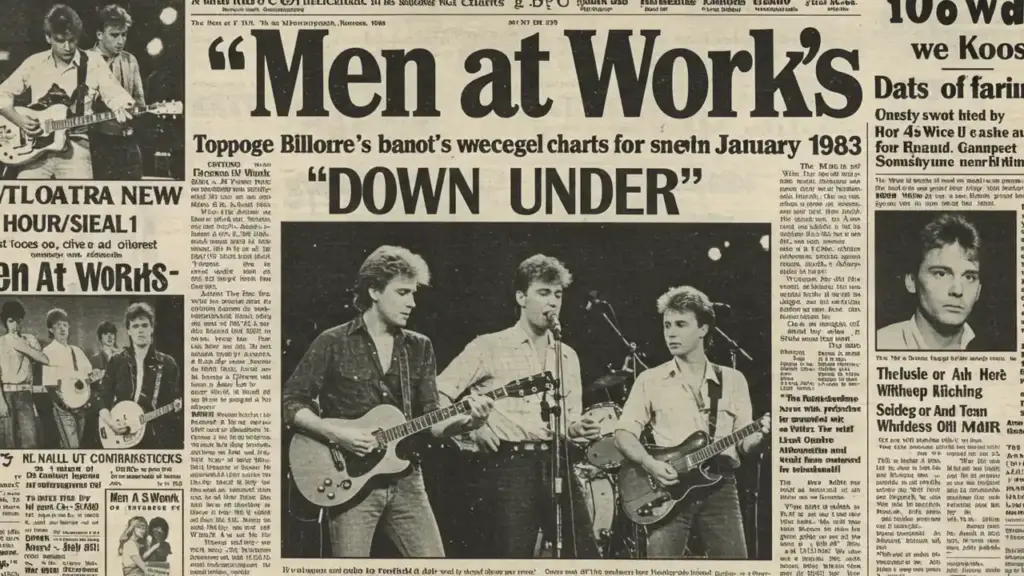
その後、世界進出を果たした楽曲は1982年後半からアメリカで徐々に火が付き、1983年1月にはビルボードHot 100で4週連続1位を記録。さらに全英チャートでも1位となり、シングル・アルバムの両方で英米同時1位を達成するという快挙を成し遂げました。
これは、当時の音楽界においても極めて異例の成功であり、メン・アット・ワークは一躍「オーストラリア発の国際的バンド」として名を轟かせました。
MTV時代が生んだ“視覚”の革命
1981年に開局した音楽専門チャンネルMTVの登場は、音楽の「聴く」体験を「観る」体験へと大きく変貌させました。『Down Under』のMVは、コリン・ヘイのコミカルな表情、広大なオーストラリアの風景、そして軽妙な演出が融合した秀逸なビジュアル作品であり、MTVという新時代にぴったりの内容でした。

「カンガルーの国」という曖昧なイメージしかなかったオーストラリアを、「陽気でユーモアに満ちた音楽の国」として印象づけたこのMVは、まさに**国を象徴する“カルチャーの輸出品”**と言っても過言ではありません。
歌詞に込められた皮肉と誇り ― “オージー魂”の奥深さ
表面の明るさと裏腹の批評性
陽気なメロディと軽快なリズムからは想像しにくいですが、『Down Under』の歌詞には、オーストラリア人のアイデンティティや文化的自嘲が巧妙に織り込まれています。
冒頭のフレーズはこう始まります。
Traveling in a fried-out Kombi / On a hippie trail, head full of zombie

これは、ヒッピームーブメントに身を投じた放浪者の姿を描いたもので、ゾンビは隠語でマリファナを意味します。旅と自由、少しの危険と緩さが混在する、典型的なオージー像が描かれています。
“ベジマイトサンド”と“男たちの略奪”
特に有名なサビの一節――
“Do you come from a land down under? / Where women glow and men plunder?”
(君は“ダウン・アンダー”の国の出身かい?/そこでは女たちは輝き、男たちは略奪するんだろ?)
この歌詞の「men plunder(男たちが略奪する)」という表現は、植民地時代の過去や開拓者精神を暗示するもので、自虐と誇りが絶妙に同居するアイロニー(「皮肉的な」「逆説的な」)となっています。

「ベジマイトサンドイッチ」という、オーストラリアの国民食を持ち出すあたりも、文化的自己紹介として非常に効果的。食文化まで自虐のネタに変えるセンスは、オーストラリア人らしいユーモアに満ちています。
音楽的魅力と“悲劇のフルートリフ”
一度聴いたら忘れないグレッグ・ハムの旋律
『Down Under』を語る上で忘れてはならないのが、キーメンバーであるグレッグ・ハムによる印象的なフルートのリフです。イントロからこの旋律が流れることで、楽曲に独特の“民族的軽快さ”が与えられています。
しかしこのフルートには、思わぬ落とし穴がありました。
著作権訴訟がもたらした後味の苦さ
2009年、このリフがオーストラリアの童謡『Kookaburra』の旋律と酷似していると訴えられ、翌年には盗用が認定。バンド側は敗訴し、過去の印税の一部支払いを命じられました。

この裁判は、ハム本人に深刻な精神的影響を与え、彼は「これで自分が記憶されるのはつらい」と語ったこともあります。そして2012年、わずか58歳で死去。原因は公表されませんでしたが、多くのファンがこの訴訟がもたらしたストレスを憂慮しました。
『Down Under』が鳴っていた1983年、日本は何を見ていたか
東京ディズニーランドとファミコン元年
1983年、日本では東京ディズニーランドの開園(4月)とファミリーコンピュータの発売(7月)という歴史的な出来事が相次ぎました。バブル経済の幕開けを予感させる、明るく新しい時代の訪れでした。
音楽面では、松田聖子や中森明菜が国民的アイドルとして絶頂を迎え、YMOは「散開」を宣言しつつもライブシーンを席巻していました。テレビでは『ベストヒットUSA』『ポッパーズMTV』などの洋楽番組が人気を博し、『Down Under』のMVも頻繁に流れていました。
ベジマイトを想像しながら、南半球へ想いを馳せた日々
「“ベジマイト”って何?」
「“Down Under”ってどこのこと?」

当時の若者にとって、『Down Under』は音楽以上の存在でした。オーストラリアという国に対する興味や、異国の風を運んでくれる入口のような存在だったのです。日本の“お茶の間”にも確かに届いていた、南半球の風――それがこの曲の力でした。
コリン・ヘイのその後 ― 不屈のソロ・キャリア
解散、苦難、そして再評価へ
メン・アット・ワークはセカンドアルバム以降、急速に勢いを失い、1986年に解散。フロントマンのコリン・ヘイはソロ活動に移行しましたが、当初は苦難の連続。アルコール依存にも悩まされながらも、ライブ活動を粘り強く続け、少しずつ評価を取り戻していきました。
『Scrubs』がもたらした復活の光
2000年代に入り、アメリカのドラマ『Scrubs』でアコースティック版『Overkill』が取り上げられたことが転機となります。番組の主演俳優ザック・ブラフが彼のファンであったこともあり、コリンは番組にもカメオ出演。若い世代に「再発見」されるきっかけとなり、今ではライブシーンで確固たる地位を築いています。
あらためて『Down Under』を聴きながら
コリン・ヘイが奏でた『Down Under』は、ただのヒットソングではありません。時代の変わり目を象徴する文化的マイルストーンであり、一国のアイデンティティを歌に込めた傑作です。

彼の誕生日である今日、ぜひあらためてこの曲を耳にしてみてください。明るく笑い飛ばすようなメロディの奥に、深く誠実な問いかけが静かに流れています。



コメント