「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
僕の勝手なBest30【ふきのとう編】第28位『水色の木もれ陽』
第28位は、「水色の木もれ陽」です。これまた、ふきのとうらしい穏やかな曲です。
春の柔らかな風に揺れる木々の葉。その隙間から漏れ差す淡い光が、記憶の中の景色を優しく照らし出す。ふきのとうの名曲『水色の木もれ陽』は、まさにそんな一瞬をすくい上げたような一曲です。

1977年のアルバム『風来坊』に収められたこの作品は、その静けさと慎ましさが、時代を越えて心に染み入るような余韻を残してくれます。
ここでは、楽曲の詩的世界、音楽的特徴、文化的背景、そして現代における意義まで、多角的に読み解いていきます。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『水色の木漏れ日』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
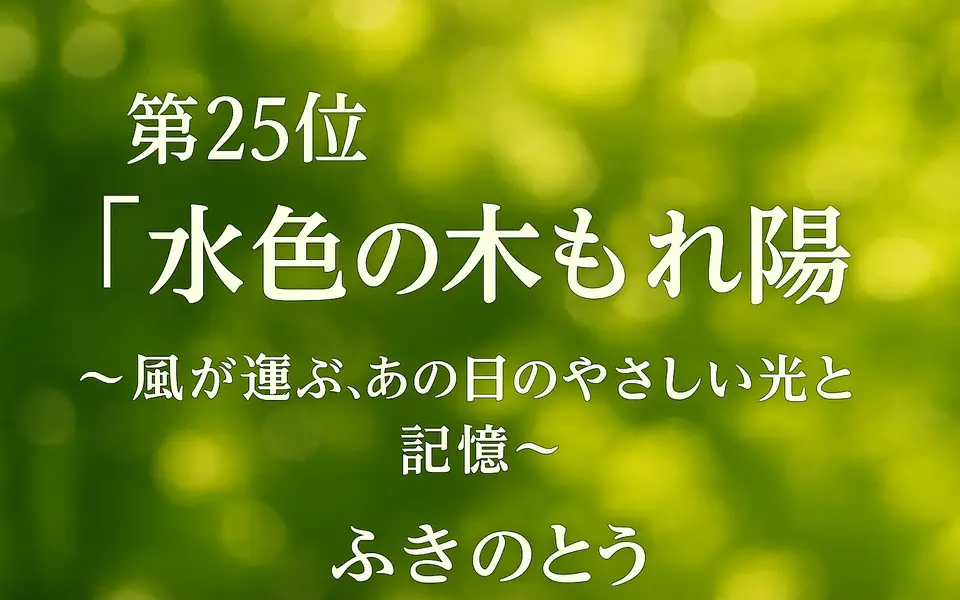
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:(公開年:2015/07/01)
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。 ※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
“木もれ陽”という言葉が持つ、日本的感性
幻想と現実の境界にある光
“木もれ陽”という語は、自然現象でありながら日本語独自の感性を体現する言葉です。直射日光のように主張せず、木の葉の隙間から静かに差し込む光は、明るさと影、確かさと曖昧さの狭間に存在し、現実と幻想の境界に浮かぶ情景を形作ります。
本作のタイトルに加えられた「水色」という修飾語も注目に値します。水色の光は実際には存在しませんが、それゆえに“心象風景”として成立し、リスナーそれぞれの記憶や願望に重なる余地を持っています。
このように『水色の木もれ陽』は、実体よりも感覚を重んじる日本文化に深く根ざした詩的表現であり、その存在自体が“記憶のスケッチ”のような役割を担っています。

文学や美術における“木もれ陽”
和歌や俳句の世界において、“木もれ陽”に相当する描写はたびたび登場します。たとえば「木陰にさす一筋の光」「風に揺れる若葉のひかり」など、明確に描写されることは少なくとも、“かすかな明かり”は自然と人の心の関係性を象徴してきました。

また、日本画や水彩の世界では、“間”や“余白”を大切にする表現の中に、木もれ陽が象徴的に描かれることも少なくありません。本楽曲が持つ“視覚化されない映像詩的魅力”は、こうした文化的伝統と連動していると言えるでしょう。
音楽的構造と、あえて“何もしない”技術
アコースティックの間合いと静けさ
『水色の木もれ陽』は、ふきのとうらしいアコースティック・フォークの構成を持っていますが、その中でも特にシンプルかつ抑制の効いた編曲が特徴です。
アルペジオ中心のギター、一定のテンポに寄り添う穏やかなストローク、ドラムやベースを極力排した設計。この“音の間(ま)”が、聴き手の呼吸に寄り添うような安心感を生み出しています。

コード進行は王道的で、劇的な転調もありませんが、その安定感が“心の風景”とリンクします。特にサビにあたる部分では盛り上げるよりも余韻を強調し、感情の波を内側に向かって導いていきます。
声の質感と距離感の演出
ヴォーカルの細坪基佳は、抑揚よりもニュアンスに重きを置いた歌唱を徹底しており、山木康世のコーラスもあくまで陰のように重なります。それは語りかけというより、心の奥で繰り返される「ひとりごと」のようでもあります。
この距離感は、耳元で囁くような親密さではなく、少し離れた場所からふと聴こえてくるような“物思い”の距離感。
だからこそ、リスナーの心に“自分の思い出”として響くのです。
1977年という時代と、フォークの役割
高度経済成長の終焉と“足元を見る音楽”
1970年代後半、日本は物質的な豊かさのピークを迎えようとしていました。家電製品が普及し、マイカー時代が到来し、新幹線も高速道路も拡張され、地方から都市への移動も活発になりました。
しかし、そうした“上昇志向”の裏で、人々の心の足元は次第に見えなくなりつつありました。
『水色の木もれ陽』が描くような“日曜日の朝”“風が吹く道”“ブランコに揺れる親子”といった風景は、まさにそうした喧騒の中で失われかけた“小さな幸せ”の象徴です。

この曲が提案するのは、成長でも革命でもない、“立ち止まることの価値”です。
フォークソング=生活詩としての力
1970年代のフォークソングは、単なる音楽ジャンルを超えた“生活の詩”でした。
吉田拓郎、かぐや姫、イルカ、そしてふきのとう。彼らは“私”の目線から“私たち”の生活へと寄り添う表現を重ねました。
『水色の木もれ陽』もまた、“誰でもない誰か”の暮らしをそっと描いた作品であり、だからこそ聴く人の心に自然と重なります。
日常を特別に見せるのではなく、“日常そのものに価値がある”ということを、メロディと詩の力で証明しているのです。
歌詞構造と音楽的文体の妙
繰り返しの構造がもたらす“記憶の定着”
『水色の木もれ陽』では、短いフレーズの反復が印象的に用いられています。
この繰り返しは、意味を増幅するためのものではなく、“言葉が空気になるまで浸透させる”ための仕掛けです。

たとえば一つの情景が何度も登場することで、説明ではなく体験としてリスナーの脳に焼きついていきます。これは音楽という媒体が持つ“記憶補助装置”としての役割を最大限に生かした手法です。
音と言葉の“間”に宿る豊かさ
また、この曲では多くの“沈黙”が演出されています。
間奏、ブレス、コードの間――それらが語るのは“言葉にできない想い”であり、そこにこそこの楽曲の最大の情緒が宿ります。
俳句や短歌にも見られる「間(ま)」の美学は、まさにこの曲の根底に流れており、日本人の心に特有の感覚である“空白の力”を体現しています。
現代における価値 ― 過剰な時代の静寂
スキップ前提の音楽と真逆の構造
現代の音楽は、イントロ数秒で判断され、フックがなければ聴かれず、情報過多のなかで消費されていきます。YouTube、Spotify、TikTok――それらが求めるのは「即効性」と「分かりやすさ」です。
しかし『水色の木もれ陽』は、そのどれにも当てはまりません。
序盤は淡々と始まり、感情のクライマックスもなく、終わりはただ静かにフェードアウトしていく。それでも、心に何かが残るのは、“何もしないことの美しさ”が、聴く人の奥底に静かに響くからです。
結びにかえて ― 小さな光が差し込むように
『水色の木もれ陽』は、注目を集めるタイプの楽曲ではありません。
誰かに自慢したくなるようなインパクトも、SNS映えする映像美もありません。
けれども、それが“忘れられない一曲”となることがあります。
静かに心を揺らし、思い出を照らし、そして何も言わずに去っていく。
そんな音楽にこそ、本当の時間が宿るのかもしれません。




コメント