「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■【前編】~北の大地から生まれたハーモニー(1970〜1976)
■【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
【ふきのとう】編-第29位『冬銀河』をご紹介!
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
🎥下の画像をクリックしてください。Youtube動画にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
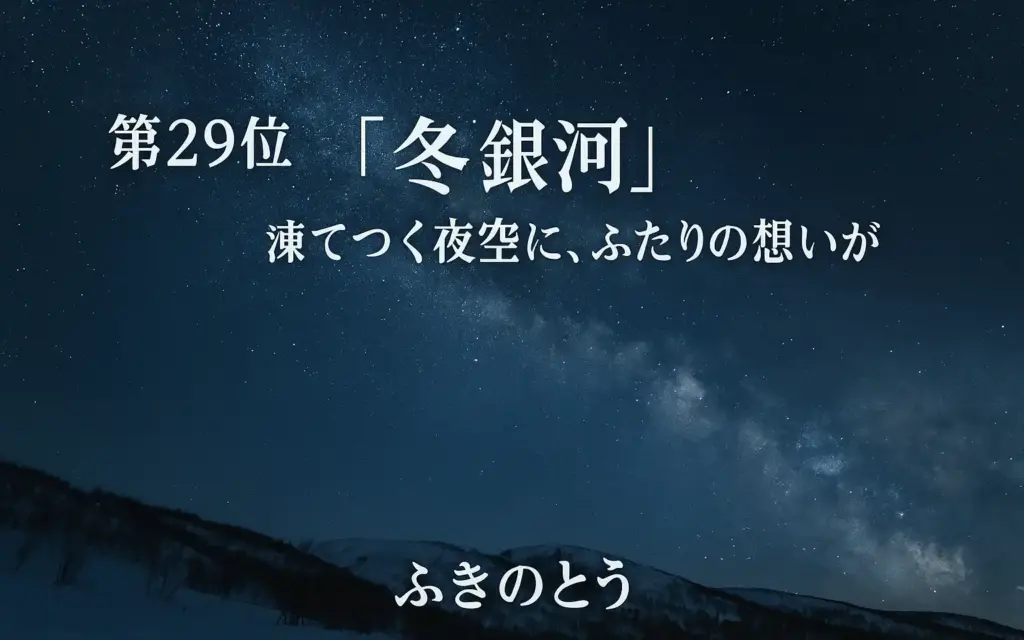
「ふきのとう/冬銀河(1980年)」
投稿者: Fukino10 Channel(非公式)
公開日: 2014/12/21
収録情報: シングル「冬銀河/成人式」(1980年10月1日発売)
※この1動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。
※公式アカウントによる配信ではありません。
※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
次は、オリジナルの「冬銀河」:ボーカル-山木康世(公式動画)です。
🎵 公式動画情報
タイトル:冬銀河
アーティスト:山木康世
提供:ポニーキャニオン
公開日:2021年7月7日
チャンネル:山木康世 - トピック(YouTube公式自動配信)
― 冬の星空に響く優しさと夢 ―
冬の朝、吐く息が白く凍りつく街角。
まだ夜の帳が下りきらない空に、星たちが最後の輝きを放っていた――。
そんな静謐な光景を自然と思い起こさせる。それが、ふきのとうの名曲『冬銀河』です。

僕の「勝手なBest30」第29位にこの曲を選んだ理由は、冬の情景と人のぬくもりを、言葉少なに、しかし深く描いた作品だからです。
派手な展開こそないものの、耳を澄ませて聴くほどに胸に染みわたる。それはまさに、冬の銀河のような存在です。
楽曲のリリース背景と特異性
シングルとしての立ち位置とセルフカバーの存在
『冬銀河』は1980年10月1日、CBS・ソニーから16枚目のシングルとしてリリースされました。
特筆すべきは、この曲がオリジナルアルバムには未収録であるという点です。のちに1992年、セルフカバーアルバム『ever last』で再録され、細坪基佳によるリードボーカルによって新たな命が吹き込まれました。

つまり、1980年発売のシングルのボーカルは、山木康世だったんです。山木さんはメロディーメーカーとして重役を担ってきましたが、やはりボーカルの表現力としては細坪さんが一枚上。
ということで、ぜひ両方を聴き比べてみてください。
作詞・作曲は山木康世、編曲はふきのとうと瀬尾一三。繊細なフォークサウンドと情景描写の美しさが融合した一曲であり、セルフカバー版ではボーカルの配置やアレンジが再構成され、まったく異なる印象を残します。
初めて出会った日のこと
1980年、僕は大学4年生。京王線の明大前駅近くのレコード店でこの曲を初めて聴きました。
そのとき耳に入ってきたのは、山木の穏やかな声と、アコースティックギターの澄んだ響き。

それから、40年くらい後のことです。YouTubeで偶然見つけた『ever last version』を再生したとき、細坪の澄んだ歌声とコーラスが重なる新たなアレンジに、思わず聴き入ってしまいました。
同じメロディーなのに、時間を超えて違う景色を見せてくれる。その体験が、この曲を「特別な一曲」に押し上げてくれたのです。
音楽性に宿る“静かな情熱”
アレンジの対比が生む二面性
1980年のオリジナル版では、アコースティックギターのアルペジオが主軸。
まるで凍てつく朝の空気のように、音数は控えめで、余白に感情を預ける構成です。

一方、1992年のセルフカバーでは、細坪のリードボーカルと山木のコーラスが美しく交差。
ハーモニーの重なりにより、まるで夜明けの光が差し込むような明るさが加わっています。
ボーカルの変化がもたらす余韻
山木康世の声には、包み込むような温かさがあります。ときに語りかけるようでありながら、静かに感情を乗せてくる独特の表現。
一方の細坪基佳は、高音の抜けと明るさが印象的で、繊細な言葉にも輪郭を与えます。2人の歌声が交差することで、『冬銀河』は一層多面的な作品として輝きを放ちます。
アレンジャー・瀬尾一三の美学
瀬尾一三のアレンジは、極端な盛り上げを避けながら、空間の美しさを際立たせる手法を採用しています。ギター、ベース、ドラムの音数は最小限に抑えられ、リスナーに「間」を感じさせる構成。
特にセルフカバー版では、細坪の歌声が際立つような調整が施されており、再構築によって楽曲がどれだけ表情を変えるかを体現しています。
時代背景と若者の心理
フォークからニューミュージックへの狭間で
1980年という時代は、フォークの全盛期が過ぎ、ニューミュージックへの過渡期にありました。
ふきのとうは、その両者の中間に立ち、時代の波に呑まれず、あくまで“言葉と旋律”の力で勝負し続けていた数少ないグループです。

学生たちの心に残った一曲
1970年代末、日本の若者は進路、就職、将来に対する不安を強く抱えていました。
急激な成長を遂げた社会の中で、自分自身の居場所を見つけられずにいた多くの学生たち――。
そんな時代にあって、『冬銀河』は、声高に主張するのではなく、「そっと寄り添う」タイプの楽曲として、深く共感されていたのです。
私的体験:心に残るあの夜
キャンパスと『冬銀河』
僕がこの曲に初めて出会ったのは、大学の4年生の頃。
卒業を間近に控えたアパート生活の中で、ふきのとうの音楽は、日常の風景にいつもる空気のような存在でした。(ふきのとうの歴史【後編】で触れています。)

『冬銀河』は、朝の窓辺で一人聴くのにふさわしい曲で、淡々とした旋律と詩が、沁み込んでくるようでした。
そして数十年後に聴いた『ever last』の細坪ボーカル版は、そのときの記憶を呼び起こし、「音楽は時を超える」という事実を改めて実感させてくれましたね!
現代的視点:2025年に聴く意味
孤独な社会に届く優しさ
2023年の国内調査によれば、全体の約4割の日本人が「日常的に孤独を感じている」と回答しています。デジタルでつながっていても、本当に誰かと心が触れ合う機会は少ない――そんな現代にあって、『冬銀河』のような優しい音楽こそが必要とされているのではないでしょうか。

特に細坪の歌声には、「君の悲しみを知っているよ」と静かに語りかけるような力があります。
だからこそ、世代を越えて支持され続けているのでしょう。
自然を感じさせる音楽の力
かつては当たり前だった星空も、いまや都市部では簡単に見られません。ふきのとうの歌では星や風、香りや夢といったモチーフは、歌詞の中で美しく織り込まれ、聴く者の心に“自然との再接続”を促してくれます。

文化的影響とファンの声
幻の名曲として語り継がれる理由
『冬銀河』はオリジナルアルバム未収録という立ち位置ゆえに、一部では“幻の名曲”として語り継がれてきました。
1992年の再録によりリスナー層が広がり、現在ではサブスクやYouTubeでも手軽に聴けるようになったことで、その評価は世代を超えて高まっています。
まとめ:なぜ第29位なのか
『冬銀河』は、冬の情景を描きながら、人間の内面にそっと寄り添ってくれる楽曲です。
風や夢、星といった言葉の奥には、誰かを想う気持ちがそっと隠されており、それが聴く人の心を温めてくれます。
この曲で、一番好きな歌詞は「幸(しあわせ)になりたいね ほんの少し ぜいたくも少し今よりすこし」です。聴いているとほほえましいやら、切ないやら…。
派手さや奇抜さはありませんが、だからこそ日々の生活の中でそっと居てくれる。
第29位という順位ではありますが、これは決して過小評価ではなく、「静かな名曲」としての誇りあるランクインです。
どうか、あなたも今朝、窓辺でこの曲を聴いてみてください。心に静かな光が差し込んでくるはずです。




コメント