Beginについて詳しくは➡Wikipediaでご覧ください。
【6月23日】は、上地 等の誕生日-『島人ぬ宝』-(Begin)をご紹介!
沖縄・石垣島に生まれた音楽家
1966年6月23日、沖縄県石垣市に生まれた上地等(うえち・ひとし)。彼はBEGINのピアニストとして、比嘉栄昇の力強いボーカル、島袋優の柔らかなギターと共に、グループの音楽に温もりと深みを与える中心的存在です。その演奏には派手さはありませんが、包み込むような優しさとリズムがあり、沖縄の原風景がにじみ出るような感触を残します。
上地の奏でるピアノは、旋律の美しさというより、「間」や「余白」にこそ魅力があります。特に『島人ぬ宝』では、歌詞のメッセージを過不足なく支える役割を担いながら、島々の記憶や海風の感触をピアノの音で表現しています。
まずはYoutube動画の(公式動画)からどうぞ!!
🎥 公式動画クレジット
動画タイトル:BEGIN「島人ぬ宝」20周年MV
公開日:2022年5月22日
💬 解説(2行)
沖縄出身のBEGINが「故郷への想い」を綴った代表曲。この20周年MVでは、字幕機能により多言語で歌詞の味わいが広がります。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 2002 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
僕がこの曲を初めて聴いたのはリリース時の2002年頃だと思います。
解説にもあるように、この年はサッカーのワールドカップが日本・韓国で開催されました。
余談ですが、僕は中高と6年間サッカーをやっていたので、大のサッカーファンです。
当時のワールドカップで、日本戦があるごとに他の家族も我家に来て、皆でビールを飲みながら、ワイワイと騒ぎまくっておりました。それが2回にわたった翌日、隣のマンションから苦情が来ました。その後は窓を閉め切って、大声で応援しましたとさ!(>_<)
話を戻します。沖縄民謡のことはよく知りませんが、この「島人ぬ宝」は「沖縄の歌だな・・・というのは誰でもわかると思います。Biginには長く聴き続けられ、そして多くのカバーされてきた曲がありますね。「恋しくて」や「涙そうそう」などなど。いずれも良い曲ですが、僕の中ではこの曲が一番です。解説の通りですが、故郷を誇りの思えるってとても素晴らしいことですよ。特に苦難の歴史に流されてきた沖縄では特別でしょう。
『島人ぬ宝』の背景と2002年の空気
日韓W杯と熱狂の2002年
『島人ぬ宝』が発表されたのは、2002年5月22日。日韓ワールドカップの開幕直前で、サッカーへの熱狂が日本列島を包み込んでいた時期でした。日本代表の活躍や韓国との共催の話題が連日報道されており、国民の高揚感はピークを迎えていました。

同年の社会的出来事
またこの年には、「タマちゃん」ことアゴヒゲアザラシが東京・多摩川に出現して大きな話題となり、人々の癒しの象徴にもなりました。科学の分野では、小柴昌俊氏や田中耕一氏がノーベル賞を受賞し、日本の希望として注目を集めました。
一方、小泉政権による構造改革が進行し、景気や雇用をめぐる不安も存在しました。このような「熱狂と不安」が交錯する時代に、『島人ぬ宝』の素朴なメッセージは、多くの人々の心に響いたのです。

ヒットチャートとの対比
J-POPとは異なる響き
2002年の代表的なヒット曲には、宇多田ヒカルの『SAKURAドロップス』、浜崎あゆみの『H』、Mr.Childrenの『HERO』、平井堅の『大きな古時計』などがあります。これらの楽曲は都市的で洗練されたサウンドを特徴としていますが、『島人ぬ宝』はまったく異なる方向性を示しました。
三線を軸とするBEGINの音楽は、都市の喧騒とは距離を置いた、素朴でありながら力強いもの。そのサウンドは沖縄の大地や風土を背景に持ち、生活に根ざしたリアルな感覚を伝えてくれます。

歌詞の構造とメッセージ
空との対話が示すもの
僕が生まれたこの島の空を
僕は一体どれくらい知っているんだろう
この冒頭部分は、抽象的な問いかけでありながら、極めて身体的・感覚的な「記憶」に接続しています。上空に広がる風景を「知っているか」と問うこのフレーズは、視覚以上に五感を刺激し、「名も知らぬ花を知っている」といった感性へとつながっていきます。

「知らない」を「受け止める」詩情
名前も知らない人たちに
支えられて生きているこの島で
情報化社会において「知らないこと」は時に恥とされがちです。しかし、この歌では「知らないこと」そのものに敬意が込められており、名もなき人々、名もなき風景の価値を肯定的に描いています。
島に生きることの誇りと切なさ
「離れてわかるもの」の真実
僕が生まれたこの島の海を
僕はどれくらい知っているんだろう
この一節は、前半の「空」と対を成す「海」への問いかけです。自然という抽象に個人的な記憶を重ねる構造が、詩としての深みを与えています。「空」と「海」は、いずれも無限に広がる存在であると同時に、具体的な場所としての沖縄を感じさせる装置として機能します。

離ればなれになった時
初めて気づいた「島の言葉」
ここでは、アイデンティティの再発見が描かれます。地元にいるときには意識されない文化や言語が、外の世界に出て初めて「かけがえのない宝」として浮かび上がる。その構造は、沖縄だけでなく、多くの地方出身者の共感を呼びました。
教科書に載らない「歴史」との接点
「宝」とは何か?
「宝」という言葉には、経済的な価値ではなく、精神的・文化的な価値が込められています。『島人ぬ宝』では、そうした目に見えない豊かさが語られています。
実際、沖縄は複雑な歴史を持つ地域であり、戦争・占領・本土復帰といった節目を経て、独自の文化とアイデンティティを維持し続けています。そうした文脈を前提にこの楽曲を聴くと、「宝」という言葉の奥行きが一層深まるのです。
詳細に言うと、沖縄の日本復帰は、1972年5月15日です。僕が中学校2年生の時でした。取り立てて感慨もなかった気がしますが、その後歴史を学ぶにつれ沖縄の置かれた立場と、民族意識を察すれば、その苦労と現在も内在する様々な事象に複雑な思いが馳せます。

それまで沖縄は、第二次世界大戦後のアメリカ統治下にありました。戦後、1945年から1972年までの約27年間、アメリカ軍政や琉球政府のもとで統治されており、日本の一部でありながら日本の法制度とは異なる体制で運営されていました。
1971年に日米沖縄返還協定が締結され、それに基づいて1972年5月15日、正式に沖縄は日本の施政権下に復帰しました。現在もこの日は「沖縄復帰の日」として記憶されています。
沖縄戦と慰霊の日
上地等の誕生日でもある6月23日は、沖縄戦の組織的戦闘が終結したとされる「慰霊の日」にあたります。偶然とはいえ、この日に生まれた上地が、平和を希求する『島人ぬ宝』という楽曲に関わっている事実には、どこか象徴的な意味が感じられます。
BEGINという表現体
地域に根ざし、世界に響く音楽
BEGINは、ローカルに深く根を下ろしながら、グローバルな評価を得てきた数少ない日本のグループです。『恋しくて』『涙そうそう』『三線の花』など、沖縄を題材にしながらも、普遍的な情感に届く名曲を多く生み出してきました。

その中でも『島人ぬ宝』は、土地への誇り、文化への敬意、人と人とのつながりをテーマに据えた、まさにBEGINの代表曲といえるでしょう。
教育現場でも注目された楽曲
教科書掲載と教材化
全国の学校で広がる教材利用
『島人ぬ宝』は、その強いメッセージ性と郷土愛にあふれる歌詞内容から、全国の小中学校や高校において教材として取り上げられた実績があります。とりわけ沖縄県内では、郷土教育の一環として使用されることが多く、「ふるさと」や「命の尊さ」「平和」「文化の継承」など、重要な教育テーマに自然とつながる楽曲として評価されています。
子どもたちの感受性に響く歌詞
実際に授業でこの楽曲に触れた子どもたちは、「自分のふるさとを言葉にする」作業に自然と向き合うことになります。『島人ぬ宝』は、そのプロセスにおいて、まさに**「言葉のヒント」**を与える存在として機能してきました。自分が育った土地の風景や、大切に受け継がれてきた文化の価値に気づくきっかけとして、多くの子どもたちの心に残っているのです。

結びにかえて:耳を澄ませば聞こえる宝の音
『島人ぬ宝』が多くの人の心に響く理由は、「自分のこと」として受け取れるからに他なりません。地元を離れた経験のある人、自分のルーツを見つめ直したい人、大切なものを再発見したい人——そのすべての人々にとって、この曲は「帰る場所」を感じさせてくれます。
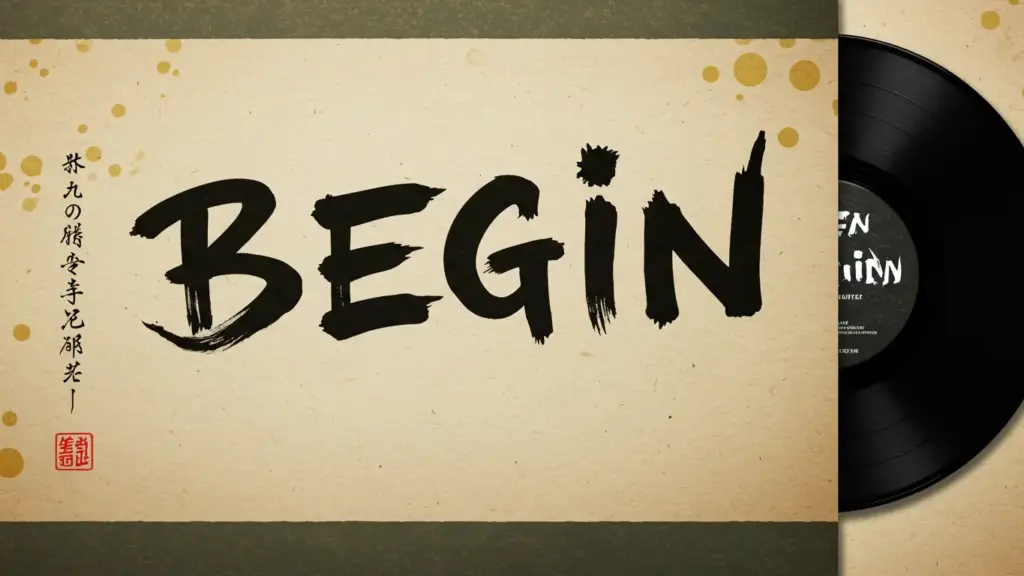


コメント