「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■【前編】~北の大地から生まれたハーモニー(1970〜1976)
■【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
僕の勝手なBest30:【ふきのとう】編を始めるにあたって!
今日より、僕の勝手なBest30として、『ふきのとう』シリーズを開始します。これまでの「勝手にBest」は多くても15曲でしたが、ふきのとうの歴史(後編)で触れている様に、僕の青春(特に大学時代)とは切っても切れない関係にあり、大切な思い出の数々とも重なっています。
とにかく大学の4年間は音楽聴きまくり状態でしたが、「ふきのとう」は空気や水みたいなもので、意識せずともいつも聞いていました。「ふきのとう」ファンでない方は約一か月の辛抱になりますが、本当にどこまでもやさしい音楽です。是非この機会に「ふきのとう」の世界を体験してください。
第30位『さようならの言葉』──静けさのなかの別れ
1977年4月にリリースされたアルバム『水車』。そのA面に収録された『さようならの言葉』は、派手なアレンジも劇的な展開もない、ふきのとうらしい静けさを湛えた1曲です。
この作品はシングルカットされることもなく、チャートにも登場しませんでしたが、むしろその“静けさ”こそが、ふきのとうの詩と旋律の本質をもっともよく表している──そんな印象を与える存在です。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『さようならの言葉』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
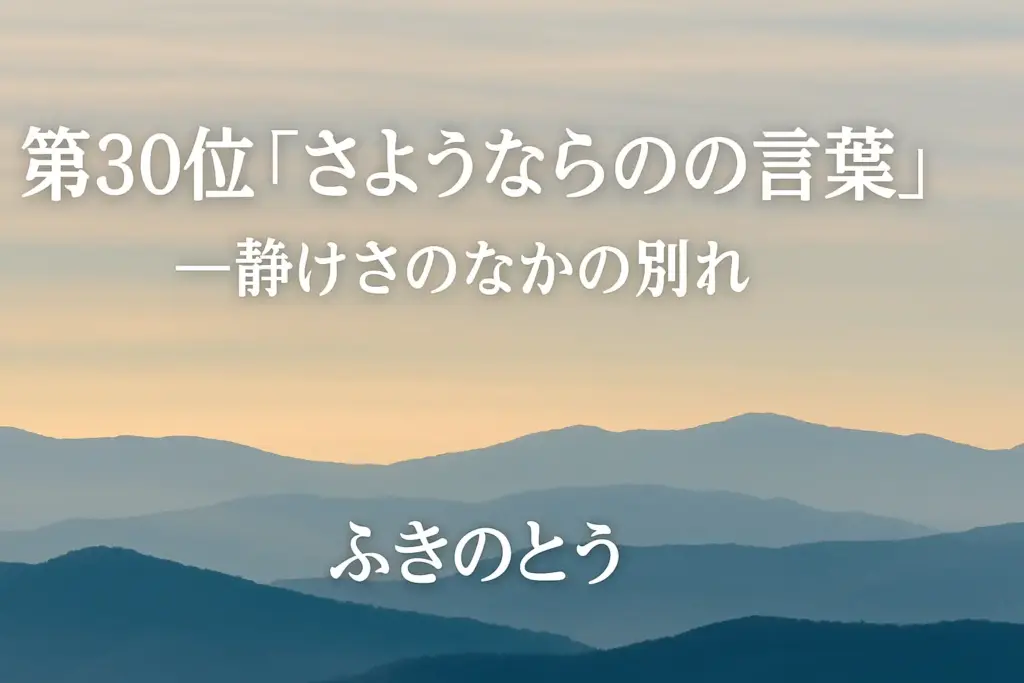
🎥公式動画ではありません。
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:さようならの言葉 (1977年)(公開年:2014/11/03)
URL:https://youtu.be/AMRBgJi2hLY?si=xGZNxyZm4vosGSzx
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。
※公式アカウントによる配信ではありません。
※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
季節と別れが交差する歌詞構造
冒頭のフレーズ「さようならの言葉の中に/うずもれてゆく青春は」は、別れの瞬間にある静かな諦念を表現しています。「若葉の頃のほろにがさ」「白く冷たいあなたの手」といった歌詞からは、まさに“春の始まりに吹く冷たい風”のような余韻が漂います。
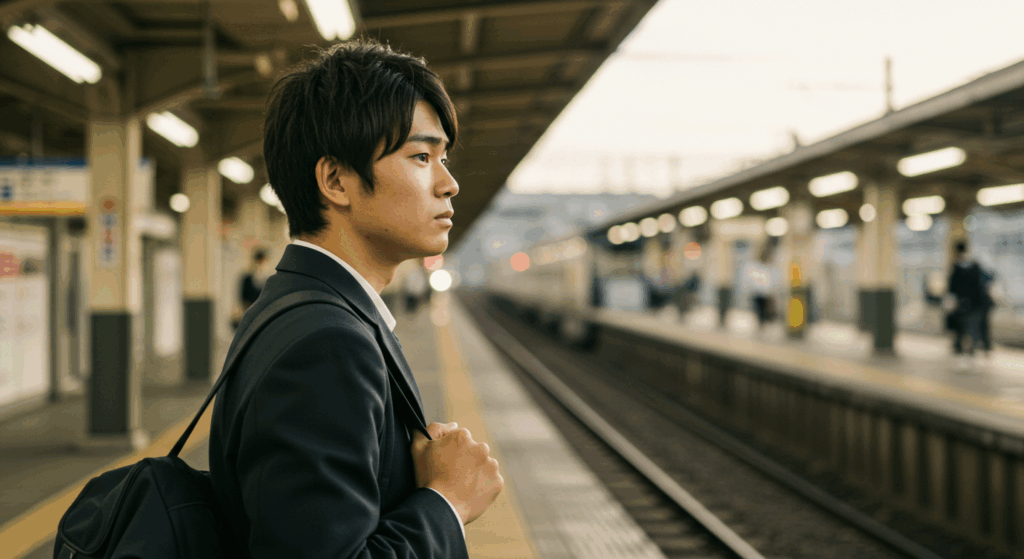
この作品では、「季節は何を運ぶのか」という問いが繰り返されます。それは別れの理由ではなく、別れの“あと”を問う言葉。問いの答えは示されませんが、ふたりの関係が「遠く離れる 恋人達に」「それぞれの道 ひとりの旅」として描かれていく中で、聴き手に残るのは“祈りに近い感情”です。
感情を押しつけない“優しい別れ”の描写
「あなたの肩が震えていた」──繊細な観察
「ごめんなさいと笑って見せて」「ほほの涙をそっと摘んだ」──この一連の描写は、別れのシーンにありがちな劇的な展開とは異なり、感情の微細な揺らぎを丁寧にすくい上げています。
「肩の震えが伝わってくる」という表現は、相手が泣いているとも言わず、泣き声も描かず、それでも“別れの本質”を的確に伝えています。ここにあるのは、痛みよりも寄り添い。叙情的でありながら決して感傷的に傾かない、ふきのとうらしいスタンスです。

感情のピークではなく、輪郭の余白
ふきのとうの歌詞には、しばしば“語られない感情”が漂います。『さようならの言葉』においても、「なぜ別れるのか」「どうしてこうなったのか」は一切語られません。
その代わりに登場するのは、雲・風・若葉・手の温度──自然の要素です。これらは心情の象徴として置かれ、聴き手の中にある経験や思い出と呼応します。感情の中心を直接描かないことで、逆により強い共感と沈黙を生み出しているのです。
“風景”を描くフォークソングの特性
自然描写と感情のリンク
「流れる雲に誘われて」「明日の風に送られて」という比喩は、直接的な感情表現を避けつつ、関係の終わりを自然に溶け込ませる役割を果たしています。ふきのとうの歌にはしばしば“風景描写”が出てきますが、それは単なる景色ではなく、心情そのものを映し出す“内的風景”です。
この曲でも、季節や空模様が登場人物の心理の代弁者のように配置されており、歌詞がひとつの短編詩として読めるほどの構造的完成度を持っています。
詩的構成と時間の流れ
『さようならの言葉』の歌詞は、過去→現在→未来という時間軸を持ちながらも、それを明示的に示すことなく、あくまで自然な言葉の流れとして提示されています。「愛する人に さよなら告げて/それぞれの道 ひとりの旅」という結びの一節に至るまで、聴き手は一篇の物語をなぞるようにこの歌を聴いています。

このような構造こそが、ふきのとうが“文学性の高いフォーク”と呼ばれるゆえんです。
歌詞構造と音楽アレンジの美学
語りかけるような演奏と沈黙の効能
本作のアレンジは、アコースティックギターを中心にした非常にシンプルな構成です。打ち込みも装飾も一切なく、むしろ“何もしていないこと”こそが、この曲の持つ力を引き出しています。ギターのストロークは、時に語り、時に支え、言葉の後ろに沈黙が残る余白を生み出しています。

「精一杯の あなたなんだね」というラインに続く空白、そのあとにふっと現れる「肩の震えが 伝わってくる」という言葉──。演奏はこの“間”に寄り添い、言葉以上の感情を残響として響かせてくれます。
録音の質感が生む“手触り感”
1977年当時の録音は、現代のようなデジタル処理とは無縁です。そのため、音の端々に“かすれ”や“揺れ”が残っています。たとえば、声の震えやギターの微かなチューニングのズレ。それらは決してマイナスではなく、“人間が録った音”としての存在感を強く伝えています。
この「温度ある音質」こそが、ふきのとうの音楽の強さのひとつです。感情をなだらかに包み込むだけでなく、その時代の空気感までも保存している──そんなタイムカプセルのような存在なのです。
“ひとりの旅”が象徴するもの
「旅立ち」は別れではなく始まり
歌詞の後半、「それぞれの道 ひとりの旅」というフレーズが繰り返されます。これは単なる別離の描写ではなく、“新しい生活の入り口”を象徴しているようにも受け取れます。
「白く冷たい あなたの手に/いつか 幸せ 乗せてあげたい」と歌う部分では、未練や後悔よりも、相手への優しい祈りが立ちのぼります。この曲の本質は、喪失ではなく“承認”。愛した人の未来に希望を託すような、非常に成熟した別れの形がここにあります。
宛名のない手紙としての役割
この曲には、主語や視点が頻繁に変化する特徴があります。たとえば、「僕が愛した 美しい女」と言っていたかと思えば、「ごめんなさいと笑って見せて」と相手の視線に移る。さらに「あなたの髪に 口づける」では、時間が止まったような映像的描写になります。

この曖昧さが、聴き手一人ひとりの心の記憶に寄り添える“余白”をつくっているのです。誰かのことを思い浮かべるたびに、この曲は少しずつ違う形で響いてくる。まるで「その人への手紙」のように──。
この曲を“30位”に置いた理由
ヒットではないが“残る”楽曲
なぜこの名曲をあえて30位という位置に選んだのか。おそらくこのランキングの中で最も静かで、最も深い余韻を残す1曲だからです。ふきのとうにはより代表的で華やかな楽曲もありますが、『さようならの言葉』は、聴けば聴くほど沁みてくる“静かな名作”。
歌詞に強いメッセージやドラマ性はなく、それでも記憶に残り続ける──そんな歌こそ、ふきのとうの音楽の神髄です。

フォーク文化における文脈での再評価
1970年代の日本のフォークソングは、社会的メッセージや市民性を帯びた楽曲が主流でした。その中でふきのとうは、あくまで個人の情感に寄り添う“私的なフォーク”を突き詰めていきました。
『さようならの言葉』は、政治や世相を語るのではなく、“ひとりの人生のワンシーン”を真摯に描く歌です。だからこそ、時代を超えて届く。こうした楽曲が、今のリスナーにとっても十分通じる“普遍性”を持ち続けていることは、評価されるべき文化的価値です。
まとめ──ふきのとうの優しさは、別れの言葉の中にある
この曲は、「さようなら」と言うための歌ではなく、「ありがとう」や「大丈夫」がその言葉の中に含まれている──そう感じさせてくれる作品です。
最後のフレーズ「愛する人に さよなら告げて/それぞれの道 ひとりの旅」は、悲しいはずの別れにどこか光を与えてくれます。ふきのとうの音楽には、いつも「決して言葉にされないけれど、そこにある気持ち」が存在します。




コメント