【6月3日】は、革ジャンの女王スージー・クアトロの誕生日です。
スージー・クアトロ(Suzi Quatro)は、1950年6月3日生まれ、アメリカ・デトロイト出身のシンガーソングライター/ベーシストです。1970年代初頭に英国でソロデビューし、革ジャン姿でベースをかき鳴らすスタイルが話題に。『Can the Can』や『The Wild One』などのヒットで、女性ロッカーの先駆者としてロック界に新たな道を切り開きました。
まずはYoutube動画の公式動画からどうぞ!!
🎬 公式動画クレジット 🎵 Suzi Quatro – The Wild One 📀 収録アルバム:『Quatro』 🗓️ リリース日:1974年10月1日 © Chrysalis Records Limited / Provided by Reservoir Media Management, Inc. ▶️ 公開日:2020年2月9日(YouTube自動生成音源) 📝 2行解説 70年代女性ロックのアイコン、スージー・クアトロが放つエネルギッシュな代表曲。 反逆と自由をテーマに、力強いサウンドで時代の空気を突き破った一曲。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 1974 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
僕がこの曲を初めて聴いたのは、リリース時の高校1年の頃だと思います。
前年(1973)に『Can the Can』をリリースしており、この曲も大好きで良く聴いた曲です。そのため彼女のことは知っていましたので、違和感なく耳になじみましたね。
ファーストインプレッションは、「ザ・カッコいい!!」ですね。楽曲もそうだし、見た目も革ジャンがクールでそれでいて美人・・・とくれば思春期真っただ中の僕なんか一ラウンドで秒殺ですよ!(恐らくレコード店でジャケットを見た程度だと思いますが!)
前にも書きましたが、中学、高校と音楽は好きでしたが、小遣いも少なく、当然アルバム聴きではなく、単発曲聴きが主流でした。
この曲は当時ラジオでよく流れていたはずです。
『The Wild One』──野性が弾けた女性ロックの金字塔
今回はまさに正当派ロックの彼女の代表曲『The Wild One』(1974年)を深掘りしてご紹介します。この楽曲は、女性ミュージシャンが自らを主張し、ロックの世界で存在感を確立した象徴とも言える名作です。エネルギッシュな演奏、力強いボーカル、そしてメッセージ性のある歌詞を通して、クアトロの魅力を今あらためて再発見してみましょう。

スージー・クアトロと『The Wild One』の基本情報
キャリアの軌跡とブレイクの瞬間
スージー・クアトロは1950年、アメリカ・デトロイトに生まれ、幼いころから姉妹でバンド活動を行っていました。彼女は1960年代にガールズバンド「ザ・プレジャー・シーカーズ」で活動を開始し、1971年にイギリスに渡ります。そこで出会った音楽プロデューサー、ミッキー・モストに見い出され、ロンドンを拠点にソロ活動をスタートさせました。

『The Wild One』とアルバム『Quatro』
『The Wild One』は1974年10月、2枚目のアルバム『Quatro』からシングルとしてリリースされました。作詞・作曲は当時ヒットメーカーとして名を馳せていたニック・チン&マイク・チャップマンのコンビ。イギリスのシングルチャートでは最高7位、オーストラリアでは5位と、クアトロにとって国際的な成功の礎を築く一曲となりました。
1974年の時代背景に見る『The Wild One』の意味
日本社会と音楽の変容
日本では第1次オイルショック(1973年)の影響がまだ色濃く残り、物価の上昇や経済の停滞が庶民の生活に影を落としていました。一方でテレビや音楽は多様化を迎え、吉田拓郎や井上陽水、天地真理らがチャートを賑わせる中、洋楽も若者層にじわじわと浸透。FM放送の拡充もあり、海外アーティストの楽曲に触れる機会が増えていった時代です。
海外ではグラムロックと社会不安が交差
同年、アメリカではウォーターゲート事件を経てリチャード・ニクソンが大統領を辞任し、政治への不信感が高まりました。音楽面では、グラムロックがピークを迎え、デヴィッド・ボウイ、T.レックス、スレイドらが若者たちのカリスマとして君臨。女性の社会進出やジェンダーの流動性が注目される中で、クアトロの存在はまさに時代の空気と重なりました。

『The Wild One』制作の裏側と誕生の意義
ワイルドなイメージの確立とレコーディング風景
『The Wild One』は、クアトロの「革ジャンを着てベースを弾く女性ロッカー」という鮮烈なイメージを音で表現するべく制作されました。ロンドンで行われたレコーディングには、彼女自身がベースで参加し、バンド全体に荒々しいグルーヴを注入。その力強い演奏と姿勢が、曲全体に説得力を与えています。

タイトルの背景にある映画的モチーフ
タイトル『The Wild One』は、1953年のマーロン・ブランド主演映画『乱暴者(The Wild One)』からのインスピレーションが明言されています。この作品はバイク乗りの若者たちの反逆精神を描いたものであり、まさにクアトロが体現するロック精神と重なります。
音楽的特徴と演奏の魅力
荒々しさと緻密さのバランスが取れたアレンジ
本作は4/4拍子のロックンロール。鋭いギターリフで始まり、シンプルながらも緊張感のあるコード進行(A-D-E)で組み立てられています。中盤にはギターソロが挿入され、バンド全体が爆発的なエネルギーを放出。特にリズム隊の推進力は強烈で、ドラムとベースが楽曲の背骨を支えています。

サビの魅力と高揚感
「All my life I wanted to be somebody」というサビのフレーズは、反復と共鳴を通して強い印象を残します。力強いシャウトと合いの手のようなコーラスが一体となり、クアトロのメッセージをよりダイレクトに伝えています。

歌詞に込められた思想と時代性
自己実現と反骨のシンボルとして
歌詞には「私は誰にも奪わせない」「私はなりたい自分になる」という明確な自己主張が込められています。この思想は、1970年代に高まっていたウーマン・リブ運動やフェミニズムとも共鳴するものであり、単なるロックソングではなく、社会的なアピールでもありました。
時代を超える共感の力
現代においても「Nobody’s gonna take it away from me」というフレーズは、自立した自己を目指す人々にとって響く言葉です。SNS時代における自己表現の自由ともリンクし、若年層に再評価される理由にもなっています。
ボーカルとステージングに見るクアトロの魅力
ハスキーで迫力ある歌声
クアトロの声は、決して技巧的に洗練されたタイプではありませんが、荒々しさと切実さが共存する唯一無二の魅力があります。Aメロでは抑えめに、サビでは爆発的に──そのコントラストが、聴き手の感情を揺さぶります。
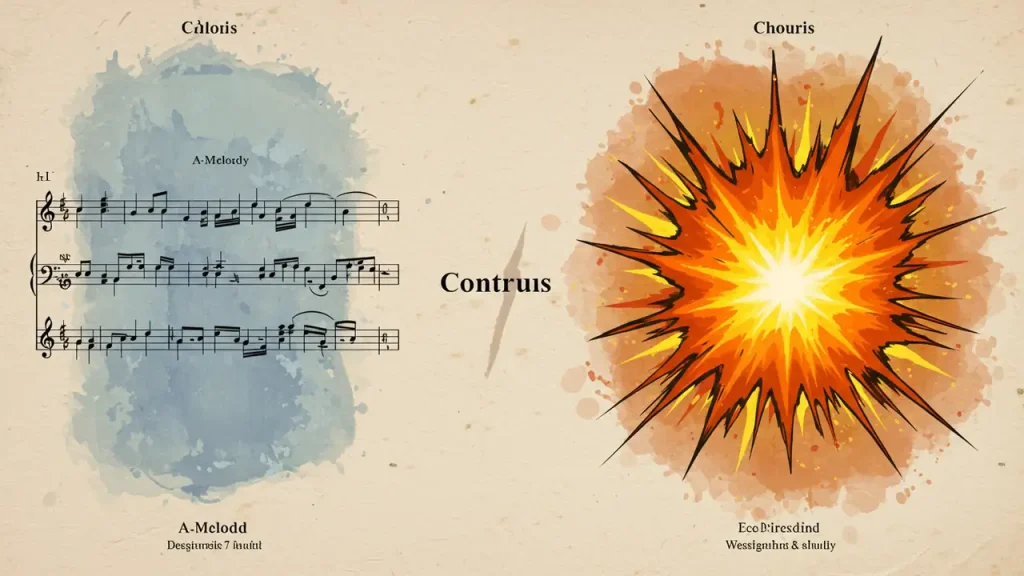
革ジャンとベースとステージの融合
ライブでは革ジャン姿でベースをかき鳴らしながら歌うスタイルが観客の視線を奪い、「女性が前に出るロック」のスタイルを体現。のちにジョーン・ジェットやプリテンダーズのクリッシー・ハインドらにも影響を与えました。
日本での影響と『The Wild One』の浸透
洋楽ブームを牽引した一曲
1970年代中盤、日本の若者の間では洋楽への関心が高まり、FMラジオや深夜テレビでスージー・クアトロの楽曲が頻繁に紹介されるようになりました。特に『The Wild One』はその象徴的存在として支持されました。
1975年の来日公演とその反響
1975年の来日公演ではこの曲がアンコールで披露され、観客は総立ち。メディアでも「女性ロッカーの新しいスタイル」として紹介され、邦楽シーンへの影響もじわじわと広がっていきました。
現代に蘇る『The Wild One』の魅力
2024年のリマスター版と再注目の動き
2024年にはリマスター音源が配信され、よりクリアな音質で当時のエネルギーを追体験できるようになりました。ベースラインの迫力やボーカルの存在感が際立ち、再評価の声がSNSでも多く見受けられます。
若者の共感を呼ぶ理由
X(旧Twitter)などでは「今聴いてもカッコいい」(まさに””)「自分を貫く勇気をもらった」といった投稿が増え、ストリーミングの再生回数も上昇中。現代のリスナーにとって、クアトロの姿勢は新鮮でありながら普遍的な魅力を持っています。
まとめ:時代を超えて響くロックの真髄
スージー・クアトロの『The Wild One』は、単なる1970年代のヒット曲ではありません。女性が音楽業界で自分自身を表現し、ロックというジャンルを超えて社会にインパクトを与えた歴史的な名曲です。彼女の誕生日である6月3日に、この曲を改めて聴くことで、あの時代の熱と、現在にも通じるエネルギーを感じ取ってみてはいかがでしょうか。

『The Wild One』―Suzi Quatro:(意訳)
私は燃えるような狐、
打ちのめされても立ち上がる、
地獄から来たハンマーのような魂。
誰にも止められない。私は“ワイルド・ワン”。他人に奇妙と囁かれようと、
私は連勝街道を突き進む。
この街を手に入れてやる。
私を抑えつけることなんてできない。
だって私は、“ワイルド・ワン”だから。誰にも私をつなぎ止められない。
もう手遅れよ。自由にして。
もっと、もっと欲しいの。
数なんて数えていられない。私はもう、惑わされない。
かつては誰かに抑えられ、振り回された。
けれど今は違う。
私は自分の足で立ってる。
だって私は、“ワイルド・ワン”なのだから。青い瞳の“危険な女(ビッチ)”。
金持ちになりたい。
だからそこをどいて。
私はここに残る。誰にも止められない。
私は、“ワイルド・ワン”。誰も私を飼い慣らせない。
私は自由、私は野性。
そして、止まるつもりなんてない。
by Ken



コメント