★「長渕剛」について詳しくは➡こちらのWikipediaでどうぞ!
僕の勝手なBest15:【長渕剛】編 – 第4位『逆流』をご紹介!
僕の勝手なBest15:【長渕剛】編の第4位は、2枚目のアルバム(逆流)挿入の「逆流」を選びました。このアルバムは相当聴き込みましたが、他の楽曲とは一味違う反骨の歌!という印象が強くあります・
冒頭に寄せて:魂の声がこだまする映像たち
今回ご紹介する長渕剛の名曲『逆流』。この楽曲の真価をより深く味わっていただくために、以下の3本の関連映像を冒頭にご紹介します。映像を観たあとで本文を読むことで、より鮮明に、当時の空気感や長渕の情熱が感じられるはずです。
まずは、公式音源をお聴きください。
🔥『逆流』オリジナルVer まずは、僕が最初に耳にした音源です。
🎮 『逆流』-長渕 剛 ALL NIGHT LIVE IN 桜島 2004.8.21」より
・・・のちの長渕剛の『逆流』の世界観をどうぞ!!
※剛の曲前の語りで、この曲を「ファーストアルバムから・・・」といってますが、挿入されたアルバムはセカンドアルバムです!な。(>_<)
はじめに:混沌の時代に差し込んだ、反骨の詩
1979年4月、長渕剛の『逆流』がリリースされました。これは、彼にとって5枚目のシングルであり、同タイトルのアルバムの表題曲でもあります。
当時の日本は、オイルショックを経て経済的には回復基調にありましたが、戦後の高度経済成長が一段落し、新たな方向性を模索していた時代です。家庭用ビデオデッキや電子レンジが普及し始め、都市部では文化が多様化しつつありました。その一方で、受験戦争や就職競争が激化し、若者の心には漠然とした不安や孤独が広がっていました。
地方から上京し、社会に適応しようともがく若者たちにとって、「流されずに生きること」は単なる理想論ではなく、日々の実感に根ざしたテーマでした。そんな中で発表された『逆流』は、体制や常識に流されずに生きようとする者の叫びを、シンプルかつ鋭く突き刺す言葉で描きました。
長渕剛という存在──等身大のリアリティ
鹿児島生まれの青年が歌い始めた理由
1956年、鹿児島県に生まれた長渕剛は、大学時代(福岡です)から音楽活動を本格化させました。デビュー当初はフォーク色の濃い、静かな語り口の歌が中心でしたが、1979年の『逆流』から、よりメッセージ性の強いスタイルへとシフトしていきます。
この曲は、単なる人生の愚痴や弱音ではなく、個人として社会とどう向き合うかという姿勢を強く示しており、後の「俺は俺だ」というアイデンティティの核がすでにここに現れているのです。
当時のインタビューなどからは、彼が自身の生い立ちや地方出身者としての孤独を原動力に、東京という大都会で居場所を見つけようとする必死さがにじみ出ています。『逆流』の根底には、そんな彼自身の人生観がしっかりと投影されているのです。

ファンとの一体感がもたらす熱
長渕のライブは、聴く者に自分の生き方を問い直させる力を持っています。語りかけるような歌唱と、感情をむき出しにした表現は、1970年代後半の音楽界でも特異な存在として評価されていました。
彼がこの楽曲を披露する際には、決まって一瞬の静寂が訪れ、観客の意識が一つに集中する空気が生まれます。まるでステージと客席が対話しているかのようなその空間は、言葉では表現しきれない一体感を生み出していました。

『逆流』の構造と意味──内なる叫びと抗う力
流されない生き方の象徴
「逆流」という言葉が持つ強烈なイメージ。そのタイトル通り、歌詞には”川の流れに逆らって進む自分”が描かれています。時代や世間の流れに安易に乗るのではなく、自分の足で歩き、自分の言葉で語る。そんな決意が行間に溢れています。
「だって僕は僕を失うために 生きてきたんじゃない」という一節は、多くのリスナーにとって、自らの心を代弁してくれるかのような響きを持ちました。
興味深いのは、この曲が特定の”敵”を明確に指摘していないことです。戦うべき相手はあくまでも、自分の内面にある”弱さ”や”妥協”かもしれない。そうした普遍性が、この歌を時代を超えたものにしているのです。
メロディが語る静かな激情
『逆流』はメロディも実に印象的です。静かなイントロから始まり、サビに向かって次第に感情が高まっていく構成は、歌詞の内面世界を見事に表現しています。
楽器編成はシンプルながらも、長渕の張り詰めたボーカルが全体を引き締め、聴き手に真剣勝負を挑むような緊張感を与えます。まるで彼が「お前はどう生きる?」と問いかけてくるような、そんな錯覚すら覚えるでしょう。
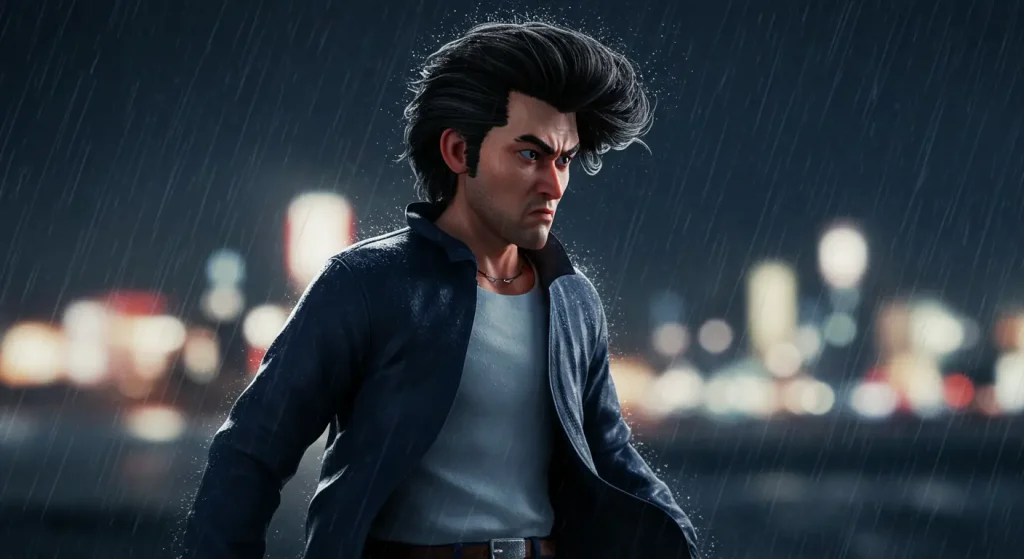
1979年の音楽シーンと『逆流』の立ち位置
1979年といえば、キャンディーズの解散やサザンオールスターズの台頭、さらにはYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)の登場など、日本の音楽界が大きく変わり始めた年でした。アイドル文化が根付きつつある一方で、フォークやロックの再定義が行われていた時期でもあります。
吉田拓郎や井上陽水といった先駆者が築いた”フォークの深化”に続き、若手アーティストがより個人的で内省的なテーマに取り組み始めた頃でもありました。長渕剛は、まさにその流れの中で、自らの実感を武器に切り込んでいったのです。
『逆流』が今なお語られる理由
この楽曲は、特定の時代の風景を描いているにもかかわらず、今のリスナーにも深く突き刺さる力を持っています。なぜなら、流れに抗うこと、自由を求めてあがくことは、時代や年齢を問わず普遍的なテーマだからです。
たとえばSNSの時代、同調圧力や空気を読むことが求められる現代においても、『逆流』の「自分の信じた道を行け」というメッセージは、鋭く響いてきます。むしろ今の方が、この歌の本質がより必要とされているのかもしれません。
まとめ:逆境の中にこそ、自分の声がある
長渕剛の『逆流』は、1979年という時代の転換点に生まれた楽曲です。しかしその本質は、時代を超えて響く「自分らしく生きる」というメッセージにあります。
安易な成功や流行に流されず、自分の信念を貫くことの苦しさと尊さ。『逆流』はそれを、熱さではなく静かな炎で伝えてくれます。
40年以上が経過した今なお、この曲が新たな共感を呼び起こしていることが、その証です。



コメント