カール・パーマーの誕生日を祝してELPの名演「展覧会の絵」を紹介
3月20日は、イギリスの伝説的なプログレッシブ・ロックバンド、エマースン・レイク・アンド・パーマー(Emerson, Lake & Palmer、以下ELP)のドラマー、カール・パーマー(Carl Palmer)の誕生日です。
1950年3月20日にバーミンガムで生まれた彼は、ELPの結成メンバーとして1970年代のプログレッシブ・ロックシーンを牽引し、その革新的なドラミングで世界中のファンを魅了しました。カールは幼少期からドラムに親しみ、15歳でプロの道へ進み、アーサー・ブラウンやアトミック・ルースターを経てELPを結成。ELPはキーボードの鬼才キース・エマースン(Keith Emerson)、ボーカル兼ベーシストのグレッグ・レイク(Greg Lake)と共に、クラシック音楽とロックを融合させた独自のスタイルで知られています。
今回は、カールの誕生日を記念して、ELPの代表作であり、クラシック音楽の再解釈として名高い『展覧会の絵』を紹介します。この曲は、ELPのダイナミックな演奏とカールの圧倒的なドラムテクニックが存分に発揮された一曲です。
まずは、公式音源でお楽しみください。(超長いですが!!)( ;∀;)
🎵 公式クレジット
「Pictures At An Exhibition (Official Audio)」– Emerson, Lake & Palmer
収録アルバム:Pictures at an Exhibition(1971)
© Atlantic Records / Emerson, Lake & Palmer under exclusive license
📝 2行解説
ムソルグスキーの組曲『展覧会の絵』をロックに大胆アレンジしたプログレッシブ・ロックの金字塔。
ELPの超絶技巧と荘厳な構成力が融合した、70年代ロックの象徴的ライブ作品です。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・
| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |
| 曲のリリース年 | 1971 | ||||||||
| 僕が聴いた時期 | ● |
僕がこの曲を初めて聴いたのは、大学生になってからでした。中学、高校とロックやポップスは大好きでしたが、さすがにELPを解釈できるほどの知識も、根性も感性も持ち合わせていませんでした。(;”∀”)
大学の頃は何度も書きましたが、音楽漬けの日々を送っていたので、この時期何でも聞いていましたね。そんな中、プログレッシブロックにも興味を持ちまして、キングクリムゾンなどかなり聴きこみました。その流れで、ELPを聴くことになります。
とはいえ、正直ELPはいまだによくわからん‥…?バンドの一つなので、結局のところリピ聴きしたのはこの曲だけ泣きもします。
ロックとクラシックの融合との説明は間違ってはないと思いますが、言い方としては「ロックです。そしてクラシックでもあります。」って感じですね。
今回取り上げる動画は、いずれも長いですが、嫌いでない方は一聴の価値ありです。聴きごたえ十分ですの是非味わってください。
エマースン・レイク・アンド・パーマー – プログレッシブ・ロックの巨匠
ELPは1970年にイギリスで結成されました。キース・エマースンはナイス(The Nice)、グレッグ・レイクはキング・クリムゾン(King Crimson)、カール・パーマーはアトミック・ルースター(Atomic Rooster)で活躍した後、3人が意気投合してバンドを結成。(ここまでで彼らの凄さがわかります!)
ELPはデビューアルバム Emerson, Lake & Palmer(1970年)から「Lucky Man」などのヒットを放ち、クラシック音楽の要素を取り入れた壮大なサウンドで注目を集めました。1971年にリリースされた2ndアルバム Tarkus では、20分を超える組曲「Tarkus」でプログレッシブ・ロックの可能性を広げ、全英1位を獲得。ELPはその後も Trilogy(1972年)、Brain Salad Surgery(1973年)などの名盤を次々と発表し、1970年代のプログレッシブ・ロックを代表する存在となりました。
カール・パーマーは、複雑なリズムと高速ドラミングでバンドのサウンドに不可欠な推進力を与え、ライブパフォーマンスでも巨大なドラムセットを使った派手なソロで観客を圧倒しました。

「展覧会の絵」の誕生とその背景
『展覧会の絵』(原題:Pictures at an Exhibition)は、ELPが1971年にリリースしたライブアルバムで、ロシアの作曲家モデスト・ムソルグスキーの同名ピアノ組曲をロックアレンジした作品です。
ムソルグスキーが1874年に作曲した原曲は、友人の画家ヴィクトル・ハルトマンの絵画展に着想を得た10曲のピアノ曲と「プロムナード」(間奏曲)から成る組曲で、クラシック音楽の名曲として知られています。
ELPはこの曲を大胆に再解釈し、キース・エマースンのモーグシンセサイザーとオルガン、グレッグ・レイクの力強いボーカル、カール・パーマーのダイナミックなドラミングで、クラシックとロックの融合を試みました。
1971年3月26日にニューカッスル・シティ・ホールで録音され、同年11月にアルバムとしてリリース。アルバムは全英3位、全米10位を記録し、ELPのライブパフォーマンスの迫力を世界に知らしめました。カールはこの曲で、複雑なリズムパターンと高速フィルインを駆使し、特に「The Hut of Baba Yaga」や「The Great Gates of Kiev」で圧倒的な存在感を示しています。
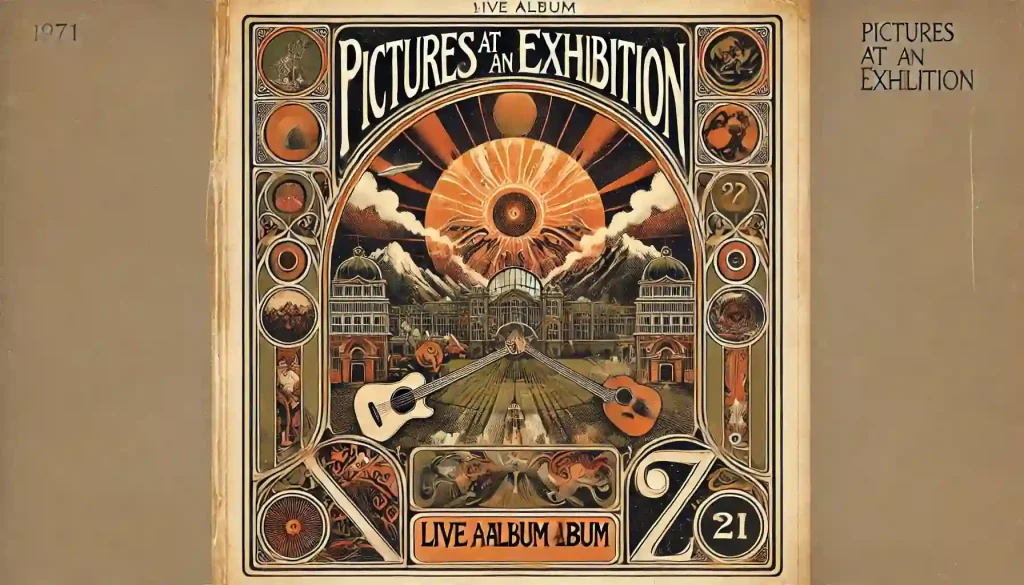
長編と短編のバージョン、その解釈
『展覧会の絵』には、長編(アルバム全体)と短編(シングルや抜粋バージョン)が存在します。
長編はアルバム全編で約38分に及び、原曲のほぼ全曲(「プロムナード」「グノムス」「古城」「ビドロ」「バーバ・ヤーガの小屋」「キエフの大門」など)をカバーし、ELPのオリジナルパート(グレッグ・レイクのボーカルによる「The Sage」やキース・エマースンの即興)も追加されています。
一方、短編バージョンはラジオ放送用やライブのハイライトとして編集されたもので、例えば「The Great Gates of Kiev」のみを抜粋したものや、「プロムナード」と「グノムス」を組み合わせた短いバージョン(約10分程度)が存在します。
- 長編の解釈:長編は、ELPのプログレッシブ・ロックとしての野心を体現するバージョンです。クラシック音楽を忠実に再現しつつ、ロックのエネルギーや即興性を加えることで、原曲の持つ絵画的な情景をさらにドラマチックに拡張。キースのシンセサイザーが描く幻想的な音色や、カールのリズミカルなドラムが、絵画が動き出すような臨場感を生み出しています。
- 短編の解釈:短編は、アルバムのエッセンスを凝縮した形で、一般のリスナーにも親しみやすいアプローチ。ラジオでの放送やライブのハイライトとして機能し、特に「キエフの大門」の壮大なフィナーレは、ELPのスケール感をコンパクトに伝える名演です。短編は、プログレッシブ・ロックに馴染みのないリスナーにも訴求する工夫が感じられます。
この長編と短編の違いは、ELPがクラシック音楽を現代に蘇らせる際のバランス感覚を示しており、両バージョンともに彼らの革新性と大衆性を兼ね備えた姿勢が反映されています。

1971年のイギリスと音楽シーンの動向
1971年は、イギリスでプログレッシブ・ロックが全盛期を迎えた年でした。キング・クリムゾン、ジェネシス、イエスなどのバンドが次々と名盤を発表し、クラシック音楽やジャズの要素を取り入れた複雑な音楽構造が人気を博しました。
一方で、グラムロックも台頭し、デヴィッド・ボウイやT・レックスが新しい音楽トレンドを生み出していました。ELPはこの時期、クラシック音楽をロックに取り入れる先駆者として注目を集め、『展覧会の絵』のライブ録音は、彼らの実験的なアプローチが具現化した瞬間でした。
イギリス社会は、経済的な停滞や労働争議が続いていたものの、音楽シーンは活況を呈し、若者文化が多様化。ELPのライブパフォーマンスは、巨大なステージセットと圧倒的な演奏で、観客に新たな音楽体験を提供しました。『展覧会の絵』は、クラシック音楽をロックで再解釈する試みとして、当時の音楽ファンに衝撃を与えました。

サウンドとアレンジが伝える物語
『展覧会の絵』の魅力は、ELPの3人が織りなすサウンドと、クラシック音楽を再解釈したアレンジにあります。
キース・エマースンのモーグシンセサイザーは、原曲のピアノパートを電子音で再構築し、幻想的で壮大な雰囲気を創出。グレッグ・レイクのボーカルは、「The Sage」などのオリジナルパートで静かな情感を添え、カール・パーマーのドラミングは「バーバ・ヤーガの小屋」などで激しいリズムを刻み、緊張感を高めます。
特にカールのドラムソロは、テクニカルでありながら感情的な表現力が際立ち、ライブの臨場感を強調。ムソルグスキーの原曲が持つ絵画的なイメージを、ELPはロックのダイナミズムで拡張し、「キエフの大門」の荘厳なフィナーレで聴衆を圧倒します。
後世への影響と現代での意義
『展覧会の絵』は、ELPのキャリアにおいて重要な位置を占め、プログレッシブ・ロックの可能性を広げました。このアルバムは、クラシック音楽とロックの融合という新しいスタイルを確立し、後進のバンド(例えばドリーム・シアターやトランス・シベリアン・オーケストラ)に影響を与えました。
ライブパフォーマンスの録音としても、ELPの演奏力とステージでのエネルギーを伝える貴重な記録です。カール・パーマーは、ELP解散後もソロ活動やアジア(Asia)での活躍を続け、2020年代にはカール・パーマー・バンドとしてツアーを実施。『展覧会の絵』は現代でもストリーミングサービスやライブで親しまれ、クラシック音楽とロックの架け橋として再評価されています。




コメント