★「かぐや姫」の歴史は➡こちら
第5位:『赤ちょうちん』
かぐや姫の「赤ちょうちん」は、1974年にリリースされた名曲で、日本のフォーク史に残る切ないメロディと歌詞が心を掴みます。南こうせつが描く青春の終わりと別れの情景は、昭和の懐かしさと哀愁を響かせます。この記事では、「僕の勝手なBest10:かぐや姫編」の第5位として、『赤ちょうちん』の魅力を徹底解剖。1970年代の背景や僕の思い出を交えながら、時代を超えるその秘密に迫ります。さあ、赤い提灯の下で一緒に一杯やりましょう!(^_-)
まずは公式権現をお聴きください。
クレジット
かぐや姫 – 「赤ちょうちん」 (Official Audio)
© PANAM / Nippon Crown
2行解説
喜多条忠作詞、南こうせつ作曲によるフォークソングの名曲。
居酒屋の赤ちょうちんを舞台に、若者の恋と生活感を描いた代表作です。
『赤ちょうちん』の物語(Short stories)
赤い灯の下で
駅前の通りを歩いていると、風に混じる焼き鳥の匂いが鼻をくすぐった。もうすぐ秋が終わり、冬の気配が近づいている。コートの襟を立てながら、僕はふと立ち止まる。通りのはずれに、赤い提灯が揺れているのが目に入った。あの店だ。五年ぶりに見るその灯は、まるで昔と変わらない顔で僕を迎えているようだった。
店は「みどり」と呼ばれていた。看板に書かれた文字は薄れ、木の扉は塗装が剥げている。それでも、赤い提灯だけは鮮やかで、暗い路地にぽつんと浮かんでいる。昔、ここで彼女とよく飲んだ。名前は彩花(あやか)。大学を卒業して、地元の小さな広告会社に就職した僕と、看護師として働き始めた彼女は、毎週末のようにこの店で顔を合わせた。
中へ入ると、カウンターには見知らぬ顔が並んでいる。ママさんだったおばちゃんはもういないらしい。代わりに、若い男がグラスを拭いていた。僕が座ると、男は無言でビールを置いてくれる。グラスに浮かぶ泡を見ていると、彩花の声が蘇る。「ビールって、見てるだけで落ち着くよね」。そう言って、彼女はいつも笑った。
あの頃、僕らは未来の話をよくした。結婚して、子供ができて、いつかこの町を出て、海の見える場所に住もうなんて。でも、現実はそう甘くなかった。仕事が忙しくなり、すれ違いが増えた。彩花は夜勤で疲れ果て、僕は残業でへとへとだった。些細なことで言い争うようになり、ある夜、彼女は突然言った。「もう、疲れたよ」。それが最後だった。次の日、彼女は荷物をまとめて実家に帰り、連絡は途絶えた。
赤い提灯の下で別れたあの日から、僕はこの店に来るのを避けてきた。でも、今日、急に立ち寄りたくなった。五年ぶりにこの町に戻ってきたのは、転勤が決まったからだ。明日には、また別の街へ発つ。最後に、ここを見ておきたかった。
ビールを飲み干し、焼き鳥を注文する。串に刺さった鶏肉がジュウと音を立てて焼ける。昔、彩花はよく自分の分を半分僕に分けてくれた。「太るからさ」と笑いながら。今思えば、そんな小さな仕草が愛おしかった。
店内を見回すと、壁に古い写真が貼ってある。常連だったおじさんたちや、ママさんの笑顔がそこにある。彩花と僕が写ったものはない。でも、このカウンターの端っこで、彼女が僕の手を握った夜を思い出す。冷たい指先が、僕の掌に触れた感触。あの時、もっと強く握り返していれば、何か変わっていただろうか。
外で、風が強くなった。提灯が大きく揺れ、赤い光が店内にちらつく。二杯目のビールを頼み、グラスを傾ける。酔いが回ると、記憶が鮮明になる。彩花が去った後、僕は仕事に没頭した。寂しさを埋めるように、遅くまで会社に残り、休日は寝て過ごした。でも、心のどこかで、彼女を待っていたのかもしれない。
「もう一杯、どう?」と男が声をかけてくる。首を振って断る。そろそろ帰る時間だ。立ち上がると、少しふらついた。五年という時間は、僕をこんなにも脆くしたらしい。
店を出て、赤い提灯を見上げる。風に揺れるその灯は、まるで彩花の笑顔のようだ。別れの夜、彼女は泣かなかった。ただ、「元気でね」と言って背を向けた。その背中が、提灯の光に溶けていくのを見送ったのを覚えている。
駅に向かう道すがら、ポケットに手を入れると、古いキーホルダーが指に触れた。彩花がくれたものだ。小さな赤い鳥が彫られていて、「みどり」で見つけて買ってくれた。捨てられなかった。五年間、ずっと持ち歩いていた。
駅に着くと、電車の到着を待つ人々がまばらに立っている。ホームの端で、僕はキーホルダーを手に持つ。そして、そっと線路に落とした。赤い鳥が闇に消えるのを見届け、胸が軽くなった気がした。
電車が来て、乗り込む。窓の外に、町の灯が遠ざかっていく。赤い提灯はもう見えない。でも、あの光が僕の中に残っている。彩花との時間は終わった。でも、彼女がいた証は、この胸に刻まれている。
---
次の朝、新しい街に着いた。荷物を解きながら、ふと思う。彩花は今、どこで何をしているんだろう。幸せに暮らしているなら、それでいい。でも、もしどこかで寂しい夜を過ごしているなら、誰かがそばにいてくれることを願う。
夜が更けると、窓の外に小さな居酒屋が見えた。赤い提灯が揺れている。思わず笑みがこぼれる。また新しい記憶が、ここで始まるのかもしれない。僕は立ち上がり、コートを羽織る。そして、その灯の下へ向かうことにした。
かぐや姫と『赤ちょうちん』の誕生秘話
1974年2月5日、かぐや姫のシングル「赤ちょうちん」がリリースされました。作詞は喜多條忠、作曲は南こうせつで、前年の「神田川」に続くヒット曲。この時期、かぐや姫は南こうせつ、伊勢正三、山田パンダのトリオとして全盛期を迎え、フォークブームの頂点に立っていました。「赤ちょうちん」はアルバム『三階建の詩』にも収録され、彼らの音楽性がさらに広がった証です。
喜多條忠は、都会の片隅で揺れる赤ちょうちんと別れの情景を詩に綴り、南こうせつがそのイメージをメロディに昇華させました。僕が中学校3年生だった1973年、この曲が流れると、どこか遠い青春の終わりを感じたものです。
南こうせつは、故郷・大分の赤ちょうちんが並ぶ路地をイメージしたと語ったとか(真偽は定かでないけど、彼らしい!)。都会の片隅で揺れる提灯と別れの情景が、シンプルなギターと柔らかな声で描かれます。僕が高校1年生(1974年)の時、この曲が流れると、どこか遠い青春の終わりを感じたものです。
1970年代のフォークシーンと時代背景
フォークブームの頂点と青春の終わり
1970年代初頭、日本は高度経済成長の余韻を引きずりつつ、オイルショック(1973年)で社会が揺れ始めました。フォークソングは、吉田拓郎や井上陽水らが牽引し、若者の心を代弁する音楽として爆発的な人気を博します。かぐや姫もその波に乗り、「神田川」「妹」とヒットを連発。1974年の「赤ちょうちん」は、フォークの全盛期に花を添えた一曲です。
この頃、僕は中学3年生から高校1年生へ。1974年(昭和49年)、16歳の春、友達と駄菓子を食べながらながら、この曲をラジオで聴いた記憶があります。受験勉強の合間に流れるメロディは、子供時代が終わる寂しさと、未来への不安を映し出したようです。
昭和の赤ちょうちんと別れの文化
「赤ちょうちん」は、昭和の飲み屋街を象徴する存在。都会の路地や田舎の駅前に揺れる提灯は、別れと出会いの場でした。歌詞に登場する「赤い提灯」は、青春の終わりを告げるシンボル。1970年代、都市化で伝統的な風景が消えゆく中、この曲は懐かしさと切なさを残しました。

(※画像の文字は無視してください。chatGPTさん、日本語が下手なので(;_;)/~~~)
『赤ちょうちん』の音楽的魅力と歌詞の深み
シンプルなメロディに宿る切なさ
「赤ちょうちん」のメロディは、アコースティックギターの素朴なアルペジオが基調。南こうせつの柔らかな声と、伊勢正三のコーラスが重なり、哀愁を帯びた響きを作ります。山田パンダのベースが低く支え、フォークらしい温かさを加えます。サビの「赤い提灯が揺れてる~」は、伸びやかな旋律で別れの情感を際立たせます。
歌詞に描かれる青春の終幕
南こうせつの歌詞は、別れと旅立ちを静かに綴ります。「赤い提灯が揺れてる/君の涙がこぼれてる」は、恋人や友との別れを象徴。明確なストーリーはなく、聴く者の想像に委ねる曖昧さが魅力です。以下、3つのポイントで深掘り:
- 別れの情景: 提灯の下での涙が、青春の終わりを静かに告げる。
- 旅立ちの予感: 「汽車の時間」が別れのカウントダウンを刻む。
- 普遍性: 具体性を避け、誰の記憶とも重なる。
かぐや姫の音楽性と『赤ちょうちん』の位置づけ
かぐや姫は、南こうせつの詩的な感性、伊勢正三のメロディセンス、山田パンダの安定感で、フォークの枠を超えた存在でした。「赤ちょうちん」は、「神田川」の都会的な恋愛や「妹」の家族愛とは異なり、青春の終わりをテーマに。1974年、彼らが解散を意識し始めた時期にリリースされ、別れの予感が込められた一曲と言えます。
1970年代の僕と『赤ちょうちん』の思い出
昭和33年生まれの僕は、1974年(昭和49年)に高校1年生、16歳でした。中学を卒業し、新しい友達と過ごす春。「赤ちょうちん」を聴いたあの日は、子供時代の終わりを実感した瞬間です。受験勉強や部活で忙しくなり、友達との別れも増えました。この曲が流れるたび、どこか遠くへ行く友の背中を思い浮かべたものです。
大学2年生の1978年(昭和53年)、20歳の時もこの曲をよく聴きました。キャンパスで仲間と語り合い、将来を夢見た夜。赤ちょうちんが揺れる飲み屋の情景が、僕の青春と重なります。会社員1年目の1981年(昭和56年)、23歳の頃には、仕事帰りの一杯でこの曲を思い出し、懐かしさに浸りました。

時代を超える影響と現代への響き
僕にとって、この曲は1970年代の記憶を繋ぐ糸。高校生の別れ、大学生の夢、会社員の疲れ――それぞれの時代で寄り添ってくれました。現代の若者にも、この切なさが届くことを願います。
まとめ:赤ちょうちんに灯る青春の記憶
「赤ちょうちん」は、かぐや姫のフォーク魂と1970年代の哀愁が詰まった名曲。青春の終わりを静かに歌い、僕の昭和の記憶を彩ります。あなたにとっての「赤ちょうちん」はどんな思い出ですか?お気に入りのかぐや姫曲をコメントで教えてください。次回のBest10もお楽しみに!
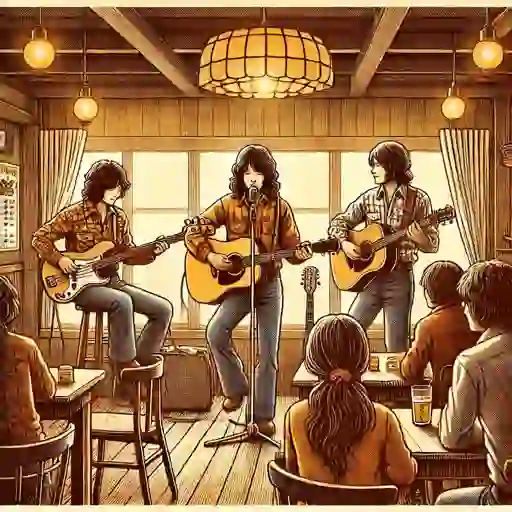


コメント