■【レッド・チェッペリン】について、詳しくはこちら・・・・➡ 🎈(Zeppelin)
🎧 音声で聴く
この記事は、約3分の音声ナレーションでもお聴きいただけます。
文章の流れに沿って、第10位「Custard Pie」が放つ、剥き出しの衝動と歪んだグルーヴをたどります。
読む前に、または読み終えたあとに、音でもぜひお楽しみください。
🇯🇵 日本語ナレーション
🇺🇸 英語ナレーション
🎸【レッド・チェッペリン編】第10位は・・・・
第10位は『Custard Pie』です。
いよいよトップ10の扉が開きます。その一曲目に僕が選んだのは、理屈をなぎ倒すような野性味に溢れたこの曲です。ZEPという巨大な山脈の、最も泥臭く、かつ最も洗練された「岩肌」を触るような体験がここから始まります。
「これぞツェッペリン!」と叫びたくなる、重厚かつ軽快な幕開け。
「これぞツェッペリン!」と叫びたくなる、重厚かつ軽快な幕開け。 ジミー・ペイジのギターと、鍵盤で内部の弦を叩いて鳴らす打楽器的な電子ピアノ「クラビネット」を操るジョン・ポール・ジョーンズ。この二人が織りなす、唯一無二の粘り腰を体感してください。

【超約:欲望のメタファー】
古いブルースの伝統に則り、禁断の果実への渇望を甘美な食べ物に象徴させて描いた物語。そこにあるのは高尚な思想ではなく、抗いようのない生命の衝動と、それをユーモアに変えてしまうタフな精神性です。溢れ出るエネルギーをそのまま音に封じ込めたような、原始的な誘惑の構図が浮かび上がります。
🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
楽曲名:Custard Pie(カスタード・パイ)
アーティスト:Led Zeppelin
収録アルバム:Physical Graffiti(1975年)
作詞・作曲:Jimmy Page / Robert Plant
音源:リマスター版(公式オーディオ)
2行解説
ブルースを基調にした骨太なリフと、ロバート・プラントの挑発的なヴォーカルが印象的なアルバム冒頭曲。『Physical Graffiti』の幕開けを飾るにふさわしい、レッド・ツェッペリンのエネルギーが凝縮された一曲。
1975年、ダブル・アルバムという「巨大な実験場」の号砲
王者の余裕が生んだ「引き算」の美学
この曲が収録された『Physical Graffiti』は、バンドにとって初の2枚組という野心作でした。過去15曲の解説の中で、僕は何度も彼らの「構築美」について触れてきましたが、この『Custard Pie』における彼らの立ち位置は、これまでとは少し違います。
すでにロック界の頂点を極めていた彼らは、ここでは過剰な装飾を捨て、自分たちのルーツであるブルースへの「回帰」と「破壊」を同時に行っています。この曲を1曲目に据えたという事実に、当時の彼らが持っていた圧倒的な自信、あるいは「俺たちが鳴らせば、どんなに泥臭い音楽も最新のロックになる」という傲岸不遜なまでの確信を感じずにはいられません。
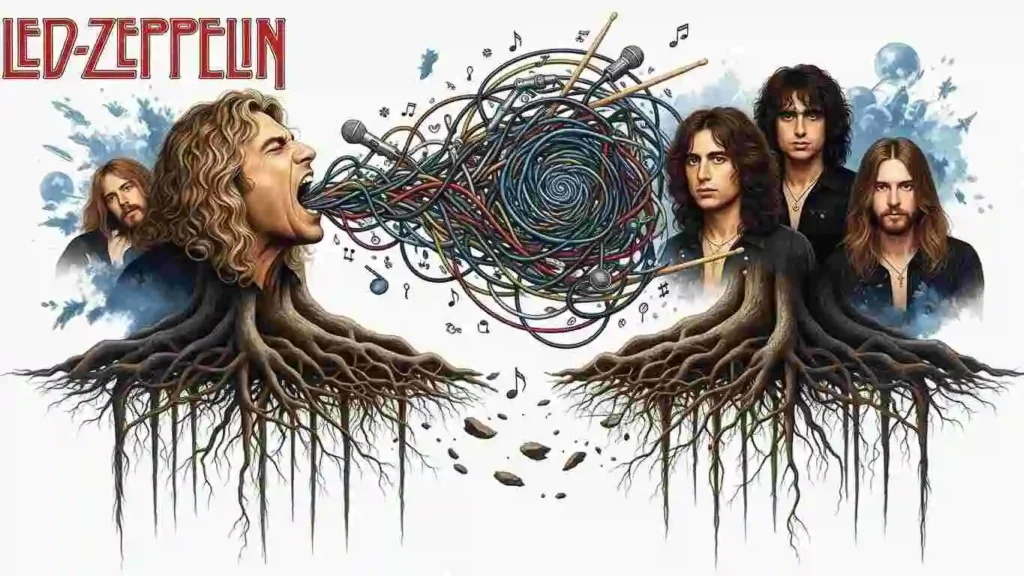
過去の遺産を「今」の熱狂へと接続する
ここで語られるべきは、単なる原点回帰ではないということです。1970年代半ば、プログレッシブ・ロックや華美な演出が流行する中で、彼らはあえて指先の汚れが見えるような、生々しいサウンドを選びました。この「時代におもねない姿勢」こそが、僕がこの曲をトップ10に滑り込ませた大きな理由の一つです。
絡み合う「音の蛇」:クラビネットとギターの共謀
専門用語を介さない「聴覚の快楽」
この曲を聴いて最初に耳を奪われるのは、左右から攻め立ててくる音の「密度」です。普通、ハードロックにおいて主役はギター一本で十分なはずですが、ここではジョン・ポール・ジョーンズが弾くクラビネットが、まるで打楽器のようにギターの隙間に滑り込んでいます。
僕には、この二つの楽器が、獲物を取り合う二匹の蛇のように見えます。どちらかが引けば、どちらかが前に出る。この絶妙な「邪魔のしなさ」が、聴き手の身体を無意識に揺さぶるのです。

重戦車ではない、しなやかな「跳躍」
過去の記事で、僕はジョン・ボーナムのドラムを「重戦車」と例えたことがありました。しかし、この曲での彼のビートは、重いのにどこか軽やかです。地面を叩きつけるのではなく、地面から跳ね返るようなスプリングの効いたリズム。
「Drop down(降りてこい)」という歌詞のフレーズとは裏腹に、音そのものは常に上へと向かっていくような、不思議な浮遊感。このアンバランスさが、僕をいつまでも飽きさせないのです。
剥き出しの言葉が投げかける「回収されない欲望」
結末のない、剥き出しのループ
この曲の歌詞を眺めていて気づくのは、そこに明確な「物語の結末」が用意されていないことです。古いブルースのフレーズをパッチワークのように繋ぎ合わせた言葉たちは、特定の誰かへの愛を誓うわけでも、深い後悔を綴るわけでもありません。
そこにあるのは、「Drop down, baby」と繰り返される執拗なまでの誘いと、満たされることのない渇望だけです。多くのロックナンバーが、サビに向かって感情を解放し、最後に何らかの「着地点」を見せるのに対し、この曲は最後まで解決を見せません。この「感情がどこにも回収されないまま、エネルギーだけが循環し続ける状態」こそが、僕がこの曲を「深い」と感じる正体です。

1975年の歪みが、今も生々しく響く理由
ロバート・プラントの声は、ここでは甘い囁きというより、ザラついた物質のような手触りを持って響きます。
歌詞の中で歌われる「Custard Pie」という比喩は、一見すると軽妙で遊び心に満ちているように聞こえますが、その背後にある演奏があまりに重厚で攻撃的なため、聴き手はそこに「単なるお遊びではない、本気の執着」を感じ取ってしまうのです。
この「言葉の軽さ」と「音の重さ」の歪な乖離。これこそが、レッド・ツェッペリンというバンドが到達した、大人の、そして少し退廃的なブルースの極致なのだと僕は思います。

1975年の針を落とした瞬間、僕の部屋は歪んだ
完璧な「導入」としての記憶
僕が初めて『Physical Graffiti』の1曲目としてこの曲を聴いた時、まず驚いたのは、その「音の近さ」でした。スピーカーから音が鳴った瞬間、部屋の空気が一変し、まるでジミー・ペイジのギターアンプの熱気が首筋に触れたかのような錯覚を覚えたのです。
それは、11位から25位までにランクインした他の名曲たちが持つ「完成された芸術品」としての美しさとは異なるものでした。もっと乱暴で、もっと不完全で、しかし抗いようのない生命力。僕にとってこの曲は、単なる音楽鑑賞の対象ではなく、自分の中にある「整理のつかない感情」を肯定してくれる装置のような存在でした。
思考を止めるための、贅沢なノイズ
日常の中で、言葉にできない焦燥感や、説明のつかない苛立ちに襲われることがあります。そんな時、僕は決まってこの曲のボリュームを上げます。
緻密に構築された楽曲を聴いて「理解」するのではなく、この『Custard Pie』の執拗なリフに身を任せて、思考を強制的に停止させる。そうすることで、逆に自分の内側にある芯のようなものが研ぎ澄まされていく。僕にとって、この曲は最も贅沢な「解毒剤」でもありました。

第10位という境界線:なぜこの曲が「聖域」の門番なのか
王道と異端が交差するポイント
なぜ、この曲が第10位なのか。
それは、この曲がレッド・ツェッペリンの「陽」と「陰」、あるいは「様式美」と「本能」が最も激しく火花を散らしている地点にあるからです。
これより上の順位(1位〜9位)に控えている曲たちは、おそらく誰もが納得するような、ロックの歴史を変えた「金字塔」のような楽曲が並びます。しかし、その「金字塔」の世界へ足を踏み入れる前に、僕たちはどうしてもこの『Custard Pie』という泥臭いフィルターを通らなければならない。そんな「門番」のような役割を、この曲に感じているのです。

この紹介順が意味するもの
25位から一歩ずつ階段を上ってきたこのシリーズにおいて、11位までは彼らの「多様性」や「技術の極致」を堪能してきました。そして今、トップ10の幕開けとしてこの曲を置いたことには、僕なりの意図があります。
それは、「ここから先は、より純度の高い、理屈抜きのエッセンスだけを抽出していく」という宣言でもあります。
『Custard Pie』が放つ、説明不要の「凄み」。それを全身に浴びた今、僕たちの耳は、ZEPが残したさらなる高みへと向かう準備が整ったと言えるでしょう。
この曲を聴き終えた後、耳の奥に残るのは、洗練されたメロディではなく、泥を跳ね上げながら突き進むような、あの歪んだギターリフの感触です。その感触を抱えたまま、次なる第9位への階段を共に登っていきましょう。

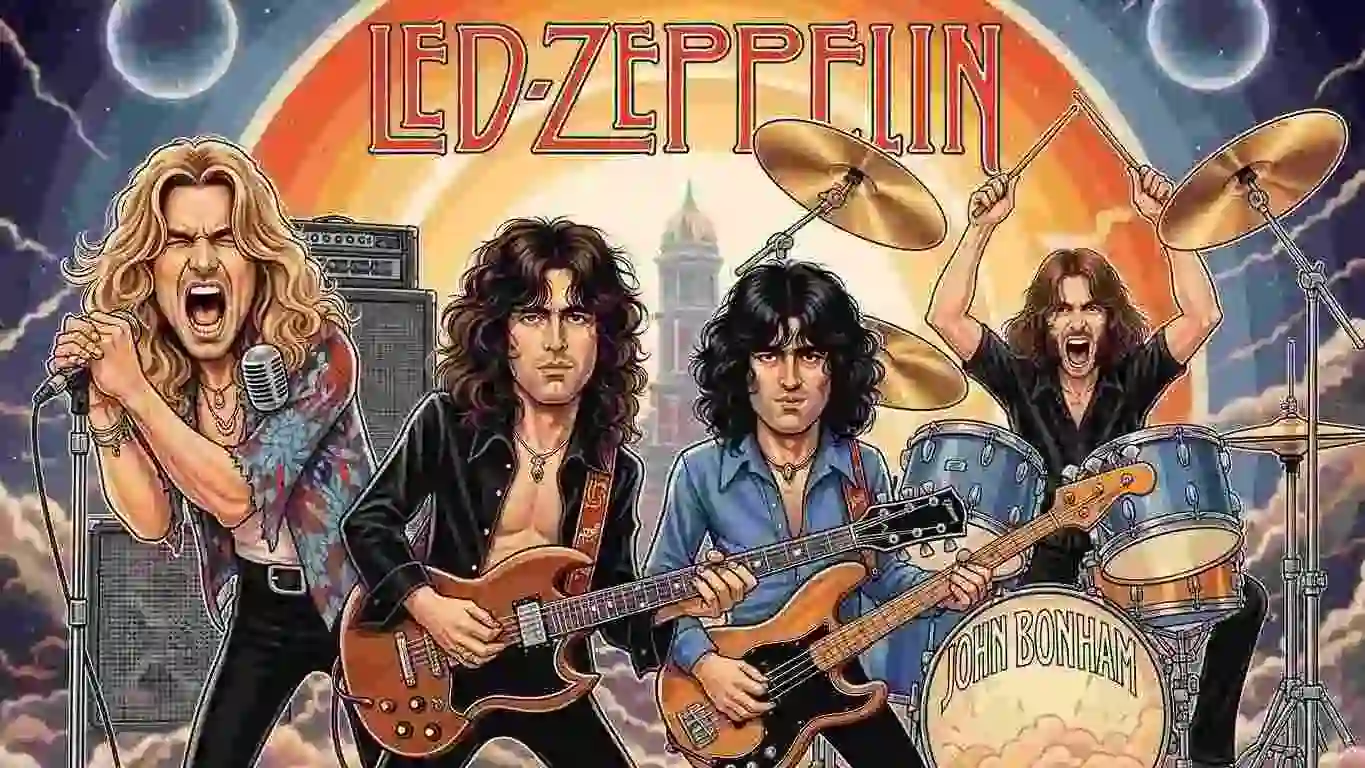


コメント