■【エリック・クラプトン】について、詳しくはこちらをご覧ください。・・・・
➡エリック・クラプトン物語 ― 栄光と試練のギターレジェンド!
🎸【エリック・クラプトン編】第16位『Old Love』です。
第16位は、『Old Love』です。この静かなる魂の叫びをぜひお聴きください。
超約
かつての恋を忘れられず、記憶の中でその面影に苦しみ続ける男の歌。
「古い愛よ、もう放っておいてくれ」と願いながらも、心の炎は消えない。
現実と幻のあいだで揺れ、終わらせたいのに終われない痛みを描いています。
🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
🎸 Eric Clapton – Old Love
© Provided to YouTube by The Orchard Enterprises|© 1989 EPC Enterprises, LLP.
Album: Journeyman
2行解説
ロバート・クレイとの共作によるブルース・バラード。
愛の終わりを静かに受け止めながらも、未練をにじませる大人の哀感が漂う名曲です。
✅ 公式クレジット
Old Love (Acoustic Live) – Eric Clapton & Robert Cray
© 1992 EPC Enterprises, LLP. Under exclusive license to Surfdog Records.
From the album Unplugged (Released 1992-08-25)
Producer: Russ Titelman/Assistant Engineer: Victor DeLugo
🎸 2行解説
エリック・クラプトンがMTV『Unplugged』で披露した名演。ロバート・クレイのギターと掛け合いながら、円熟したブルースの哀感を静かに刻むライブテイクです。
🎬 公式動画クレジット(ライブ音源) 🎸 Eric Clapton - Old Love (Live at The Royal Albert Hall) © 2023 Eric Clapton, from 24 Nights — official release by Warner Records / Reprise. 📖 2行解説 クラプトンが「24 Nights」公演(1990–91年)で披露した名演。 深いブルースフィールとギターの泣きが光る、円熟期クラプトンを象徴するライブ・テイクです。
『Journeyman』期に刻まれた“内面のブルース”
迷いと再出発の時期に生まれた曲
『Old Love』は、1989年リリースのアルバム『Journeyman』に収録された1曲です。作詞・作曲はエリック・クラプトンとロバート・クレイ。ギターの技巧を誇示するタイプの作品ではなく、むしろ感情の整理を音にしたような静かなブルースです。
当時のクラプトンは、依存や人間関係の喪失を経て、再び自分を立て直す時期にありました。キャリアの中で最も成熟しつつ、最も脆い時期でもあったと言えるでしょう。『Old Love』は、その転換期に生まれた“心の鏡”のような作品です。

リリース背景とサウンドの特徴
『Journeyman』自体が「再生」をテーマに掲げたアルバムであり、クラプトンはプロデューサーのテッド・テンプルマンとともに、以前よりも構成を整理し、音数を減らしています。その中で『Old Love』は、アルバムの“静の核”を担う楽曲です。
全体のサウンドは低音を中心に据え、スティーヴ・フェローニのドラムが淡々と脈を刻み、ネイザン・イーストのベースがそれを包みます。クラプトンのギターは決して前に出すぎず、言葉の余白に呼吸のように入り込む。ここには、彼がたどり着いた「控えめで誠実な音作り」が凝縮されています。
歌い出しに見える“心の現在形”
一行の独白がすべてを決める
『Old Love』の始まりは、まるで独り言のようです。
“Too much confusion / Going around through my head”
(頭の中を混乱がぐるぐる回る)

この短い一節が、曲全体の空気を作っています。物語を語るのではなく、いまこの瞬間の心の状態を描いています。クラプトンは「思い出している」のではなく、「思い出してしまった」瞬間を歌っているのです。
特定の時間や場所を設定せず、ただ心のざわめきだけを提示する。そこにリアルな普遍性が宿ります。派手な演出を削ぎ落とし、聴く人それぞれが自分の記憶を重ねられる余地を残しているのです。
感情の温度を一定に保つボーカル
ボーカルは力まず、低めの音域で淡々と進みます。クラプトン特有のハスキーな声は、感情を押し出すよりも、感情を“留める”方向に働きます。聴く者に考える余地を与える歌い方です。
この「抑制された表現」こそが『Old Love』の魅力です。声の揺れや語尾の長さが、どの楽器よりも雄弁に心の動きを伝えます。
3つのバージョンに見る“距離の変化”
スタジオ版:心の輪郭を描く
『Journeyman』のスタジオ版では、ギターとピアノが水平に並びます。打ち込み的なリズムではなく、人の手で刻まれた自然なテンポ。クラプトンはここで、「悲しみ」を誇張せず、一定の距離を保ちながら歌っています。
泣きのギターと呼ばれる彼の代名詞的スタイルも、この曲では一歩引いています。むしろ沈黙の中に意味を見出すアプローチ。音を足すのではなく、削ることで“現実の呼吸”を取り戻しているのです。

『Unplugged』版:声の近さが際立つ
1992年、アコースティック・ライブ『Unplugged』で披露されたバージョン(2番目に紹介している動画です)では、空気の温度が一変します。
エレキの艶を取り除き、木の響きが前面に出ることで、声が圧倒的に近く感じられます。ギターの響きが小さな部屋の壁に反射するような質感で、聴く人の“個人的な記憶”に近い空間が作り出されます。
クラプトンはここで、技術ではなく「語る声」で勝負しています。息の流れが音楽そのものになっている。まさに成熟期の証です。
ライブ版:個人の感情が群衆に届く瞬間
ライブバージョンでは、演奏の流れに合わせてギターが徐々に前に出ます。後半に向けてソロが伸びていくものの、それは絶叫ではなく、粘り強い“滞留”。
観客の歓声と混ざりながら、個人の痛みが共同の感覚へと変わる。ブルースの本質である「共有される孤独」を体現する場面です。
クラプトンは観客に語りかけてはいません。それでも聴く者が自分の経験を重ねられるのは、彼が一切の演技を排除しているからです。

“怒り”が向かう先と、その静かな表情
感情の行き場を探す
曲の中盤に現れるフレーズ、
“It makes me so angry / To know that the flame still burns”
(炎がまだ燃えていると知ると、ひどく腹が立つ)
この怒りは、他人ではなく自分自身に向けられています。
忘れようとしても心が従わない。その矛盾に対する自己嫌悪が、ここでは静かに描かれます。

クラプトンはこの「内向きの怒り」を叫ばずに伝えます。感情を外に投げないからこそ、心の密度が上がる。ブルースが社会や不運を嘆くジャンルだとすれば、『Old Love』は“自分という不確かな存在”への嘆きです。
内面を描くブルースの新しい形
この静けさは決して弱さではありません。
むしろ、感情を見つめる覚悟の表れです。クラプトンは、強がりもドラマも排し、ただ「残ってしまった想い」と向き合う。
その姿勢が、のちの『Tears in Heaven』や『Running On Faith』へとつながっていくのです。『Old Love』はその起点に位置する作品だといえるでしょう。
心の命令形――「忘れたい」と「忘れられない」のはざまで
言葉の強さが、弱さを語る
『Old Love』のサビには、印象的な命令文が並びます。
“Old love, leave me alone / Old love, just go on home”
(古い愛よ、もう放っておいてくれ/家に帰ってくれ)
この一節は一見、強い拒絶のように聞こえます。
しかし実際には、心の中で何度も繰り返している自己暗示のようなものです。
命令形で言葉を押し出している時点で、まだ心に残っている証拠。
自分でも気づかぬうちに、未練を抱えたまま時間が流れている——そんな静かな現実を、クラプトンは正面から描いています。

ここには、ブルース特有の「感情を外へ吐き出す力」はほとんどありません。
むしろ、感情を抑えながら“抑えきれない自分”に苦笑しているような、成熟した諦観が滲みます。
理性と幻影の交差点に立って
幻を見ていることを理解している
中盤のフレーズに、次のような一節があります。
“I can see your face / But I know that it’s not real / Just an illusion”
(君の顔が見える、でも本物じゃない、ただの幻だ)

ここで主人公は、すでに「現実」と「記憶」を明確に区別しています。
つまり、幻想の中で生きているのではなく、幻を自覚したまま生きている。
その冷静さこそが、この曲の核心です。
クラプトンは、この一行で理性と感情の“時差”を見せています。
頭では終わったと理解しているのに、心はその事実に追いつかない。
この矛盾を、彼はドラマではなく「音の呼吸」で表現しています。
ギターの一音ごとに、忘れたい気持ちと忘れられない現実が交錯する。
それは、悲しみよりも現実的で、ブルースが長い時間をかけて到達した“静けさの美”と言えます。
“乗り越えられない”のではなく、“共に生きる”
諦めではなく、共存の感覚
終盤に登場するフレーズ、
“I’ll never get over / Know now that I’ll never learn”
(もう乗り越えられない、学ぶこともないと今は分かる)

この言葉は、失恋ソングの“絶望”とは違います。
これは敗北の宣言ではなく、共存の選択です。
「消せないものを抱えながら生きる」——それを受け入れた人間だけが見える風景がある。
クラプトンの声には、もはや痛みすら滲みません。
そこにあるのは“冷めた悲しみ”ではなく、“静かな了解”です。
忘れる努力ではなく、思い出と共に呼吸していく覚悟。
『Old Love』のラストは、そんな穏やかな境地に着地します。
現実の中で鳴るブルース
クラプトンがこの曲で示したのは、ブルースを「怒りの音楽」から「受容の音楽」へと進化させたことです。
外の世界を責めるかわりに、自分の中に残る痛みをそのまま見つめる。
そこには、1970年代の若きクラプトンにはなかった静けさと、人生の厚みがあります。

音と沈黙のあいだにあるもの
それでも消えない炎
一見、完全に冷静を取り戻したようでいて、曲の根底には小さな“炎”が残っています。
“The flame still burns”
(炎はまだ燃えている)
この短い一節が、曲全体を支える背骨です。
それは、もう恋愛ではなく“生きること”そのものに転化した熱。
過去の痛みを抱えたまま、それでも音楽を続ける——そんなクラプトン自身の姿勢を象徴しています。
“Old Love”という普遍のテーマ
誰もが持っている「忘れたい記憶」は、年月を経てもふと蘇ります。
クラプトンはそれを過去形にせず、現在形のまま歌いました。
そこに、彼の音楽家としての誠実さと、ひとりの人間としての実感が共存しています。
この誠実さがある限り、彼の音楽はいつまでも聴き手の生活に寄り添うのです。

🎵まとめ
『Old Love』は、忘れられない人を責めず、自分を責めもしない――
ただその存在を静かに受け入れるという境地に到達した曲です。
クラプトンの長い旅路の中で、もっとも小さな声で、もっとも深いことを語った瞬間。
だからこそ、この曲は聴くたびに「大人になるとはこういうことか」と思わせてくれるのです。
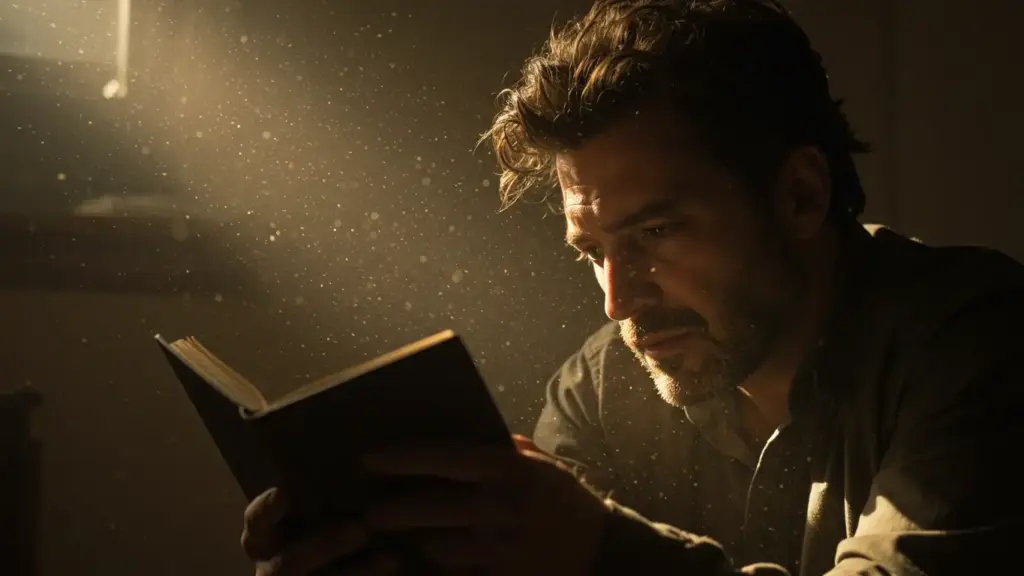



コメント