■【エリック・クラプトン】について、詳しくはこちらをご覧ください。・・・・
➡エリック・クラプトン物語 ― 栄光と試練のギターレジェンド!
🎸【エリック・クラプトン編】第14位『Presence of the Lord』
第14位は、『Presence of the Lord』です。
1969年、エリック・クラプトンがスティーヴ・ウィンウッド、ジンジャー・ベイカー、リック・グレッチとともに結成したスーパーグループ「ブラインド・フェイス」。その唯一のアルバム『Blind Faith』に収録されたのが『Presence of the Lord』です。作詞・作曲はクラプトン自身で、彼がリードヴォーカルも担当しました。華やかな名声の只中でありながら、彼が書いたこの曲には、内省と感謝、そして静かな救済が流れています。
🔸超約
ようやく、自分の生き方と居場所を見つけた。
与えられるものは少なくても、心は解き放たれた。
すべての真実はすでに知られており、今、私は「神の色(あるいは存在)」の中で生きている。
——迷いや欲から離れた、静かな悟りの境地を歌っています。
🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
Provided to YouTube by Universal Music Group
Presence Of The Lord · Blind Faith
Album: The Cream Of Clapton(© Universal Music Operations Ltd.)
🎧 2行解説
エリック・クラプトンが作詞作曲した、ブラインド・フェイス唯一のアルバム収録曲。
静と動が交錯する構成の中で、内面の「救い」と「安らぎ」を描いた代表的スピリチュアル・ナンバーです。
🎬 公式動画クレジット(ライブ音源)
YouTube によって配信提供:The Orchard Enterprises
『Presence of the Lord(Live from Madison Square Garden)』/エリック・クラプトン、スティーヴ・ウィンウッド
収録アルバム:『Live from Madison Square Garden』
(© 2009 TDF Ltd.、The Orchard Enterprises による独占ライセンスのもとで配信)
🎧 2行解説
クラプトンとスティーヴ・ウィンウッドが再会を果たした2008年NY公演のライブ音源。
互いの成熟した演奏と声が交差し、ブラインド・フェイス時代の祈りが40年越しに蘇ります。
心の静けさを描いた、クラプトン最初の祈り
内省と救済のバランス
この曲をひとことで表すなら、「満たされぬ者が、ついに生きる場所を見つけた」という小さな祈りの歌です。大きな勝利も、宗教的熱狂もありません。あるのは、自分の限界を知った者が、やっと安心して立てる場所を見つけたという穏やかな悟りです。激しいギターと静寂が交錯しながら、曲はその「心の転換点」を描き出します。

リリースと背景にある“空白の時間”
ブラインド・フェイスという一瞬の旅
ブラインド・フェイスは、クリーム解散後のクラプトンが一時的に結成したグループです。周囲の期待はあまりに大きく、アルバム発売前から“伝説の誕生”と騒がれました。しかし本人はその状況に戸惑い、リーダー的存在としての重圧を感じていたといわれます。『Presence of the Lord』は、その中で生まれた“内なる回心”の記録でもありました。
名声の裏側にあった葛藤
クラプトンは当時、宗教的な意味での「信仰告白」をしていたわけではありません。それでもこの曲には、“何かにすがらずには生きられない”という心情が明確に刻まれています。ロックの形式を使いながら、彼は自分にとっての“救い”を模索していたのです。

歌詞が語るもの:足りない自分を受け入れる
“I have finally found a way to live”の意味
“I have finally found a way to live”
(ついに生きる方法を見つけた)
“Just like I never could before”
(これまで一度もできなかったような生き方で)
冒頭から、彼は感情を抑えた口調で語り始めます。「ようやく生きる道を見つけた」という一文には、遅すぎた安堵が漂います。彼は次の行でこう続けます。
“I know that I don’t have much to give”
(与えられるものは多くないと知っている)
“But I can open any door”
(それでもどんな扉でも開けることができる)
この対比が、曲全体を貫くメッセージの核です。自己肯定と自嘲の狭間で、クラプトンは“自分の価値”を再定義しようとしています。彼の言葉には説教臭さがなく、むしろ「弱さの中にしか本当の力はない」という静かな確信が感じられます。

“Everybody knows the secret”に込められた皮肉
“Everybody knows the secret”
(誰もがその秘密を知っている)
“Everybody knows the score”
(誰もがその真実の成り立ちを知っている)
信仰というより、人間の本質への洞察に近いフレーズです。「誰もが知っているはずのことを、私はようやく思い出した」というニュアンスで読むと、彼の言葉の深みが見えてきます。
そして最後にこう締めくくられます。
“I have finally found a way to live
In the presence of the Lord”
(ついに生きる方法を見つけた——主の御前において)
宗教的な言葉を借りながらも、彼が語る“Lord(主)”は神というより、安らぎそのものを象徴しています。混沌とした時代にあっても、自分を支える何かを見つけたという実感。それこそが、この曲の静かな感動の源です。

音の構成に潜むドラマ
静寂が支配する前半の構築
『Presence of the Lord』の構成は、非常にシンプルでありながらドラマティックです。前半はピアノとオルガンの穏やかな響きで始まり、まるで礼拝堂に射す朝の光のような雰囲気をつくります。ここでクラプトンは抑えた声で語り、スティーヴ・ウィンウッドのオルガンがその背後を柔らかく支えます。音数は少なく、空間に余白があり、静寂こそが主役です。
ワウ・ギターの爆発が象徴する心の解放
中盤で曲の空気は一変します。ギターが唸りを上げ、ワウ・ペダルによる鋭いソロが炸裂します。しかしそれは派手な演出ではなく、心の奥に隠してきた激情の一瞬の解放として響きます。爆発は短く、再び静けさが訪れ、曲は穏やかに終わります。この「静と動」の対比は、クラプトンが後年に至るまで貫く表現の原型となりました。
“Color”と“Presence”の間にある意味の揺らぎ
聴き間違いが生んだ二重の解釈
曲の最後に繰り返されるフレーズは、聴き手によって「In the presence of the Lord」とも「In the color of the Lord」とも聞き取られます。録音の重なりやコーラスの響きによるもので、実際には“presence”が正しいとされていますが、この曖昧さがむしろ魅力になっています。
“presence(臨在)”が精神的な安らぎを示すなら、“color(色彩)”は世界を包む感覚的な祝福を暗示します。どちらにしても、クラプトンが辿り着いたのは“信仰”ではなく“受容”です。彼は救いを外側に求めず、自分の中の静けさとして見出したのです。
制作エピソードとスタジオの空気
ブラインド・フェイスという“奇跡の短命”
1969年のロンドン。クラプトンは、ジンジャー・ベイカーとの確執を抱えながらも、スティーヴ・ウィンウッドの誘いを受けてブラインド・フェイスに参加しました。ウィンウッドの音楽的感性に惹かれつつも、前バンドの“ギター神話”から逃げたいという思いが強く、クラプトンはこの新しい環境を「自分を取り戻すための避難所」のように感じていたといわれます。
『Presence of the Lord』は、そんな複雑な心理の中で書かれました。彼にとってこれは、キャリアの中で初めて“個人的な祈り”を曲として形にした瞬間でした。
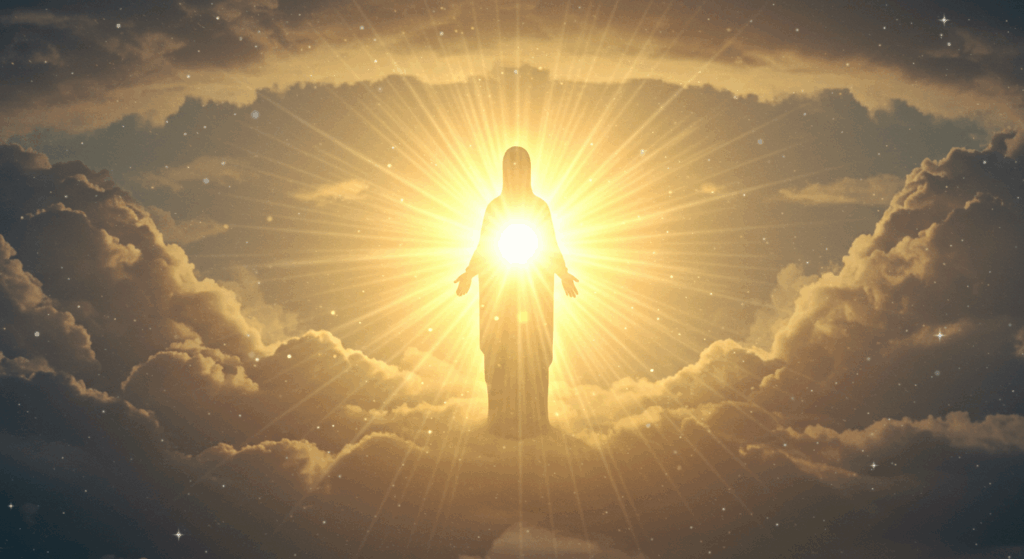
録音現場のやり取り
セッションでは、ウィンウッドのオルガンが先に録られ、その上にクラプトンがギターとヴォーカルを重ねました。録音の際、ウィンウッドは「もう少しゆっくり歌ってみたら?」と提案したといいます。テンポを落とすことで、言葉の余韻と静けさが生まれ、結果的にこの曲の象徴的なテンポ感が決まりました。
この“間”の取り方は、のちのクラプトン作品にも通じる特徴であり、彼が「弾かないことを弾く」という境地に向かう出発点にもなりました。
ライブ演奏の変遷
再発見される「静」の力
ブラインド・フェイスが解散した後、この曲は長い間ライブで取り上げられませんでした。しかし、1976年のツアーでクラプトンが再び演奏すると、観客の反応は驚くほど温かいものでした。ギターソロの部分では、若い頃の爆発的な勢いはなく、代わりに時間をかけて“沈黙に還る”ような演奏が印象的でした。
クラプトン自身、「この曲は自分にとって“祈るための場所”のようなもの」と語ったことがあります。演奏のたびにテンポやアレンジは変わりますが、祈りの構造は一度も壊れていません。
現代版の“Presence”
2004年の『Crossroads Guitar Festival』では、クラプトンとウィンウッドが再会し、この曲を共に演奏しました。二人の声が重なる瞬間、観客席には静寂が流れ、35年前の空気がそのまま蘇ったように感じられました。ギターソロの後も観客は歓声を上げず、むしろ息を殺して聴き入る――その反応が、この曲の本質を物語っています。
総括:クラプトンが見つけた“音楽の祈り”
“ギターヒーロー”から“人間”への回帰
『Presence of the Lord』を聴くたびに感じるのは、クラプトンという人間が自分を取り戻していく過程です。
派手な技巧よりも誠実さを選び、名声よりも心の静けさを求めた結果、この曲が生まれました。
彼にとって“Lord”は信仰の対象ではなく、“音楽そのもの”だったのではないでしょうか。音に身を委ね、言葉に頼らず、ただ生きる方法を見つけた――そのシンプルな姿勢が、今もこの曲を特別なものにしています。

今も古びない理由
『Presence of the Lord』が時代を超えて輝きを保つのは、過剰に語らず、過少にもならない絶妙な均衡を持っているからです。静かな語り、短い解放、控えめな結論。
どれもが慎ましく、しかし一点の曇りもない。
クラプトンはこの曲で、技巧よりも“態度”を示しました。彼の音楽人生を貫く軸――「真実を語るために静けさを選ぶ」という姿勢は、この曲から始まったのです。
結びに
『Presence of the Lord』は、クラプトンのキャリアを語る上で小曲に見えるかもしれません。
しかし、その短い時間の中で彼は、名声や技術を越えて“人としての在り方”を示しました。
静かに生きること、受け入れること、そして祈ること。
その三つを音楽に変えた瞬間――それが、この曲の真の価値です。



コメント