■【ビリー・ジョエル】について、詳しくはこちらをご覧ください。・・・・Wikipedia!
🎸【ビリー・ジョエル編】第8位『Allentown』を深掘り!
第8位は、『Allentown』(アレンタウン)です。アメリカ・ペンシルベニア州の都市名です。
彼の哲学や思想が詰まった一曲です。斜に構えた表現ではなく、淡々とユーモアを交えて歌うジョエル。カッコいいです!
🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
Billy Joel - Allentown (Official Video)
© Billy Joel / Columbia Records
提供:Billy Joel 公式YouTubeチャンネル(登録者数215万人)
公開日:2009年10月4日/視聴回数:約1,190万回
📖 2行解説
1982年のアルバム『The Nylon Curtain』収録曲で、工業都市アレンタウンの衰退と労働者の苦境を描いた社会派ロックナンバー。全米チャートでヒットを記録し、80年代アメリカの経済不安を象徴する楽曲として知られている。
🎬 公式動画クレジット(ライブ音源)
Billy Joel - Allentown (Live from Long Island)
© Billy Joel / Columbia Records
提供:Billy Joel 公式YouTubeチャンネル(登録者数215万人)
公開日:2018年12月10日
📖 2行解説
1982年アルバム『The Nylon Curtain』収録曲「Allentown」を、地元ロングアイランドで披露した貴重なライブ映像。社会的メッセージを込めた歌詞と力強いパフォーマンスが観客を魅了した名演となっている。
作品の位置づけと基本情報
1982年発表のアルバム『The Nylon Curtain』収録曲で、同年にシングルとしてもリリースされました。全米チャートではトップ20圏内のヒットとなり、MTV黎明期の象徴的なビデオも話題に。作者名義は当然ビリー・ジョエル、テーマはアメリカ北東部の製鉄・炭鉱地帯に生きる人々の現実です。
ここでのポイントは「特定の街の賛歌」ではなく、80年代初頭の産業構造の転換期を生きた無数の街の縮図として描かれていること。地名は象徴であり、語りは“私たち(we)”の複数形で進みます。

超約
工場が閉まり、仕事が消えゆく町で、若い世代は親から受け継いだ誇りと不安の両方を抱えて暮らしています。学校で教わった「努力すれば未来は開ける」という約束は果たされず、旗やスローガンだけが空回りする。それでも地元を離れず、今日も踏ん張って立ち続ける――そんな等身大の決意を刻んだ歌です。
地図から読み解く『Allentown』
地名が連なる理由
歌は“ここ(Allentown)に生きている”という宣言から始まり、すぐに“Bethlehem”という隣町も登場します。製鉄で知られる地域名を並置することで、単なる郷愁や観光案内ではないことを早々に示します。地名=固有名詞の連打は、「誰の話でもあるが、誰かの具体的な暮らしでもある」という二重焦点を作る装置です。

三つのレイヤー(家族/学校/職場)
この曲は大きく三層でできています。
- 家族の記憶:父の世代が戦後の好況に寄与した事実と、その誇り。
- 学校の約束:努力すれば報われるという教育の物語。
- 職場の現実:工場閉鎖、書類の山、行列、そして組合の弱体化。
三層が縦に重なり、世代間のズレが横方向へ広がる――その立体感が、個別の嘆きではなく共同体の時間を描き出します。

“we”と“they”の距離
語りの主語は“we”。対置されるのは“they”――工場を閉める側、約束を掲げた側、政策や企業判断を行う側です。“I”単独の嘆きにしないことで、歌は個人の不幸話に閉じません。聴き手は“we”の中に自分を置き、“they”との距離を測ることになります。
歌詞の勘所
1) 開口一番の現場描写
「closing all the factories down(工場が次々閉まる)」という強い動詞から曲は始動します。名詞よりも動作を先に提示することで、“変化の速度”を耳に乗せる効果が生まれています。続く「Filling out forms / Standing in line」(書類の記入 / 列に並ぶ)は韻律をそろえた二連の現在分詞。動きはあるのに前へ進まない停滞感を、そのまま音価に変換しています。
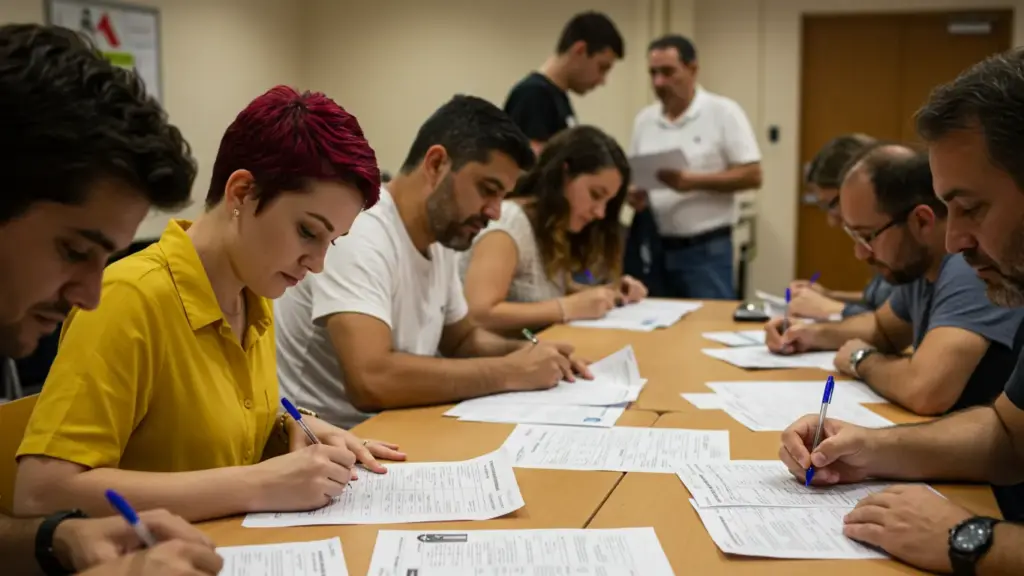
2) 父の世代の物語
「our fathers fought the Second World War」(私たちの父親は第二次世界大戦で戦った)は、戦後アメリカの“正統性”の源泉をワンフレーズで示します。週末に海岸へ出かけ、USOで母と出会い、ゆっくり踊った――という穏やかな情景は、働く喜びと生活の安定を背景に持つ黄金期の縮図です。ここで過去の幸福を丁寧に置くからこそ、現在のコントラストが効いてきます。

3) 約束された未来は来なかった
「the promises our teachers gave」という表現は、教育制度そのものを敵視しているわけではありません。むしろ“努力=報酬”という単線的な成功物語が、構造転換期には機能しないことを指摘しています。壁に掛かった卒業証書は「graduations hang on the wall」、しかし現実の役には立たなかった――紙の権威と就労の現場が切断される瞬間を、視覚イメージで描きます。
4) シンボルの逆流
「They threw an American flag in our face」は刺激的ですが、反米ではありません。国旗=共同体の理念が、当事者の実感に追いつかないときに生じる“象徴の空回り”を示す比喩です。理念が悪いのではなく、接続のやり方が問題だ――と読むのが妥当です。
5) 決意としての言い返し
サビ付近の「hard to keep a good man down」善良な人を抑えつけるのは難しい)は、自己鼓舞の定型句。ここでは“善良で勤勉な人間は打ち負かせない”という共同体の倫理を、軽い皮肉を込めて再掲しています。諦観ではなく、踏みとどまる意志の宣言として機能します。

音・映像・語り口――鑑賞ガイド
行進感と機械感のブレンド
リズムは規則正しい刻みで、足踏みのような行進感が続きます。装飾は華美にしない。メロディは口ずさみやすい範囲に収まりますが、要所で半音階が表情を曇らせ、明るいだけの“応援歌”に堕しません。キャッチーだが浮かれない、このさじ加減が曲の生命線です。
ビデオが補う“身体性”
ビデオでは、工場や更衣室、ライン作業を思わせるシーンが続きます。ダンサーの整然とした動きは、規律を強いられる身体のメタファーでもあります。派手な特撮や大がかりな物語は不要で、集団の身体を画面に定着させたことがこの曲の映像的強みです。

ユニークなエピソード
この曲は当初、別の地名アイデアから発想が広がったと言われます。結果として“製鉄の街”を象徴する名称に焦点が定まり、歌の普遍性が増しました。実在の住民の間でも当初は賛否が分かれたものの、長い時間の中で“地域の記憶を伝える歌”として受け止められるようになった、という点も示唆的です。固有名詞を掲げることの重みと責任を、ビリー自身が熟考した作品だと感じます。
何が胸に残るのか――三つのアイデア
①「努力すれば報われる」をめぐる再検討
この歌は努力の価値を否定しません。ただ、努力だけでは越えられない壁がある現実を見据えます。個人の気合や自己責任論に回収されない目線が、今聴いても古びません。
② 家族史が地域史へ、そして国家史へ
父の世代のダンスホールから、卒業証書の壁、工場の門、組合の衰退、国旗の象徴性へ――個人→家族→地域→国家と視点がスムーズに拡張していきます。拡張の軸がぶれないのは、語り手が常に“we”を起点にしているからです。
③ それでも残るユーモア
深刻な題材ながら、言い回しやメロディの設計には乾いたユーモアが差し込みます。過剰な悲壮感を避け、聴き手が自分の生活に引き寄せやすい温度を保っているのが見事です。
日本の読者に向けた読み替え
この歌を“遠い国の昔話”と片付けるのは簡単です。しかし、産業の転換・人口流出・教育と雇用のミスマッチは、現在の日本各地でも起きています。

- 資格や学位の価値が地域によって不均等に配分されてしまう問題。
- 非正規比率の上昇が若年層の将来設計に与える影響。
- 地域アイデンティティとキャリアの両立。
『Allentown』は、これらを劇的な告発ではなく、生活の語彙で語ることを教えてくれます。住む場所を変えない選択も、離れる選択も、どちらも誇り得る選択である――その含みを残すのがこの歌の成熟です。
まとめ:『Allentown』を手元の生活へ
- 固有名詞を掲げながら、普遍的な“働く町の物語”へと開いた歌。
- “we/they”の構図で個人の嘆きに閉じず、共同体の時間を描き切る。
- 過去の栄光、教育の約束、職場の現実――三層の交差が聴きどころ。
- 反復と簡潔な比喩で、諦めではない持続の意思を刻む。
聴き始めの合図は、あの平坦な足取りのビート。今日のあなたの歩幅で数えてみてください。派手な名フレーズに頼らないからこそ、生活の中で効く一曲です。



コメント