■僕の勝手なBest10【エリック・カルメン編】にプロフィール(歴史)を記載してます。
🎸僕の勝手なBest10【エリック・カルメン(Eric Carmen)編】第9位
『Make Me Lose Control』:夏の疾走感が弾ける恋のアンセム
エリック・カルメン編:第9位は、『Make Me Lose Control』です。
エリック・カルメンといえば、『All By Myself』に代表される繊細で内省的なバラードが印象的です。しかし、1987年にリリースされたこの『Make Me Lose Control』は、そのイメージを大きく覆す、情熱的かつ爽快なポップソングでした。

この曲には、夏の夜風のような高揚感と、胸が高鳴る恋の瞬間が閉じ込められており、リスナーを一気に非日常へと連れ出してくれます。
🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
🎬 公式動画クレジット(ライセンス提供)
曲名:Make Me Lose Control
アーティスト:Eric Carmen
提供元:Arista/Legacy(YouTubeによるライセンス配信)
動画公開日:2014年11月7日
📖 2行解説
1987年に全米3位を記録した、夏のポップ・アンセム。
恋と音楽の高まりを軽快に描いた、エリック・カルメンの代表的な快作です。
🎬 公式動画クレジット(オフィシャルビデオ)
曲名:Make Me Lose Control
アーティスト:Eric Carmen
提供元:Eric Carmen公式チャンネル
動画公開日:2014年2月1日
📖 2行解説
映画『Deadpool & Wolverine』でも話題となった、エネルギッシュなラブソング。
1987年の全米ヒットが、新たな世代にも響く公式映像で蘇ります。
本記事では、アレンジ、歌詞、構造、そして背景に至るまで、この曲の魅力を多角的に掘り下げていきます。
リリース背景
ソロ後期の快進撃を象徴する一曲
『Make Me Lose Control』は1987年にシングルとしてリリースされ、全米Billboard Hot 100チャートで第3位を記録する大ヒットとなりました。

同年、映画『ダーティ・ダンシング』で使用された『Hungry Eyes』と並ぶ成功作であり、エリック・カルメンのソロ後期の代表作といえる位置づけです。
本作はスタジオアルバムには未収録で、のちにベスト盤などに収められましたが、結果的にこの楽曲がカルメンの音楽的多面性を再認識させる契機となりました。
アレンジと音作りに見る、1980年代的な洗練
シンプルなリズム構造が導く躍動感とドラムマシンとリバーブ処理の妙!
この曲はストレートなリズム構成と強めのスネアで疾走感と緊張感を保ちつつ、1980年代特有のリバーブ処理によって厚みと広がりのある音像を生み、サビの高揚感を効果的に演出しています。
シンセとギターの重ね方に見る“音の絵画”
シンセサイザーが広がりを、ギターが輪郭を与える――そうした役割分担が、巧みにレイヤーとして積み重ねられています。
音数は決して多くないにもかかわらず、豊かに感じるのは、この配置の妙によるものでしょう。

左右に振られたステレオ演出
ギターやパーカッションの定位を左右に分散させることで、音の奥行きが強調されています。
このバランス感覚には、プロデューサーJimmy Iennerの音像設計へのこだわりが表れています。
アレンジの工夫が曲のテーマと直結する
サビ前で一度リズムを引いてブレイクを挟み、サビに向けて再び爆発させる構成などは、まさに「感情が抑えきれず溢れ出す」というテーマと呼応しています。
音の配置や強弱そのものが、歌詞世界と感情曲線を視覚化しているかのようです。
声の表現力が生むドラマ性

この楽曲の魅力のひとつは、ボーカルとコーラスによる立体的な「声の演出」にあります。
歌い出しのリードボーカルは抑えたトーンから始まり、サビに向かって力強く展開していく構成を取っています。これにより、物語が進行していくような感覚が生まれます。
一方で、コーラスは単なるハーモニーにとどまらず、空間の広がりや感情の余白を支えるような存在として機能しています。
リードボーカルの表現の幅
この曲では、エリック・カルメンのボーカルスタイルが、それまでの「泣きのボーカル」から、よりストレートで伸びやかな歌唱へと変化しています。
Aメロでは抑制的に感情を内側に込め、Bメロ以降で一気に情熱を放出する構成は、彼の表現力の幅の広さを感じさせます。
仲間と歌うような開放感
コーラスが生む一体感
“Baby, baby”(ベイビー、ベイビー)や“Hold me close”(そばにいて)といったコーラスパートは、サビの中で主旋律に絡みながら繰り返され、まるで友人たちと車内で合唱しているような雰囲気を演出しています。

この“仲間と共有している感じ”が、曲全体に親しみやすさと躍動感をもたらしています。
コーラスワークに見る80年代的スタイル
複数人が交互に歌っているようなコーラスの厚みは、80年代ポップスに典型的な手法ですが、本作ではそれが非常に効果的に機能しています。
特にコーラスのタイミングとリズム感は、リスナーが思わず一緒に口ずさみたくなるような親近感を生み出しており、曲への没入感を高めています。
歌詞に込められた“音楽の記憶”
懐かしい曲名の引用と意図
歌詞の中には、1960年代の名曲を思わせるフレーズがいくつか登場します。
たとえば冒頭の一節、
“Jennifer’s got her daddy’s car, she’s playing ‘Uptown’ on the stereo”(ジェニファーはお父さんの車を乗り回し、ステレオで『Uptown』をかけている)
では、Archie Bell & the Drellsの楽曲を思わせる“Uptown”が登場。

さらに、“Jennifer’s singin’ ‘Stand by Me’”(ジェニファーは『スタンド・バイ・ミー』を歌っている)というフレーズでは、Ben E. Kingの永遠の名曲が引用されています。
こうした挿入は、恋の情景に過去の名曲を重ね合わせ、リスナーの記憶とも共鳴する仕掛けになっています。
“Be My Baby”という象徴
ブリッジでは、“Be My Baby comes on and we’re movin’ in time”(『ビー・マイ・ベイビー』が流れ、私たちはリズムに合わせて身体を揺らす)という一節が登場します。

これは、1963年にThe Ronettesが発表した名曲への明確なオマージュであり、音楽と恋の記憶が絡み合う“時間の溶解”を象徴しています。
音楽が時間を溶かす装置になる
このように、歌詞に古典的ポップソングを巧みに織り込むことで、“音楽が感情と記憶を喚起する媒体”であることを示しています。
カルメンはポップミュージックの系譜を意識しながら、自らの青春とリンクする音楽体験をリスナーと共有しようとしているのです。
映像との結びつき:MTV時代の感性
ミュージックビデオにおける視覚的設計
『Make Me Lose Control』のミュージックビデオは、MTV文化が成熟しきった1980年代後半を背景に制作されました。

ラジオ、車、海辺、若者たち――そうした要素が断続的に登場し、視覚面からも“夏の高揚感”を伝える工夫が施されています。音・歌詞・映像という3つの要素が有機的に連動し、五感で楽しめる作品としての完成度を高めています。
記憶に溶け込むような構成
映像には明確な物語や起承転結はありませんが、それによって見る者自身の経験や記憶を投影しやすくなっています。
この構成が、視聴者の個人的な感情と自然に重なり合う仕組みとして機能しており、結果として楽曲そのものの印象を強く残す効果を生んでいます。
普遍性と現代的な価値
懐かしさと新鮮さが共存する理由
『Make Me Lose Control』は、1960年代の名曲を連想させる引用やアレンジを用いながらも、時代に取り残されることなく輝き続けています。その理由は、それらが単なる模倣ではなく、音楽的文脈を踏まえた再創造として機能しているからです。
レトロな雰囲気と現代的な聴き心地が同居する稀有な楽曲であり、だからこそ長く愛されるのです。

リスナーと曲の関係性
サマーソングとしての定着
『Make Me Lose Control』は、今なおサマーソングとして多くのプレイリストに組み込まれています。

特にSpotifyやApple Musicでは、「ドライブ」「1980年代ヒッツ」「夏の思い出」といったテーマにおいて高頻度で登場しており、季節感や情景との相性の良さが、曲の再生回数を押し上げる大きな要因となっています。
『All By Myself』との明確なコントラスト
1975年の代表曲『All By Myself』は、孤独や自己の内面と向き合う内容でしたが、『Make Me Lose Control』では、他者とのつながり、共有する時間の高揚感が描かれています。

両者は方向性が全く異なりながら、どちらも感情の核に迫るという共通点を持っています。それによって、エリック・カルメンという人物の表現領域の広さが際立つのです。
『Hungry Eyes』との併走:映像との親和性
同年にヒットした『Hungry Eyes』も、映画『ダーティ・ダンシング』との融合によって印象深い作品となりました。
両曲とも視覚との結びつきが強い楽曲ですが、『Hungry Eyes』がムード重視のラブソングであるのに対し、『Make Me Lose Control』は軽快で快活なエネルギーを放っています。

同じ年に生まれたにもかかわらず、楽曲が担う“感情の温度”は対照的であり、それぞれが補完し合うような存在といえます。
現代における再評価
2020年代の耳で聴く『Make Me Lose Control』
2025年の現在において、この楽曲が単なる“懐かしの80年代ヒット”ではなく、いまも新鮮に響く理由を整理すると、以下の3点に集約されます。
恋と音楽に没頭する普遍的な主題
タイトルの“Make me lose control”(自分を抑えられなくなる)というフレーズには、恋の熱情や音楽の高揚に飲み込まれていく様子がストレートに描かれています。

この体験は、時代が変わっても共通する人間的な感覚であり、誰もがどこかで経験しているものです。
80年代サウンドの再注目
現在の音楽シーンでは、シティポップや80年代リバイバルの潮流が強まり、当時の音楽のスタイルや質感に再びスポットが当たっています。
その中で、リバーブの効いたスネア、透明感のあるシンセ、明るく広がるコーラスといった要素を備えたこの曲は、今の耳にも自然と馴染みます。
プレイリスト文化との高い親和性
プレイリストのキュレーションでは、“場面”や“気分”に合った楽曲が求められます。
『Make Me Lose Control』は、「ドライブ中」「夏の夕暮れ」「懐かしい気分になりたいとき」など、さまざまなシーンにフィットする万能性を持っています。
その結果、ストリーミングでも繰り返し選ばれ、新しいリスナーとの接点が持続しているのです。
結び
“明るいエリック・カルメン像”の象徴
『Make Me Lose Control』は、エリック・カルメンのキャリアにおいて異色かつ象徴的な存在です。
それは、彼が内面の痛みや孤独を描くバラードのイメージから離れ、誰かと時間を過ごす喜びや、音楽に夢中になる瞬間を前向きに描いたからです。
この曲に詰まっているのは、感情の衝動、美しい過去へのまなざし、そしてリスナーと共有できる明るい時間の記憶。
それゆえに、『Make Me Lose Control』は、何年経っても心を駆け抜けるような一曲として、私たちのそばにあり続けるのです。
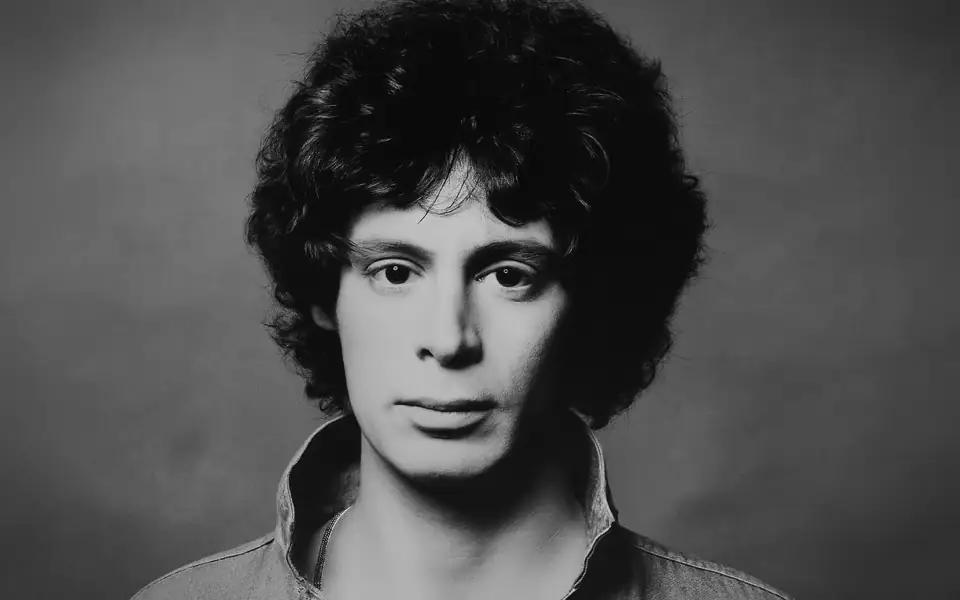

コメント