「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
いよいよふきのとう編も、Best7に入ります。
第7位は、100回や200回以上は間違いなく聴いている曲で、大好きな「風の船」です。
では、早速『風の船』について、その魅力と奥深さを詳しくご紹介いたします。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『ふきのとう/風の船(海よりも深く…) 』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
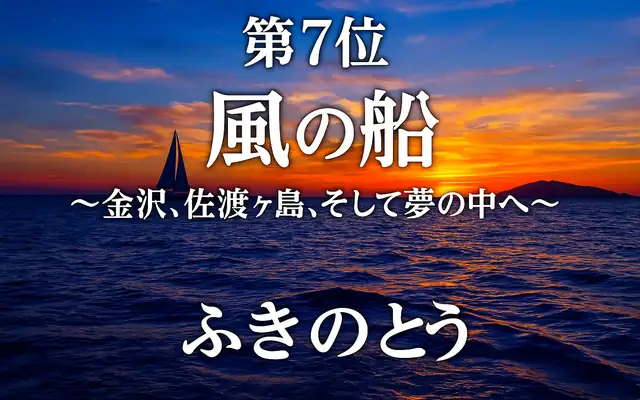
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル: ふきのとう/「風の船(海よりも深く…)」
作詩・作曲:山木康世/編曲:瀬尾一三
リリース:(1976年6月21日発売)
動画公開年: 2015/12/30
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
旅と哀しみが重なる“音の絵画”――『風の船』の基本情報
1976年6月21日、ふきのとうの5枚目のシングルとしてリリースされた『風の船』。この曲は、同年7月1日に発売されたサード・アルバム『風待茶房』にも収録されています。
作詞・作曲は山木康世、編曲は瀬尾一三が担当。
ふきのとうの作品群の中でも、特に情感と映像性に富んだ一曲として、ファンの心に刻まれています。
映像的な詞世界とストーリー性
『風の船』の最大の特徴は、詞に描かれる風景の鮮明さと、そこに重ねられる感情の奥行きです。
一人の旅人が喪失と向き合いながら新たな地平に踏み出す姿が描かれており、まるで映画を見ているようです。
“喪失”をテーマにした叙情詩
この曲が扱っているのは、過去の恋を手放しきれずにいる心情です。失われた関係を忘れるために旅に出た主人公は、思い出の地に身を置くことで逆に感情を揺さぶられていきます。その心理のゆらぎが、ごく自然に、しかも丁寧に描かれている点に、本楽曲の真価が宿っています。

歌詞に登場する地名と風景描写の力
『風の船』の歌詞では、具体的な地名が登場します。これが作品全体のリアリティを支える重要な要素となっています。
金沢・佐渡ヶ島がもたらす情景のリアルさ
冒頭の「船は行く波の上 あなたが好きだった街」という一節に続いて、「あこがれの金沢へ ぼくを連れて走れよ」と綴られます。金沢という具体的な都市名が登場することで、聴き手は一瞬で旅の舞台に引き込まれます。

さらに、佐渡ヶ島の描写も印象的です。
暮れて行く夕闇に 佐渡ヶ島が見える
潮風に月あかり 夏の夜は始まる
地名が示す風景と時間帯が織り重なり、旅情とともに感情の広がりを感じさせてくれます。

実際の航路についての補足
金沢と佐渡を直接結ぶ定期航路は存在しないため、これは詩的な構成であると考えられます。ただし、佐渡が「遠く見える存在」として描かれているため、物理的な正確性よりも象徴的な距離感と情緒に重きが置かれているのです。
主人公の内面と、風景の関係性
この楽曲の魅力は、主人公の感情を直接的に語らず、風景を通じて間接的に映し出している点にあります。
“言わずに語る”情感描写
忘れるために来た 一人の旅なのに
それでも あなたの面影 夢に見る

風景の描写はあくまで静かで、過度な比喩や感傷に頼らず、情景に心を託す構成が貫かれています。
流れ星と潮騒に込められた時間の流れ
流れ星 おやすみ 遠く 潮騒の空に
夜空に流れる星や、遠くから聞こえる潮騒。それらが時の流れを象徴し、主人公の「忘れようとしながらも忘れられない」複雑な心境をやわらかく包み込んでいます。

二人の声が織りなす、ふきのとうの真骨頂
主旋律を導く、細坪基佳の澄んだ歌声
この楽曲では、細坪基佳がメインボーカルを担当しています。その透明感あふれる歌声は、主人公の繊細な心情とよく調和し、感情を押しつけすぎることなく、静かに語りかけてくれます。
特に、“忘れるために来た一人の旅なのに”というくだりでは、理性と未練のはざまで揺れる心がにじむような歌唱が印象的です。
聴き手はその歌声に、自身の過去や旅の記憶を重ね、そっと心を寄せたくなる瞬間を味わうことになります。
山木康世のハーモニーが加える奥行き
山木康世のコーラスは、細坪さんの透明感ある声と美しく絡み合います。その響きには土の匂いや体温が感じられ、どこか懐かしい風景を想起させる効果があります。
特にサビでのハーモニーは、感情の波が重なり合いながら押し寄せてくるような効果を生んでいます。この「二つの声が交差する時間」こそが、ふきのとうが持つ表現力の核心であり、リスナーに強い印象を残す所以でもあります。
タイトル『風の船』に込められた意味
この楽曲のタイトルである『風の船』という言葉には、直接的な登場こそないものの、全体を貫くような詩的な含意があります。
船は心、風は運命
歌詞にはたびたび「船が波の上を進む」情景が登場しますが、これは単なる移動の描写にとどまりません。主人公の心そのものが、風に揺られながらあてもなく進む“船”として象徴されているのです。
終盤では、主人公が「北の国へ帰る」決意を語る場面が描かれます。ここで登場する“青く光る風”という表現が、タイトルの“風”を強く印象づけます。
この風は、自然の力であると同時に、主人公の心を再び日常へと導くための意思や感情の流れとも解釈できます。

“風の船”とは何か
すなわち『風の船』とは、過去を振り切るために旅に出ながらも、結局は風(=運命や記憶)に流され続ける心のありようそのものを表しているのかもしれません。
クライマックスに訪れる感情の解放
この楽曲の最後に登場するサビは、それまで抑制されていた感情が一気にあふれ出す、物語の頂点に位置づけられます。
「今でも愛している」と告げる決意
終盤、主人公は風に想いを託し、こう願います:
もう一度あの人に伝えて この心
今でもあなたを愛してる
この一節は、ただの未練ではなく、“いまこの瞬間にも変わらずに愛している”という現在形の確信として描かれています。
旅の終着点は、記憶の彼方ではなく、“心の現在地”だったのだと気づかせてくれます。

比喩としての「海よりも深く」
愛の深さを比喩的に表すこの表現は、ベタに見えるかもしれませんが、本曲の舞台が「北陸の海」であることと響き合うことで、より詩的な効果を持ちます。
自然の情景と内面の感情がシンクロしているため、「海よりも深く」という言葉が抽象ではなく“実感”として迫ってくるのです。
色褪せない“音の旅”――『風の船』の普遍性
1976年に発表された『風の船』は、リリースからおよそ半世紀が経過した現在も、ふきのとうファンをはじめ多くの音楽リスナーに愛され続けている名曲です。
理由は、この曲が描くテーマが、時代や世代を超えて共有可能な“人間の感情”に根ざしているからに他なりません。
誰しもが経験する“忘れられない旅”
「旅に出ることで心の整理をつけようとする」「思い出の場所を訪れ、かえって感情が深まってしまう」
――こうした感覚は、特別な人生経験ではなく、多くの人が持っている普遍的な感情のひとつです。

ライブ演奏での評価と、聴き手とのつながり
『風の船』は、ふきのとうのライブでも何度も披露されてきた楽曲であり、そのたびに観客の心を静かに揺さぶってきました。
静かな曲に、深い感動が宿る
細坪基佳がソロ活動を始めた後も、『風の船』はしばしばステージに登場し、静寂の中に染み込むような余韻を残しています。
爆発的な盛り上がりとは対極にある演奏スタイルですが、観客との“感情の共鳴”という意味では非常に強い力を持っているのです。
おわりに:聴くたびに広がる、心の風景
『風の船』は、情景描写に富んだ詞と、確かな演奏、そしてふたりの歌声が織りなす静謐な世界で構成されています。
旅・喪失・未練・希望――さまざまな感情を内包しながら、聴き手に委ねる余白を残しているからこそ、何度聴いても新しい発見があります。




コメント