「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
【ふきのとう】編-第9位『思い出通り雨』をご紹介!
第9位は、「想い出通り雨」です。いい曲です!!
フォークデュオ「ふきのとう」の作品には、まるで一編の物語を読むような、豊かな情景と物語性がいつも宿っています。その中でも『思い出通り雨』は、失恋というテーマを扱いながら、どこか静かで透き通るような印象を残す、不思議な魅力を持った一曲です。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『ふきのとう/思い出通り雨 (1978年)』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
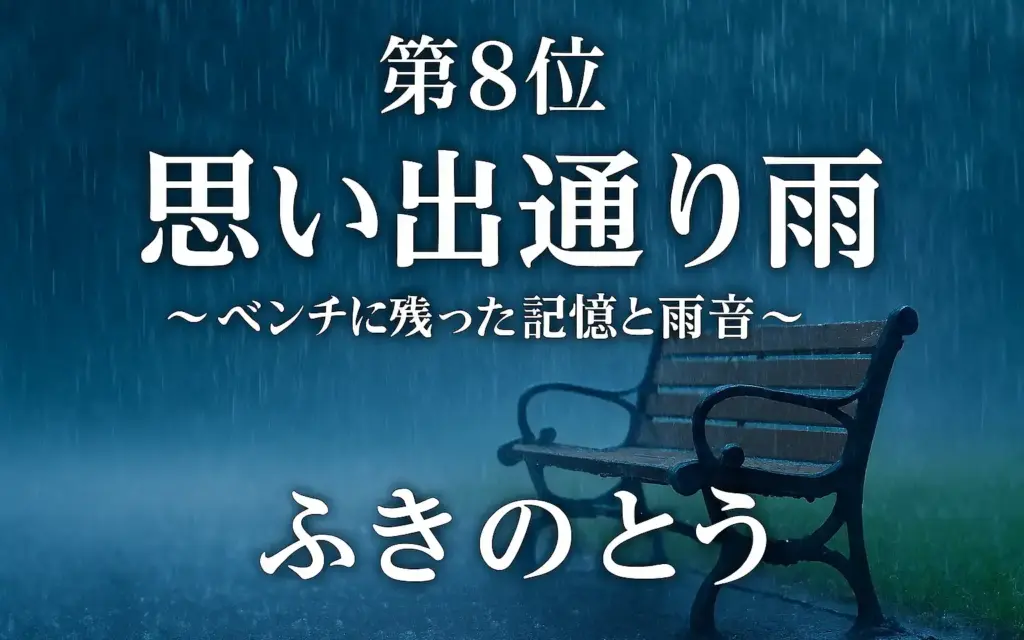
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:ふきのとう/思い出通り雨
作詩・作曲:山木康世/編曲:瀬尾一三
動画公開年: 2014/11/07
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
はじめに 〜忘れられない、心の通り雨
ふきのとうは、山木康世と細坪基佳の二人によるフォークデュオ。1970年代から80年代にかけて活動し、多くの名曲を生み出しました。山木の叙情的で物語性に富んだ詞と旋律、そして細坪の清らかで透明感のある歌声。この二人が織りなす音楽世界は、聴く人の記憶の深層に入り込み、長く心に残ります。

そんな彼らの名曲群の中から、今回は個人的なランキング第9位として『思い出通り雨』を選びました。この記事では、その歌詞に込められた物語の奥行きと、音楽が描き出す感情の風景を丁寧に掘り下げていきたいと思います。
作品情報
リリースと基本情報
『思い出通り雨』は1978年7月21日、オリジナルアルバム『思い出通り雨』のタイトル曲として発表されました。同年9月21日には『初恋』との両A面シングルとしてもリリースされています。
歌詞の物語性
冒頭:過去に囚われたまなざし
この曲は、たった数連の詩の中に、ひとつの心の旅路が丁寧に描かれています。たとえば、冒頭の「君の目は寂しそうに 遠くを見てる」という一節。遠くを見つめる視線の先には、別れた恋人への想いが滲んでおり、過去に囚われた心情がにじみます。

ベンチに座る記憶の再訪
続いて登場するのは「ベンチ」というモチーフ。誰かと語り合った記憶の場所に、今はひとりで腰掛けている。そこには、幸せだった時間との対比が静かに流れています。
決意の瞬間:手紙を捨てる
やがて彼女は「手紙を捨てる」。あの人の匂いが残るその手紙を手放すという描写からは、過去への執着を断ち切ろうとする決意が読み取れます。行動に託された心の変化が、さりげない語り口で描かれている点が印象的です。
終章:雨の中を歩き始める

最後に「雨の中を歩き始める」という場面で締めくくられます。失ったものを抱えながら、それでも前に進もうとする姿勢。静かながら力強いメッセージが、聴き手の心に静かに届きます。
サビに込められた象徴性
印象的なのは、サビで繰り返されるフレーズ:
思い出通り雨 も一度 降れ降れ
気まぐれ通り雨 優しく 降ってやれ
“通り雨”という儚い自然現象に、記憶と再生の感情を重ね合わせたこの比喩表現は秀逸です。ただ“忘れる”のではなく、一度しっかりと「降る」こと——つまり感情を流しきることによって、ようやく前に進めるという心の流れを示しています。

そして何より、「優しく降ってやれ」と結ばれることで、この歌は誰かに対する怒りや後悔ではなく、あくまで“静かな思いやり”に包まれているのです。捨てられた手紙も、ベンチに残る記憶も、全てが美しい風景として曲中に溶け込んでいます。
メロディと歌声が織りなす繊細な世界
メロディラインの佇まい
『思い出通り雨』の魅力は、歌詞だけでなく、その音楽的構成においても際立っています。山木康世の描くメロディは、哀しみと品格を同時に内包するフォークらしい旋律を持ちつつ、淡々とした美しさを保っています。

細坪基佳の語るようなボーカル
そこに細坪基佳のボーカルが加わることで、この曲の世界は一層引き締まります。細坪の声は、ただ透明感があるというだけでなく、どこか距離を保ちながら語るようなスタイルで、楽曲に“語り”としての魅力を与えています。その表現は、ふきのとうの最大の特徴ともいえるでしょう。
声の重なりがもたらす温度感
この曲でも、主旋律を担当する細坪に対し、山木が重ねる低音のハーモニーが印象的です。ふたりの声が溶け合いながらも、完全には混ざりきらない微妙な距離感が、この楽曲に独特の温度感を生み出しています。
アレンジと音の構築美
アコースティックギターが描く静けさ
編曲を担当した瀬尾一三の仕事も見逃せません。イントロのアコースティックギターは、まるで雨粒のように静かに始まり、聴く者の感情を優しく包み込んでいきます。ギターの音色には、触れればこぼれてしまいそうな繊細さがあります。

ハーモニカとストリングスの補助線
中間部にさりげなく挿入されるハーモニカの音色も見逃せません。郷愁を誘うこのサウンドは、都市の雨というよりも、どこか懐かしい地方の風景を思わせる響きを持っています。

さらに、後半にかけて加えられるストリングスは、降りしきる雨の情景をドラマティックに広げる役割を果たします。ただし、あくまでも歌詞とメロディを支える“背景”として控えめに機能しています。
こうした音の設計によって、『思い出通り雨』は聴くたびに異なる印象を与え、聴き手自身の記憶や感情を映し出す鏡のような存在となっているのです。
なぜ『思い出通り雨』は心に響くのか?
普遍的なテーマとしての「別れ」
『思い出通り雨』が今なお多くの人の心を打つのは、それが「別れ」という、誰もが一度は経験する感情を普遍的に描いているからです。恋愛に限らず、人は人生の中でさまざまな“別れ”に直面します。それを受け止め、心の中で整理していく過程を、あくまでも静かに、そして優しく描いた本作は、どの時代のリスナーにも寄り添う力を持っています。

この曲に描かれている心の動きは、決して特別な体験ではありません。過去に想いを馳せ、記憶を抱えながら前へ進む。その繰り返しこそが人生であり、『思い出通り雨』はまさにその一端をそっと切り取ったような作品です。
時代背景と“静けさ”の価値
1978年という時代は、都市の喧騒や情報量の多さとは対照的に、この楽曲は“静けさ”そのものを大切にし、心の奥を見つめる時間を与えてくれます。
現在のように音や言葉があふれる時代において、必要なのは「語らないこと」からにじみ出るメッセージです。この曲には、まさにそうした余韻や慎ましさがあります。『思い出通り雨』は、そのことを音楽で証明しているのです。

若い世代にも届く感情のリアリティ
「ふきのとう」の音楽は、一見すると時代性の強いフォークの枠に収まりそうですが、細やかな情景描写や感情の丁寧な表現は、若い世代にも十分響く要素を持っています。特にこの曲では、語られる言葉の量よりも、音の持つ表情が大きな役割を果たしており、むしろリスナー自身の想像力を刺激するつくりになっています。
SNSで自らの心情を発信することが当たり前となった今だからこそ、このような“語らないけれど伝わる”作品に新しい意味が生まれているのかもしれません。
おわりに 〜記憶の中に降り続ける雨
聴き終えたあと、まるで雨上がりのような澄んだ気持ちになるこの楽曲は、「悲しみの中にある美しさ」や「心を整理する勇気」といった、日々を生きる私たちにとって大切な何かをそっと教えてくれます。
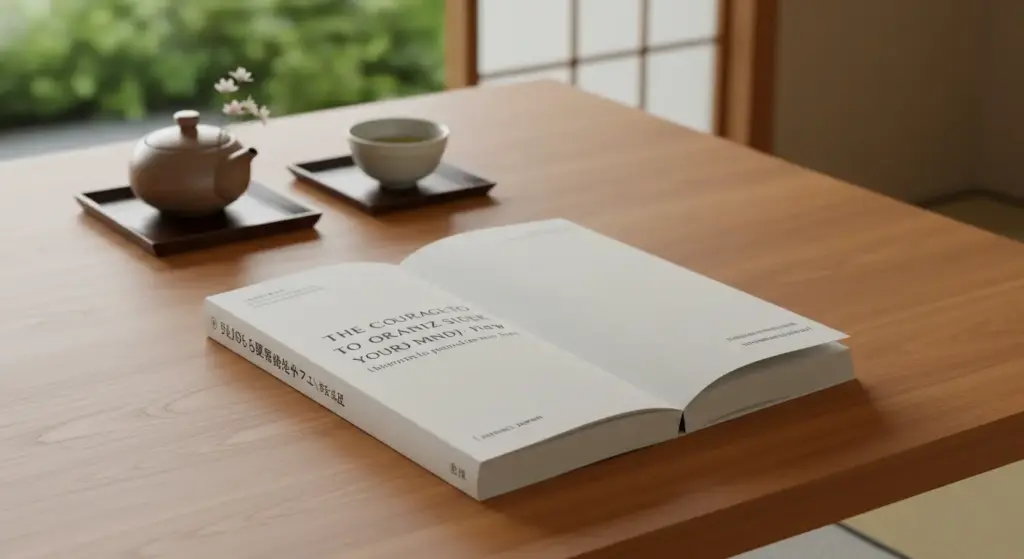



コメント