「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
僕の勝手なBest30:【ふきのとう】編、第11位
は1974年リリースの『プラットフォーム』です。ふきのとう初期の作品で、いつものごとく、優しくも悲しい歌です。いよいよ明日からは、Best10に突入します。これまでの締めくくりの一曲としてもふさわしいと思っています。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『プラットホーム /ふきのとう』にリンクしています。
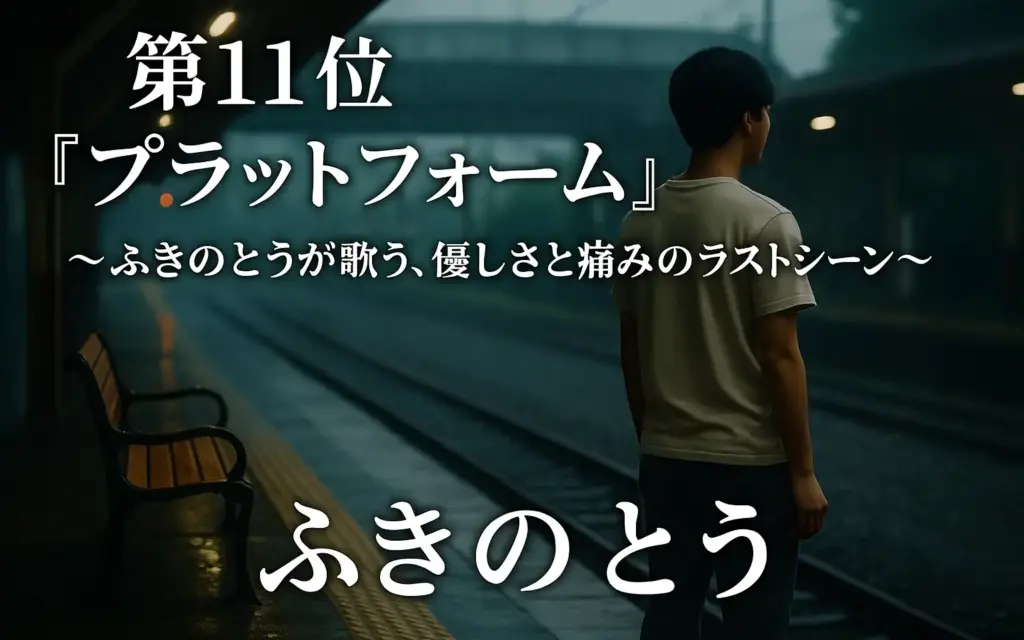
(※動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:プラットホーム /ふきのとう
作詩・作曲:山木康世/編曲:石川鷹彦
挿入アルバム:1st.『ふきのとう』(1974年10月21日発売)
公開年: 021/09/07
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
冒頭の一言がすでに“結末”を示している楽曲
1974年10月21日、フォークデュオ「ふきのとう」がリリースしたデビューアルバム『ふきのとう』は、今もなおフォークファンの記憶に残る名盤として知られています。その中に収められた『プラットフォーム』という一曲。タイトルは駅のホーム、つまり「分岐点」を意味しながらも、そこには単なる“別れの歌”では括れない、時間と感情の編集が施されています。

この曲を聴いてまず感じるのは、“物語”よりも“シーン”の強さです。始まりの一節、「プラットホームまで 送って行こう 辛くなる事は 知ってるけど」。この一言は、これから展開されるすべての情景を、ワンカットの映像として静かに提示してきます。
あえて言えば、この作品には明確な起承転結がありません。恋の始まりも、なぜ別れに至ったのかという説明もほとんどなく、ただ「いま」だけが描かれているのです。そう考えると、この作品が映し出しているのは、ある別れの“クロースアップ”であり、物語の中盤やクライマックスというより、ワンシーンだけをフィルムから切り取ったかのような感覚を抱かせます。
駅のホームは、記憶の保管庫でもある
“雨”は情緒を演出する小道具ではない
『プラットフォーム』の舞台は、雨が降る駅のホーム。この設定だけでも、ドラマや小説のエンディングシーンを連想する人も多いでしょう。けれど、この曲における“雨”は、単なる情緒的な演出ではありません。
むしろ、音や空気の湿り気、視界のぼやけ、体温の低下……そうした物理的な変化を伴って、聴き手をその場に「留める」ための装置として機能しています。濡れた床、傘に当たる水音、そして視界を遮る雨脚。それらはすべて、感情ではなく感覚としての記憶を喚起させるトリガーとして構成されています。

このように、映像ではなく「音」の中で時間を固定するという手法は、当時としても非常に先鋭的でした。
列車の去り際は“編集点”である
「君の乗った汽車は 白い煙を残して行ってしまった」。この一節を聴いた瞬間、まるでカメラが後方に引いていくような映像が脳内に広がる人もいるでしょう。駅を出発する列車の描写は、物語の終わりではなく、視点の切り替わり、すなわち“編集点”として位置づけられています。
1974年当時、蒸気機関車はすでに引退期にあり、「白い煙」は現実よりも比喩の力を持っていました。だからこそ、それは物理的な移動ではなく、関係性が“空に溶ける”プロセスそのものを意味しているのです。

しかもこの場面には、主人公の台詞もモノローグもありません。ただ“去っていく背中”と“残された視点”が静かに映し出されるだけ。まるで、台本に語られぬ行間を残したまま、観客の想像力で補ってもらうことを前提とした脚本のようです。
「伝えないこと」が伝わる、逆説的な演出
説明を拒むことで生まれるリアリティ
この楽曲には、「なぜ二人は別れたのか」「どちらが別れを切り出したのか」といった背景がほとんど描かれていません。
冒頭の語りは、セリフでありながら、どこかナレーションのようにも響きます。登場人物が舞台に立ち、演出された光の中で、ひとつの動作を淡々と演じている。しかもそこにあるのは激情ではなく、整理された静けさです。

感情の「発露」ではなく、あとに残る「響き」だけが配置されている構成だからこそ、この曲は何度聴いても、新たな感じ方の余地が生まれてくるのではないでしょうか。
サウンドがつくり出す“静かな情動”
石川鷹彦の編曲がもたらす構造的な奥行き
『プラットフォーム』の編曲を担当したのは、アコースティック・フォークの名職人として知られる石川鷹彦。彼の編曲には、楽曲の構造そのものに情景を刻む手腕があり、それはこの曲でも明確に現れています。
冒頭、ギターのアルペジオが静かに響き始めると、雨の匂いと湿気を感じさせるような空間が広がります。このイントロ部分ではメロディが語られるより先に、聴き手の感覚が呼び起こされていく。その感触こそが、映像的でありながらあくまで音楽的な演出なのです。

曲が進むにつれてリズムがやや前に出てきますが、それでもあくまで控えめ。楽器群は主張せず、言葉と旋律を下から支える立場に徹しています。
アコースティックギターによる“時間の保持”
ギターのフレージングは、風景を描くのではなく、時間の進行そのものを留めるような働きをしています。特に2番に入ったあたりから現れるストロークは、決して勢いをつける役割ではなく、歩みの速さや足音のリズムを刻むようなもの。
“駅のホームを歩く”という、何の変哲もない動作が、音楽のなかで一つの情感へと変換されていく。ギターは単なる伴奏ではなく、記憶を静かに反復する装置として機能しているのです。
歌声が語る“心の輪郭”
細坪基佳の声が物語の温度を決めている
『プラットフォーム』でリードボーカルを務めるのは細坪基佳です。その歌声は、澄んだ水のように透明でありながら、どこか湿り気を含んでおり、まさに雨の情景にふさわしい質感を持っています。
背景としてのコーラスがあったとしても、それは細坪の声を引き立てるにすぎず、二人のデュオ感を打ち出すものではありません。この曲では、あくまで細坪一人の語りとしての歌声が前面に据えられています。
言葉と音が生む“密度の高い沈黙”
「楽しかった想い出だけは大切にするよ」という一節
このフレーズは、別れの場面においてよく使われる常套句のようにも思えます。しかし、本作におけるその言葉は、空々しい慰めや言い逃れとしては響きません。むしろ、“どこにもぶつけようのない感情”を整理するための、自分への小さな言い聞かせとして機能しているのです。
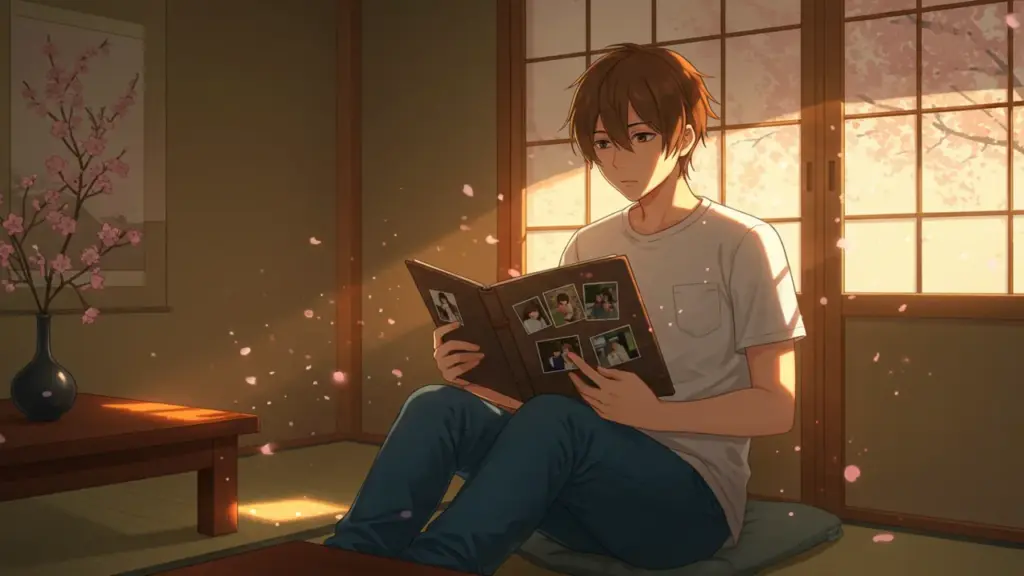
このセリフのあとの空間には、音楽的な“間”すら存在しない。ただ静かに次のフレーズへと移行していきます。にもかかわらず、この一言の印象が強く残るのは、そこに演出の手がほとんど入っていないからです。飾られず、装飾もなく、まるで日常のつぶやきのような言葉こそが、この曲の真骨頂を表しています。
「楽しいことだけが人生じゃないよ」という記憶
主人公がふと思い出すこの一言。言ってしまえば、これは自己防衛です。別れを受け入れざるを得ない立場に立たされた人間が、過去の言葉にすがりつつ、自分の心を整理しようとする。ここにはドラマチックな動きはありませんが、その静けさの中に、人生の奥行きが宿っているように感じられます。
今もなお聴き手の心に残り続けているのはなぜか
感情に頼らず、風景で語るという作法
『プラットフォーム』は一般的なフォークソングとは一線を画すスタイルを持っています。大きな抑揚や激しい感情の起伏を排し、あくまで一つの出来事――それも“日常の延長線にある別れ”を、淡々と描いています。

それが地味に聴こえるという人もいるかもしれません。しかし、感情を語るのではなく、感情が立ち上がる状況を描く。それによって、聴き手は楽曲の中に自分自身を重ね合わせる余地を得るのです。
強調ではなく、解像度の高い静けさ

たとえば「君が好きだから 離したくない」というフレーズ。あまりにも率直なこの言葉が、なぜこれほど胸に残るのか。それは、背景で鳴っている楽器がそれを持ち上げることなく、ただ淡々と進行するからです。感情を強調せず、聴き手の想像力に多くを委ねることができる。そうした構造的な“静けさ”の演出が、この曲の個性を際立たせています。
聴き手の経験と結びつく構造
背景を語らず、余分な情報を持たせない
この曲を聴き終えたあとに残るのは、ひとつの物語を体験したような充足感です。
『プラットフォーム』は、誰かの物語ではなく、“自分の記憶”として受け取る余地を与える構成になっています。それこそが、何十年経っても人の心に残り続ける普遍性の鍵です。
年齢とともに意味が変化していく楽曲
若い頃にこの曲を聴いたときには、恋の別れとしてしか受け取れなかったかもしれません。(まさに僕が僧でした。) しかし年齢を重ね、人生におけるさまざまな別れ――家族、友人、仕事、習慣――を経験するにつれ、この楽曲の持つ“別れの中の温度”が少しずつ変わって感じられるようになります。
それは単なるノスタルジーではなく、“今の自分の感情”を照らすひとつの鏡として、この曲が機能しはじめているということです。ふきのとうの楽曲にはそうした“変化する再生”の力を持つものがいくつかありますが、『プラットフォーム』はその好例といえるでしょう。
まとめ:映画のワンシーンのように残る歌
ふきのとうのデビューアルバムに収録されたこの一曲には、フォークデュオとしての彼らの“原型”とも呼べる要素が凝縮されています。繊細なメロディ、描写としての歌詞、音の間に込められた感情、そして過度な演出を拒む構成。
どこか懐かしく、でも今の自分にもまっすぐ届いてくる――
そんな一曲を、ぜひこのタイミングであらためて聴いてみてください。
駅のホームでふと立ち止まるように、静かに心の奥を見つめる時間が始まるはずです。




コメント