「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
【ふきのとう】編-第13位『初恋』
第13位は、初恋です。いい曲なんです。初々しいというか、懐かしいというか?!
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『初恋/ふきのとう』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
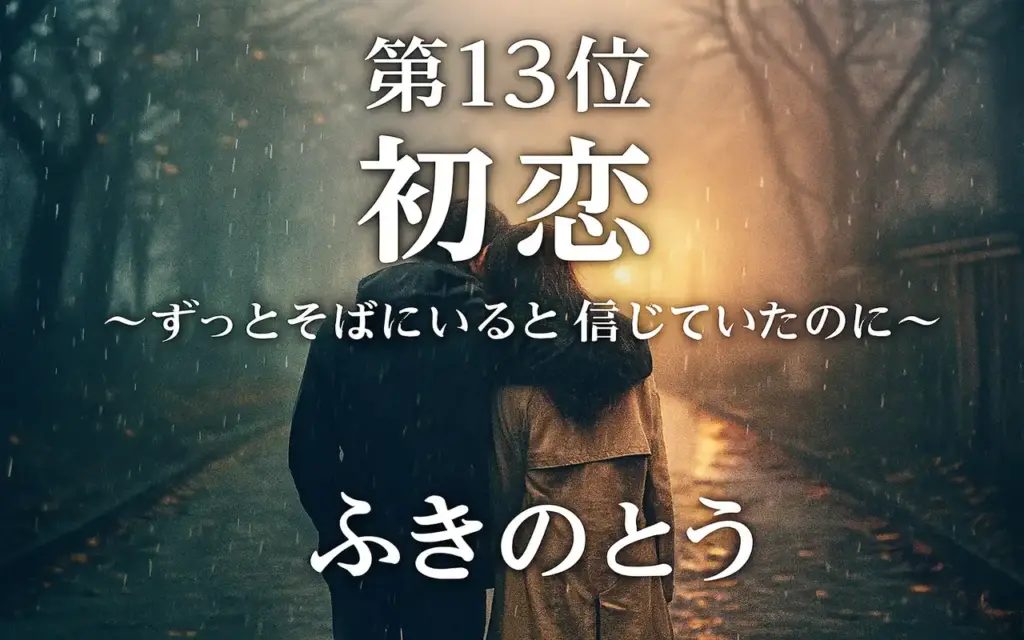
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより 動画タイトル:ふきのとう/初恋 作詩・作曲:細坪基佳/編曲:瀬尾一三 挿入アルバム:『思い出通り雨』(1978年7月21日発売) 公開年: 2014/10/31 ※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
僕の勝手なBest30:【ふきのとう】編 − 第13位『初恋』
雨にけぶる記憶とともに──非情に静かな幕切れの物語
1980年に発表されたアルバム『思い出通り雨』に収録された『初恋』は、細坪基佳が作詞・作曲を手がけた一曲です。
タイトルにある「初恋」という言葉からは、一般的に甘酸っぱく瑞々しい印象を思い浮かべがちです。しかしこの作品で描かれるのは、そうした感傷ではなく、すでに過去となった関係を静かに受け止める大人の視点です。語り口は淡々としていながら、その行間には割り切れない想いが確かに流れています。
冒頭の場面──六月の雨の朝に現実を知る
信じていた未来と、突きつけられる現実
物語は「6月の雨の朝」に幕を開けます。その日は、主人公のかつての恋人が別の男性と結婚する日。主人公はかつて、「その花嫁の隣に立つのは自分だ」と信じて疑わなかったことが語られます。
彼は、未来のどこかで彼女と結ばれると当然のように思い描いていたのでしょう。しかし現実には、自分は招かれた側にすぎず、彼女は別の誰かと新しい人生を始めようとしています。その静かな落差の中に、言葉にならない感情が滲み出てきます。

記憶に残る彼女の描写
身近な描写で浮かび上がる輪郭
回想のなかで描かれる彼女の姿は、抽象的な理想像ではなく、具体的で生身の人物として浮かび上がってきます。たとえば、好んで着ていた服や、困ったときの癖など、些細な描写の積み重ねによって、聴き手の想像力が自然と働く構成になっています。

「好きだった」だけでは済まされない思い
それらの細部から伝わってくるのは、「好きだった」では語り尽くせない、もっと複雑で深い想いです。日々の中で彼女を観察し、その一挙一動を心に刻んできたからこそ描ける視点が、ここにはあります。
別れの瞬間──わずかな動作がすべてを物語る
言葉のない別れの描写
主人公は、傘を持つ彼女の手にそっと手を伸ばします。その瞬間、特別な言葉は交わされず、ただ静かに時間が流れます。

雨が頬に触れた感覚が、涙なのか、雨粒なのか、区別がつかないまま、彼はその場を走り去ってしまいます。別れの場面にドラマチックな演出はなく、だからこそ、現実の重みと切なさが強く心に残るのです。
『初恋』における音楽的アプローチ
アレンジの全体像──音響の重心設計
瀬尾一三によるアレンジは、余計な装飾を排し、主旋律を際立たせる方向で構成されています。冒頭から中盤にかけてはピアノとギターのみで進行し、楽曲の中盤以降にストリングスが加わる構成です。音数を絞った冒頭部が、後半の重層的な響きを際立たせる仕掛けとなっており、ドラマ性を音響的に演出しています。
録音と音響設計──アルバム全体との対比
『思い出通り雨』の中でも、この曲は特に空間処理が丁寧に施されています。ボーカルは定位がやや中央寄りで、残響は控えめ。ギターやピアノは左右に配置され、空間を左右に広げつつ、中央の声が際立つバランスに整えられています。結果として、ひとつの小さな舞台を見つめるような立体的な印象を与えています。

細坪の歌唱と語感のニュアンス
細坪の歌い方は、技巧的な要素よりも、語尾の処理や語感の選び方に特徴があります。たとえば「さよなら」という言葉一つにも、語尾を伸ばさず、短く切ることで冷静さを保ちながらも、声のトーンで感情の機微を伝えるような工夫が凝らされています。
終幕の描写に漂う、静かな決断
「走り去る」という選択が意味すること
物語のクライマックスで、主人公は彼女の前から突然立ち去ります。言葉ではなく行動で別れを示すこの場面には、感情をあらわにする代わりに、自らの感情を呑み込む覚悟が見てとれます。

それは未練や後悔を引きずるのではなく、「これ以上、見ていると戻れなくなる」という危うさの境界線での選択です。感情を直接描くのではなく、視線の動きや歩みの速さでそれを暗示する手法は、ふきのとうの表現として極めて洗練されたものといえるでしょう。
タイトル「初恋」に込められた皮肉と深意
単なる回顧では終わらない構成
「初恋」と銘打たれたこの作品には、「原点への回帰」や「時間によって変質しない想い」といった、通俗的な初恋像への言及はほとんどありません。むしろ、この言葉は「過去に区切りをつけるための最終章」として機能しているように思えます。
失われたものを振り返るのではなく、「かつて、あの人を強く想った時間があった」と、自分の人生の一部として整理しようとする――その意思が、曲全体を通して感じられます。
大人の視点で語られる“回想ではない回想”
この作品には、「あの頃はよかった」と懐かしむような態度はありません。むしろ、感情の距離感を保ちながら、“今ここにある自分”が“過去の誰か”を語っているような、自己対話的な構成になっています。
『初恋』が持つ位置づけと、ふきのとうらしさ
感情の整理と表現のバランス感覚
『初恋』は、ふきのとうの作品群の中でもとりわけ「整っている」印象を与える楽曲です。アレンジや詞の構成、ボーカルの発声まですべてが一貫しており、どの要素も飛び出すことなく、ひとつの風景として調和しています。

それが結果的に、「誰かの心に入り込む」ような楽曲ではなく、「誰かの傍らに静かに置かれる」ような存在感を生み出しているのです。
派手さのない完成度こそが、“ふきのとうの本質”
『白い冬』や『風来坊』のような代表曲と比べると、決して耳を奪われるようなインパクトはありません。しかし、だからこそ、ふきのとうの本質――つまり、“過剰な演出を持たずに人の感情に寄り添う方法”を、最も的確に体現している楽曲といえるかもしれません。
それは例えるなら、声を張り上げて歌われるラブソングではなく、背中越しにそっと語られるような独白に近いもの。聴き手の心の準備が整ったときに、そっと染み込んでくるような余韻があります。
締めくくりに──「初恋の頃の夢を今も」
作中に一度だけ登場する「初恋の頃の夢を今も」という一節は、物語の“出口”に置かれた唯一の希望とも呼べる言葉です。これは「まだ彼女を想っている」という意味ではなく、「あの頃に信じていた何か」を、今もどこかで守り続けているという示唆でしょう。
それは決して、彼女との未来を夢見る未練ではなく、「かつて誰かを大切に想った経験」を、自分の中に根づかせて生きていこうとする姿勢です。この結びの一行が、静かに、しかし確かに、この曲をただの失恋ソングではなく、「人生の一断面としての恋」を描いた作品に昇華させています。




コメント