「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
誰もが心のどこかに持つ、「風来坊」の記憶
ふきのとう第17位は、1977年発表した『風来坊』です。アルバム『風来坊』の表題曲としてもリリースされた代表作のひとつです。同年にはシングルとしても発売され、彼らの名をさらに広く知らしめるきっかけとなりました。
この楽曲は、そのタイトルの通り「風来坊」という人物を描いていますが、単なる旅人や自由人のロマンにとどまらず、むしろ「戻る場所を失った者」の静かな姿を、抑えた言葉と音で描いています。
ふきのとうの作品には、共感と共鳴を誘う“名もなき男”が多く登場します。本作もまた、その延長線上にあるといえるでしょう。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
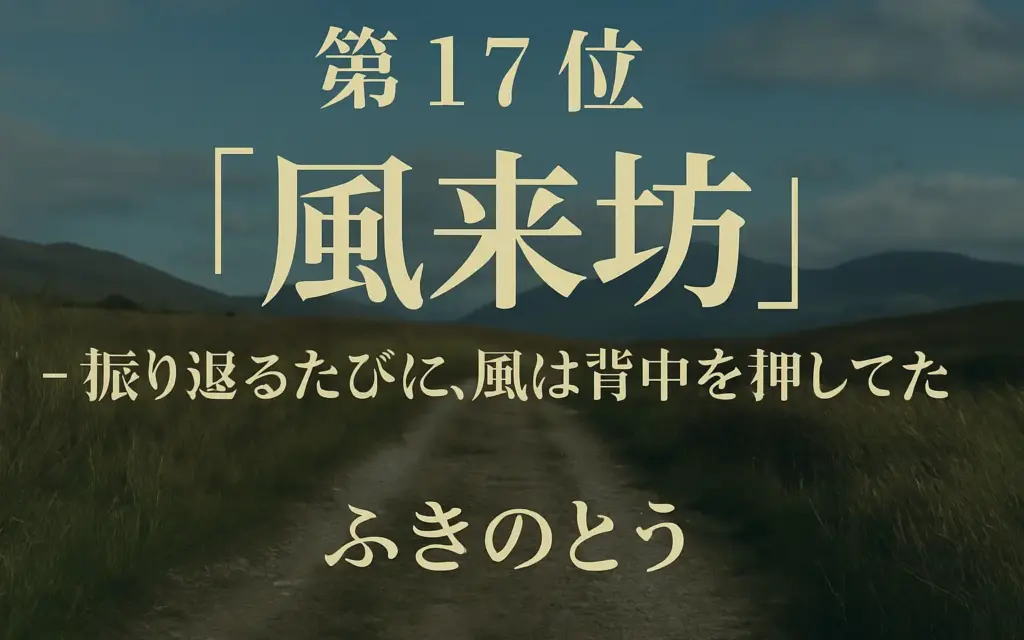
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル: ふきのとう/風来坊
作詞・作曲:山木康世/編曲:瀬尾一三
公開年: 2019/09/23
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
「風来坊」とは、どこへ行く人なのか
「旅」の歌ではなく、「帰れない」者の歌
「風来坊」とは、行き先も定まらず、ふらりと現れてはまたどこかへ去っていく人。語源をたどれば、「風のようにやって来る者」という意味に由来するとされます。

けれども、ふきのとうが描いたこの“風来坊”には、明るい放浪のイメージや楽天的な自由さはありません。むしろそこには、「居場所を失い、仕方なく歩き出す人間」の哀しみがにじんでいます。
この楽曲では、「どこかへ行く」というよりも、「もう戻れない」という感覚が圧倒的に濃く描かれています。
「お前と見上げたかった」「お前と暮らしたかった」
― どの願いも、既に叶うことのないものとして歌われています。
つまりこの“風来坊”とは、未来に向かって軽やかに進む人ではなく、「かつていた誰かのそばから、離れてしまった人」なのです。
見えない「君」の存在が生む余白
誰のための旅なのかを、あえて語らない構成
この曲の特徴は、主人公の心に深く残っている「君」の存在が、最後まで具体的には語られないことにあります。

“君”は実在したのか、それとも心の中だけにいる存在なのか、あるいはすでにこの世にいないのか……それは聴き手に委ねられています。
この“語らなさ”が、聴く側にそれぞれの人生経験を重ねて解釈することを可能にしています。この手法は、ふきのとうの作品全般に共通するものであり、たとえば『白い冬』や『春雷』でも同様の構造が見られます。
旅の風景に託された人生の残像
坂と道は、日常そのもの
この曲には、空、風、道、坂といった自然の風景が何度も登場します。どれもが単なる背景ではなく、「主人公が誰かと過ごしたかった情景」として機能しています。

- 空 → 夢や未来への象徴
- 風 → 逆風や社会的な障害
- 道 → 歩んできた人生そのもの
- 坂 → 越えがたい困難や年齢的な重み
これらは全て「戻れない場所」や「叶わなかった想い」の象徴として扱われ、旅路のなかに人間の記憶が静かに織り込まれています。比喩に頼りすぎず、過剰な装飾を避けているからこそ、ふきのとうの表現は押しつけがましくならず、リスナーの心に自然と沁み込んでいくのです。

1977年の日本と“男性像”の転換点
寡黙な男から、感情を抱える個人へ
1977年頃は人々の暮らしの中に「孤独」や「迷い」という感情が、はっきりと輪郭を持って立ち現れている時でした。
そんな中、『風来坊』に描かれる主人公は、それまでの“強く無口な男”のイメージとは明らかに異なります。彼は過去を背負いながらも、それを無理に隠そうとせず、自らの痛みを言葉にすることも辞さない存在です。
「お前と見上げたかった」
「お前と暮らしたかった」
といった繰り返しには、願いが叶わなかったことへの静かな悔いが滲んでいます。
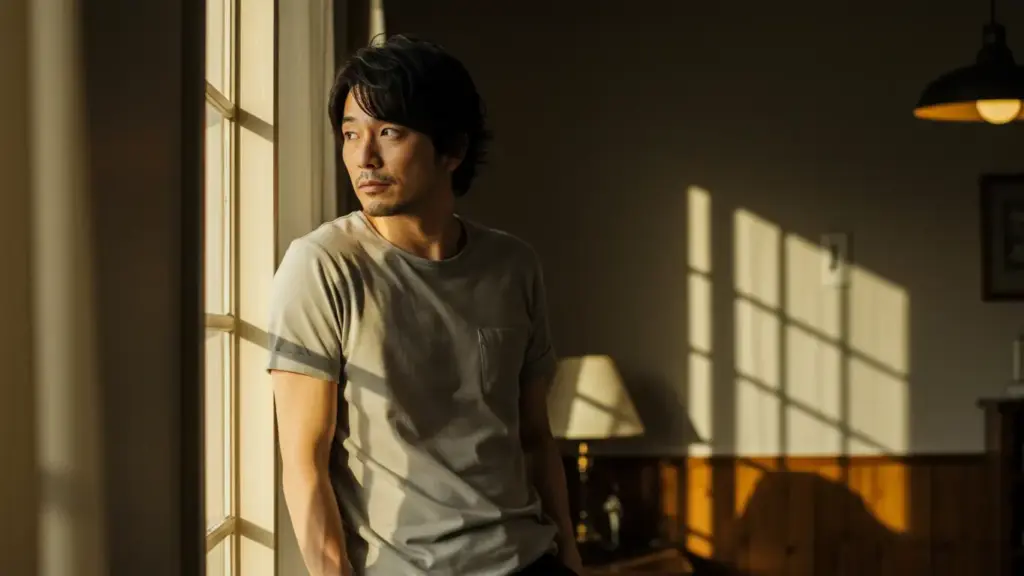
その一方で、「泣く」や「叫ぶ」といった感情の爆発は描かれず、抑えたトーンのまま語られていく点に、むしろ深い感情の存在を感じさせます。
「言わない」ことで伝わること
不在を描くことで、存在を際立たせる
『風来坊』は、ある意味で「語らないこと」が最も雄弁な表現手段となっている曲です。しかしその“語らなさ”こそが、この楽曲の核をなしているといえるでしょう。
願望形の繰り返し――「○○したかった」という言い回しが何度も登場しますが、それは「既に実現できなかったこと」としてリスナーに深く伝わります。
言葉にしないからこそ、感情が滲み出す。
語られない記憶が、かえって鮮明になる。
この逆説的な手法は、ふきのとうならではの“静かな表現美”として、今なお聴き手を惹きつけてやみません。これまで選曲してきたほとんどの曲に共通する手法と言えます。
「孤独」は弱さではなく、強さの証として
「風来坊、独りがよく似合う」という境地
この楽曲の終盤に登場する「風来坊、独りがよく似合う」という一節には、孤独を悲しみとして捉えるのではなく、それを“ひとつの境地”として受け入れた姿が描かれています。

これは決してネガティブな諦めではありません。むしろ、「誰にも頼らず、誰も責めず、ただ自分の足で歩いていく」という覚悟のようなものが感じられます。
「影が長く伸びる」「坂が続く」
― どちらも、人生の後半を生きる者の視点を象徴する言葉です。
ふきのとうの多くの楽曲には、人生の一場面を静かに切り取るようなリアリズムがありますが、本作はとりわけ「人生の折り返し地点を過ぎた人の声」が丁寧に刻まれています。
聴く人の年齢や経験によって、受け取り方が少しずつ変わっていくという点でも、非常に奥行きのある楽曲だといえるでしょう。
音に込められた“透明な芯”――ふきのとうのアレンジ美学
アコースティック編成が生む、飾らない真実味

ふきのとうの楽曲には、歌詞の内容と並んで、その音作りにも一貫した美学が貫かれています。
『風来坊』も例外ではありません。ギターとハーモニカを基調としたアコースティックな編成は、派手な装飾を加えることなく、歌の持つ世界観をそのまま伝えるための“最低限の器”として機能しています。
音数を抑えることで、言葉の輪郭がくっきりと浮かび上がる。
― それが、ふきのとうのサウンドアプローチです。
現代に響く、もうひとつの“ささやき”
「強さ」ではなく「静けさ」に価値がある時代へ
2020年代に生きる私たちは、SNSや映像コンテンツの波に日々さらされながら、「大きな声」や「目立つ言葉」に囲まれて暮らしています。

表現としての“静けさ”は、決して弱さではなく、時に最も強靭なメッセージを放つ手段になり得るのだと、ふきのとうは早くから体現していたのです。
誰とも競わず、誰にも媚びず、ひとりで歩いていく。
― それが『風来坊』の主人公であり、同時に私たちのもう一つの姿かもしれません。
「共感」ではなく、「自分の内側を見つめる歌」
理想でも憧れでもない、等身大の生き方
『風来坊』は、誰かに励ましを与えようとしたり、夢を肯定しようとしたりするタイプの歌ではありません。むしろ、
- 叶わない夢
- 届かなかった想い
- もう戻れない日々
そうした現実のなかで、それでも「歩いていく」という姿勢を、ただ静かに提示する曲です。
希望が語られないからこそ、“希望のかけら”を見つけたくなる。
そんな心の動きこそが、『風来坊』の本質なのだと思います。




コメント