「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
静けさが描く、やさしさの余白
1970年代の日本フォーク界において、深く静かに浸透していったデュオ「ふきのとう」。1974年のデビュー以来、細坪基佳と山木康世の奏でる繊細な歌声と詩的な表現は、世代を超えて長く愛されてきました。
そんな彼らの楽曲のなかでも、とりわけ静謐で思索的な魅力を放つのが『おやすみ(Good Night)』です。この曲は、目立つ演出や複雑な構成とは一線を画し、むしろ“音の静けさ”によって心をほぐす作用を持っていると感じています。

ということで、僕はこの一曲を第21位という位置に据えることいたしました。冒頭からまるで自分の影に自分が重なっていくように、細坪さんの歌が一瞬だけ自身の余韻に重なり、時間の流れがわずかに撓む感覚がある、その部分が何とも言えず良いのですよ。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
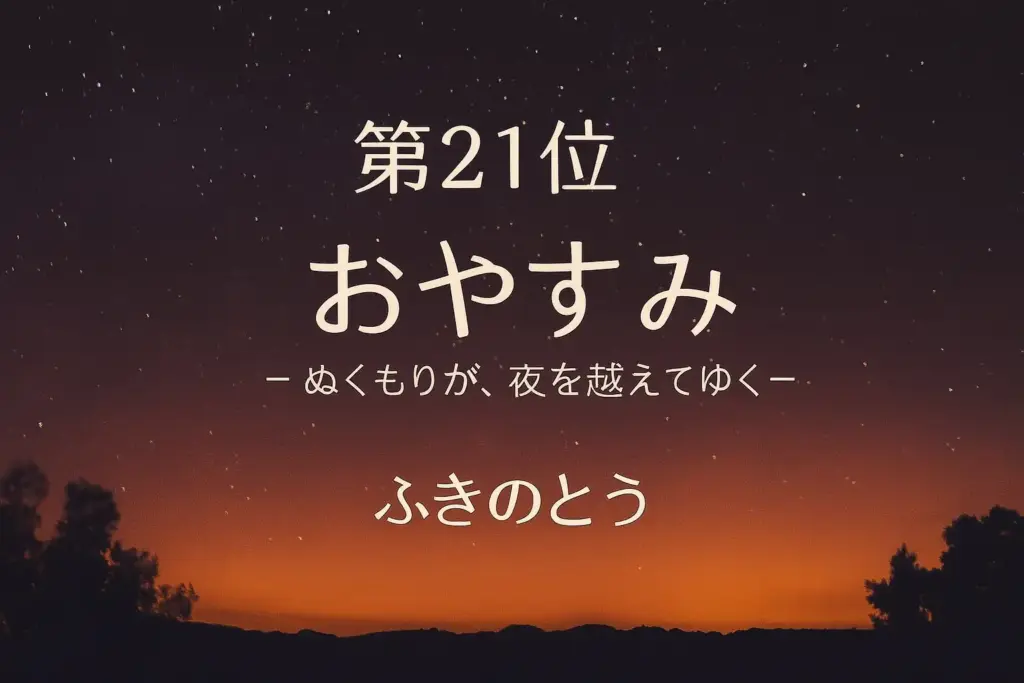
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
ふきのとう/おやすみ(Good Night)
作詩・作曲:細坪基佳/編曲:瀬尾一三
公開年: 2014/11/01
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。
※公式アカウントによる配信ではありません。※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
『おやすみ』の初出とその後の歩み
シングルB面からの静かな船出
『おやすみ』は、1976年9月21日にリリースされたシングル『雨ふり道玄坂』のB面曲として登場しました。
作詞・作曲は細坪基佳、アレンジは瀬尾一三。まだデビューから2年という初期の時期に書かれた作品ながら、その表情は落ち着きがあり、早くもふきのとうの成熟した音楽性の一端を示しています。
『水車』に収録されて、作品として定着
翌1977年4月21日、3rdアルバム『水車』に正式収録されました。
LPのB面ラストにあたる8曲目に配置されたこの曲は、アルバム全体の空気感に静かな陰影を与える一曲として機能しています。
『おやすみ』は、当初大きな注目を集めたわけではありませんが、“静かな共鳴”を重ねながら息長く愛される存在となっていきました。
長い年月を経た今でも、深夜のラジオでふと流れてきたとき、その静謐さに目を閉じたくなるような、そんな音楽です。

音を削ぎ落とすことで生まれた、感情の輪郭
研ぎ澄まされた音像の美
『おやすみ』の魅力は、まずその音づくりの姿勢に現れています。
アコースティックギターの素朴なアルペジオと、控えめに重ねられる歌声だけで完結するこの構成は、無理に感情を押し出すことなく、静かに染みわたるような音場を作り出しています。
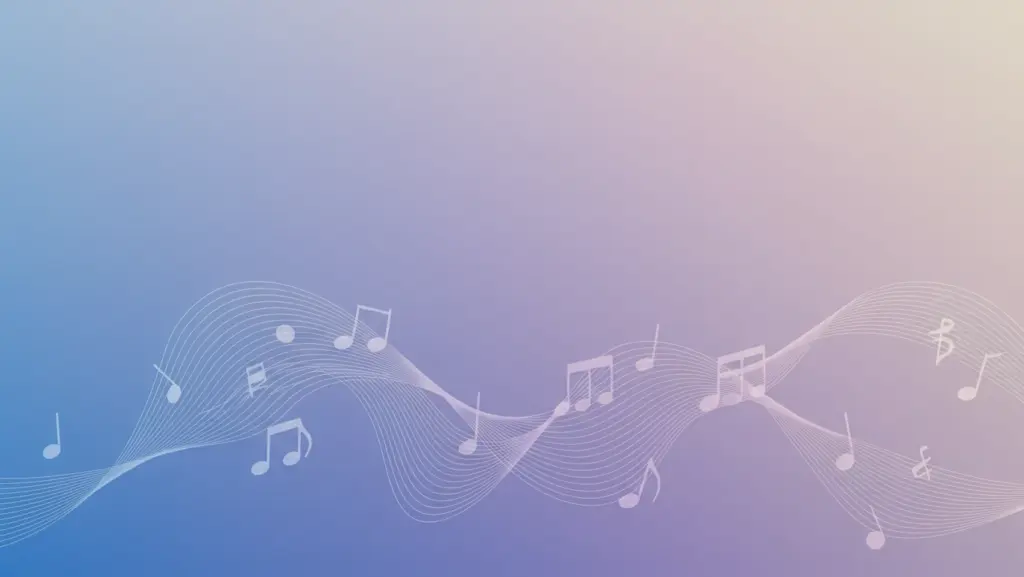
繰り返される「おやすみ」という言葉は、単なるあいさつではなく、胸の奥に潜む想いを、ことば少なに伝える手段として響いてきます。
その一言の重みが、聴く人それぞれの体験や記憶にリンクし、静かな感情の振動を起こすのです。
「おやすみ」が内包する多義性
日常語の奥に潜む、多層的なニュアンス
「おやすみ」という言葉は、ごく当たり前に交わされる日常語でありながら、感情の振れ幅が非常に広い表現です。
- 子どもに語りかけるときのやさしさ
- 恋人との別れ際の名残惜しさ
- 心の中だけでつぶやく、永遠の別れへの祈り
ふきのとうは、この言葉をあえて明確に定義することなく、あらゆる感情に開かれた入口として提示しています。

この解釈の自由さが、時代を超えて共感を呼び続ける理由のひとつです。
言い換えれば、「おやすみ」とは、“すべての感情を静かに見つめる”ための短い詩でもあるのです。
他のヒット曲とは異なる、その位置づけ
“照明”ではなく、“静寂”で描く感情の輪郭
ふきのとうの代表曲といえば、『白い冬』『風来坊』『春雷』といった楽曲が挙げられます。
これらは、感情や風景を鮮やかに描き出す“照明のような曲”だとすれば――

『おやすみ』は、それとは反対に、静かな空間のなかに明滅する気配を描く楽曲です。
感情の中心を直接照らすのではなく、光の届かない部分にこそ響くような位置づけ。
その“影の部分を尊重する姿勢”こそが、この作品の真骨頂と言えるでしょう。
リスナーの声に見る、『おやすみ』の浸透力
日々の中で静かに寄り添ってきた一曲
ネット上を見てみると、『おやすみ』に思い入れのある人の投稿が見つかります。
「父の介護をしていた夜、この曲が心の支えになった」
「新生活の不安で眠れなかったとき、聴いていて涙が出た」
「付き合っていた人との電話の終わり、毎晩“おやすみ”と言っていたのを思い出す」
どれも、特別なドラマがあるわけではないけれど、その人の“夜”の記憶にそっと残っているようなエピソードばかりです。

この曲が、多くの人にとって暮らしのなかの静かな時間や感情に、いつでもそばにいた存在だったことが伝わってきます。
決してメディアで目立つことなくとも、誰かの心に確かに刻まれてきた。
そのあり方こそが、『おやすみ』が今も生き続けている証しだと思います。
現代に響く“静かな音楽”の価値
騒がしい時代にこそ必要な、音の呼吸
現代の音楽シーンでは、情報量の多さやテンポの速さがもてはやされる傾向があります。
その一方で、言葉や音を極限まで削ぎ落とした曲が心に届く瞬間も、確実に存在しています。
『おやすみ』はまさにその代表的な一曲です。
深夜、スマートフォンの通知をすべて切って、照明を消した部屋で――
この曲をそっと流してみてください。
音楽が、言葉ではなく“静けさの気配”としてそばにいてくれる感覚が、きっと得られるはずです。
終わりに:読者へのひとこと
僕自身にとっても『おやすみ』は、寝る前に合う曲で、夜の終わりに聴いてきた曲です。
聴くたびに印象が変わるのは、自分の心の状態が変化しているからでしょう。
その変化すら受け止めてくれるような懐の深さが、この曲にはあります。
第21位という順位は、きらびやかな代表作には届かないかもしれません。
ですが、この曲にしか持ち得ない“静けさの本質”が、ふきのとうの音楽の深い魅力の一端を担っていると僕は思います。
まだ聴いたことがない方は、ぜひ夜の終わりにこの曲と向き合ってみてください。



コメント