「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
第6位『南風の頃』〜懐かしさの温度で描かれる、音の風景画〜
ふきのとう編、第6位は、「南風の頃」です。
あまったるいな・・・って誰か言いました??
それでも、好きなんだから仕方がない!!
やはり、それはそれは優しい歌なのです。
ふきのとうの楽曲には、日々の暮らしの中で見過ごされがちな感情や光景を、穏やかに響かせる魅力があります。その中でも『南風の頃』は、1976年リリースのアルバム『水車』に収録されている作品で、シングルではないにもかかわらず、今なお多くのリスナーに支持されている名曲のひとつです。
この曲は、旋律とアレンジを通じて、記憶の深層にある風景を音で呼び起こすような表現に満ちています。言葉よりも先に感触が届いてくる、そんな不思議な体験をもたらしてくれる楽曲です。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『ふきのとう/南風の頃』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
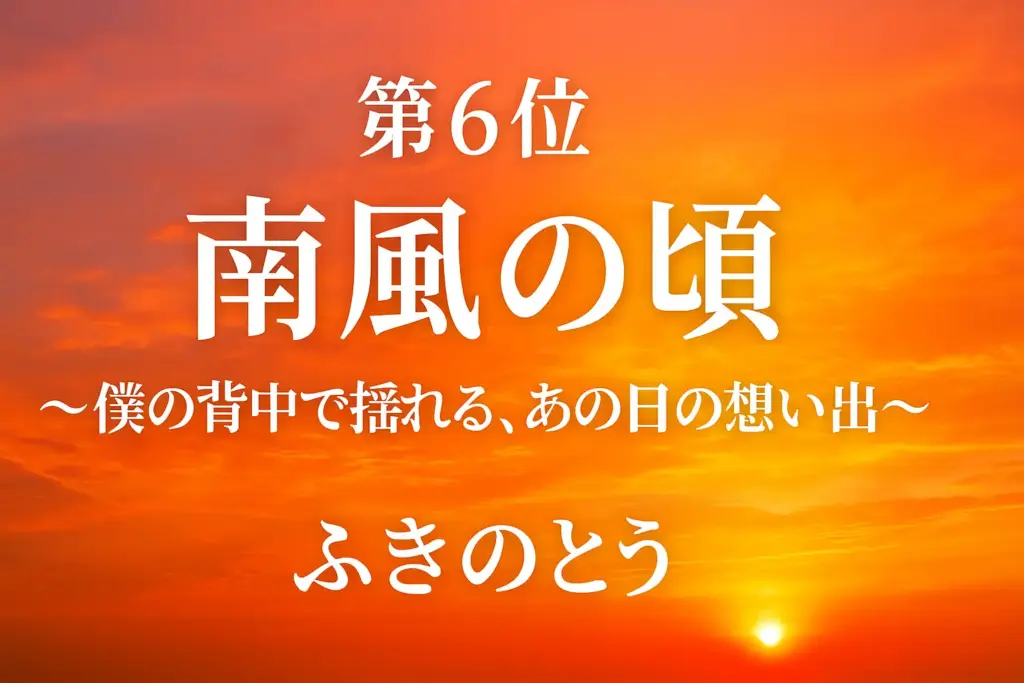
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:ふきのとう/南風の頃(1975年2月21日発売)
作詩:村上実/作曲:山木康世/編曲:瀬尾一三
動画公開年: 2015/06/23
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
記憶と結びついた風景の表現力
『南風の頃』は、ただ季節感を表現するだけの歌ではありません。登場するのは、本棚の写真帳や色褪せた日記帳、縁側で過ごすひとときといった、誰もが一度は目にしたことのある情景ばかりです。それらが淡く丁寧に配置されており、聴く人それぞれの記憶と自然に結びついていきます。

この曲が描き出すのは、感情を強調するような場面ではなく、時間の堆積の中で静かに刻まれてきた生活の断片です。だからこそ、押しつけがましさを感じさせず、聴く側の心にそっと入り込んできます。
アコースティックギターの交差が描く風のレイヤー
この曲の音世界を支えるのは、ふきのとうの原点ともいえるアコースティックギターのアンサンブルです。左右に分かれた2本のギターは、それぞれ明確な役割を持ち、静かに物語を形づくっています。
右チャンネル:安定を支えるストローク
右側から聴こえるギターは、一定のリズムでコードを刻むストローク奏法が中心です。おそらく山木康世による演奏と思われ、その温かな響きは、縁側の木の手触りや、初夏の柔らかい陽光を想起させます。
左チャンネル:表情を添えるアルペジオ
一方、左側には装飾的なフレーズが織り交ぜられています。アルペジオや短いオブリガートが、楽曲に抑揚や奥行きを与えており、情景に彩りを加える役目を果たしています。

この演奏は細坪基佳か、またはスタジオミュージシャンによるものかもしれません。どちらにしても、その控えめで繊細なタッチは、庭先の草の動きや光の揺れを音に変えたかのようです。
マンドリンが響かせる過去の揺らぎ
この曲を象徴するもう一つの要素が、イントロや間奏で登場するマンドリンです。細かなピッキングによるトレモロが、記憶のなかの揺らぎや、過去の断片を音として浮かび上がらせています。
間奏で展開されるマンドリンのソロは、決して派手ではないながらも、独特の存在感を放っています。技巧に走ることなく旋律の美しさを重視し、感情の中心をそっと指し示すような響きで包み込みます。

マンドリンの音色は、アメリカのルーツ音楽に由来するものですが、この楽曲では異国情緒を意図的に導入することで、現実と非現実の境界線をあいまいにしています。ふきのとうの音楽に内在するフォーク的感性との相性も良く、瀬尾一三による精緻なアレンジが見事に生きています。
二人の声が生む、時の重なりと距離感
ユニゾンが描く“二重の時間”
『南風の頃』の冒頭を聴くたびに、頭に浮かぶのは、午後の日差しが和室の畳をじんわりと照らしている光景です。ふと目をやった先にある古い本棚。そのすみに収まっていた写真帳を取り出して、何気なくページをめくる。そんな何でもない仕草の中に、この歌が描いている「心の動き」が潜んでいるように思います。

ふきのとうの二人は、この曲でほとんどのパートをユニゾンで歌っています。つまり同じ旋律を、声の異なる二人が揃って歌っている。その響きは、まるで昔の自分と今の自分が、小さな声で一緒に話しているような不思議な感覚を生み出します。
声が時間をなぞるように響く
たとえば、遠くに住む兄弟と久しぶりに会って、同じ写真を見ながら「これ、覚えてる?」と語り合うような──声に出す言葉は違っても、共有している時間が確かにそこにある、そんな雰囲気です。

サビに現れる、記憶の背中合わせ
背中から押し寄せる記憶
「僕の背中で想い出が ゆらゆら揺れてます」というフレーズ。
想い出とは、ふいに感じるものなのだと、歳を重ねてから気づきました。目の前にある景色や音楽に引き寄せられて、急に思い出す、かつての誰かの笑い声や、夏の日の空の色。『南風の頃』は、そういう記憶の浮上の仕方を音で表現しているのです。
日常のなかの“感情の瞬間”
台所で冷たい麦茶を注ぎながら、風に揺れるカーテンが頬に触れた瞬間に──その背後から、まるで小さな波のように昔の情景が押し寄せる。サビの一行は、そんな“体の背面で感じる記憶”を音楽にしたような描写なのだと、今では思えます。

古い町並みと、知らないのに懐かしい感覚
この曲を聴いていて不思議なのは、歌詞にある風景を自分が実際に体験していなくても、なぜか“懐かしい”と感じてしまうところです。たとえば「南風吹いたら流れ雲流れて」「本棚の写真帳」──これらの言葉は、誰の家にもあったような、あるいはテレビドラマのなかで見たような、曖昧でそれでいて鮮明な記憶を呼び起こします。
たとえば、小学校の帰り道に祖母の家へ寄り、縁側でスイカを食べながら眺めた空。大人になって記憶の奥にしまい込んでいたその風景が、この曲を聴くことでふと蘇るような気がするのです。

音楽が描いているのは、誰かの具体的な人生ではなく、“聞き手それぞれの心の中にある風景”です。それがこの曲の持つ強い共感力の秘密なのだと思います。
『水車』というアルバムの静かな核として
アルバム『水車』の中で『南風の頃』は、明らかに“速度を落とす”役割を持っています。アップテンポな曲や物語性の強い楽曲が並ぶ中、この曲はまるで足を止めて、少しのあいだ立ち止まらせるような位置づけにあります。
あなた自身の記憶と重なる瞬間
最初にこの曲を聴いたときは、静かすぎてあまり印象に残らなかったという人もいるかもしれません。ですが、ある日、ふと耳に入ったときに、なぜか涙が出そうになる──そんなタイプの曲です。

たとえば、晴れた日に押入れを片付けていたら、昔のカセットテープや日記が出てきて、それを再生したときのあの感じ。『南風の頃』には、そんな“予期せぬ再会”のような性質があります。
サビに宿る、声の重なりが映す心のゆらぎ
ハーモニーが描く、心の内側
『南風の頃』のサビは、Aメロ・Bメロで続いてきたユニゾンから一転して、ふきのとうの二人による繊細なハーモニーが展開されます。この変化は、単なる音楽的な彩りではなく、歌詞に込められた想いと深く結びついています。
二人の声が重なりながらも微妙に揺れていることで、“心の中の層”が浮き上がってくるように聴こえてきます。

主旋律と対旋律の関係がもたらす効果
細坪基佳の澄んだ高音と、山木康世の落ち着いたミドルボイスが絡み合うサビでは、それぞれの声が役割を持ちながらも、どちらが主か従かという関係性に縛られていません。
あくまでも“並列”でありながら、“温度差”を生んでいる。この構造こそが、聴き手の胸に「過去と今」が交差する感覚をもたらしているのです。
音楽が記憶をつなぐ“鍵”になるとき
日常に隠れた記憶の引き金
『南風の頃』を何度も聴いていると、ただの歌ではなく、ある種の“記憶の鍵”のような存在に思えてきます。たとえば、日曜の午後に流れていたラジオの音や、こたつの中でみかんを食べながら見たテレビ番組。あるいは、夕方の台所に漂っていた煮物の匂いと、母の口ずさむ鼻歌。
こうした何気ない記憶が、『南風の頃』の音楽によって静かに呼び戻される瞬間があります。
静かな曲が持つ、長く響く力
“派手ではない”が、時間とともに残っていく
第一印象で強く残る曲と、じわじわと染み込んでくる曲があります。『南風の頃』は明らかに後者です。最初に聴いたときは「なんとなく静かな曲」という印象で終わるかもしれませんが、何年か経ってから再び耳にしたとき、まるで別の意味を持って聴こえてくる。
そういう曲は、人生の中で少しずつ役割を変えながら、静かに傍にいます。記憶を美化するわけでもなく、現実から逃避するでもなく、「時間の流れそのもの」と一緒に生きていくような感覚があります。

まとめ:あなたの「南風の頃」はどこにありますか?
聴き手の記憶が完成させる歌
この曲の面白いところは、押しつけがましくない言葉、控えめな音の配置、そしてハーモニーのわずかなゆれ。これらが、個々人の心の中に“自分だけの南風の頃”を作り出していく。
この曲を聴きながら、ふと昔の自分に思いをはせる。それは特別な思い出ではなくてもいいのです。たとえば、祖父母の家で昼寝をしたときの静けさや、洗濯物が風に揺れていた情景。そんな“忘れていたけど確かに存在した時間”を思い出すために、この曲は存在しているのかもしれません。



コメント