第6位は、【愛という名のもとに】です。
いよいよ残り6曲となってきました、正直に言うと浜省の楽曲の中でも、特にバラード系が大好きです。
第6位もその代表格の1曲です。秋も深まりつつある今日この頃。ぜひ静かに、思いにふけるもよし、聞き流すもよし、都のような状況でも染み入る一曲です。
超約
別れを受け入れながらも、互いの思いを断ち切れない男女の心情を描いた歌。
過ぎ去った日々の温もりと、もう戻れない現実との狭間で揺れる切なさが滲む。
眠れぬ夜に再びつながろうとするその衝動は、愛の名を失った後の痛みそのもの。
静かな言葉の裏に、時の経過と未練が深く刻まれています。
まずは公式動画をご覧ください。
✅ 公式動画クレジット
浜田省吾 Official YouTube Channel
🎵『愛という名のもとに』(Album 愛の世代の前に/1981年)
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
© 1981 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.
💬 2行解説
1981年のアルバム『愛の世代の前に』収録曲で、浜田省吾が30代を迎える直前に描いた初期の名作の一つです。「正義」「愛」「希望」といった普遍的テーマを静かに問いかける歌詞が印象的で、後年の作品群へとつながる精神的な原点となっています。
作品の概要と位置づけ
アルバム『愛の世代の前に』の中での存在感
『愛という名のもとに』は、1981年9月に発表されたアルバム『愛の世代の前に』に収録された楽曲です。僕にとって特に印象深いアルバムです。
このアルバムは、浜田省吾がアメリカン・ロックからシンガーソングライター的な語り口へと深化していく過程を示した重要作であり、彼のバラード群の中でも“静かな力”を持つ作品として評価されています。
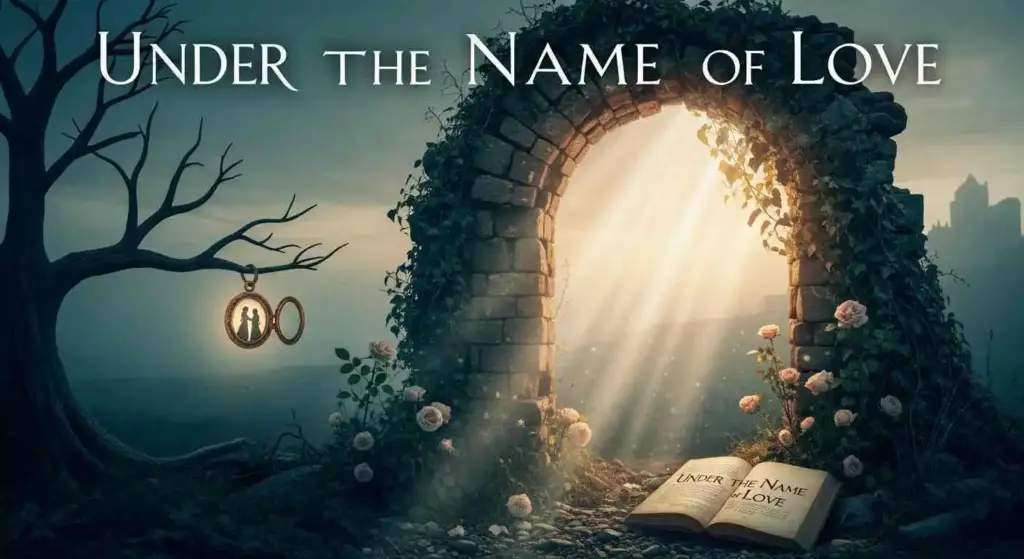
同作には「風を感じて」や「我が心のマリア」など、ライブで長く愛される曲が並びますが、『愛という名のもとに』はその中で最も“夜の私語”に近い距離感をもつ曲です。
派手なサビや高揚はなく、むしろ“沈黙と電話の音”が支配するような静かな空気。その控えめな演出こそが、この曲の深みを支えています。
時代背景とリスナーの共感
1980年代初頭、日本の音楽シーンはシティポップやニューミュージックが成熟し、都会的で洗練されたサウンドが好まれた時代でした。
その中で浜田省吾の描く“愛”は、洒落た恋愛よりも、もっと現実に根ざした人間的な揺れを描いていました。
『愛という名のもとに』に登場する二人は、理想や夢に破れたわけではなく、ただ時間の流れとともに少しずつすれ違った。
この等身大の別れ方が、多くのリスナーに「自分の物語」として響いたのです。
歌詞に描かれる“静かな別れ”
ドアの前のスーツケースが語るもの
冒頭の数行――
ごらん街の灯りが消えて行くよ
もうすぐ始発が走り出す
このたった二行で、場面のすべてが決まります。
夜明け前の静けさ、始発が出る時間、別れの直前。
ここには、若者らしい衝動ではなく、“終わりを受け入れる大人の呼吸”があります。

続く「君の肩を抱くことも出来ないまま」という一節では、未練をあえて飲み込むような抑制が見えます。
ドアの前に並んだ二つのスーツケース、机の上の鍵。
何気ない生活の断片が、逆にふたりの長い時間を感じさせます。
この「何も起こらない情景」を描く力こそ、浜田省吾の真骨頂です。
電話がつなぐ“やり直しの余地”
サビにあたる部分で繰り返される「眠れぬ夜は電話しておくれ」というフレーズ。
この言葉が持つ力は、現代の“スマホ社会”では少し想像しにくいものがあります。
1981年当時、深夜に電話をかけるのは簡単なことではなく、ためらいや勇気が必要でした。
だからこそ、このフレーズには「まだ君を思っている」という確かな意思がこめられています。
真夜中のドライブ・イン 昔のように
急いで 迎えに行くよ
別れを決めたはずなのに、迎えに行くと言い切る。
この一行で、物語の温度が一気に上がります。
それは“未練”ではなく、“約束を捨てきれない優しさ”です。
恋人としての形式は失っても、人としての繋がりはまだ切れていない。
浜田省吾が描く愛は、常にその中間にあります。

ベッドの中の回想と、欠けた夢の色
互いの不完全さを受け入れる描写
中盤の回想では、ベッドの中で過ごした夜の描写が登場します。
時計の音だけ聞いてたね
互いに欠けてる夢の色を
別の何かに置きかえて

この部分は、浜田省吾らしい“説明しすぎない語り”です。
愛し合っていたはずの二人が、すでに何かを埋めようとしていた。
言葉にしない距離感を、音ではなく沈黙で伝える。
この描写があるからこそ、ラストに向かう「もう一度探そう」という言葉が生きてきます。
「愛という名のもとに」という皮肉と希望
タイトルの「愛という名のもとに」は、どこか逆説的です。
愛という言葉を掲げたことで、かえって素直に笑えなくなった――
歌の終盤で「無邪気な君の笑顔を」「無邪気な僕の笑顔も」と語るのは、その象徴です。
愛を“守るもの”ではなく、“失わせるもの”として描く。
それは恋愛を突き放して見る大人の目線ですが、浜田省吾はそこに必ず“再生”を置きます。
「二人もう一度探そう」と繰り返すことで、失われたものをもう一度取り戻す勇気を静かに促しているのです。

1981年の「現実感」とリスナーの共鳴
失恋を“特別視しない”リアリズム
1981年といえば、世の中はバブル前夜の活気を帯び始めた時期でした。
都会では恋愛も仕事もスピードを増し、ドラマティックな恋が好まれる傾向にありました。
しかし『愛という名のもとに』は、そうした流行の恋愛観とは一線を画しています。
この歌は、泣き叫ぶような失恋ではなく、“淡々と片づけられた別れ”を描いている。
つまり、誰の人生にもある「静かな終わり」を正面から見つめているのです。

ここに浜田省吾の誠実さがあります。
彼は愛を「永遠のロマン」として飾るのではなく、“日常の選択”として捉えました。
別れても電話できる、迎えに行ける――その現実的な距離感が、80年代初期のリスナーにとってはむしろ救いだったのです。
どこかで似た夜を経験した人たちが、静かにこの曲に自分を重ねていました。
『SAND CASTLE』以降のバラードとの比較
「語り」から「描写」への進化
1980年代後半以降、浜田省吾のバラードはより叙情的で構成的な物語性を帯びていきます。
たとえば『悲しみは雪のように』では、季節や時間が象徴的に扱われ、まるで短編映画のような世界が作られました。
一方、『愛という名のもとに』はそれ以前の作品でありながら、すでに“感情を描写で語る”という後の作風の原点を示しています。
この曲では、登場人物の台詞や心理説明が一切出てきません。
代わりに、スーツケース、電話、時計の音など、モノだけで物語が進行します。
まるで映像のワンカットを並べるような構成で、聞く人それぞれが空白を埋めながら物語を完成させる。
この“余地のある語り口”が、後年の浜田省吾作品に受け継がれていきます。

音楽的には控えめな設計
『愛という名のもとに』は、アレンジ面ではきわめてミニマルです。
ピアノとストリングスが穏やかに流れ、ギターがやさしく包み込む。
リズムは淡々と、ボーカルを邪魔せず支える。
これは「感情を語るのは声だけでいい」という哲学を感じさせます。
浜田省吾の声は、当時まだ粗削りな部分を残していましたが、それがかえって真実味を与えています。
技巧ではなく、言葉の温度そのもので聴かせる――それがこの時期の浜田省吾の強みです。
なぜ今も聴かれ続けるのか
愛という言葉の“重み”と“脆さ”
この曲が時代を超えて愛される理由は、「愛」という言葉に対する距離の取り方にあります。
多くのラブソングは、愛を絶対的な価値として描きます。
しかし浜田省吾は、愛を“失われることもあるもの”として扱う。
しかもその失い方は、裏切りや悲劇ではなく、日常の延長線上にある。
その現実感が、聴くたびに違う響きを生みます。

歳を重ねて聴くほど、「二人もう一度探そう」という言葉の意味が変わっていくのも魅力です。
若い頃は“元に戻りたい”という願いに聞こえ、
中年になれば“もう一度笑える関係を探したい”という穏やかな願いに聞こえる。
人生の段階によって聴き方が変わる――それこそが、浜田省吾の歌が長く残る理由でしょう。
現代のリスナーへのメッセージ
SNS時代の“つながり疲れ”に効く歌
現代では、電話よりもLINEやSNSで簡単につながる時代になりました。
しかし、気軽に連絡できる分、かえって心の距離を保つことが難しくなっています。
『愛という名のもとに』の「眠れぬ夜は電話しておくれ」という一節は、
“本当に誰かを想うときには、声を届けることが大切だ”という普遍のメッセージを思い出させてくれます。
また、愛を名前で呼び、形にしようとすることの危うさも、この歌はそっと指摘しています。
「愛という名のもとに なくした無邪気な笑顔」――
この言葉に、現代人が感じる「疲れた愛」のリアリティが重なります。
愛とは支配ではなく、もう一度“笑える余白”を見つけること。
浜田省吾は、その本質を40年以上前にすでに描いていたのです。

まとめ
『愛という名のもとに』は、別れをテーマにしながら、実は“やり直す勇気”の歌です。
夜の静けさや電話のベル、部屋の鍵といった生活の音が、失恋の痛みをやさしく包み込みます。
その繊細な構成と誠実な言葉の選び方が、今もファンの心に残り続けている理由でしょう。
浜田省吾が描く“愛”は、決して劇的ではなく、日常の片隅で灯る小さな希望です。
それは、別れを経験したすべての人に向けた――
「まだ終わっていない」という静かな励ましでもあります。

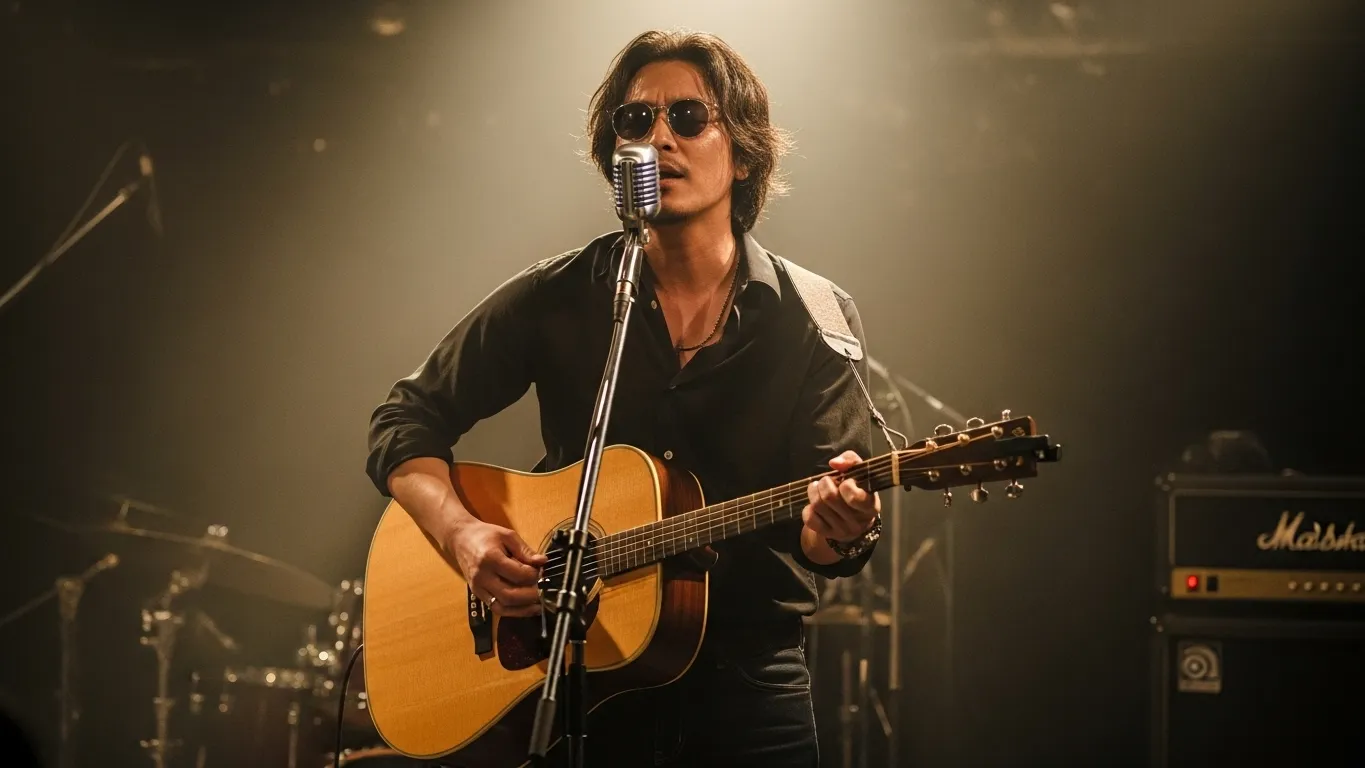


コメント