カンサスについて詳しくは➡Wikipedia
今日6月15日は、スティーヴ・ウォルシュの誕生日―異能の表現者
6月15日は、アメリカン・プログレッシブ・ロックの代表格、カンサス(Kansas)の黄金期を支えたフロントマン、スティーヴ・ウォルシュの誕生日(1951年)です。彼は彼はアメリカ・ミズーリ州セントルイスで生まれで、カンサスでは圧倒的なハイトーン・ボーカルとステージ上での情熱的なパフォーマンスで知られ、キーボーディストとしても高く評価されてきました。
彼の名を聞いて多くの人がまず思い浮かべるのは、『Carry On Wayward Son(伝承)』での強烈なシャウトかもしれません。しかし、今回紹介するのは、その対極に位置するような静謐な楽曲『Dust in the Wind』です。そこには、ウォルシュのもう一つの顔とも言える「抑制の美学」が鮮やかに刻まれています。

今日の紹介曲:
まずはYoutube動画の(公式動画)からどうぞ!!
🎥 公式動画:Kansas - Dust in the Wind (Official Video)
📝 公開元:KANSAS 公式YouTubeチャンネル
📅 公開日:2009年11月7日
👁🗨 視聴回数:3億回以上(302,388,713回以上/2025年6月時点)
🎵 解説(2行)
1977年発表のバラードで、カリー・リブグレンが作詞・作曲したKansas最大のヒット曲。静かなアコースティックサウンドに乗せて「人間のはかなさ」を詩的に歌い上げている名作です。
僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫
| 僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫ | |||||||||
| 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 曲のリリース | 1977 | ||||||||
| 聴いた時期 | ● | ||||||||
僕がこの曲を初めて聴いたのは大学に入学した年です。
前年の1976年リリースのカンサス4枚目のアルバム『永遠の序曲』で、伝承(Carry On Wayward Son)(過去記事で紹介してます)を聴いていたので、バンドのイメージはありました。
しかし、実際は、今日紹介する「すべては風の中に(Dust in the Wind)」がとても気に入ったので、それまでの他の曲は遡って聴いたというのが事実です。
当時はプログレサウンドが流行しており、カンサスもその仲間です。しかし一番好き楽曲はこの「すべては風の中に(Dust in the Wind)」なんです。とにかく色んなシチュエーションで耳にしたくなる一曲です。是非ご堪能ください。
カンサス史上もっとも異質な一曲?
『Dust in the Wind』は、1977年に発表されたアルバム『Point of Know Return』に収録されています。この曲がカンサスの中でいかに特異な存在かは、彼らの通常の音楽性を知るとより明確になります。

彼らは通常、シンフォニックなサウンドと複雑な構成、哲学的な歌詞を武器とするアメリカン・プログレッシブ・ロックの雄でした。シンセサイザー、ヴァイオリン、ギターを巧みに重ね合わせ、壮大な楽曲世界を描き出すのが特徴です。
しかしこの曲は、アコースティックギター一本のアルペジオから始まり、余計な装飾を一切排除した極めてシンプルな構成。ヴァイオリンもシンセも姿を消し、ボーカルも抑え気味。これは、音楽的な”突然変異”とも言える大胆な挑戦だったのです。

ギターの指慣らしが生んだ名曲
この楽曲には有名な誕生秘話があります。ギタリストのケリー・リヴグレンが、指慣らしのために弾いていたギターフレーズを、たまたま妻が耳にして「それ、素敵ね。歌詞をつけてみたら?」と助言したことがきっかけだったのです。
当初、バンドの楽曲として発表するつもりはなかったと言います。カンサスのイメージとはあまりにかけ離れていたからです。しかし、実際に制作され、収録されると、あっという間にバンド最大のヒット曲となりました。
このエピソードは、偶然と日常の中に潜む創造の種、そして装飾を排した純粋な旋律の力を雄弁に物語っています。

スティーヴ・ウォルシュの抑制の芸術
『Dust in the Wind』におけるウォルシュの歌唱は、彼の他の楽曲とはまったく異なるアプローチが取られています。彼はあえて声を張らず、感情を抑えながらも、内面の深い共鳴を生み出しています。
"I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone"
(目を閉じれば、一瞬にしてその時は過ぎてしまう)
この歌い出しだけで、リスナーは人生の儚さや、時間の不可逆性を直感的に感じ取ることができます。声高に叫ぶのではなく、ささやくように語ることで、より一層の深みと説得力を与えているのです。

無常を歌う哲学的なバラード
この曲はその旋律の美しさだけでなく、歌詞に込められた哲学的な深みでも評価されています。
仏教と旧約聖書に通じる世界観
“All we are is dust in the wind”(私たちは風の中の塵にすぎない)
この象徴的な一節は、アメリカ先住民の詩集に由来するとも言われていますが、その根底にある思想は、仏教の「諸行無常」や旧約聖書の「塵から生まれ、塵に還る」という教えとも共鳴します。
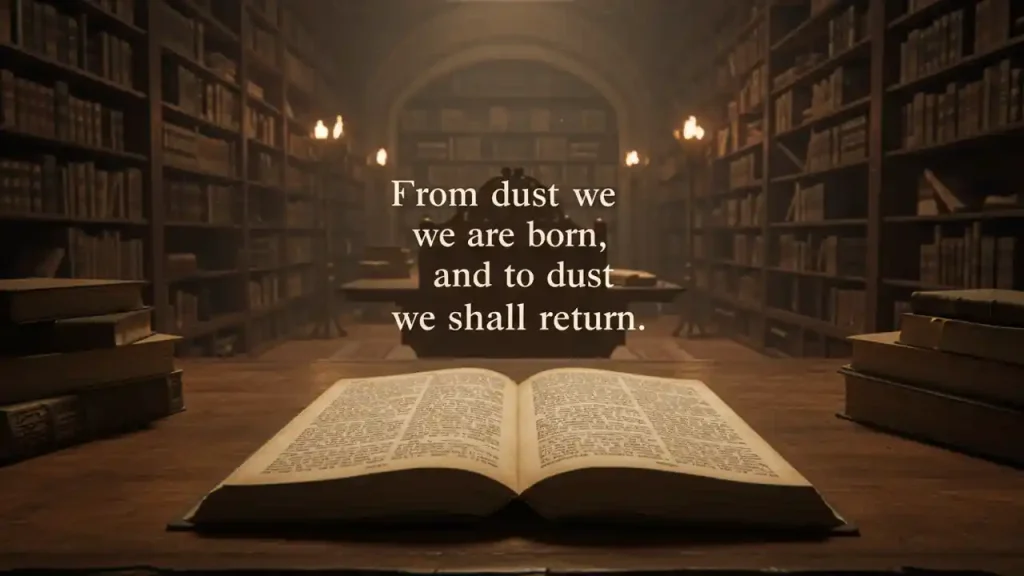
カンサスのようなアメリカのロックバンドが、こうした内省的なテーマに真正面から取り組み、リスナーの魂に問いかけたことは、当時としても非常に珍しい試みでした。
成功の絶頂で歌われた儚さ
この曲が収録された『Point of Know Return』がリリースされた1977年、カンサスは絶頂期にありました。アリーナ・ロックの代表格として、全米のスタジアムを満員にし、アルバムも数百万枚を売り上げていた時期です。
その絶頂で、「永遠なものはない」「すべては塵にすぎない」と歌った意味は重く、哲学的です。富や名声の虚しさに気づきながら、それでも歌い続けるという姿勢が、多くのリスナーの共感を得た理由のひとつでもあるでしょう。

1977年という時代背景
1977年は音楽の転換期でもありました。アメリカではボストン、ジャーニー、スティクスなどのアリーナロックが主流を極めていた一方で、パンクロックが勃興し、旧来のロックを激しく批判し始めていた時期です。
その中で『Dust in the Wind』は、どちらにも属さない独立した存在としてリスナーの心に残りました。
一方、日本ではピンク・レディーが大ヒットを飛ばし、ニューミュージックが台頭するなど、歌謡曲と個人の心情を描く音楽が共存しはじめた頃です。『Dust in the Wind』が持つ繊細な内省性は、当時の日本の空気にも通じるものがあったと言えるでしょう。
スティーヴ・ウォルシュのその後
ウォルシュは1981年に一度カンサスを離れ、1985年に再加入。その後もバンドとともに活動を続けましたが、加齢とともに声が衰え、2014年に正式に引退しました。
『Dust in the Wind』のボーカルに見られる繊細な表現は、彼のキャリア全体においても特異な瞬間であり、同時に最も普遍的なメッセージを伝えたものとして評価されています。
映像作品での使用と影響
この曲は多くの映画やテレビドラマでも使用されてきました。たとえば映画『オールド・スクール』(2003年)では、仲間の死を悼む場面で印象的に流れ、観客の涙を誘いました。

そのほかにも、人生の転機や別れの場面などで使用されることが多く、シンプルでありながら感情を揺さぶる楽曲として、多くの人の記憶に残っています。
現代における再評価
この楽曲の持つ「Dust in the Wind=直訳:すべては風の中の塵」というメッセージは、情報があふれ、変化が早く、先が見えにくい現代社会において、むしろ一層強いリアリティを帯びています。
AIやSNS、格差や気候変動といった不安定な世界で生きる私たちにとって、永遠や確実なものがないという視点は、悲観ではなく一種の解放でもあります。
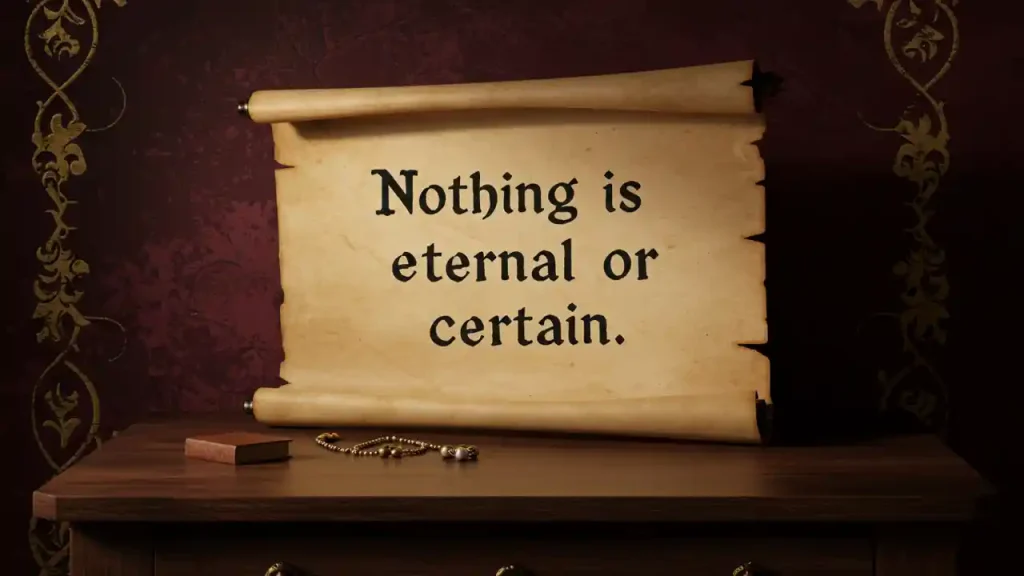
人生の節目に選ばれる理由
『Dust in the Wind』は、葬儀、卒業式、退職、旅立ちなど、人生の転機に寄り添う音楽として、多くの人に選ばれています。
それは、メッセージが強すぎず、聴き手の感情を静かに受け止めてくれるからです。慰めるでもなく、教えるでもない。ただ”共にある”という感覚が、この楽曲には込められています。
結びに
力強く歌うことだけが、表現ではありません。声を抑え、言葉を慎重に紡ぎ、余白に思いを託す――それが『Dust in the Wind』が私たちに教えてくれる最大の美学です。
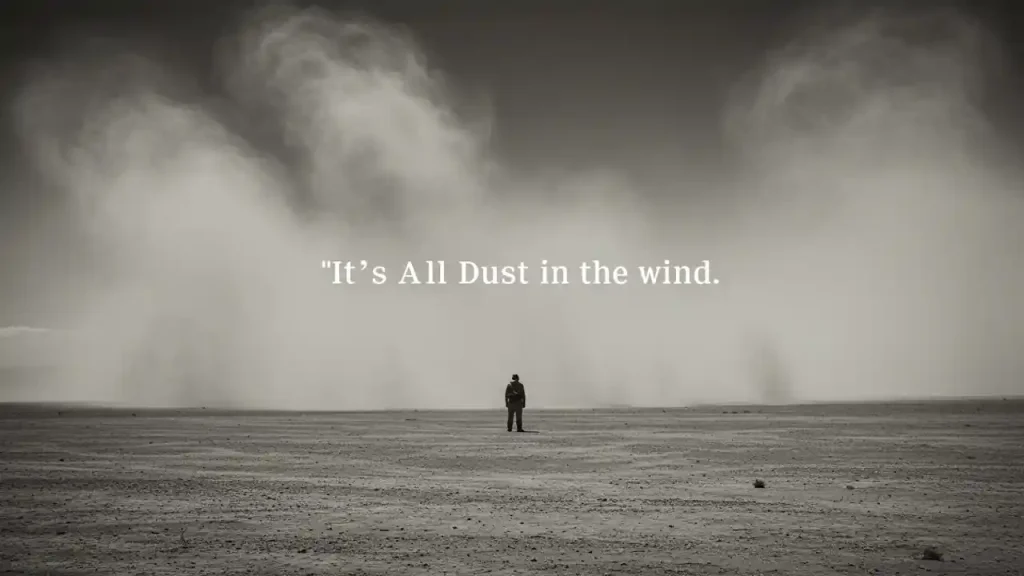



コメント