「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
静けさのなかで心を照らす一曲――『微笑み』という名のささやき
1970年代から80年代にかけて活動したフォークデュオ「ふきのとう」は、決して派手な存在ではありませんでしたが、独自の音楽的美学を貫き、今なお根強い支持を集めています。彼らの楽曲は、自然や日常の風景を通して、聴く者の内面に静かに語りかけるものが多く、聴くほどに味わいが深まります。
その中で『微笑み』は、穏やかな情緒をたたえた名曲として知られています。感情を激しくぶつけるのではなく、まるで心の奥にやさしく触れるような語り口――それが、この曲が持つ一番の魅力です今回はこの『微笑み』を、「僕の勝手なBest30」シリーズ第20位として取り上げ、その音楽的な魅力、歌詞の世界観、そして文化的な意義までをじっくり掘り下げてみたいと思います。

まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『微笑み/ふきのとう』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
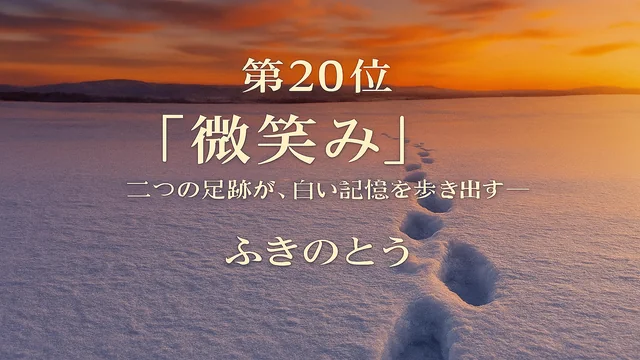
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
タイトル:「微笑み」―ふきのとう
作詩・作曲:細坪基佳/ストリングス・アレンジ:瀬尾一三
D.S.ダルセーニョ』 (1981年5月21日発売)
公開年:2021/09/13
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。
※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
メロディーの造形:言葉以上に語る旋律
シンプルであることの美しさ
『微笑み』の旋律は、装飾を一切排除しながらも、聴く人の胸にじんわりと染み込む力を持っています。穏やかなコード進行と繰り返されるギターのアルペジオが、まるで風のように自然に広がっていきます。

このようなシンプルな構成は、聴き手の想像力に委ねる余白を多く残し、歌詞の世界観への没入を深めてくれます。旋律自体が言葉となり、感情を語る役割を果たしているのです。これはまさに、ふきのとうが一貫して追求してきた“音楽で心に語りかける姿勢”そのものです。
レコーディングに込められた工夫
1980年前後、日本の音楽スタジオはようやくマルチトラック録音が本格化し始めた時期でしたが、機材の性能や編集の自由度にはまだ限界がありました。そんな中、『微笑み』はノイズを抑えながらも、アコースティックギターやヴォーカルの温もりをしっかりと残したナチュラルな音質に仕上がっています。
歌詞の描く世界観:情景と感情の交差点
雪と足跡に託された心の比喩
『微笑み』というタイトルに反して、この曲が描くのは明るさだけではありません。むしろ、静かな雪景色と孤独の中に生まれる人とのつながりが、詩的な言葉で深く描かれています。
印象的なのは「雪」と「足跡」のモチーフです。かつて一人で歩いていたはずの雪道に、ふと気づくと二つの足跡が並んでいる――この描写は、孤独の中で他者の存在に気づいた瞬間を象徴しています。

こうした表現は、都市生活の中では生まれにくい感性であり、北海道という自然豊かな土地で育まれたふきのとうならではの視点だといえるでしょう。
“微笑み”が象徴するものとは
曲の中で“微笑み”は頻繁に繰り返されるわけではありませんが、その象徴性は圧倒的です。特に「あどけない微笑み」が心を癒す様子は、恋人や家族という具体的な存在を超え、人生そのものに差し込む小さな光のように描かれています。
この“微笑み”は、日々の中で見落としがちな優しさであり、私たちが人間として何とか歩んでいくために必要な最低限の希望ともいえる存在です。
『微笑み』が生まれた背景と制作の舞台裏
『微笑み』は、1981年5月21日に発売された8作目のオリジナルアルバム『D.S.ダルセーニョ』に収録されています。作詞・作曲は細坪基佳、ストリングスアレンジは瀬尾一三が担当。全体として穏やかで内省的な世界観をたたえた楽曲で、ふきのとうの中でも静かに聴き手の心に残る作品として支持を集めています。

抑制されたヴォーカルや繊細なアレンジが、この曲の持つ“語りかけるような魅力”を引き立てており、ふきのとうが表現した“心情フォーク”の到達点のひとつとして位置づけられる楽曲です。
現代の音楽シーンにおける再評価
若い世代からの支持とカバー文化
SpotifyやApple Musicなどのサブスクの登場により、70〜80年代の音楽が若い世代にも簡単にアクセス可能になった現代。ふきのとうの作品も、再び脚光を浴びています。
『微笑み』のような内面の揺らぎを描いた楽曲は、SNS世代にとって“自分の感情を代弁してくれる歌”として共感を呼び、多くの若いリスナーが耳を傾けています。

現代のインディーフォークやアコースティック系のアーティストの中には、ふきのとうを自身の“原点”と位置づける声も少なくありません。特に、北海道や東北地方を拠点に活動するシンガーソングライターたちは、「雪と孤独」「静けさの中の情感」といったテーマを表現する際に、ふきのとうの作品に親しんできたと語っています。
『微笑み』のように、行間から感情がにじみ出るような静かな曲は、過剰な演出に頼らず、むしろ控えめな表現の中にこそ本物の温度を感じさせるものです。そうした感覚は、今も変わらず、時代を超えてリスナーの心に届き続けています。
音楽が心に与える作用:癒しと内省
“耳から入る鎮静剤”としての効果
『微笑み』のような緩やかなテンポと柔らかな歌声は、音楽療法の観点からも注目される存在です。副交感神経を優位にし、心拍数を整え、呼吸を深くさせるような作用を持つこの曲は、まさに“耳から入る鎮静剤”といっても過言ではありません。

ストレス社会に生きる現代人にとって、この曲は心を整えるひとときの安らぎを与えてくれるでしょう。
聴くことで始まる“自分との対話”
『微笑み』はまた、聴く人自身に“問い”を投げかける力も持っています。「これは愛の歌なのか、それとも別れの歌なのか」「癒しなのか、それとも祈りなのか」――明確な結論が示されていないからこそ、聴くたびに受け取り方が変わります。
なぜ『微笑み』は第20位なのか
通好みの一曲が持つ静かな強さ
本シリーズでは、楽曲の完成度だけでなく、再評価の可能性やリスナーの心への影響も評価基準に含めています。『微笑み』はその点で、静かながら確かな力を持つ一曲です。
『白い冬』や『春雷』のように、強烈なビジュアルやメロディの印象を残す代表曲に比べれば、目立つ存在ではないかもしれません。しかし、それゆえに“通好み”であり、じっくりと向き合うことでしか味わえない深みを持っています。
20位という順位は、その特性を肯定的に評価した結果でもあります。
結びに――あなたの「たったひとつの愛」とは?
『微笑み』は、ふきのとうが築き上げた音楽哲学の結晶のひとつです。多くを語らず、風景と感情の重なりを通して聴く人の心に染み渡る――それがこの曲の力です。
いまこの曲を聴くあなたが、どんな時間を過ごしているのか。それによって『微笑み』はまったく異なる表情を見せてくれるでしょう。懐かしい記憶がよみがえるかもしれませんし、これから守りたい何かに気づくきっかけになるかもしれません。



コメント