■僕の勝手なBest10【ミッシェル・ポルナレフ編】・・・・プロフィール(歴史)はこちら!
🎸第1位『忘れ時のグローリア』!─ポルナレフ史を象徴する楽曲
いよいよ第1位の発表です。
予想通りの方もいたのではないでしょうか?
ミッシェル・ポルナレフの「Gloria(邦題:忘れじのグローリア)」は1970年に発表されたシングルです。彼の作品群のなかでも突出した存在感を放ち、50年以上経った今も色褪せることなく聴かれ続けています。
この曲を第1位に据えた理由は明快です。旋律と歌詞が、ポルナレフならではの「繊細さと激しさの同居」を端的に表現していること。沢山の楽曲がある中でも、とびぬけて好きな1曲です。
🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。
🎬 公式動画クレジット(公式音源)
楽曲名: Gloria: Gloria
チャンネル: Michel Polnareff Officiel
提供元: Universal Music Group
アーティスト: Michel Polnareff
収録アルバム: Pop rock en stock
発表年: ©1970 Semi / Meridian
YouTube配信開始日: 2017-12-08
レコーディング/アレンジ: Ben Shepherd
📖 2行解説
1970年に発表されたポルナレフの楽曲で、アルバム『Pop rock en stock』に収録。
情熱的なボーカルと独自のアレンジが際立つ、70年代ポップロックの代表曲のひとつ。
🎬 公式動画クレジット(ライブ:公式音源)
楽曲名: Gloria:
Vocals, Producer: Michel Polnareff
Musician: Dynastie Crisis
© 1972 Barclay / 提供:Universal Music Group
📖 2行解説
1972年オリンピア劇場での名演を収めたライブ映像。ポルナレフの歌声とダイナスティ・クライシスの演奏が一体となった歴史的ステージです。
リリースの経緯とディスコグラフィ上の位置づけ
このシングルは1970年にフランスで発売され、B面には「Je suis un homme(邦題:私は男)」が収録されました。発売直後に国内チャートへランクインし、のちのベスト盤やライヴ盤にも繰り返し収められています。今日では「シェリーに口づけ」や「愛の休日」などと並ぶ代表的レパートリーのひとつとして定着しています。
盤情報から分かる事実
中古盤や音楽データベースを参照すると、A面が「Gloria」、B面が「Je suis un homme」という構成が確認できます。型番やジャケット仕様も複数の資料で一致しており、当時のリリース状況を裏付けています。シングル中心に活動していた時期の作品であることが、彼のキャリアにおける本曲の重みをさらに際立たせています。
曲が描く“光”と“影”のせめぎ合い
「Gloria」が聴き手を惹きつける理由のひとつは、光と影の要素が一曲の中で交錯する構造にあります。冒頭は別れを静かに告げる言葉から始まりますが、やがて抑えきれない執着があふれ出し、激情へと変わっていきます。

導入部の落ち着きと不安
冒頭のフレーズは短く、ほとんど独り言のようです。「たとえ君が終わりだと言っても」と淡々と語られる言葉には、すでに未来が閉ざされていることを示す絶望感があります。しかし、旋律が落ち着いているため、聴き手は静かな悲しみの中に引き込まれます。
中盤で噴き出す激情
曲が進むにつれて、言葉は次第に切迫し、感情のうねりを伴って膨れ上がります。リフレインされる「Gloria, Gloria」の叫びは、失ったものを取り戻せない悔恨の表出であり、音楽全体が熱を帯びていきます。伴奏はピアノを核としつつ、ストリングスが厚みを加え、声の震えをさらに際立たせます。

終盤に差し込むかすかな光
やがて歌詞には「長い道の果てで待つ」「僕の岸辺へ戻ってきて」といった句が登場します。別れの歌でありながら、わずかな希望を手放さない主人公の心情が垣間見えます。完全な暗闇で終わらず、聴き手に余韻を残す点も、この曲が長年愛される理由のひとつです。
歌詞に込められた核心
別れを受け入れられない心理
「たとえもう会えないとしても」という冒頭の断定は、主人公が現実を認識していることを示します。しかし同時に、それを認めまいとする激しい抵抗も歌い込まれています。短い句を何度も重ねる表現方法が、諦めきれない感情の揺れをリアルに伝えています。

「鳥かご」という衝撃的な比喩
もっとも有名なのは「君を閉じ込めておくべきだった、鳥かごの中に」という部分です。現代の感覚では過激に聞こえるこの表現は、ただの独占欲ではなく、「どうしても失いたくなかった」という悔恨を極端な形で吐露したものです。美しい言葉で飾るのではなく、愚かさや身勝手さを正直に表現することで、聴き手に強い印象を与えています。
短句のリフレインが生む緊張感
「Gloria, Gloria」と繰り返す呼びかけは、曲の中で感情を何度もリセットし、緊張を高める役割を果たします。大きな声量に頼らずとも、言葉そのものの強さが聴き手の胸に迫ってくるのです。

アルバム全体における役割
「Gloria」は単独シングルでありつつ、のちにさまざまなコンピレーションやライヴ盤に収められました。彼の代表的アルバム群――たとえば『Polnareff’s』や『Coucou』といった60〜70年代前半の作品群――の間をつなぐ存在としても機能しています。
シングル中心の活動スタイル
当時のポルナレフはアルバムアーティストというより、シングルで強烈な印象を与えるスタイルを取っていました。そこに「Gloria」が加わることで、レパートリーに“重いバラード”の柱が立ちました。軽快な「シェリーに口づけ」、甘美な「愛の休日」と対照をなす存在として、この曲がもたらす陰影は大きかったのです。
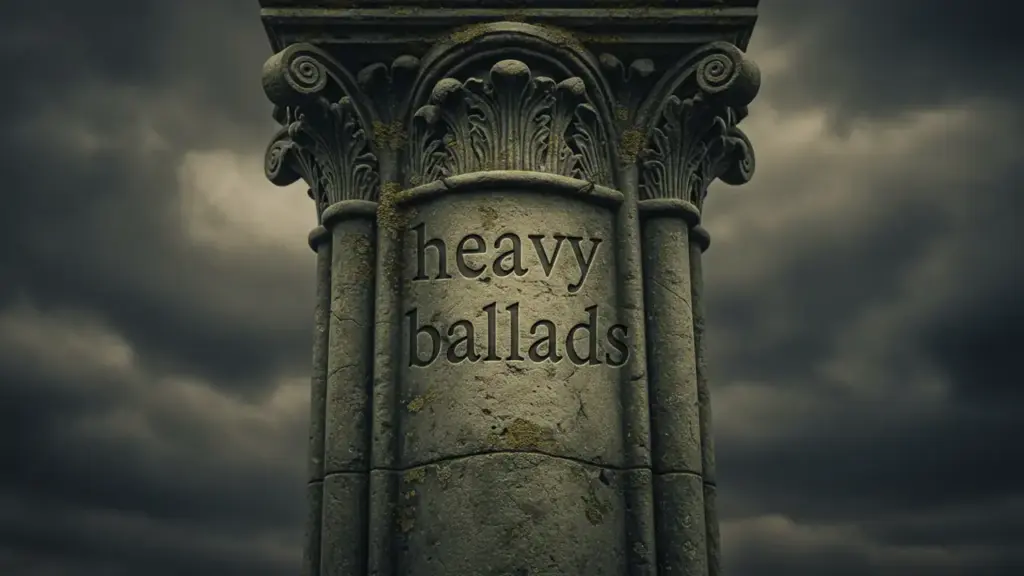
1972年オリンピア公演における「Gloria」
伝説的コンサート「Polnarévolution」
1972年に開催されたオリンピア劇場での公演は、ポルナレフのキャリアを語る上で欠かせない一幕です。「Polnarévolution」と名付けられたこのコンサートは、華美な演出と革新的なステージングで当時の話題を独占しました。(2番目に紹介しているライブ演奏です)
そのセットリストの中に「Gloria」が組み込まれていた事実は重要です。アップテンポで観客を煽る曲と並べられながらも、バラードの核として配置され、ステージの緩急を生み出しました。華やかな照明の下で、ポルナレフがピアノに向かい「Gloria」を歌う場面は、観客にとって強烈な印象を残したと記録されています。

ライヴならではの変化
スタジオ版に比べ、オリンピアでの演奏はテンポや声の使い方に細かな違いがありました。特に「Gloria, Gloria」と繰り返す箇所では、観客の反応に合わせて感情を引き絞るように歌い上げ、張り詰めた空気を作り出しています。ライヴ音源で聴くと、歌詞の痛切さがさらに前面に出てくるのが分かります。
国際的な音楽シーンとの対比
1970年代初頭、国際的にはビートルズ解散後のソロ活動や、アメリカ西海岸のシンガーソングライター・ブームが台頭していました。キャロル・キングやジェームス・テイラーが内省的な歌を届ける一方で、イギリスからはグラムロックが派手に登場します。
そのような国際的潮流と比べても、ポルナレフの「Gloria」はユニークです。アメリカのフォーク的内省とは異なる、フランス語の語感を生かした凝縮感。グラムロックの派手さとは逆に、静から激へと心情の振幅を描く抑制と解放のリズム。この独自性が、彼を単なる模倣者ではなく、フランスから世界へ発信する存在に押し上げました。
フランス国内における立ち位置
当時のフランスは、セルジュ・ゲンズブールやフランソワーズ・アルディといった個性豊かなアーティストを輩出していましたが、彼らとは異なり、ポルナレフは「視覚的インパクト」と「情念の濃さ」を前面に出しました。その中で「Gloria」は、華美なヴィジュアルの裏にある痛みを示すことで、彼の二面性を決定づけた楽曲だったといえるでしょう。
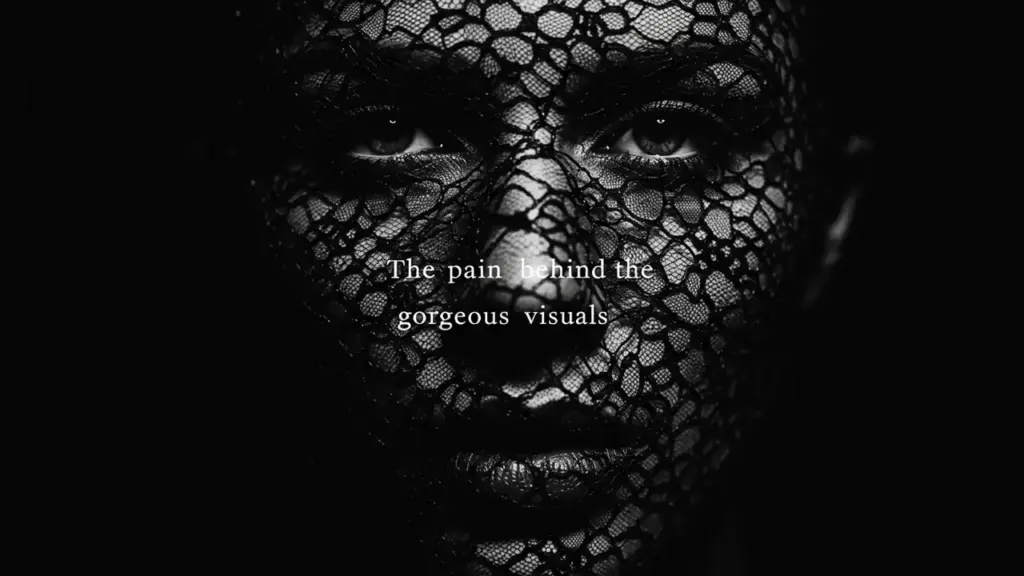
「忘れじのグローリア」が示す音楽的完成度
「Gloria」の最大の特徴は、音楽的な完成度と人間的な脆さが矛盾なく共存している点にあります。旋律はシンプルでありながら、言葉の選び方と配置によって深い余韻を生みます。オーケストラ編成は派手すぎず、あくまで声の表情を引き立てるための伴奏に徹しており、バラードとして理想的なバランスを保っています。
同時代のフランス・ポップに見られる軽快さとは一線を画し、むしろクラシカルな荘厳さを帯びています。これはポルナレフが「大衆向けポップスター」でありながら「作曲家としての矜持」を失わなかったことの証でもあります。
聴き手が共感するポイント
- 失ったものを手放せない心情:普遍的なテーマであり、時代や文化を超えて共感を呼びます。
- 言葉の強度:「鳥かご」という過激な比喩は、人間が持つ独占欲や後悔の本質を突き、聴き手の記憶に残ります。
- 声の表現力:ポルナレフの歌声は高音域での揺れが特徴的で、抑制から爆発へ移行するダイナミクスが感情の振幅をそのまま伝えています。
こうした要素の積み重ねが、半世紀を超えてなお聴かれ続ける理由につながっています。
評価の変遷と現在の位置づけ
当時の受容

1970年のリリース当初、「Gloria」はシングルとして一定のヒットを記録しましたが、社会的スキャンダルやポルナレフ本人の派手なイメージに隠れ、楽曲そのものが過小評価される側面もありました。(歴史に記しています)
しかし時間の経過とともに、華美なビジュアルや話題性ではなく、純粋に音楽作品として再評価されるようになります。特に1990年代以降、CD再発やベスト盤企画で取り上げられる機会が増え、代表的なバラードとしての位置が確立しました。
現在の視点から
今聴き返すと、「Gloria」は単なる70年代フレンチポップの一曲ではなく、ポルナレフというアーティストの生涯を通じたテーマ──「栄光と喪失」「自由と孤独」──を凝縮した象徴的作品に思えます。特に、のちのアメリカ亡命時代や沈黙期を知った上で聴くと、この歌に込められた未練と後悔は彼自身の人生そのものを予告するかのように響きます。

他の代表曲との比較
「シェリーに口づけ」との対比
軽快な「シェリーに口づけ」はポルナレフの明るい側面を象徴しますが、「Gloria」は真逆の陰影を持つ曲です。二曲を並べることで、彼の音楽がいかに多面的であるかが理解できます。
「愛の休日」との連続性
「愛の休日」はロマンティックな愛を正面から描いた曲ですが、「Gloria」は愛の終わりと喪失を描いています。表と裏のような二曲をあわせて聴くと、ポルナレフが単なる恋愛歌手ではなく、感情の両極を等しく描き切ったことが分かります。
第1位としての必然性
このランキング企画の締めくくりに「Gloria」を選んだのは、単なる好みではありません。
- 歌詞・旋律・声が三位一体で迫る力
- 個人的な体験を普遍的テーマへ昇華した構造
- 50年以上経っても古びない表現力
これらが重なり合うことで、「Gloria」はポルナレフの音楽的頂点であると同時に、聴き手自身の人生と重ねて味わえる作品になっています。
結びにかえて
「忘れじのグローリア」は、喪失の痛みと未練を真正面から描いた作品です。倫理的に整えられた言葉ではなく、むき出しの感情を歌に託したからこそ、聴く人の胸に強烈な印象を残します。
この曲を第1位に置くことは、ランキングを単なる「好みのリスト」から「音楽史の証言」へと引き上げる意味を持っています。ポルナレフを知らない人にも、まずこの曲を聴いてほしい──そう思わせる説得力がここにはあると思います。



コメント