「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
夜明けが来ても、心は遠いまま
1970年代末から80年代初頭――フォーク・デュオ「ふきのとう」が静かに放った一曲、『作品A』。この楽曲は、彼らの代表曲群とは少し趣を異にしながらも、聴く人の心にじわりと残る“静かな傷”のような存在です。
本記事では、僕が選んだ【ふきのとうベスト30】の第19位としてこの楽曲を取り上げ、その魅力を多面的に掘り下げていきます。
『作品A』の魅力は、誰かの物語ではなく、「あなた自身の心の奥」に語りかけてくる静けさにあります。耳元でささやかれるような歌声が、言葉では届かない感情をそっとすくい取っていくような一曲です。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『ふきのとう/作品A』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
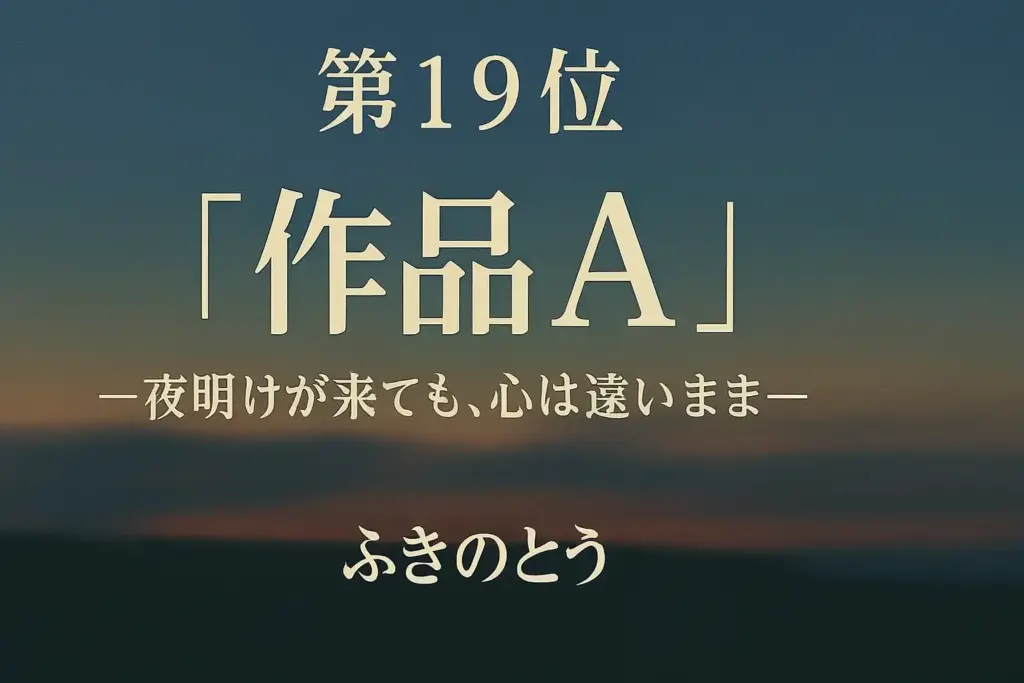
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:ふきのとう/作品A
作詩・作曲:細坪基佳/編曲:瀬尾一三
公開年:2015/01/07
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。 ※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
抽象的なタイトルが示す「普遍性」
具体的なものは何もない。
『作品A』というタイトルには、具体的な情景も固有名詞もありません。地名も季節も背景も描かれず、タイトルから楽曲の内容を推測する手がかりは皆無です。
しかし、それこそがこの楽曲の最大の強みでもあります。何も描かれていないことで、誰しもの「記憶の空白」を埋める余地が生まれるのです。ふきのとうが得意とする「情景描写」や「郷愁」をあえて封じ、感情そのものの断片を聴き手に託す。そうした構造に、彼らの創作姿勢の変化を垣間見ることができます。

『作品A』は、1980年にリリースされたアルバム『風待茶房』のA面3曲目に収録された楽曲です。作詞・作曲は細坪基佳、編曲は瀬尾一三が担当し、当時のふきのとうの音楽性を象徴する静謐なバラードとして位置づけられています。タイトルの抽象性や感情の広がりを活かした詞世界は、リスナーが自身の経験と重ねて受け取ることを可能にしており、“ふきのとうらしさ”を濃密に感じさせる作品です。
さらに注目したいのは、このタイトルの“無記名性”が、リスナーの想像力を解き放っている点です。たとえば、『白い冬』や『春雷』といったタイトルが情景や季節の予感を与えるのに対し、『作品A』はまるで手紙の仮タイトルのように、意味を委ねる広がりを残しています。
感情が暴走する瞬間――冒頭の焦燥
曲の冒頭では、感情がうまく処理できないまま突き動かされてしまう主人公の姿が浮かび上がります。理性よりも衝動が勝ってしまった結果、相手の部屋に向かってしまった――そんな一幕が描かれます。

「空回り」という表現には、熱意が報われないむなしさと、止めようのない切迫感の両方が込められており、その心理的リアリティが胸に迫ります。
この楽曲では自然描写が一切登場せず、感情の内側にだけ焦点が当てられています。これはふきのとうとしては非常に異色な手法であり、その分だけ聴き手の心に直接触れる構成となっています。
ふとしたきっかけで言葉にできない気持ちが溢れ出し、それが誤解や戸惑いのもとになってしまう――そんな不器用さを誰しもが経験したことがあるのではないでしょうか。
伝え方が分からないもどかしさ
感情が大きくなりすぎると、人はうまく言葉にできなくなります。この曲の主人公もまた、自分の気持ちを届けたいのに空回りしてしまう。その姿は、恋愛に限らず、あらゆる対人関係における「伝えられなさ」の象徴のように感じられます。

すれ違いの予兆:距離が生まれる瞬間
本作の主題は「別れ」そのものではなく、むしろ「別れが始まる前の不穏な空気」を静かにすくい上げています。まだ一緒にいるのに、心だけが遠ざかっていく――そうした感覚が、抑制された言葉の中でじわじわと描かれます。
関係の綻びに最初に気づいたのは、自分なのか相手なのか。その境目さえも曖昧になる瞬間、人は動揺し、何もできなくなるものです。けれどその違和感を見ないふりをしてしまう。『作品A』は、その“目をそらしたい本音”を静かに突いてきます。

このような描写は、ただの恋愛ソングにはとどまりません。友人や家族など、あらゆる人間関係において、誰もが心当たりのある“心の距離”を思い起こさせます。
相手ではなく、自分が変わってしまったという痛み
「優しさが分からなくなった」という言葉に象徴されるように、かつては受け取れていた愛情が、あるときから心に届かなくなってしまう。『作品A』の核心は、まさにその“感受性の変化”にあります。
愛する気持ちが強くなればなるほど、「もっと分かってほしい」「もっと深くつながりたい」という欲求が高まり、それが“満たされなさ”となって心に影を落とすようになります。その影が、優しささえも疑わせてしまうのです。

この曲は、感情のねじれや複雑さを、決して断定的には語りません。ただ、「そうなってしまった」という事実だけが、淡々と提示されます。それがむしろ、リスナーの共感を深めるのです。
心が閉じていくプロセス
人は心に余裕がなくなると、他者の優しさすら受け取れなくなることがあります。それは決して冷たくなったわけではなく、防衛反応の一種かもしれません。『作品A』は、そうした“心の内閉化”を静かに表現しているようにも思えます。
感情の移ろいを追う歌詞構成
この曲の最大の特徴は、構成そのものが“感情の流れ”に沿っているという点です。冒頭から終盤にかけて、心の動きが段階的に変化していきます。
最初は焦りや衝動、中盤での違和感と失望、そして終盤には静かな諦めや孤独感――その移り変わりが時間軸と連動し、まるで一編のモノローグを聴いているような構成になっています。
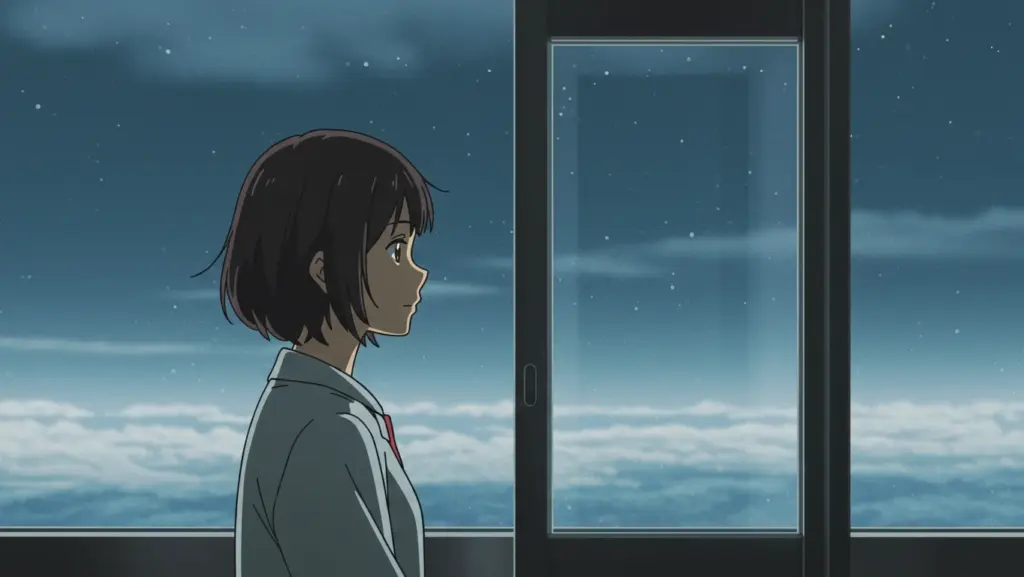
メロディもその流れに沿って緩やかに変化し、盛り上がりを意図的に避けた展開が“感情の内向きなベクトル”を強調します。
この設計の妙により、聴く人は自分の記憶や経験と自然に重ね合わせることができ、より深い没入感を得られるのです。
細坪基佳の歌声が描き出す静かな激情
この曲における細坪基佳の歌唱は、まさに語りと歌のあいだに位置しています。発声は抑制され、語尾に至るまで息づかいが丁寧にコントロールされており、「語りかけ」のような印象を残します。
また、アレンジもきわめてシンプルです。アコースティックギターのアルペジオを基調とし、必要最小限の音で空間を構築。これは、ふきのとうの中でも特に研ぎ澄まされたアプローチです。
音数を減らすことで、逆に「言えなかった言葉」が聴き手の想像力によって補完され、曲の世界観が一層広がる効果を生んでいます。毎回のように登場する言い回しですが、ふきのとうの世界感とは、そういうものです。
他のバラードとの明確な違い
ふきのとうは多くのバラードを生み出してきました。『白い冬』では雪景色に別れを溶かし込み、『春雷』では自然現象に心のざわめきを重ねました。
しかし『作品A』では、視覚的要素を極限まで排除し、感情そのものだけに焦点を当てています。これは、ふきのとうの楽曲群の中でも異例です。
また、楽曲の展開も内向きで、派手なサビや転調などは一切ありません。むしろ「聴いた後に心にじわっと残る」ことを目的とした、“内面回帰型のバラード”と言えるでしょう。
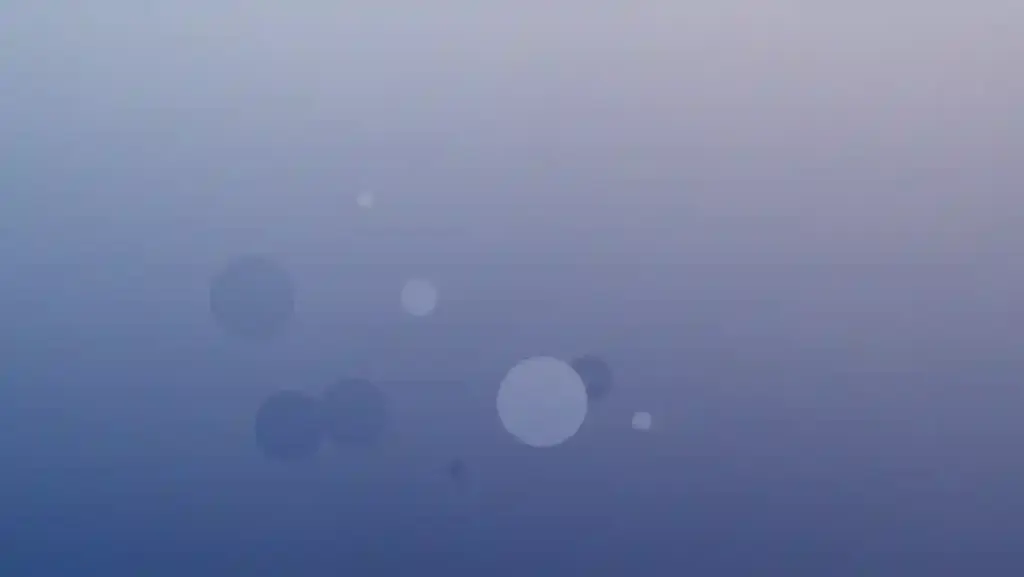
聴き込むごとに意味が少しずつ変化し、受け取る側の状態によって印象が異なる。そうした「育つ楽曲」としての特質も、この曲ならではの魅力です。
結びに代えて:静かに寄り添う楽曲
『作品A』は、誰にでも起こりうる「心のズレ」や「感情の変質」を、繊細かつ抑制的に描いた楽曲です。・・・・「好きだと言わず何も聞かない その方が良かったみたい」切ないけれどこの曲で一番好きな歌詞です。


コメント