「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
私的な思い出を呼び起こす旋律
おはようございます! 今回はベスト30企画の第16位、『メロディー』をご紹介します。
普段は当たり前すぎて気づかないのに、ふと耳にしたとき、心の片隅にしまわれていた記憶が静かに呼び出されるような曲――それが『メロディー』です。
表面的な華やかさではなく、感覚の深部に働きかけてくるような音の重なり。ふきのとうの音楽の中でも、内面的な感触を持った楽曲といえるでしょう。
控えめな旋律のなかに、確かな存在感が宿っている。
それはまるで、慌ただしい日々の中で不意に差し込んだ午後の光のように、私たちの心の隅を静かに照らしてくれるのです。
この曲が持つ「日常と記憶をゆるやかにつなぐ力」――そこには、どこか“語ることの少なさ”を通して、逆に聴き手自身の内面を引き出すような効果があると感じます。その魅力と特異性に、今回はじっくりと迫ってみたいと思います。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
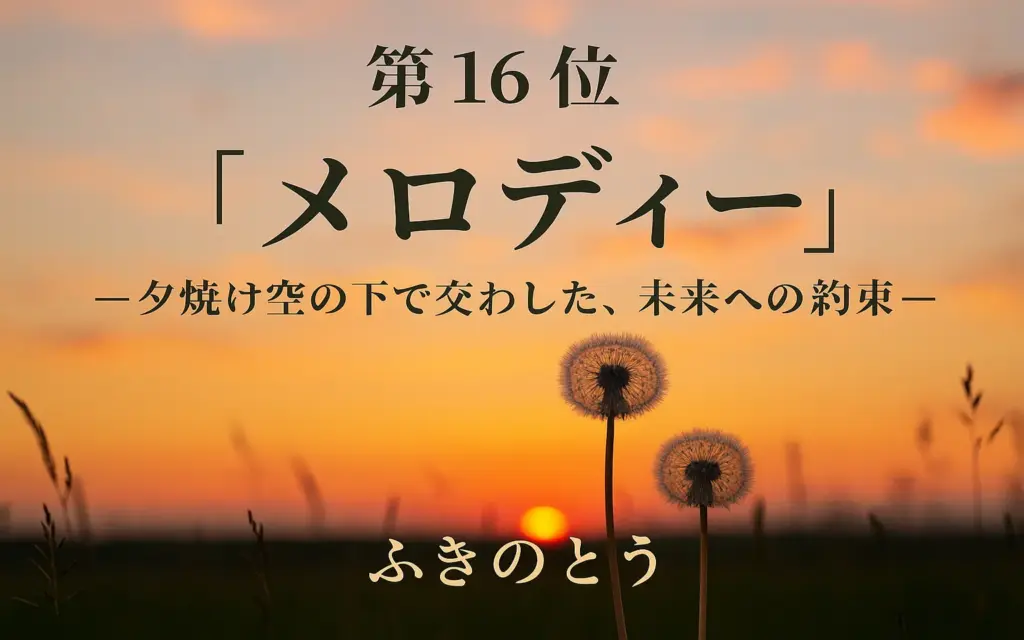
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:ふきのとう/メロディー
作詞・作曲:山木康世/ストリングス・アレンジ:瀬尾一三
公開年: 2014/12/21
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
シングル発表とアルバム収録の経緯
『メロディー』は1981年5月21日、山木康世のソロ名義でシングルリリースされました。
この時期はふきのとうが活動を続けながらも、メンバーそれぞれが個の表現にも挑戦し始めていた過渡期でもありました。
山木康世にとってこの作品は、いわば私的な節目と重なるものだったとも言われます。愛情や記憶、言葉にしづらい内面の機微に焦点を当てた歌詞は、当時のフォークシーンのなかでも静かな共感を集めました。

その後、同年に発表されたふきのとうのアルバム『D.S.ダルセーニョ』に収録。
このアルバム全体は、春から初夏にかけての柔らかな空気感や、成長と回想が交錯するような構成がなされており、『メロディー』はその中でもひときわ静謐な立ち位置にあります。
他の収録曲が外の世界や季節の移ろいを描こうとしているのに対して、『メロディー』はあくまで“内側に向かう歌”として沈黙の中に立っています。
それは「語らずに語る」のではなく、“受け止める姿勢”を音楽に託した楽曲なのです。
歌詞に浮かぶ記憶の断片
抑制された描写がもたらす感情の広がり
この曲の歌詞は、冒頭からあえて説明を抑えた描写で始まります。
緑に囲まれた 北国の街
あなたを見かけた 思い出の道

このわずか二行の中に、「風景の広がり」「記憶の場所性」「再会の偶然性」といった複数の要素が折りたたまれています。
具体性を極力排したことで、聴く人それぞれの過去や感情が、この空白に自然と流れ込むような構造になっているのです。
たとえば、リスナーがこれを“夏の夜”や“学生時代の通学路”として受け取ってもまったく違和感がないように。
歌詞の描写が地図のように正確でないからこそ、誰にとっても「自分の記憶と接続できる歌」となっています。
「メロディー」が意味するもの
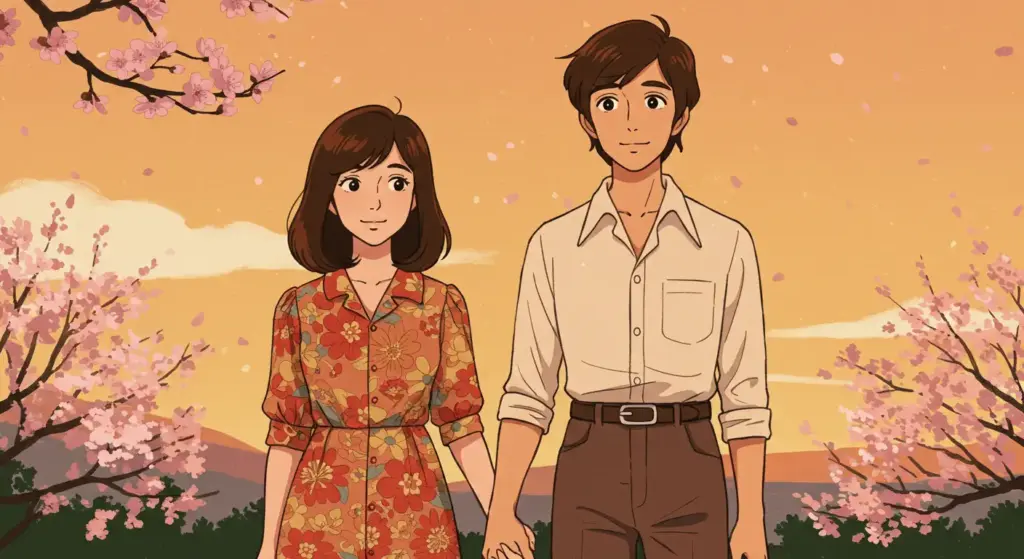
サビで繰り返されるフレーズは、シンプルでありながら印象的です。
若い日のあなたと私のメロディー
若い日のあなたと私のメロディー
この繰り返し自体が、記憶のリフレインを象徴しています。
「メロディー」という言葉が単なる楽曲タイトルを超えて、時間・感情・記憶の連なりを象徴するキーワードとして機能しているのです。
この“メロディー”が何を意味するのかは、あえて詳細に描かれません。
具体的なエピソードを描かずに、心の底に沈んでいる感情や関係性を思い起こさせる仕掛けになっているのです。

“メロディー”とは、旋律そのものではなく、過去の時間の連なりや、胸に刻まれた記憶の輪郭。
この曲ではそれが、音楽そのものの力として提示されています。
少ない語で深く伝える表現力
控えめな言葉で輪郭を描く
もう一つ印象的なのは、次の一節です。
あなたの温もり 思いやりが
手にとるように分かり うれしかったよ
ごく短い言葉ながら、その中に「共有された時間」「感情の理解」「忘れがたい瞬間」などが重層的に込められています。
多くを語らずに、心情の断片だけをそっと置いていくような手法は、山木康世の作詞における重要な特徴のひとつでしょう。

このように、比喩や強調に頼らず、音の流れと感情の起伏を最小限の語で伝える姿勢は、フォークというジャンルの枠を超えた文学性を帯びています。
聴く人の記憶や感情の余地を奪わずに、むしろ静かに導くようにして共鳴を促す――そんな表現がここにはあります。
心に刻まれるメロディーの力
最後に残るのは、耳ではなく心で聴いたもの
『メロディー』という曲には、何かを伝えるために声を張るのではなく、記憶の中にそっと入り込み、胸の奥で静かに鳴り続ける力があります。
リリースから何十年経った今も、ある日ふとこの曲が流れてきたとき、「ああ、この音だった」と記憶のどこかで思い出す。そう感じる方も多いのではないでしょうか。
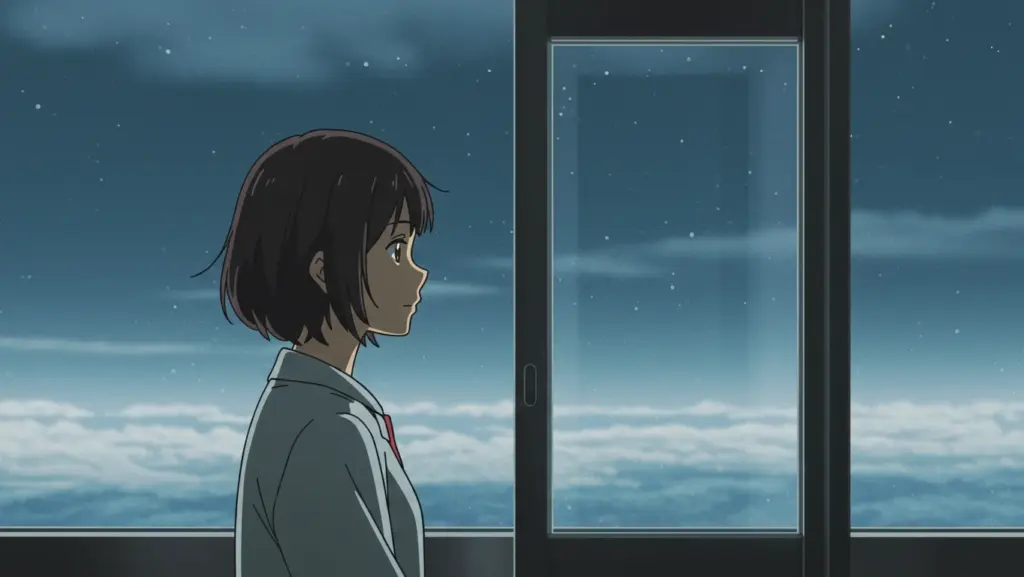
音楽の記憶とは不思議なもので、旋律よりも、その音に包まれていた時間や空気、あるいは隣にいた誰かの表情の方が、強く心に刻まれていたりします。
結婚式のBGMとして選んだ理由
私の人生に重なった『メロディー』
この曲を、僕は自分の結婚式のBGMとして選びました。特別に誰かに披露するというよりも、自分たちの時間をそっと記録するように。そしてその妻とは、もう40年近い年月を共にしています。
当時の私は、この歌を通して「これから」の時間に静かに期待を込めていました。改めて聴いてみると、『メロディー』は決して悲しみを帯びた曲ではありません。
むしろ、今の自分が過去の自分に手紙を書くような、あるいは遠くにいる誰かへ小さな贈り物を届けるような、そんな温かさに満ちています。
静けさが語る、音楽の終わり方
この曲の終わり方も印象的です。大きなクライマックスを迎えることなく、まるで「これでいいんだよ」と言わんばかりに、静かに曲が閉じていく。その静けさが、むしろ聴き手の心を締めつけます。

きっぱりと切るのではなく、柔らかく封をする。そんな音楽の終わり方が、人生のある時期を受け止める形と重なって、深く心に残ります。
歌声に宿る表現の強さ
“ふきのとう”という名の歌声の意味
『メロディー』は、単なる懐かしさを呼び起こすための作品ではありません。
細坪基佳の声に宿る揺るぎなさ
細坪基佳の歌声には、弱さと強さが同居しています。決して大きな声で主張するのではないけれど、揺るぎない芯が通っている。

山木康世の詩がつくる感情の構図
山木康世が描き出す情景や心情は、あえて細部を描写しすぎることなく、聴き手の記憶や経験によって補完されることを前提としています。
説明を省きながらも、伝えるべき核心を残す。その作詞術が、この楽曲にも見事に息づいています。
音楽が導く、過去と現在の交差点
今、この曲があなたに届けるもの
音楽には、不思議な“再会”の力があります。若い頃に聴いた曲を、何十年も経ってから再び耳にしたとき、その瞬間だけ過去と現在が静かに重なり合う――そんな経験は、誰にでもあるはずです。
かつてこの曲を聴いたことがある人にも、今回初めて出会う人にも、『メロディー』が届けてくれるものは、同じです。
それは、名前もついていないような記憶の断片。自分でも忘れていたような感情のしずく。それらがそっと胸の奥で反応し、静かに居場所を取り戻すような時間です。
ぜひ一度、何も考えずにこの曲を流してみてください。きっと、その日の風の温度や、光の角度までもが、少しだけ変わって感じられるはずです。




コメント