「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
【ふきのとう】編-第15位『柿の実色した水曜日』をご紹介!
ふきのとう編第15位は、この曲『柿の実色した水曜日』。1979年5月21日に発売されたアルバム『人生・春・横断』に挿入されています。
このアルバムも大学時代に繰り返し聴きましたが、初めてこの曲を聴いたとき、最後の一行の歌詞に鳥肌がたったのを覚えています。冗談ではないです。最後の最後の、「・・・・初めて恋をした~」というメロディーと歌詞。それまでの歌詞の流れとコントラストが素晴らしく、この部分が際立っています。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『ふきのとう/柿の実色した水曜日』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
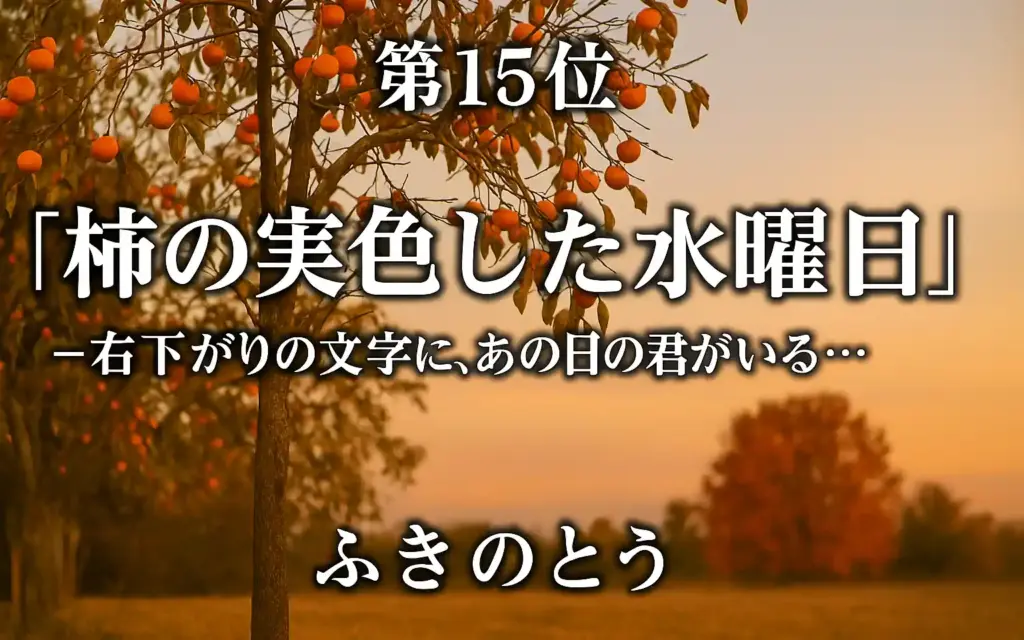
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより 動画タイトル:柿の実色した水曜日 公開年: 2015/06/23 ※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
色彩が情景を呼び起こす――『柿の実色した水曜日』の世界へ
1979年、フォークデュオ「ふきのとう」は7枚目のアルバム『人生・春・横断』を発表しました。その作品群の中で、やや異色の存在ともいえるのが『柿の実色した水曜日』です。作詞・作曲は山木康世。ふきのとうの代表的な作風と比べて、より柔らかく、私的な語感を持ったこの楽曲は、静かな風景描写と記憶の陰影を交差させた印象的な一曲となっています。

この記事では、従来の楽曲解説とは趣向を変え、アーティストの経歴や時代背景をできる限り切り離して、この曲が内包する「色」と「心の揺れ」に注目します。余計な装飾を排した音像と、素朴なことばの中に宿る“私小説的な瞬間”を、見つめ直してみましょう。
柿の実が色づく午後に浮かぶ風景
『柿の実色した水曜日』というユニークなタイトルがまず惹きつけるのは、「色」に対する感覚です。柿の実――その言葉が連想させるのは、濃い橙色、やわらかな陽射し、そして少し切ない秋の気配です。ここでは、自然が見せるほんの一瞬の美しさが、まるで絵画のように定着されています。

「柿の実色」という言い回しは、単なる季節描写にとどまらず、心象風景の一部として作用しています。たとえば、色づく柿の実が見える風景の中で、主人公が誰かを想っているような――そんな情景が思い浮かびませんか?
音楽的には、アコースティックギターの穏やかな音色が、歌詞の持つ温かみをさらに強調します。メロディは決して派手ではなく、むしろ控えめで、聴き手の心の内に語りかけるような印象を与えます。
「水曜日」という言葉がもたらす、ひそやかなリズム
タイトルに含まれる「水曜日」という曜日名にも注目してみましょう。週のちょうど真ん中にある水曜日は、週末の解放感とも、月曜の緊張感とも違う“中間の静けさ”を象徴しています。この曲には、その静けさが通奏低音のように流れているのです。

楽曲のテンポもミディアムスローで、語りかけるような構成になっており、聴き手の心にささやかに触れてきます。抑揚の少ない構造ながら、言葉の選び方や音の運び方がとても丁寧で、その中に心のひだが隠されています。
この「水曜日の午後」に起きた出来事が、人生の中ではささやかな通過点にすぎなかったとしても、当人にとっては決して忘れられない記憶である――そんな感覚が、じんわりと伝わってくるのです。
日常という名の小さな物語
記憶のなかで、音もなく灯る風景
『柿の実色した水曜日』は、劇的な展開や明確な出来事の描写はなく、まるで夢の続きをぼんやり思い出すかのように、静かな感情が立ち上がってきます。
登場人物の動作や背景は、あえて説明されていません。それでも伝わってくるのは、その「場」に漂う空気、流れる時間、そして視線の先に広がる風の色です。
「物語」があるのではなく、「気配」が残されている。そこにこの曲の美しさがあります。
声に染み込んだ記憶のざわめき
細坪基佳のボーカルは、この楽曲において一段とやわらかく響きます。どこか遠くから響いてくるような、淡いまなざしを感じさせる声。語りかけるでもなく、呼びかけるでもない――ただそこに在る、という雰囲気に満ちています。
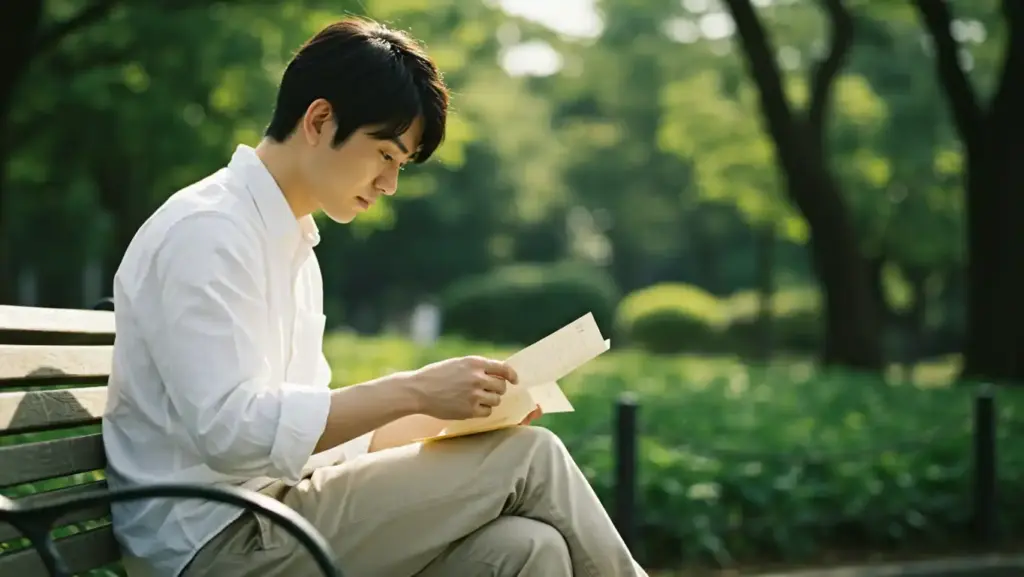
特筆すべきは、声のなかに込められた微妙なニュアンスです。息遣いや言葉の間にこめられた静かな振動が、まるで手紙を読むような感覚を与え、時間を忘れて耳を傾けたくなります。
静けさの中に見出される強さ
飾り立てずに描き出す深み
この曲が印象に残る理由のひとつは、聴き終えたあとに余韻のようなものが静かに残る点です。装飾を削ぎ落とし、直線的でない流れの中に、聴き手が自分の感情を重ねやすい構造となっています。
音の配置やメロディの展開に無理がなく、むしろ簡素であるがゆえに、かえって奥行きが生まれているのです。

豪華な装飾ではなく、静けさの中に芯を据えたようなスタイル。こうした表現手法は、ふきのとうの真骨頂といえるかもしれません。
情緒を先回りしない美学
また、楽曲全体として、聴き手の感情を先に誘導するような構成にはなっていません。むしろ、こちらが感じるまでは待っていてくれるような「間」が設計されており、それが心地よいのです。

あえて明示しないことの力、整然としすぎないことへの信頼。そのバランス感覚こそが、何度聴いても飽きない魅力となり、日常にそっと紛れ込むような存在感を生み出しています。
風景としての歌詞――言葉と音が織りなす静かな情景
「柿の実色」とは何を意味するのか
楽曲のタイトルにある「柿の実色した水曜日」という表現。これほどまでに具体的でありながら、同時に曖昧さを含んだタイトルも珍しいのではないでしょうか。「柿の実色」という語感には、鮮やかなオレンジ色や熟した果実のぬくもり、さらには秋の気配といった多層的な意味が漂っています。
その色が「水曜日」という曜日と結びつけられることで、ぐっと私的な空気が生まれます。たとえばこの一節――
柿の実色した 水曜日には 君がとても まぶしかった
このニュアンスの歌詞たちから伝わってくるのは、色彩と記憶が強く結びついているということ。季節感と心情が交差するこの描写は、風景が感情の引き金になっている好例です。
忘れがたい理由と、この曲の現在地
なぜ『柿の実色した水曜日』は記憶に残るのか
ふきのとうの楽曲群のなかでも、この作品が特別な位置にあるとすれば、それは「風景として記憶に残る」という点でしょう。恋愛の終わりや、別れの場面を直接描くのではなく、あくまで“その手前”の心の動き――たとえば、何かが始まるか終わるかの予感のようなもの――を描いているからです。
まるで古いアルバムの中に、ふと見つけた色あせた一枚の写真のように、具体的な出来事よりも、そのときの「空気」や「光」が残っていく感覚です。

このように、「個の記憶」と「誰にでも通じる記憶」のあいだを巧みに行き来する詞世界は、ふきのとうならではのものです。
今、改めて聴く意味
時を超えて、「あの午後」が蘇る
ふきのとうの多くの楽曲がそうであるように、この作品にも「時間軸を飛び越える力」が備わっています。特別なイベントが描かれていないにもかかわらず、聴くたびに何かが蘇る――その「何か」は、聴き手自身の過去かもしれませんし、まだ言葉にならない感情かもしれません。

『柿の実色した水曜日』は、そんな「声にならない記憶」をそっと拾い上げてくれる作品です。だからこそ、年齢や時代を超えて、幅広い層に深く受け入れられているのではないかと感じます。
まとめ――なぜこの歌は、いつまでも残るのか
『柿の実色した水曜日』は、いわゆる名バラードのような派手さや、大サビでの感情の爆発を持つ作品ではありません。それにもかかわらず、これほどまでに人の心に残るのはなぜか――その理由は、曲全体が「感情の余地」をたっぷりと残してくれているからです。
秋が深まる頃、ふとこの曲が聴きたくなる日が、また訪れる――
そんな未来の一瞬までも、そっと先回りしてくれるような温かさが、この歌には込められているのです。




コメント