「ふきのとう」の歴史はこちら➡
■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)
■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」
僕の勝手なBest30,ふきのとう編第12位は、1975年リリースの『初夏』です。
7月も三分の一が終わったとはいえ、「初夏の候」とはそんなの遠く離れてはいません。
いつもの”ふきのとう”ではありますが、これまでの曲も、これ以降の上位曲も、順位こそつけてはいますが、僕の中では、どの曲も競うことなくほぼ横一線というのが正直な気もちです。どの曲も大した特別感はないけれど、そのかわりどの曲も、愛おしく、離れがたく、味わい深い楽曲たちという感じです。
これまでの楽曲解説でも、「ふきのとう」の曲を突き詰めると、どうしても解説の表現が似てこざるを得ません。これが致し方ないことも事実なんです。どの曲も切り口により、テイストが似ているのは認めますが、見方を変えると、実に見事な歌詞と歌唱力の数々。狭いエリアを自ら作り出し、それを微妙に展開していく力は見事だと思います。
ぜひ、これまで「ふきのとう」を知らなかった人も、ゆっくりと30曲を味わってほしいと切に願っています。では、今回の12位「初夏」の解説を始めましょう。
まずはYoutube動画から紹介しましょう。
下の画像をクリックしてください。Youtube動画『初夏/ふきのとう』にリンクしています。
(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)
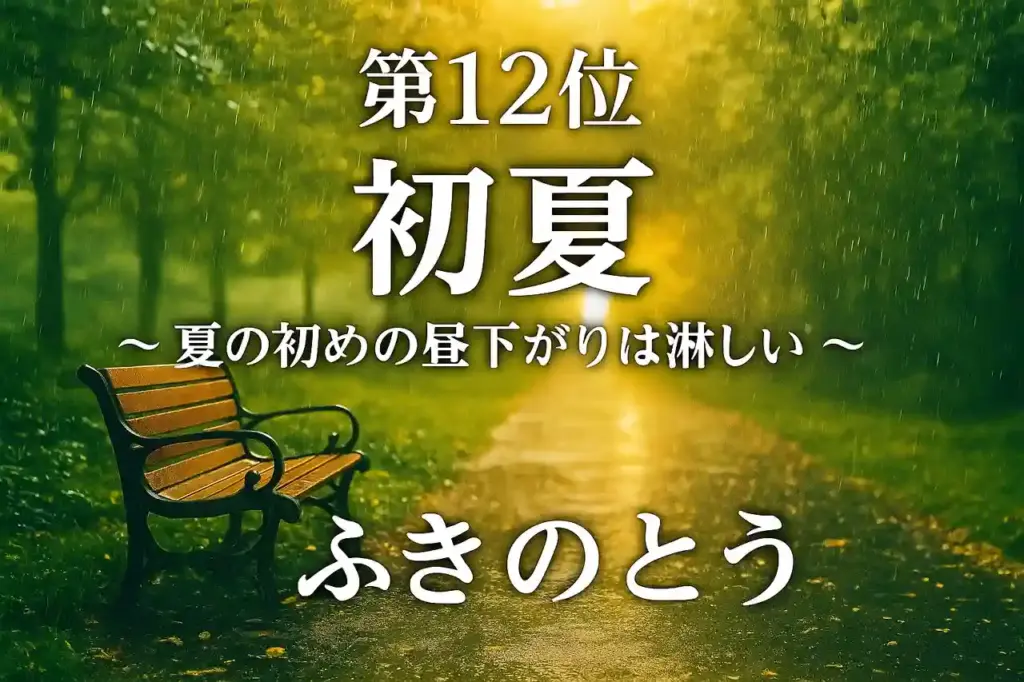
🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより
動画タイトル:ふきのとう/初夏
作詩・作曲:山木康世 編曲:瀬尾一三
アルバム:『ふたり乗りの電車』(1975年6月1日発売)
公開年: 2015/06/07
※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。
都会の昼下がりに立ち止まるとき
人の流れに身を委ねながらも、ふと足を止めた瞬間――
誰の心にも、理由のない淋しさや、居場所の曖昧さが芽生えることがあります。

そんな心の襞(ひだ)にそっと触れてくるのが、ふきのとうの『初夏』という楽曲です。
1975年にリリースされたこの作品は、決して大ヒット曲ではありませんが、その静かな佇まいと深い余韻によって、いまもなお多くのリスナーの記憶に残っています。
『初夏』という楽曲が描く“都会の孤独”
ふきのとうの中でも異色の存在感
『初夏』は、ふきのとうの3枚目のシングル曲として、1975年5月21日にリリースされました。
作詞・作曲は山木康世氏、編曲は瀬尾一三氏が担当。
わずか10日後の6月1日には、セカンドアルバム『ふたり乗りの電車』にも収録されました。

北海道・札幌を拠点とする彼らの作品群のなかで、『初夏』は自然描写や郷愁的風景ではなく、都会の喧騒とそこで生きる若者の孤独に焦点を当てた、少し異なる側面を持った一曲です。
山木康世の詞世界と札幌の風景
『初夏』の歌詞には、大通公園の噴水、時計台、狸小路といった札幌市の実在の風景が織り込まれています。
これにより、楽曲は特定の都市を舞台にした「ご当地ソング」としての表情も見せつつ、同時にそれらの風景は、“どこにでもありそうな都市”の象徴として機能します。

つまり、この作品は札幌に馴染みがある人にとっては具体的な記憶を呼び起こし、そうでない人にとっても、自身がかつて感じた都市の空気や孤独感を想起させる、普遍性を備えた歌詞なのです。
三つの視線、三つの風景――『初夏』の構成
この楽曲の詞構成は、主人公「ぼく」の視線を追うことで成立しています。
彼の視線が移動するたびに、異なる風景と、それにまつわる“他者”が登場し、それらと対比されることで、彼の孤独や葛藤が輪郭を帯びていきます。
噴水前の記念写真と「ぼく」
冒頭に描かれるのは、噴水の前で新婚カップルが記念撮影をしている場面です。
主人公はそれを少し離れた場所から眺めています。ここで描かれるのは、「幸せそうな人々」と、それを見つめる“自分”との間に横たわる、静かな断絶です。

その対比は、「とうきびの殻をつつく鳩」という描写とともに、ささやかな初夏の情景に溶け込んでいきます。 しかしその“のどかさ”は、どこか空虚で、主人公の心には響いていないようにも見えます。
時計台の下の“カニ族”と「ぼく」
次に視線は、札幌の象徴とも言える時計台の下へと移ります。そこには「黒いカニ族の家族」が描かれています。1970年代に流行した「カニ族」は、大きなリュックを背負って自由な旅をする若者たちを指し、当時の社会の中である種の若者文化として確立していました。
しかし主人公は、その若者たちを「見ないふり」し、「声をかけぬように」努めます。ここに描かれているのは、ただの人見知りではありません。
他者との距離を保とうとする心理的な防衛反応、あるいは自分がその中に溶け込めないという無意識の劣等感――それらが複雑に交差した、静かな葛藤です。
地下街に降りる――自分の内面へと向かう視線
地下街の雑踏と「ぼく」

物語のラストシーンは、地下街へと舞台を移します。
時計台や噴水が象徴する“開けた都市の風景”とは対照的に、地下街は薄暗く閉ざされた空間です。
ここで「都会の顔をしている地下街」と「田舎扱いされる狸小路」という対比が語られます。
センチメンタルの“演技”が意味するもの
この場面で最も印象的なのが、次の一節です。
センチメンタルに浸った振りして
これは非常に示唆的なフレーズです。
主人公は、自分の感情に真正面から向き合っているようでいて、実はどこかで“演じている”ことを自覚しています。言い換えれば、彼は悲しみに溺れることさえ、どこか他人事のように扱っているのです。
それは、都市に生きる人々が身にまとう“無関心の仮面”とも通じています。あえて感情をオフにしなければ都市では生きにくい。そうした“都会人としての処世術”が、このひとことに凝縮されているようにも思えます。
地下鉄を待つ姿に映る孤独の終着点
して彼は、地下鉄の電車を待っています。
それはただの交通手段ではなく、「誰とも話さず」「誰にも見られず」にその場を離れられる“逃避の装置”のようにも描かれています。

“どこかへ行く”のではなく、“ここを離れる”ための電車。
それは、彼が抱える孤独がすでに行き場を失っていることの暗示でもあります。
音の隙間に滲む感情――サウンドとボーカルの美学
細坪基佳のボーカルが描く“曖昧な感情”
『初夏』における細坪基佳の歌唱は、情熱的でも劇的でもありません。
むしろ、言葉と言葉の間にある“沈黙”を丁寧に紡ぐような、慎ましいトーンが特徴的です。

それが逆に、聴く側にとっては想像の余地を与えます。
主人公が言葉にしない感情、うまく伝えられない気持ちが、音としてはっきりと語られるのではなく、“気配”として伝わってくる。そうしたボーカルの距離感が、この曲の世界観に深みを与えているのです。
瀬尾一三による編曲と芳野藤丸のギター
編曲を手掛けた瀬尾一三氏は、あくまでも詞の世界を引き立てる方向で、サウンドを構成しています。アコースティックギターを主軸に据えたシンプルな構成は、都市の空気感と主人公の静けさを巧みに包み込んでいます。
中でも特筆すべきは、芳野藤丸氏によるリードギターのフレーズです。
感情の波を起こさず、ただそっと滑るように流れていく旋律は、都市の中をさまよう“ぼく”の足取りや心の起伏を見事にトレースしています。

リフレインに刻まれた、“感覚としての孤独”
「夏のはじめの昼下がりは とても馴じめず淋しくなる」
この楽曲で繰り返されるリフレインは、聴く者の心に深く残ります。
「夏のはじめの昼下がりは」という、何の変哲もない時間帯。しかし、そこに「馴じめず」「淋しくなる」と続けることで、特別な出来事が何も起きていないからこそ襲ってくる、“理由のない感情”がリアルに表現されています。
『初夏』が投げかけるもの――感情と風景の交差点
日常に潜む、説明のつかない感覚
『初夏』が描き出しているのは、ある特定の物語ではありません。
誰もが日常の中でふと感じる、明確な理由もないままに訪れる“やるせなさ”や“浮遊感”。
そんな言葉にならない感情が、風景描写という形を借りて、静かに綴られています。
「新婚カップル」「カニ族の家族」「地下街の雑踏」といった“他者の存在”を通して、主人公は常に「その輪の外側」にいます。しかしそれを嘆くでもなく、怒るでもなく、ただ淡々と受け止めている。この“あきらめに似た透明な感情”こそが、『初夏』の持つ深い魅力のひとつです。
季節と感情の“ずれ”に宿る普遍性
「夏のはじめの昼下がり」という季節の入り口は、明るく穏やかなはずの時間帯です。
にもかかわらず、主人公はその空気に馴染めず、孤独を感じている。

この“季節と感情のズレ”は、私たちがふとした瞬間に感じる違和感そのものです。
嬉しいはずの出来事に喜べなかったり、誰かと一緒にいても孤独を感じたり。
そんな心のずれを、そっと抱きしめるように描いた『初夏』は、どこか癒しにも似た温度を持っています。
ふきのとう作品の中での位置づけ
「ふきのとうらしさ」の本質を映す一曲
細坪基佳のボーカルが見せる繊細なニュアンス、瀬尾一三氏の静かな音の設計、そして札幌という舞台が持つ象徴性――それらが相まって、まるで一枚の印象派の絵画のような作品が成立しているのです。
おわりに:それぞれの『初夏』に耳を澄ませて
『初夏』という曲は、札幌という具体的な街を舞台にしながらも、
聴く人一人ひとりの心の中にある「見えない孤独」や「言葉にならない感情」を静かに映し出してくれる存在です。
他者と比べてしまう自分。人混みのなかで感じる“ひとり”。
そんな感覚は、多くの人にとってどこか心当たりのあるものでしょう。
それぞれの人に訪れる初夏。暑い夏を迎える準備もしなくてはなりません。




コメント